【ピアノ】「19世紀のピアニストたち 正編・続編」(千蔵八郎 著)レビュー
► はじめに
本書は通常のピアノ音楽史概論とは異なり、演奏家の人物史に焦点を当てたユニークなアプローチを取っています。
正編では、19世紀に先立つ時期のピアニストからフランツ・リストあたりまで、続編では20世紀に少し入ったところまでがまとめられています。
「19世紀のピアニストたち」
「続・19世紀のピアニストたち」
・出版社:音楽之友社
・初版:正編 1985年、続編 1987年
・ページ数:正編 217ページ、続編 252ページ
・対象レベル:初級〜上級者
19世紀のピアニストたち 著:千蔵八郎 / 音楽之友社
続・19世紀のピアニストたち 著:千蔵八郎 / 音楽之友社
► 内容について
‣ 本書の特徴
豊富な人物紹介
正編・続編を通じて、20世紀の人は含めずに500人近いピアニストが取り上げられているのは圧巻です。クララ・シューマンの腹違いの妹「マリー・ヴィーク」や、「バナナ(黒人の歌)Op.5」を作曲したゴットシャルクなど、ややマニアックな人物まで幅広くカバーされています。
続編では、女流ピアニストとして初めて有名になった人物やその時代背景など、従来の音楽史では触れられることの少ない人物やその背景部分まで詳しく言及されています。
読みやすい文体
ただの事実の羅列ではなく、著者の見解や時には皮肉まで織り込まれた読みやすい文体が魅力的です。専門的な内容でありながら、親しみやすい語り口で書かれているため、非常に楽しく読み進めることができるでしょう。
‣ 各巻の内容
正編の構成:
・踊り、踊らされた人々
・ツーリング・ヴィルトゥオーソの時代
・ピアノフォルテの登場
・クレメンティ、そのヴィルトゥオーソへの道
・ピアニスト軍団、動きはじめる
・ベートーヴェン、登場
・ピアノ教育用機器の出現
・話題の人、カルクブレンナー
・《ヘクサメロン》成立事情
・ピアニスト人間模様(1)
・ピアニスト人間模様(2)
・レンツ報告―リストとショパン―
・仄聞 フランツ・リスト
・四人の先生、その素顔
・終章に代えて―人の世の旅のたのしさ―
続編の構成:
・さらに自立をせまられるピアニストたち
・台頭する女流ピアニスト
・ユニークさでは、人後におちないヘンゼルト
・早逝したボードビル・ピアニスト―ルイス・モロー・ゴットシャルク
・コンセルヴァトワールの世紀
・世紀後半へかけてのピアニストたち
・『ドイツでの音楽修行』を書いた才媛―エイミー・フェイ
・小さな手の天才ピアニスト―カール・タウジヒ
・ピアニストのロシア楽派―アントン・ルービンシテイン
・世紀後半のピアニスト群像(1)
・一人は客席を睨み、一人は逃亡―ビューロとプランテ
・美人で才媛、しかも卓越した3人の女流―メンター、エシポフ、カレーニョ
・レシェティツキの一番弟子―イグナチ・ヤン・パデレフスキ
・世紀後半のピアニスト群像(2)
・リストの弟子たち
・レシェティツキの弟子たち
・二つのピアニスト養成センター
・世紀末のピアニストたち
・終章―パフォーマンスの世紀
‣ ピアノ音楽史の5つの流れにおける本書の位置
著者は、姉妹書「20世紀のピアニストたち 上・下」において、ピアノ音楽の歴史を5つの流れに分類しています:
1. 直接的なテクニックにかかわる奏法の進展
2. それを実証的に実践したピアニストたちの活動
3. ピアノの楽器としての機能的な変遷
4. 音楽自体の審美観と様式の変化
5. どんな作品が書かれるようになったかという作品論
本書は主に「2. ピアニストたちの活動」に焦点を当てており、人物史の観点からピアノ音楽史を俯瞰できる構成となっています。
‣ 本書の注意点
・書籍タイトルからも明らかだが、20-21世紀以降の情報は含まれていない(20世紀初頭のみわずかに記述あり)
・海外のピアニストのみで、日本の演奏家についてはほとんど触れていない
・その後の音楽界の変化や新世代のピアニストについては別途情報収集が必要
・続編に両巻を通しての索引が収載されており、正編には索引はない
► 実際の使用体験と活用法
‣ 筆者自身の体験談
筆者自身、購入当初は通読によってピアノ音楽人物史の大きな流れを把握することから始めました。従来のピアノ音楽史では作曲家や作品に重点が置かれがちですが、本書を通じて演奏家という視点からの理解を深めることができたのは大きな収穫でした。
千蔵八郎氏の他の音楽史関連著作との併読による相乗効果も感じました。同一著者による資料を用いることで情報の整合性が保たれ、効率的な学習方法となりました。
現在では、特定のピアニストについて調べる際の参考資料として使用しています。例えば、クララ・シューマンの作品を聴く前に該当項目のみを読み返すなど、音楽鑑賞の理解を深める資料として重宝しています。
‣ 効果的な読み方の提案
推奨読書法:同著者の関連書籍との併読
・「20世紀のピアニストたち 上」および「20世紀のピアニストたち 下」
・「最新ピアノ講座(7)(8)の音楽史部分」(全43ページ)
・「ピアノ音楽史事典」
・「最新ピアノ講座(5) より 第7章 ピアノ奏法の歴史」
これらの併読により、前述の5つの流れのうち本書で手薄な部分も補完できます。同一著者による資料併読の最大の利点は、情報の整合性の高さにあります。
► 終わりに
19世紀のピアニストたちの人物史に特化した貴重な資料として、ピアノ音楽に関わるすべての人におすすめできる一冊です。ただの音楽史の勉強としてではなく、読み物としても十分に楽しめる内容となっています。
同著者の他の書籍については、以下のページでレビューを確認してください。
19世紀のピアニストたち 著:千蔵八郎 / 音楽之友社
続・19世紀のピアニストたち 著:千蔵八郎 / 音楽之友社
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
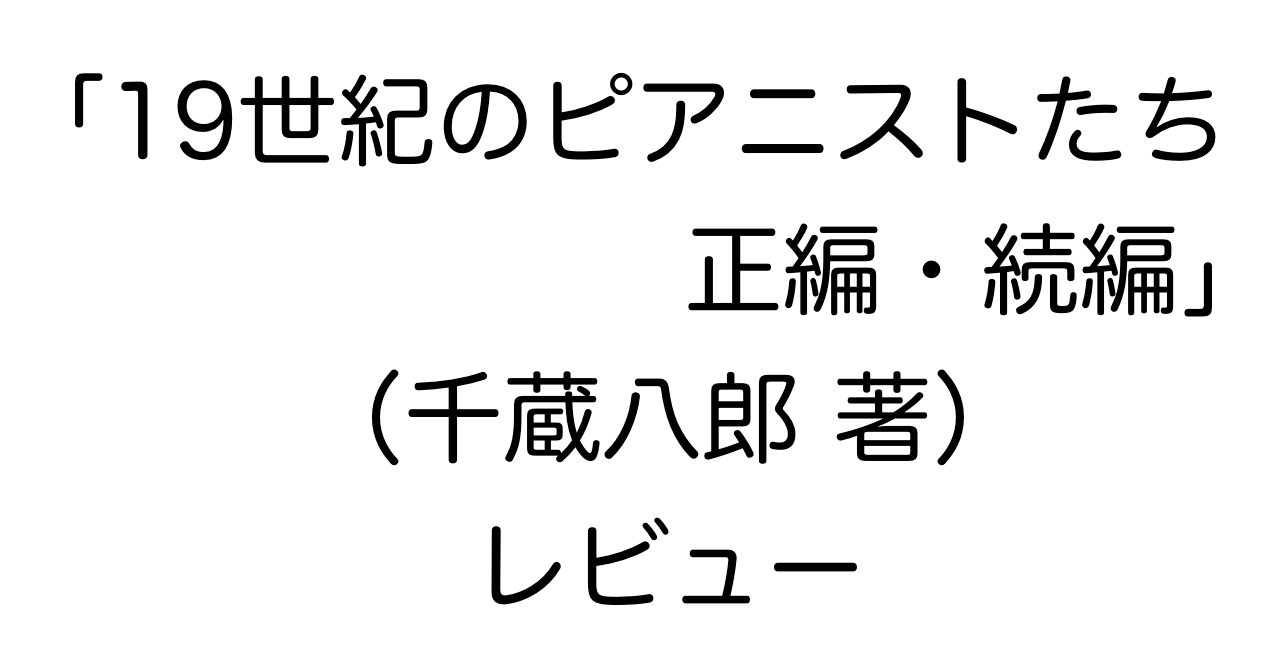


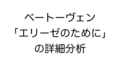
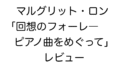
コメント