【ピアノ】映画「アマデウス」レビュー:状況内外音楽の巧妙な使い分け
► はじめに
「アマデウス(Amadeus)」は158分の大作であり、音楽的にも注目すべき点が数多くあります。本記事では、その中でも鍵盤音楽に関連する部分を中心に解説していきます。
・公開年:1984年(アメリカ)/ 1985年(日本)
・監督:ミロス・フォアマン
・ピアノ関連度:★★☆☆☆
► 内容について(ネタバレあり)
以下では、映画の具体的なシーンや楽曲の使われ方について解説しています。未視聴の方はご注意ください。
‣ 音楽演出の基本概念:状況内音楽と状況外音楽
状況内音楽とは:
・ストーリーの中で実際に聴こえている音楽
・登場人物がピアノを弾いているシーンのBGMなど
一方、外的に付けられた通常のBGMは「状況外音楽」となります。
‣ たどたどしさから予測できる状況内音楽
精神病院でアントニオ・サリエリが演奏するシーンでは、演奏者の姿は最初映されませんが、そのたどたどしい演奏から「人がその場で実際に弾いている」ことが推測できます。これは音楽そのものが情報を伝える演出例です。
‣ 一度提示された状況内音楽の有機的な活用 7場面
本映画では、一度提示された状況内音楽が形を変えながら繰り返し使用される例が多く見られ、物語に深みを与えています:
1. 楽器を変えた反復
子供時代のモーツァルトが「クラヴィーア小品 ヘ長調 K.33B」を鍵盤で演奏し(状況内音楽)、直後にヴァイオリンで同じメロディを奏でます(状況内音楽)。同一楽曲の楽器変更により、モーツァルトの多才さを効果的に表現しています。
2. 状況内から状況外への移行
精神病院でサリエリが鍵盤を演奏し(状況内音楽)、その直後に指揮の真似をするとオーケストラが鳴り響きます(サリエリの頭の中で鳴っている、状況外音楽)。現実から回想への橋渡しを音楽が担っています。
3. 即興アレンジによる才能の対比
サリエリが作曲した「歓迎のマーチ」をモーツァルトがその場でアレンジして演奏するシーン(共に、状況内音楽)。音楽を通じて両者の才能が鮮明に描かれます。
4. スタイル模倣による音楽的ユーモア
モーツァルトが、妻と父レオポルドの3人でパーティへ出かけた場面では、その会場で流れている音楽(状況内音楽)を、その場で「バッハ風」「サリエリ風」で演奏します(状況内音楽)。その場に居合わせたサリエリは、モーツァルトの才能をより強く認識することになります。
5. 時間軸の操作
モーツァルトが屋外で「ピアノ協奏曲 第22番 K.482 第3楽章」を披露している時に(状況内音楽)、その音楽を残したまま、サリエリがモーツァルトの家へ侵入している場面へ(状況外音楽)。両場面が同じ時間軸であることを強調する使い方です。また、後にその音楽をカットアウトし、サリエリが別の場所にいる場面へ。急激にカットアウトすることで、時間軸が別であることを強調しています。
6. 内面世界の音楽化
病床のモーツァルトが、作曲しながら口で歌ったもの(状況内音楽)をサリエリが楽譜へ書き取る場面では、完成版のオーケストラ演奏(モーツァルトの頭の中で鳴っている、状況外音楽)も併行して流れます。作曲家の頭の中の音楽を具現化した印象的な演出です。
7. 冒頭と結末の呼応
序盤でサリエリが「アイネ・クライネ・ナハトムジーク 第1楽章」のメロディを鍵盤で演奏し、ラストで第2楽章がBGMとして流れます。はじめと終わりに同一楽曲の異なる楽章を配置することで、映画全体に統一感を与えています。
補足:
・「2. 状況内から状況外への移行」で取り上げた「サリエリの頭の中で鳴っている、状況外音楽」は、過去の音楽
・「6. 内面世界の音楽化」で取り上げた「モーツァルトの頭の中で鳴っている、状況外音楽」は、未来の音楽
‣ 状況内音声による「伏線」の表現
· 伏線とは
伏線とは「その後に起こることを予めほのめかしておく手法」であり、「映像表現+”音”の表現」として伏線をはることもできれば、「音楽表現(純粋な音楽)」として示すこともできます。
· 本映画で見られる伏線表現
オペラ「魔笛」公演中の大きな雷音は、ただの舞台効果を超えて、直後にモーツァルトが倒れることを暗示する音響的伏線として機能しています。「状況内音声」であり、音楽の一部であるため「状況内音楽」とも言えるでしょう。
この後、物語は急速にモーツァルトの衰弱へと向かいます。
‣ 音楽史的視点から見た留意点
詳細は映画本編で確認して欲しいのですが、本映画の内容は、有力とされているベートーヴェンの音楽史の内容と異なる点もあります。あくまで映画として楽しむことを重視しましょう。
► 終わりに
「アマデウス」では、音楽映画ならではの、状況内音楽と状況外音楽の巧妙な使い分け、楽曲の有機的な反復、音響による伏線など、様々な音楽や音声演出技法が効果的に使われています。
鍵盤音楽の登場は限定的ですが、鍵盤楽器を通じてモーツァルトの天才性を表現する場面や、楽しげに演奏活動をする場面は印象的で、ピアノ学習者にとってもおすすめできる一作です。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
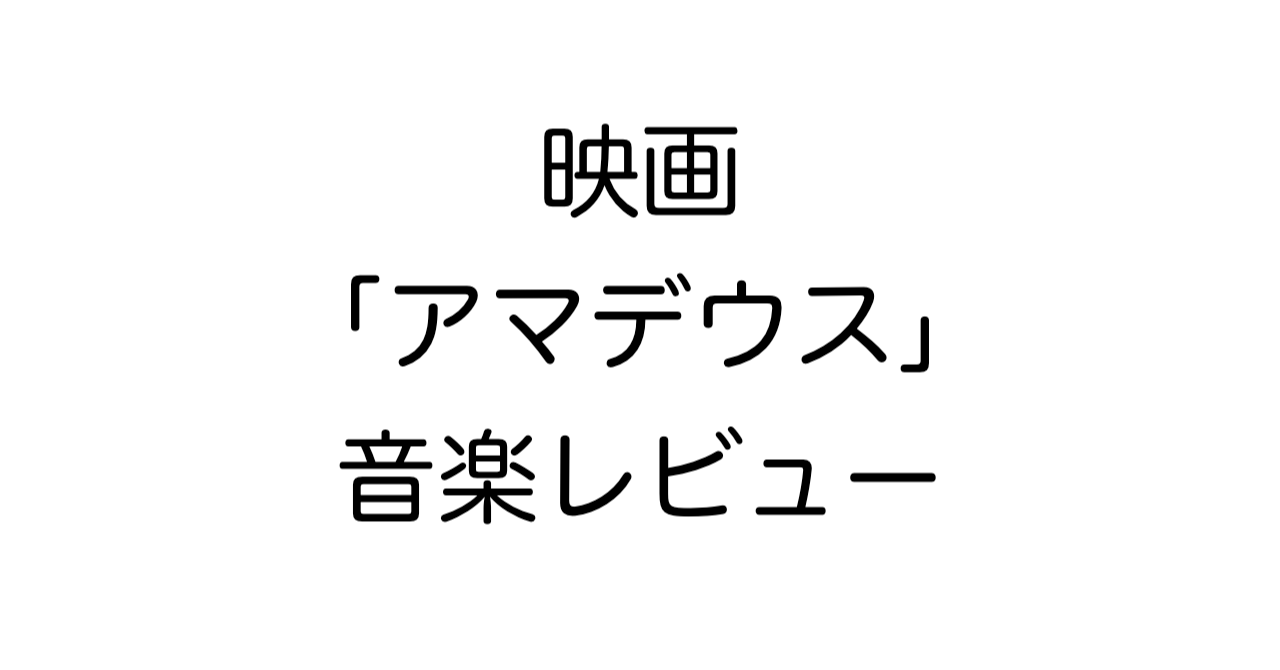
![アマデウス [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51St0YmKKNL._SL160_.jpg)
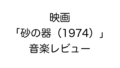
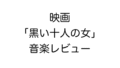
コメント