【ピアノ】初心者必見の演奏姿勢改善ガイド
► はじめに
本記事では、ピアノ演奏における姿勢の重要性と、具体的な改善方法を詳しく解説します。根本から見直し、より自然な姿勢と演奏を実現しましょう。
► A. 演奏姿勢の基本
‣ 1. 演奏姿勢が悪化する根本的な原因
演奏しているときには気づかなくても、写真や動画などで自分の演奏姿勢を見るとひっくり返りそうになることもあるはずです。一度気がついてそのときに直しても、結局少ししたらまた元に戻ってしまうことでしょう。
理由はシンプルで、小さい楽譜をのぞきこんでいるからです。
原則、市販のクラシックピアノ楽譜で標準のA4強よりも小さなサイズの楽譜は使わないようにしましょう。
ネットプリントサービスなどで手に入れた楽譜は、とにかく大きなサイズでプリントアウトしてください。
iPadなどのタブレットでも楽譜を見る方は、横置きにして画面の中に大譜表を2-3行だけ表示させるのがおすすめです。それで練習しにくい場合は、早く暗譜して景色だけで弾けるようにします。そうすれば、縦置きで1ページすべてを表示させてものぞきこむことにはなりませんので。
譜読みをしている限り、文字通り「楽譜を見る」ということを常に行っているため、小さい楽譜を使っているとのぞきこむのをやめられません。こういった元の原因を無くさない限りは、いくら表面上気をつけてケアしても再発します。
のぞきこまないと読めないような楽譜は使わない。いつでも実践できることなので、意識してみてください。
それでも姿勢が改善されない場合は:
・座り方に問題アリ
・座る位置に問題アリ
・呼吸が浅い
・気持ちを入れようとするあまり、首から上に力を入れ過ぎている
・日常生活の姿勢からすでに乱れている
などの理由も疑う必要があるでしょう。
‣ 2. 楽譜を見るときに顔をひねらずに済む工夫
楽譜をオンライン購入してA4プリントする場合は、譜面台へ一度に置く楽譜は、A4を2枚までにしましょう。譜面台に4枚も5枚もしきつめて練習していると、ほとんどずっと顔をひねっていることになり姿勢に良くないからです。
本番のときに顔をひねっては弾きません。連弾をするときには、1台のピアノの前に2人が座る特殊性から譜面を見るために顔をひねることもありますが、少なくともソロの練習ではそうならないように気をつけましょう。
また、A4を2枚までにしている場合であっても、譜読みの初期はそれをずらして、見ているページが自分の真正面へくるようにしてください。譜読みはじめでは少しづつ丁寧に読んでいくので、一度に2ページを見る必要はありません。
A4を2枚と言えども、そのまま置いたらやや視線を中心からずらすことになりますし、書き込みをするときにもやや身体をひねることになります。見るページのみが中心にくるように置けば解決します。
譜読みが済んで楽譜にかじりつかないようになってから、通常へ戻せばいいのです。
‣ 3. 楽譜との距離を変えて、姿勢を改善する方法
見やすい楽譜を使うこと以外にも、簡単にできる姿勢対策があります。
譜面台を手前へ引き出してみましょう。引き出せないタイプのピアノを使っている場合は、譜面台へ楽譜などを1冊置いて、そこへ重ねるように使いたい楽譜を置いてください。
自分がのぞきこまなくても楽譜との距離を物理的に近くすればいいのです。顔を近づけるのではなく楽譜側から近づけましょう。
まず、グランドピアノの場合について。
ほとんどのグランドピアノでは譜面台を手前へ引き出すことができるので、指一本分くらい引き出してしまいましょう。多少音響が変わってしまうのですが、譜読みで楽譜へかじりついているときは、いったん、楽譜の見やすさを優先してもいいでしょう。
(写真)

写真は、譜面台を一番奥まで押し込んである状態です。この状態ではチューニングピンなどが見えます。一旦音響のことは無視して、これらのピンが見えなくなるくらい手前へ引き出してしまってください。
次に、譜面台を引き出せないタイプのピアノの場合について。
効果はそれほど大きくありませんが、譜面台へ楽譜などの土台を1冊置いて、そこへ重ねるように使いたい楽譜を置いてください。
譜面台の形状にもよりますが、メインで使いたい楽譜と顔との距離を多少近づけることができます。
特に、アップライトピアノの譜面台では少しの効果しか期待できません。一部の電子ピアノの譜面台では、台自体の奥行きがあり厚みのある土台楽譜を置くことができるので、ある程度の短縮を期待できます。
とにかく、譜読みのときに首を伸ばして楽譜をのぞきこむのだけはやめましょう。そのクセはずっと残ってしまい、暗譜後など、楽譜を見ていないときの演奏姿勢にまで悪影響を与えてしまいます。
► B. 姿勢改善のテクニック
‣ 4. 顔を上げることで変わる演奏姿勢
演奏中にまずやるべきなのは、顔を上げることです。上を向くのではなく、顔を起こして、頭をきちんと首の上へ乗せてあげてください。
加えて、「覗き込まないと見えないような小さな楽譜は使わない」など、上記したような環境作りで、根本的な原因を減らしていきましょう。
ピアノを弾くときというのは、多少腕を伸ばしていますし、奏法上、どうしても前屈み気味になりがちです。だからこそ、譜読みが終わってからも気は抜けません。ことあるごとに、顔を上げましょう。
おすすめは、不意打ちチェックです。
タイマーをセットし、練習中の忘れた頃に鳴るようにして、そのタイミングで即座にチェックするのです。筆者も、姿勢に悩んでいた時期に取り入れていました。
‣ 5. 左足のお行儀を何とかしよう
初心者向け教材でも一番右のペダル(ダンパーペダル)を使うことはあるので、右足の姿勢については比較的問題になりません。
一方、左足についてはどうでしょうか。
結構な確率でお行儀の良くない左足が散見されます。放り出されていたり、内側へ畳まれて椅子に突っ込まれていたり。
とりあえず左足については、投げ出したり、畳み込んだりしないで、腰掛けたときの自然にいる位置でキープさせておきましょう。
このような良くないクセをつけないためのポイントがあります。
譜読みをするときや好きな楽曲を初見で弾くときなど、ある程度リラックスしながら学習するときでも、足元は常にきちんとしておくように心がけることです。
最低限の気をつけるべきことを意識して、あとは目の前の音楽を思いきり楽しみましょう。
► C. 初心者のための実践的アドバイス
‣ 6. 姿勢改善のための具体的な方法
入門者・初心者の段階では、なかなか思うように指が動かなかったり楽譜の読み方が怪しかったりすることもあるでしょう。それに関してはピアノ弾きの誰もが通ってきている道なので、心配いりません。少しずつの積み重ねで確実に良くなっていきます。
一方、ピアノを弾いているときの姿勢だけは良くするように心がけましょう。あまり指が動かなくても、楽譜が苦手でも、姿勢だけは…です。
「とりあえず、姿勢を良くしよう」と意識するだけで構いません。姿勢は良いほうが上達も速くなる傾向にあります。無駄な力を秘めることがなく、動作もスムーズになるからです。
基本的に「意識しているかどうか」だけなので、入門者・初心者にも頑張って頂きたいと思います。
ピアニストの演奏を鑑賞するときに、「出てくる音は素晴らしいのに、姿勢が悪くて残念だな…」などと思ったことはありませんか。
聴衆は見た目でも演奏を聴きます。まずは、姿勢を正して堂々と演奏するのが出発点です。良くない姿勢はクセになるので、練習のときから心がけが必要です。例えば、以下のような部分をチェックしてみましょう:
・首や顔が前に突き出ていないか
・猫背になっていないか
・肩が上がっていないか
上記の項目で述べたように姿勢が悪くなる原因は複数ありますが、首や顔が前に突き出たり、猫背になる場合は、椅子の位置が下がり過ぎている可能性があります。
また、肩が上がっている場合は、椅子の位置が前に出過ぎて手元や脇が窮屈になっている可能性があります。肘が内側に入り、脇が閉まり過ぎると、肩が上がってしまいます。
‣ 7. 自己観察と継続的な改善
あるとき、練習中にふと右へ目をやると、ガラスに映った自分の姿勢がひどくてひっくり返りそうになった覚えがあります。この経験は想像以上に衝撃的で、汗をかくことなりました。エスカレーターのガラスに映った自分の日常姿勢に関しても、同じようなことを感じたことがありました。
「素になったときに本当の自分が出る」と言われることがありますが、姿勢にも言えることです。少しでも不安に思った方は、「演奏姿勢の悪さは日常に出る」ということを頭の片隅に置いておきましょう。
演奏姿勢の良くなさを自覚するためには、やはり、ピアノの横に鏡を置くことです。必ずしも全身が映らなくても、上半身は映るようなものを置くといいでしょう。とりあえず置きっぱなしにしておいて、忘れて油断をした頃にふと目に入って反省する、という使い方が効果的です。置いたらいったん忘れてしまって構いません。
筆者自身、さすがに今はもう取っ払ってしまいましたが、以前は置いている時期がありました。時々ふと目をやっても常に良い姿勢をキープ出来ている状態が続くようになるまで置きっぱなしにしておくといいでしょう。
また、演奏姿を録画してみると、改善点が沢山見えてきます。例えば:
・首や顔を前に突き出しながら演奏していた
・猫背になっていた
・肩が上がっていた
・演奏中、口があいていた
・思っていたよりも、無駄な動きが多く見えた
・無意識に顔や手先でカウントをとるクセに気づいた
・両手とも休符になるところで緊張感が切れて見えた
・最後の音を弾き終わった後の「気の抜け」が早過ぎていた
・座ってから弾き始めるまでの動作が挙動不審に見える
これらのような見た目というのも、理想と現実のギャップを埋めることが重要。もちろん、「変えられない骨格的なこと」を言っているのではなく「意識次第で変えられる演奏姿」のことです。
► 終わりに
姿勢は見た目の問題だけではなく、演奏の質と上達速度を左右する重要な要素です。良い音楽は良い姿勢から生まれることを忘れずに練習するようにしましょう。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
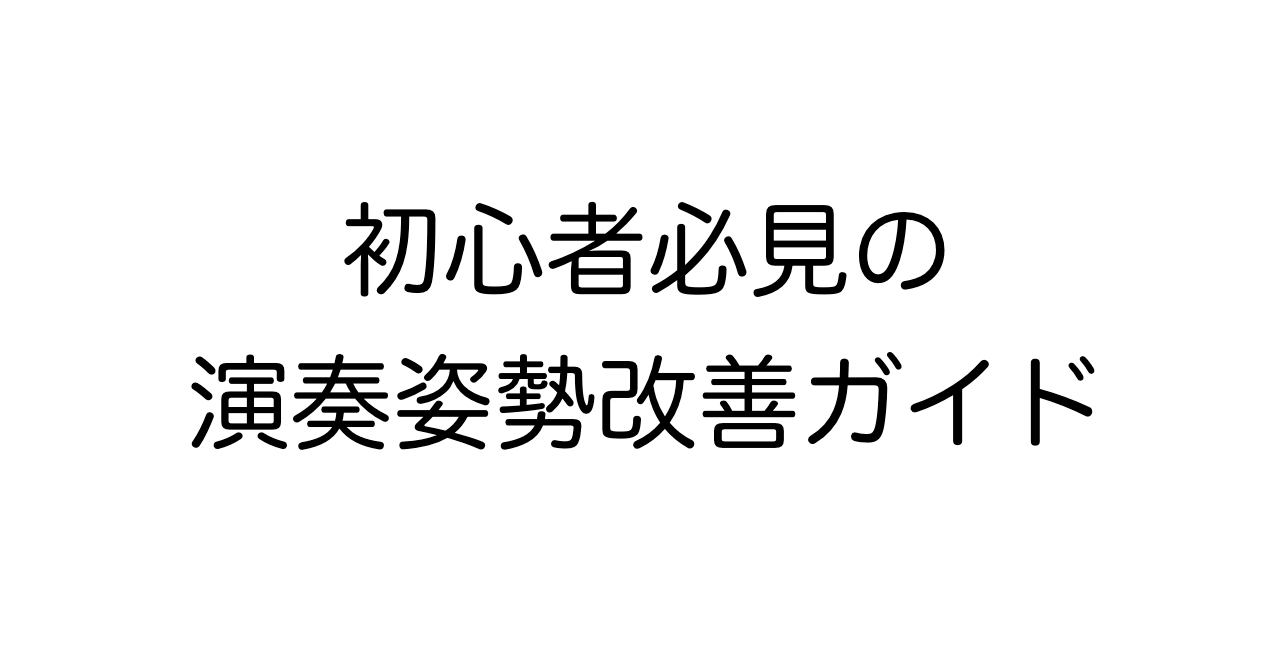
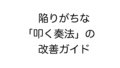
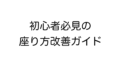
コメント