【ピアノ】実体験:大人のピアノ練習嫌いを直すために効果があった方法
► はじめに
「昔はピアノが好きだったのに、最近は練習するのが億劫で…」そんな経験はありませんか。
筆者自身も、中学生の頃まではピアノが何よりも優先だった時期から、作曲学習に重心が移るにつれて練習が嫌いになった時期がありました。しかし、いくつかの工夫を重ねることで、再びピアノと向き合えるようになりました。
本記事では、実際に効果があった「練習嫌い」を克服する具体的な方法をシェアします。同じような悩みを抱えている方の参考になれば幸いです。
► 大人になってから起きたピアノ離れ
‣ 練習が当たり前だった頃
筆者の場合、中学生くらいまでは「何をするよりも何よりもピアノの時間」という感じで、練習嫌いとは程遠い状況でした。土曜日にあるスポーツの部活の大会よりも、日曜日にあるピアノの発表会のほうが、自分の中では圧倒的に優先度が高かったのです。
‣ 転機:作曲学習への集中
しかし、転機になったのは作曲の学習が中心になった時期でした。理由は明らかで、圧倒的に一点集中型の性格だったからです。
なぜ、ピアノから遠ざかったのか
同じ音楽でも、創作と演奏では異なる要素が多くあります。作曲に集中しているときに「ピアノも弾こう」と思うと、どちらにも中途半端になってしまい、結果的にピアノの練習が億劫に感じられるようになりました。
► 練習嫌いを直すためにやった3つのこと
筆者の場合、ピアノ自体が嫌いになったわけではなかったので、以下の3つを意識することで比較的スムーズにピアノの近くにいられる毎日に戻ることができました。
‣ 1. ピアノ学習のすべてを作曲に結びつけた
ピアノの学習すべてを作曲に「寄せていく」学習をすることで、一点集中学習ができるようになり、心が穏やかになりました。
具体的な実践方法:
選曲の基準を変更:ピアノで練習する曲はすべて、作曲の観点でよくできていると思えるものだけに限定
テーマの統一:そのとき作曲で学習しているテーマ作曲家のピアノ曲を優先的に練習
分析的アプローチ:練習する曲はすべて楽曲分析をし、作曲学習の題材としても活用
この方法により「ピアノの練習」と「作曲の勉強」が同時に進んだため、一点集中に近い状況を作り出すことができ、継続しやすくなりました。
‣ 2. 練習開始までのハードルを徹底的に下げた
「使うものを出したままにすること」「使うものまでの到達手順をワンステップ減らすこと」を実践してきました。結果、少なくともズボラな筆者の性格には非常に合っていました。
実際に行った環境整備:
・楽譜の配置:次の日に確実に使う楽譜はピアノの上に出しっぱなし、開きっぱなしにする
・鍵盤の管理:鍵盤のフタは閉めるが、鍵盤カバーはかけない(1ステップ削減)
・椅子の位置:ピアノ椅子はピアノの下にしまわず、引き出しっぱなしにする
・メトロノームの配置:絶対にしまわず、「手の届く位置」に常に出しっぱなしにする
重要なポイント
あらゆることにおいて、開始するまでのハードルを少しでも下げておかないと、たった数秒の手間が「やる気を無くす原因」になってしまいます。特に疲れているときや時間がないときほど、この差は大きく感じられます。人間は、数秒で上れる自宅のロフトにすら上らなくなるのです。
‣ 3. 目先の本番を設定した
作曲の学習が中心になってからは演奏の本番の回数が激減していたので、負担にならない程度で目先の本番を入れるようにしました。緊張するような本番もありましたが、小さな集まりで弾いたり、レストランでピアノBGMのアルバイトをしたりと、楽しめる場でも弾くようにしました。
また、先程の「寄せていく」話と結びつくのですが、人前で弾くときは、原則、自分で作曲か編曲した作品しか弾かないようにしていました。
プロでも同じ?
ピアニストでも、「仕事に関係なく趣味でピアノに向かうことはない」という方は実は多くいます。また、筆者が以前師事していた作曲家は、「好きなように自由に曲を作る趣味はない」と断言していました。つまり、人によっては目先の目標や本番がないと音楽から遠ざかってしまう可能性があるのです。以前の筆者はこの傾向が強かったと思います。
► すぐに実践できる練習嫌い克服法
‣ 自分の「続けられた瞬間」を分析する
練習が続いた時期について、自身の場合を振り返ってみましょう。例えば:
・ピアノに座りさえすれば、自然と続けられたか
・練習開始までのハードルを下げれば継続できたか
・目先の本番が決まっていれば頑張れたか
・誰かから褒められた直後は継続できたか
・基礎練習が嫌いなだけで、好きな曲を弾いているときは時間を忘れられたか
これらを分析し、自分なりの「腰を上げる方法」を見つけることが継続の鍵です。
‣ 今日から始められる小さな工夫
工夫例:
・楽譜を開きっぱなしにしてピアノの上に置いておく
・練習のはじめからICレコーダーを回し、誰かに見張られているような緊張感を持つ
・タイマーで練習時間の積み重ねを「見える化」する
・作曲家の自筆譜ファクシミリ版を眺めて自己啓発する
・音楽仲間を作って巻き込んで続けていく
► 練習嫌いを直す「荒技」
‣ タイプの先生のところへ習いに行く
一つ、知人の大人の学習者にとって非常に効果があったのは、「好きなタイプの先生のところへ習いに行く」という方法です。普段独学の方は、スポット(単発)レッスンを活用するのもいいでしょう。
なぜ、効果的なのか:
・外的動機の活用:「先生にいいところを見せたい」という気持ちが練習の原動力になる
・楽しみの創出:「先生に会うこと自体が楽しみ」になることで、レッスンが待ち遠しくなる
知人の場合、このアプローチにより様々な理由でピアノに向かうようになり、結果的にピアノを弾くこと自体が楽しくなったそうです。
‣ 場合によっては、一時的に辞めてしまう手もある
それでも楽しく感じられない場合は、無理をしてまでピアノを弾く必要はありません。音楽との関わり方は人それぞれで、時期によっても変わるものです。一時的に距離を置くことで、また新たな気持ちでピアノに向かえることもあります。
筆者自身も、上記のようにピアノとの関係が希薄になった時期があったからこそ、今ではより深い付き合いができるようになったと考えています。
► 終わりに
練習嫌いの克服は、自分の性格や生活スタイルに合った方法を見つけることが何より重要です。本記事で紹介した方法がすべての方に当てはまるわけではありませんが、一つでも参考になるものがあれば幸いです。
筆者の場合、現在はこのWebメディアの運営もあるため、創作からもピアノに触れることからも離れることがなくなりました。読者の皆さんも、自分なりの「ピアノと関わり続ける理由」を見つけられることを願っています。
推奨記事:【ピアノ】モチベーション維持と継続学習のための完全ガイド
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
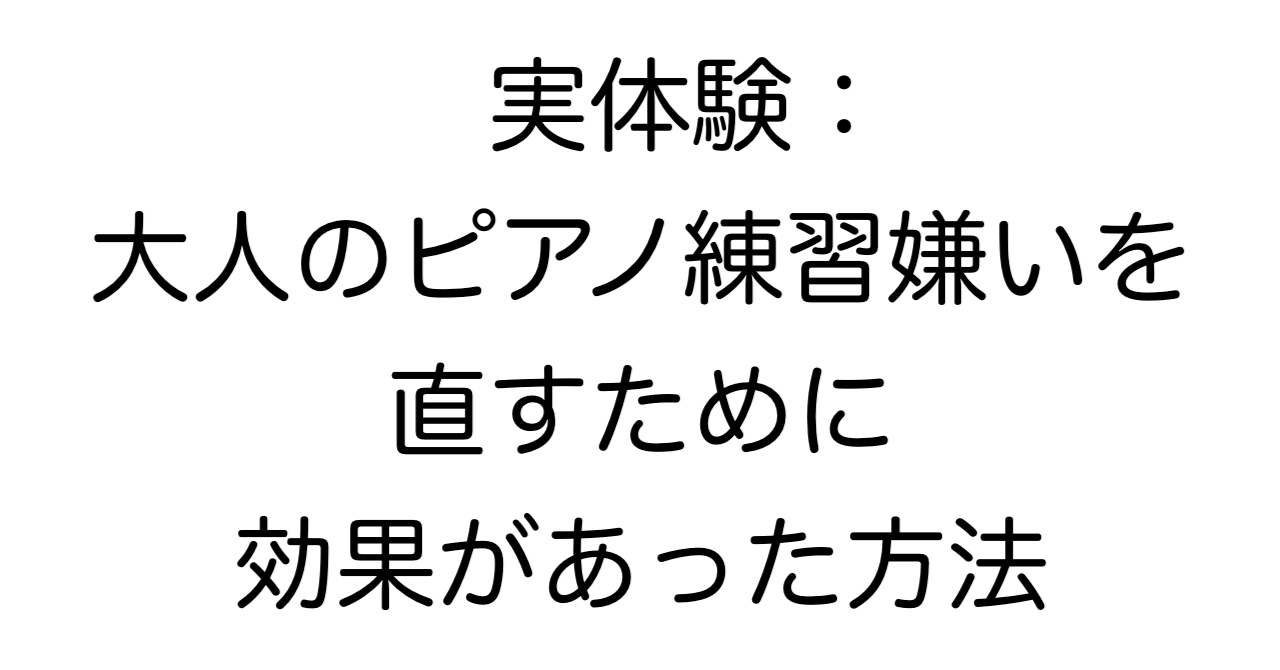
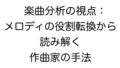
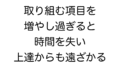
コメント