ピアノ学習にあたって、楽曲分析の必要性は様々な場面で実感していることでしょう。
本記事では、「基本的な楽典以外の音楽理論の知識が無く、これから楽曲分析に入門したいピアノ学習者」へ向けて、「三種の神器」的教科書を使った楽曲分析入門の方法を解説します。分析に関しては、近年も様々な参考書が出版されていますが、今回は、定番かつ古典的な3冊を用いた方法を提案します。
取り組みの条件:
・楽典の基礎知識を持っていること
・ピアノ学習がバイエル修了程度まで進行していること
・様々な楽式の知識
・最低限の和声の知識
・その他、具体的な種々の分析手段による実践
これらの3つを学ぶと楽曲分析の基礎力が上がるため、これらの3冊を選びました。
また、「楽式論」の著者の石桁氏は、「和声と楽式のアナリーゼ」の著者の島岡氏とともに「和声 理論と実習」三色シリーズに関連している人物であり、全体的な解説表現傾向は似ています。したがって、整合性を保った学習をするためにも効果的な組み合わせと考えました。
実際に筆者も、この3冊はすべて学習したものです。
・和声と楽式のアナリーゼ バイエルからソナタアルバムまで 著:島岡譲 / 音楽之友社
・演奏のための楽曲分析法 著:熊田為宏 / 音楽之友社
・楽式論 著:石桁真礼生 / 音楽之友社
・和声と楽式のアナリーゼ バイエルからソナタアルバムまで 著:島岡譲 / 音楽之友社
► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
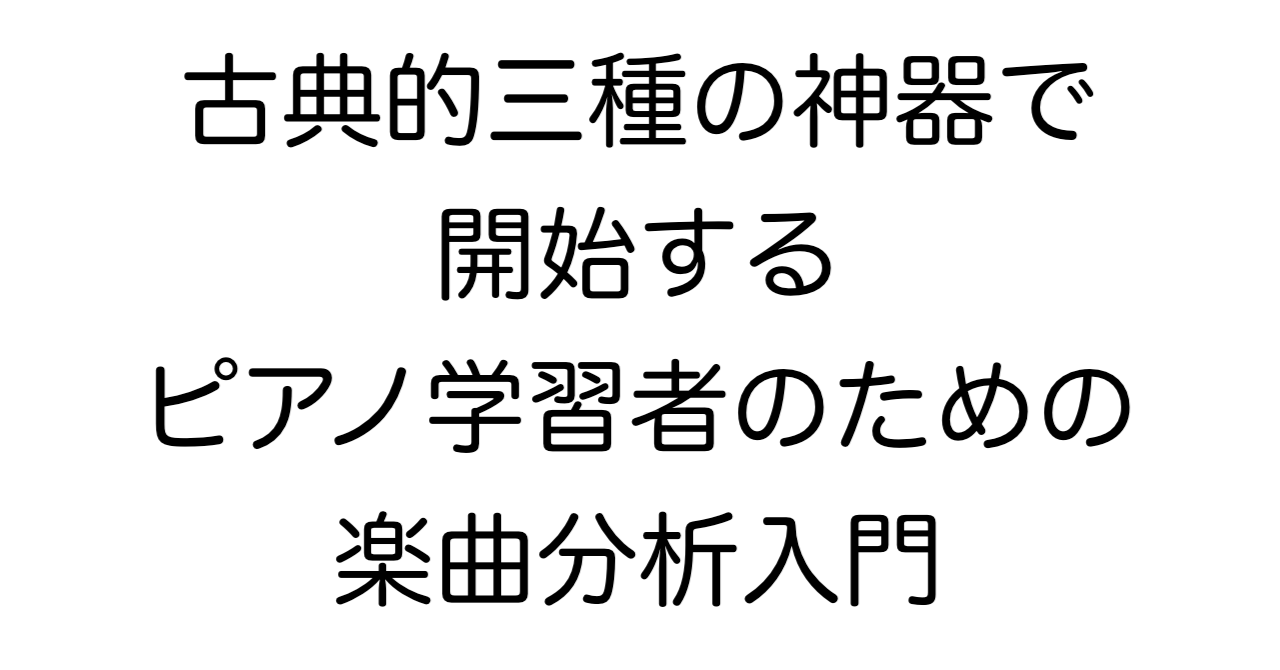



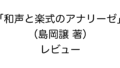
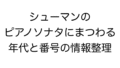
コメント