【ピアノ】奏法や解釈を吟味する過程をすっ飛ばさない
► はじめに
ピアノを学ぶ大人の方々にとって、練習の効率化や上達のためのショートカットを求めたくなる気持ちは自然なものです。しかし、音楽学習においては「近道」が必ずしも最良の道とは限りません。
本記事では、ピアノ演奏において「慣れ」に頼りすぎることの危険性と、各楽曲に対して向き合い、奏法や解釈を丁寧に吟味していくことの大切さについて取り上げます。名ピアニスト、ヴァルター・ギーゼキングの言葉も紐解きながら、より深い音楽表現への道筋を探っていきましょう。
►「慣れ」に甘えない
‣ 楽曲毎に別の顔だと思うべき
「慣れ」というのは良し悪しです。慣れによって、本番で自信を持てたり、奏法を習得できたりするわけですが、マイナス面もあります。例えば、良く起こりがちなのは:
・「こういう音型では、こういう弾き方をしてしまっていいよ」
・「スタッカートが書かれているけど、ペダルを踏んでいるから、手であまり切らないほうが弾きやすいよ」
などと、Tipsのようなことを教えられて経験してしまうと、別の楽曲で似たようなところが出てきた時に、その楽曲ではどうなのかを考えずに、楽なほうへ楽なほうへ流れてしまうことです。しかし、1曲1曲別の顔だと思って譜読みをしなければいけません。
ある程度パターンで考えていくこと自体は悪いことではありませんが、あまりにもそれに甘えてしまって奏法や解釈を吟味する過程をすっ飛ばさないようにしましょう。
‣ なぜ「慣れ」が危険なのか
「慣れ」に潜む危険性について、もう少し具体的に考えてみましょう:
1. 技術的難度を下げる視点の偏重
「この音型はこう弾くと楽」という発想だけでは、音楽的表現が二の次になってしまいます。技術的な容易さだけを追求すると楽曲の本質的な美しさや魅力を表現できなくなる可能性があります。
具体例:‣ 37. 両手で分担した途端に魅力がなくなるパッセージ
2. 演奏の個性や様式感の喪失
定型的なアプローチに頼り過ぎると、「どの時代の作品を弾いてもロマン派の弾き方になってしまう」など、個性が無くなり、様式感にも疎くなってしまうでしょう。
過去の経験則を活用することは確かに効率的です。しかし、それが「考えることを放棄する」ことになってはいけません。
では、新しい楽曲を譜読みするときにはどう取り組めばいいのかについてですが、簡潔に言うと、「生活と気持ちに余裕を持って、しっかりと時間をかけて試行錯誤しながら判断すること」です。楽曲分析をするのもいいのですが、前提として「余裕」が無いと、全てが雑で楽な方へ流れます。
► ギーゼキングの言葉
‣ 発言内容
「ピアノとともに」という書籍の中で、ギーゼキングは、以下のように発言しています。
芸術的に非難の余地のない解釈(=演奏)が、ただ解釈者(=演奏者)が作曲家の表現意図を実現しようと、つまりその指示に従順であろうと努力する場合にのみ、生まれるということは、もはやくり返す必要もないほど自明のことである。
(抜粋終わり)
・ピアノとともに 著:ギーゼキング 訳:杉浦博 / 白水社
‣ ギーゼキングの発言について考える
ヴァルター・ギーゼキング(1895-1956)は、20世紀を代表するピアニストでした。彼はドビュッシーやラヴェルの演奏で特に高い評価を受け、記憶力と楽譜の分析力に優れていたことでも知られています。
ギーゼキングが上記の言葉で強調しているのは、演奏者の役割とは何かという本質的な問いです。彼の考えによれば、演奏者は「音の再生装置」ではなく、作曲家の意図を理解し、それを実現するための創造的な仲介者です。しかし、その創造性は、あくまでも「作曲家の指示を知ったうえで」を前提としています。
彼がこだわった「作曲家の表現意図」とは、楽譜に書かれた音符やダイナミクス記号だけではありません。それぞれの作品が書かれた時代背景、作曲家の美学、その作品が音楽史の中でどのような位置づけにあるのかなど、総合的な理解が必要なのです。そのことが、上記抜粋の続きの文章から読み取れます。
ギーゼキング自身は、新しい曲を学ぶ際に、楽譜を徹底的に分析し、実際に鍵盤に触れる前に頭の中で明確にイメージするという方法を実践していたそうです。これは彼の卓越した能力にも関連していますが、より本質的には、音楽を深く理解しようとする姿勢の表れだったと言えるでしょう。
► 終わりに
限られた練習時間の中で、効率性を求めるのは当然のことです。しかし、「効率」の名の下に思考を省略してしまっては、音楽をする根本的な喜びを見失ってしまいます。
ギーゼキングが言うように、再現芸術の分野における演奏者の重要な使命は、作曲家の表現意図を実現することです。そのためには、楽曲ごとに新鮮な目で向き合い、奏法や解釈を丁寧に吟味する過程を大切にしましょう。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
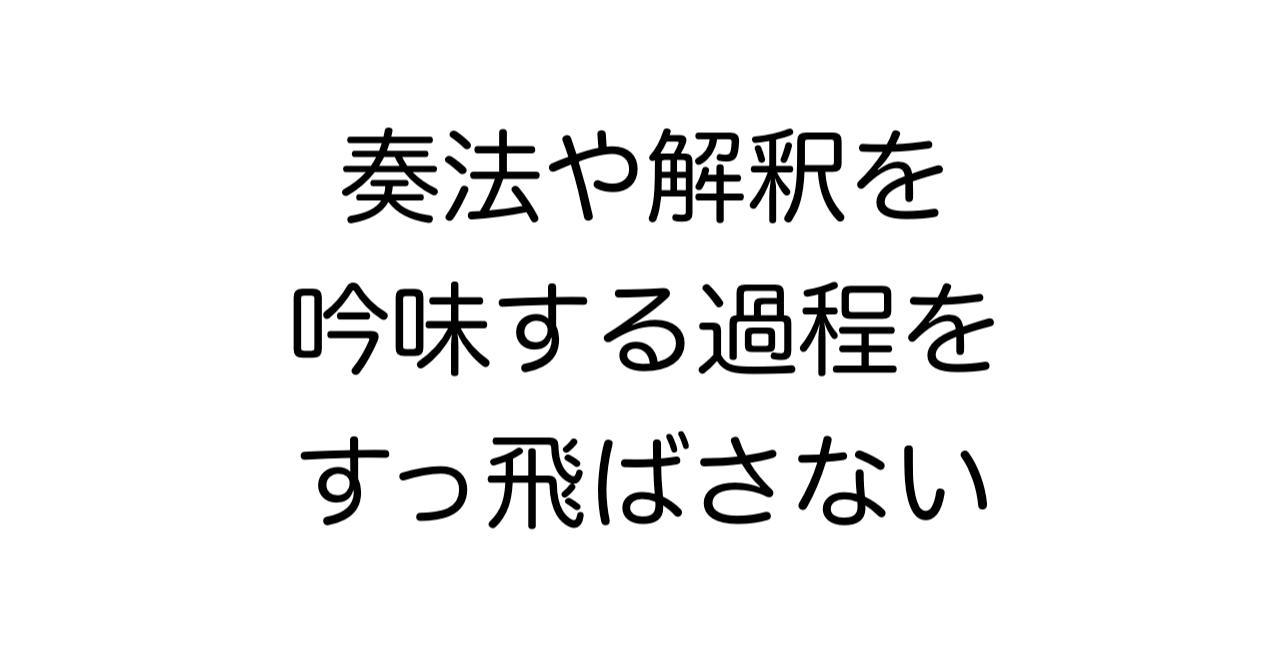

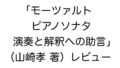
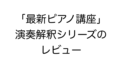
コメント