【ピアノ】知っている作品数を圧倒的に増やすヒント
► はじめに
本記事では、知っている作品数を圧倒的に増やすヒントを紹介します。
あらゆる楽曲を知っていると、例えば次のような利点があります:
・作曲家の作風の特徴が見えることで、結果的に今取り組んでいる作品の理解にもつながる
・音楽に詳しい人物と会話ができるようになる
・演奏会を聴きに行ったときに眠くならなくなる
・指導するときの引き出しになる
・知る過程で、思いがけない将来のレパートリー候補に出会うことがある
► A. 知識拡大の基本戦略
‣ 1. 作曲家と時期に焦点を当てた作品探索
未知の作品を探すときには、適当にあさってみるのも悪くはありません。一方、「作曲家を決めて、同じくらいの時期に作曲されたピアノ作品をまとめて聴いてみる」というやり方はおすすめできます。
例えば、「ドビュッシーの喜びの島が好き」と思ったのであれば、ドビュッシーの作品の中から「喜びの島」(1904年 作曲)に加えて:
・「スケッチブックから」1904年 作曲
・「仮面」1904年 作曲
などを聴いてみましょう。
ポイントは「まずは3曲」ということです。
「3曲」という量は、ある一定のまとまりとしては適量です。内容の傾向も見えてきますし、少な過ぎることもありません。「聴けば作品名は分かる」というくらいまでにはしておきましょう。
ここまで済んだら、ワンセット終了です。
聴いた作品を必ずメモし、一覧としてためておきましょう。
そうすることで、時間が経ってからの復習が容易ですし、「見える化」することでモチベーションの維持にもなります。
続いて:
・「次は、ドビュッシーの晩年のピアノ曲から3曲聴いてみようかな」
・「シューベルト、全然知らないから初期の作品から3曲聴いてみようかな」
などといった要領で、どんどんと知っている作品のネットワークを張り巡らせていきましょう。
‣ 2. ジャンルを通じた作曲家理解の深化
「その作曲家が生涯取り組んだジャンルに目をつける」のも有効です。
ここでいうジャンルとは:
・インテルメッツォ
・プレリュード
・エチュード
・ノクターン
・ワルツ
などをはじめとした、あらゆる応用楽式のことです。
例えば、フォーレは全13曲のノクターンを生涯の幅広い時期に渡って書き続けました。「ノクターン 第13番 Op.119」は、フォーレが作曲した最後のピアノ曲です。つまり、ノクターン全曲を聴くなり弾くなり調べるなりして学習すれば、一通りフォーレの生涯の変遷などを知ることができます。
全ジャンル全曲を端から見ようとして中途半端になったり挫折したりするよりはいい学習になります。
‣ 3. 作品番号と音楽性の同時学習法
知っている楽曲を増やしていく学習を楽しくする方法があります。
一人作曲家を決めたら、作品番号を目にしただけで作品名がスラスラ言えるようにドリルしてみましょう。
まずは有名な作品中心でOKです。これができるようになると、ある程度まとまった情報を手にした感覚がじかに得られるので、学習が楽しくなります。
例えば、以下のシューマンのピアノ曲の作品名を作品番号のみを頼りにスラスラ言えるでしょうか。右側の作品名が伏せ字になっていると思ってトライしてみてください。
メジャーどころを20作挙げます:
Op.1 → アベッグ変奏曲
Op.2 → パピヨン
Op.6 → ダヴィッド同盟舞曲集
Op.7 → トッカータ
Op.8 → アレグロ
Op.9 → 謝肉祭 4つの音符による面白い情景
Op.11→ ピアノソナタ 第1番
Op.12 → 幻想小曲集
Op.13 → 交響的練習曲
Op.14 → ピアノソナタ 第3番
Op.15 → 子供の情景
Op.16 → クライスレリアーナ
Op.17 → 幻想曲
Op.18 → アラベスク
Op.20 → フモレスケ
Op.21 → 8つのノヴェレッテ
Op.22 → ピアノソナタ 第2番
Op.26 → ウィーンの謝肉祭の道化
Op.68 → ユーゲントアルバム(子供のためのアルバム)
Op.82 → 森の情景
これをただ単に丸暗記するのではなく「作品番号ごと覚えてしまおう」という視点を持って作品を聴いていくと、“音楽の内容とともに” 自然と覚えることができます。あとはスラスラ言えるようにドリルするだけです。
いつも同じやり方では学習にも新鮮味がなくなってしまうので、こういった学習方法も取り入れてみてください。作品の音楽性と音楽知識とを両どりできる方法です。
► B. 学習技術とアプローチ
‣ 4. 作品番号を軽視しない
日頃取り組んでいる楽曲に作品番号がついている場合は、必ずその番号も調べて把握しておいてください。
なぜかというと、その作品が作曲家にとってどのような位置づけにあるかを把握できるからです。
中には、作品番号が必ずしも作曲された時系列に沿っていないこともあります。その場合は、作品番号の意図を調べることも含めて、その楽曲についての理解を深めてください。
推奨記事:【ピアノ】シューマンのピアノソナタにまつわる年代と番号の情報整理
作品番号を把握しておく利点は、将来その作曲家の他作品に数多く取り組んで曲数が増えてきたときに、特に効果を感じることでしょう。
生涯にわたって作風が変わらない作曲家は意外と少なく、作品番号を知っていると、概ね作風などの特徴が分かるものです。番号を耳にしただけでその作曲家と作品とのことをざっくり解説できるくらいになるのが理想です。
‣ 5. 系統的な音楽学習の方法
未知のピアノ音楽を知るために、1日1曲新しい作品を聴くか弾くかすることをおすすめしています。
テーマの作曲家を決めて聴いていくのが取り組みやすいやり方ですが、作品数も多く、結局何から手をつけていいか悩む場合もあるでしょう。
そんなときにおすすめしたいのが、「アルバムをまるっと聴いてしまう」というやり方。
以下の手順を踏んでみましょう:
手順1 作曲家縛りのアルバム音源を一つ用意する
手順2 その収録曲全曲の楽譜をIMSLPで用意する
手順3 楽譜を閲覧しながら、最低1日1曲聴いていく
手順4 全曲が大体分かったら、日常生活でそのアルバムを流しっぱなしにする
このやり方のいいところは、アルバム収録曲なので、多少のマニアックな作品はありつつもその作曲家の外すべきでない作品も知ることができるという点。
以下、もう少し詳細に解説していきます。
【手順1:作曲家縛りのアルバム音源を一つ用意する】
まずは、CDでもレコードでもサブスクでもいいので、作曲家縛りのアルバムを一つ用意しましょう。
例えば、「20世紀の偉大なるピアニストたち ヴラディーミル・ソフロニツキー」というCDアルバムには、ショパン縛りのディスク1とスクリャービン縛りのディスク2がセットになっています。仮に、「スクリャービンの楽曲に明るくないから、知っておきたい」という場合は、そのアルバムをはじから聴いていけばいいわけです。
ちなみに収録曲は、以下のようなラインナップです:
・ピアノソナタ 第3番 嬰ヘ短調 Op.23
・ピアノソナタ 第9番「黒ミサ」 変ホ短調 Op.68
・ピアノソナタ 第2番「幻想ソナタ」 嬰ト短調 Op.19 第1楽章のみ収録
・詩曲「焔に向かって」 Op.72
・2つの舞曲 Op.73
・24の前奏曲 Op.11-16 変ロ短調
・3つの前奏曲 Op.35-2 変ロ長調
・4つの前奏曲 Op.37-1 変ロ短調
・2つの詩曲 Op.32
・8つのエチュード Op.42-3 嬰ヘ長調
・ピアノソナタ 第4番 嬰ヘ長調 Op.30
4種類のピアノソナタは必ず知っておくべきです。その他の小品も、作品番号の浅い分かりやすいものから、ピアノソナタ 第9番「黒ミサ」よりも後に作曲されたものまで、魅力的な作品が集められています。
まずはこのようなアルバムを学習することで:
・その作曲家における外すべきではない作品が分かる
・大曲と小品をそれぞれ知ることができる
というメリットを享受しましょう。
【手順2:その収録曲全曲の楽譜をIMSLPで用意する】
ご存知の方も多いと思いますが、「国際楽譜ライブラリープロジェクト(IMSLP)」を活用することで、パブリックドメインになっている作品の楽譜を合法で無料閲覧することができます。
上記、①で用意したアルバムの収録曲の楽譜をすべて集めてください。
【手順3:楽譜を閲覧しながら、最低1日1曲聴いていく】
IMSLPで集めた楽譜を参照しながら、1日1曲聴いていきましょう。
IMSLPにある楽譜はPDFで手に入るので、iPadでGoodnotesのアプリにそれらのPDFを取り込んで、気づいたことを書き込みながら音源学習していくのがおすすめです。気になった部分は、実際にピアノで音を出して確認してみるといいでしょう。
もちろん、自分の学習のためだけに使うべきです。そして、「これは」と思える作品に出会ったら、実際の楽譜を購入してください。
【手順4:全曲が大体分かったら、日常生活でそのアルバムを流しっぱなしにする】
③までの過程でアルバムをひと通り学習したら、それを日常生活の中で流しっぱなしにしてください。何度か通し聴きしていると、全曲を「知っている楽曲」まで押し上げることができます。
はじめから流し聴きしてもいいのですが、ここまでの「楽譜を見ながら学習する過程」を通過していることで、より楽曲と親密になることができるでしょう。
このようなやり方で何枚かのアルバムを回していくと、知っている作品がどんどん増えていきます。
‣ 6. 全音ピアノピース一覧表の活用法
全音ピアノピースを買うと、裏面に「難易度付き楽曲一覧表」が収載されています。探している作品がピースで出ているかを確認したり難易度を確認したりするために活用していると思います。
一方、この一覧表は未知の作品を知るきっかけづくりにも使えるので、その視点でも活用してみてください。
具体的には、一覧表に載っている作品を1日1曲、はじから聴いていくのです。
全音ピアノピースには、ピアノ学習者は是非知っておくべき名曲ばかりがラインナップされているわけですが、本当の有名曲以外の作品は意外と知識から抜け落ちているはずです。少なくともこのシリーズに出てくるピアノ曲だけは全部知っている状態を目指して、コツコツと聴いていきましょう。
一覧表の楽曲を聴いていく利点は、楽譜を参考にしたい楽曲や弾きたい楽曲に出会ったら、その楽譜を1曲単位ですぐに手に入れられることです。
作品音源は「全音ピアノピースによる ピアノ名曲集」シリーズが販売されています。
► C. 音楽理解の深化
‣ 7. 周辺情報からの作品発見
様々な作品を譜読みしてみたり音源を聴いていく中で、どうしても自分の動ける範囲内で動くだけになってしまう傾向があります。
そこでやって欲しいのが、「少なくとも、関連内容で話題として出てきた楽曲は覚えるようにする」というやり方です。
以下のようなやり方に着目しましょう:
・今取り組んでいる作品の関連楽曲をすべてチェックする
・音楽書籍で出てきた作品をすべてチェックする
・音楽仲間との会話の中で出てきた作品をすべてチェックする
【今取り組んでいる作品の関連楽曲をすべてチェックする】
今取り組んでいる作品について調べていると、関連楽曲として別の楽曲の話題が出てくることもあります。例えば:
・モーツァルト「ピアノソナタ K.457」を調べていると、「幻想曲 K.475」の話題が出てくる
・モーツァルト「ピアノソナタ K.545」を調べていると、「ピアノソナタ K.547a」の話題が出てくる
後者の楽曲を知らなければ、即刻聴いてみて忘れないように引き出しへ入れましょう。この繰り返しで少しずつ知っている作品が増えていきます。
【音楽書籍で出てきた作品をすべてチェックする】
読んでいる音楽書籍で話題として出てきた作品をすべてチェックするのもおすすめです。
例えば、「楽式論 著:石桁真礼生 / 音楽之友社」で楽式の学習をしていると、解説の中でたくさんのピアノ曲が出てきます。その中でも楽式教材として深く解説されている作品は以下のものです:
(書籍での登場順)
・シューマン「幻想小曲集 飛翔 Op.12-2」
・ドビュッシー「子供の領分 より 2.象の子守歌」
・ベートーヴェン「ピアノソナタ 第8番 悲愴 Op.13 第3楽章」
・ベートーヴェン「ソナチネ Anh5(2) 第2楽章」
・モーツァルト「ピアノソナタ 変ロ長調 K.281 第3楽章」
・ウェーバー「舞踏への勧誘」
・クレメンティ「ソナチネ Op.36-1 第1楽章」
・クーラウ「ソナチネ Op.20-2 第1楽章」
・ベートーヴェン「ピアノソナタ 第1番 Op.2-1 第1楽章」
・ベートーヴェン「ピアノソナタ 第23番 熱情 Op.57 第1楽章」
・ブラームス「2つのラプソディ 第2番 Op.79-2」
・J.S.バッハ「平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第11番 フーガ」
・J.S.バッハ「平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第16番 フーガ」
・モーツァルト「ピアノソナタ イ長調 K.331 第1楽章」
・ベートーヴェン「エロイカ変奏曲」
・ベートーヴェン「ピアノソナタ 第29番 op.106 ハンマークラヴィーア 第1楽章」
・ベートーヴェン「ピアノソナタ 第23番 熱情 Op.57 第3楽章」
有名な作品ばかりですが、これらの他にもちょっと話題に出てきた作品すべてに目を光らせます。
あらゆる書籍の中で話題として出てくるあらゆる作品を決して見逃さずに自分の引き出しへ入れていくように心がけるといいでしょう。
【音楽仲間との会話の中で出てきた作品をすべてチェックする】
音楽仲間との会話の中で出てきた楽曲も知識を広げる材料です。会話の中で知らない作品が出てきたら、曲名を覚えておいて後ほど学習するようにしましょう。
筆者の知り合いで、知らない楽曲名や演奏家名を耳にする度に「えっ、何それ?」などといちいち反応していちいちメモを取り始める面白い人物がいます。意識高い系というわけではなく、本当に好きで楽しんでやっている感じが伝わってきます。
あからさまに表へ出す必要はありませんが、これくらい貪欲に吸収しようと思っていていいですし、筆者もそのように心がけています。
‣ 8. 3ランク易しい作品を、最低週2曲は譜読みする
初級のうちは目の前の1曲に取り組むだけでもかなり大変だと思います。一方、中級程度になってきたら「3ランク易しい作品を、最低週2曲は譜読みする」というのを目標にしてみましょう。
「3ランク易しい」選曲というのは例えば:
・全音ピアノピースでいう、ランクDに普段取り組んでいる方はランクAを
・ランクEに取り組んでいる方はBを
・ランクFに取り組んでいる方はCを
というような選曲の仕方のこと。
3ランクくらい易しい作品を使うことで、無理なく楽しみながら学習することができて、なおかつ、普段離れがちな「小品」という分野に手を出すことができる点が大きいでしょう。
あくまでざっくりとした目安なので、多少ランクのずれたものを選曲したり、全音ピアノピース以外の楽譜を使っても全く構いません。
譜読み力の向上に必要なのはトレーニング。知識的に知っている作品が多いというのは財産。
時間をかけてもなかなか弾けないような挑戦的な楽曲ばかりへ向かっていると、どうしても触れることのできる作品数がわずかになってしまいます。「3ランク易しい作品を、最低週2曲は譜読みする」というのを目標にしてみるのは多くの学習者にとって有益だと確信しています。
筆者自身も、このやり方で知っている作品数を大きく伸ばしました。
‣ 9. 日常生活に音楽を溶け込ませる工夫
ピアノを弾く知人の話をきいていると、日常生活で音楽を聴くことはあまりないという方が意外と多い印象です。楽器を弾いていないときまで音楽を聴きたくないわけではなく、家族に気を遣っているわけでもなく、ただ単に習慣がないだけという方がほとんどです。
弾く時間があまりなくても、流し聴きを上手く活用することで、知っている楽曲を圧倒的に増やすことができます。真正面から向かうと理解できないようなとっつきにくい作品と仲良くなることもできます。そして何よりも、日常が音楽であふれて幸福度が上がります。
筆者は、毎日大体4-5時間は音楽を流しっぱなしにしています。
中々楽器練習の時間がとれない方は、せめて、音楽の流しっぱなしを利用して生活を音楽で満たしてみてください。今までとはひと味異なる、さらに楽しい毎日になるはずです。
► D. 音楽学習の拡張戦略
‣ 10. 難解な作品への接近方法
とっつきにくい作品の分類は人によって異なるはずですが、多くの場合は「覚えにくい作品、分かりにくい作品」とも言い換えられるでしょう。
例えば、ドビュッシー「前奏曲集 第1巻」の中で人気の作品ベスト3となると:
・亜麻色の髪の乙女
・沈める寺
・ミンストレル
あたりになると思いますが、これらは、聴きやすさ分かりやすさランキングを作ってもベスト3に入る作品です。
つまり、「分かりにくさ」を何とかしなければ仲良くはなれないのです。もちろん、曲そのものを分かりやすく変えることはできないので、自分から楽曲側へ近寄っていく必要があります。
特にとっつきにくい作品へ接近するポイントは、一生懸命聴こうとしないで、何度も何度もループで聴き流すことです。具体的には、「YouTubeのループ再生機能を使って、家事の間などに聴き流す」のがいいでしょう。
YouTubeで「ピアニストが演奏している ”公式の” 音源」を見つけてください。余程マイナーな作品でない限り、すぐに見つかるはずです。それをYouTubeのループ再生機能を使って聴き流します。
真剣に聴く必要はありません。家事の時間などにBGMとして浴びるようにします。
これを数日継続すると、どうなると思いますか。
たとえ分かりにくい楽曲でも、記憶に残る部分が出てくるのです。例えば:
・この後、あの激しい部分が来るぞ
・ここからはすごく高い音が出てくるはず
などと、「歌える」まではいかなくても自分の頭と音楽が結びつきます。こうなれば占めたもの。もう十分に「知っている楽曲」認定と言えるでしょう。その後は:
・楽譜を眺めるなり
・実際に弾いてみるなり
・このまま聴く専門でいくなり
自由に付き合っていけばOKです。
「知っている」というのは大きいことだと認識しましょう。「よく知らない、分かりにくい作品」を、「分かりにくいけど、何となく分かってきた作品」まで持っていく。そうすると、同じ「分かりにくい曲」へも愛着が出てきます。演奏会で聴いても飽きません。
とっつきにくい作品は「スルメ」なので、ある程度まで近寄ったらジワジワ長く付き合っていけば、ジワジワ良さが分かってきます。
‣ 11. 必聴のピアノ曲セレクション
筆者が学生だった頃に、作曲の先生に薦められて影響を受けた作品も含め、作曲の観点から判断して非常に良くできている作品のみを取り上げています。
本項目はリスト表だけの紹介に留めます:
・J.S.バッハ : 2声のインヴェンション、平均律クラヴィーア曲集
・ベートーヴェン : ピアノソナタ(初期、後期)
・シューベルト : ピアノソナタ 第21番 D 960
・シューマン : クライスレリアーナ Op.16
・ブラームス : 3つの間奏曲 Op.117
・ドビュッシー : 前奏曲集 第1巻 / 第2巻 を中心に、ピアノ曲全曲
・ベルク : ピアノソナタ Op.1
・シェーンベルク : 6つの小さなピアノ曲 Op.19
・ヴェーベルン : ピアノのための変奏曲 Op.27
・武満徹 : ピアノ曲全曲
まずは聴き流しでも良いので、これらの楽曲を日常生活の一部に取り入れてみて欲しいと思います。これらのような内容が深い作品をよく知っておくと、クラシック音楽に対する見方が変わってくることでしょう。
‣ 12. 作曲家の多角的理解法
今取り組んでいる作品の作曲家が作った「ピアノ曲以外」も聴いてみることは、取り組んでいる作品への理解を深める意味でも非常に有効な勉強方法です。しかし、「作品の種類があり過ぎて何を聴いたらいいか分からない」 という方もいるはずです。
選曲方法を3パターン紹介しておきましょう:
・まずは弦楽四重奏から
・今取り組んでいるピアノ曲と同時期に書かれた作品もチェック
・余裕が出てきたら作曲家の作品を「時代別」にたどっていく
【まずは弦楽四重奏から】
まずは「弦楽四重奏」を聴いてみることをおすすめします。
ほとんどの作曲家は弦楽四重奏を残しており、この編成では、その名の通りほとんどの箇所が「四つの声部」で書かれているので、ピアノ曲のときと近い感覚で聴くことができます。
選曲のポイントは、作品番号が若い作品から聴いてみることです。
作曲家によっては、作品番号が若いからといって必ずしも早い時期に書かれた作品になっているというわけではありません。しかし、全体的な傾向としては、「作品番号が若い作品のほうが聴きやすい」という特徴があります。例えば、ベートーヴェンの「初期ピアノソナタ」と「後期の31番、32番」あたりを思い出してみても、同様のことが言えるでしょう。
【今取り組んでいるピアノ曲と同時期に書かれた作品もチェック】
次第に弦楽四重奏以外にも目を向けて、「今取り組んでいるピアノ作品と同時期に書かれた、ピアノ曲以外の作品」もチェックしましょう。
「作品番号が若い作品から聴いてみる」のは、あくまで聴くべき楽曲が全く決まっていない場合のことです。今取り組んでいるピアノ作品と同時期に書かれた作品を探っていく場合には、後期の作品をみても構いません。例えば:
・ショパン「ポロネーズ 第7番 幻想 Op.61」(1845年 作曲)を練習しているのであれば
・「チェロソナタ Op.65」(1845年 作曲)を聴いてみる
などといった方法を試してみましょう。
【余裕が出てきたら作曲家の作品を「時代別」にたどっていく】
余裕が出てきたらで構いませんが、ピアノ曲も含め作曲家のあらゆる作品を「時代別」にたどっていくと、その作曲家のことがよく分かってきます。
例えば、日本の作曲家「武満徹(1930-1996)」は:
・作品を発表し始めた50年代の作風
・国際的に有名になった60年代の先鋭的な作風
・70年代末あたりからの作風
それぞれが大きく異なっています。
それぞれの時代の作品をたどっていくと、作風が異なるとは言えども、共通点も多く発見できます。こういったことは、作曲家の作品を時代別に見ていくことではじめて知ることができるものです。
知っている曲数を増やすことができる点でも有益な学習と言えるでしょう。
► 終わりに
知っている作品数を圧倒的に増やす学習は、ピアノへ向かえる時間が限られている方であっても実践できます。実技とのバランスをとりながら、自身の学習へ取り入れてみましょう。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
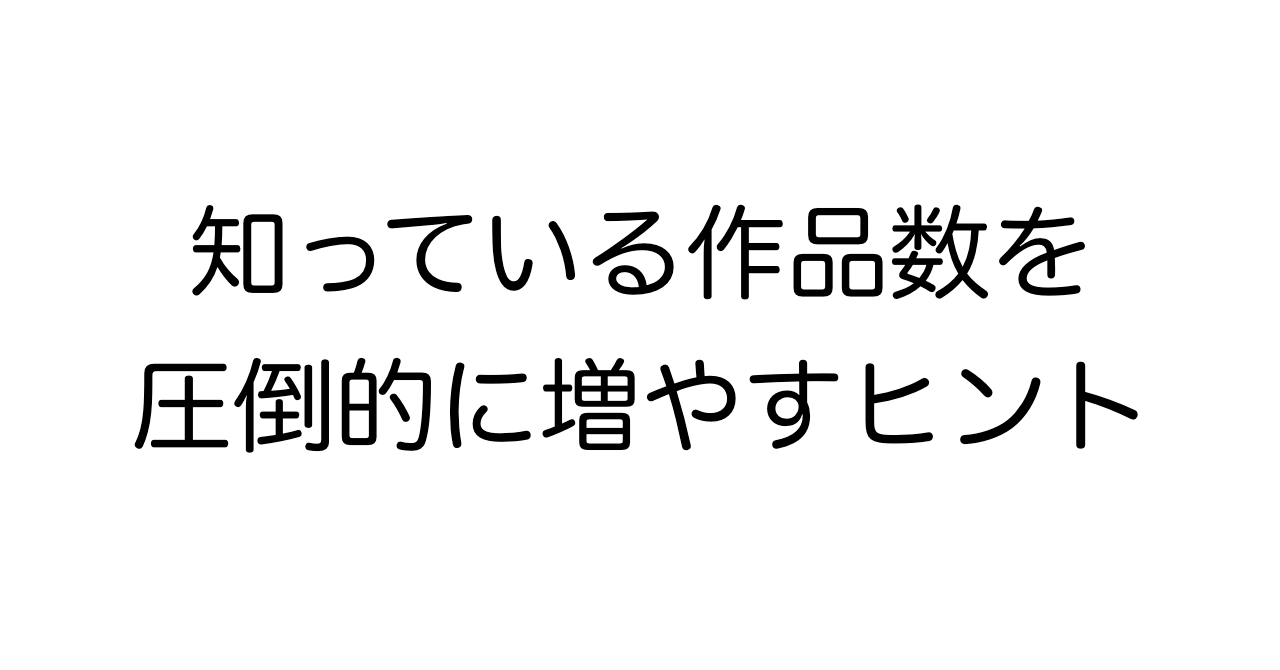


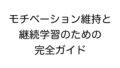
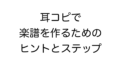
コメント