【ピアノ】ソナタ形式学習のための5つの実践ポイント
► はじめに
ソナタ形式の学習ポイントを、実践的な視点から5つのポイントに分けて解説します。これらの要点を押さえることで、より深い演奏表現へとつながる学習をすることができます。
► 5つのポイント
‣ 1. 似ているけれども異なっているところを調べる
例えば、ロンド形式では「Aのセクション」が何度も出てきますが、ソナタ形式でも「セクションの分かりやすい繰り返し」があります。それはもちろん、「提示部に対する、再現部」です。
再現部は「一種の繰り返し」ですが、ほとんどの場合は提示部に「変更」が加えられています。そこで、「どこが同じで、どこが似ているけど異なっているのか」を譜読みの段階から丁寧に整理しておくことが欠かせません。
暗譜の際に特に重要です。ソナタ形式の楽曲で暗譜が飛んでしまうケースの多くが、「再現部で提示部と同じことを弾いてしまって、それ以降が分からなくなってしまう」という理由によるものです。
ベートーヴェン「ピアノソナタ 第18番 変ホ長調 Op.31-3 第1楽章」
譜例(PD楽曲、Finaleで作成)

「再現部の167小節目」に注意(譜例右)。うっかり手癖で「提示部の31小節目」(譜例左)と同じように弾いてしまうと、提示部に戻ってしまいます。矢印で示した箇所が、「違う方向」にそれ始めるポイントです。
暗譜で苦戦する箇所の定番は、似ているけど少し異なっている箇所。ここを丁寧に整理することで、確実な暗譜が可能になります。
‣ 2. ソナタを全楽章学ぶべき理由
多楽章制のソナタから一つの楽章だけを抜き出して学ぶケースは多く見られます。もちろんそれでも構いませんが、もし他の楽章にも挑戦できるくらいの力がついてきた場合には、「全楽章」を練習してみましょう。
ソナタにおける各楽章は意図を持って位置付けられています。例えば、ソナタ形式である悲愴ソナタの第1楽章は、規模的にも性格的にも、明らかに他の楽章との「対比」が意図されています。
また、少し踏み込んだ話をすると、「ハ短調」の第1楽章が他の楽章とどのような調性関係になっているのかを考えて調べることも、作品を理解するうえで欠かせません。
作品によっては、第1楽章で出てきたテーマが第3楽章で再登場したりと、分かりやすい形で関連しているものもあります。
全楽章を学ぶことで各楽章同士の関連性が分かり、その結果、演奏解釈などの表現面にまで影響が及びます。
‣ 3. 他の楽章の特徴を調べる
仮に全楽章に取り組まない場合でも、他の楽章の特徴を調べることはしておきましょう。
特に「ハイドン以降」のソナタの場合、形式、テンポ、調性、拍子、素材など、様々な点で楽章同士のバランスがとられています。他の楽章の特徴を調べることで、演奏する楽章の特徴もより浮き彫りになってきます。
簡単なところで言えば、「このソナタは第2楽章がレッジェーロで第3楽章がプレストだから、第1楽章はテンポを速くし過ぎないほうがバランスがいいかな」などと、全体のバランスを考えていくきっかけになります。
‣ 4. ソナタ全体を考慮したテンポ設定
ピアノソナタなどの多楽章による楽曲を弾く場合、単独の楽曲を弾くのとは違った注意点も出てきます。
各楽章間の性格の違いを読み取ったうえで、それぞれをどう表現するのか。「音色」「アーティキュレーション」など、キャラクター表現一つとっても様々な視点がありますが、最も基本的かつ注意すべきものは、テンポ設定です。
多くの古典派のソナタにおける第1楽章と最終楽章のように、急速な楽章は大抵複数含まれています。まずは、これら同士のテンポの違いを調べてください。
前項目でも触れましたが、仮にその時は第1楽章しか学習しないとしても、いったん他楽章の楽譜を眺めてそれぞれのテンポについて調べてみることで、第1楽章のテンポを決める参考にもしていくのがおすすめです。
テクニック面でのテンポのコントロールについては、以下のような傾向に注意しましょう:
・緩徐楽章は、音は弾けてしまうので速くなりがち
・急速楽章は、弾くのが忙しくて遅くなりがち
このように両端が圧縮されてしまう場合、全楽章の視点で捉えるとテンポ表現が平坦に聴こえてしまうので注意しましょう。
フレーズごとのニュアンスが「木」だとしたら、一つの楽章は「森」。全楽章で「地域」でしょうか。「地域」の特徴を知ったうえで、「木」を育む。そうすることで、その地域に根ざす「森」が出来上がります。そんなイメージを持ってみましょう。
ソナタはトータル演出をすべき音楽です。
‣ 5. 一番のヤマが展開部にあるとは限らない
ピアノ演奏において「クライマックスの活かし方」には注意しましょう。「一番のヤマ」がどこなのかに気をつけて演奏しないと、ヤマがいくつもできてしまいます。
展開部というのは、提示部で出てきた重要な素材の展開を主としていますが、必ずしも楽曲(楽章)の一番のヤマがくるとは限らないのです。展開部よりも「再現部の(後の)終結部分」に音楽的、音量的な頂点がくる楽曲も多くあります。
関連して、ダイナミクス面での演奏ポイントにも触れておきましょう。
f(フォルテ)を見たときにすぐにマックスにならないことが重要です。「f よりも上のダイナミクス領域」というのはまだまだあります。sf などの各種アクセントがつくこともあれば、ff、fff など、時代によってはさらにダイナミクスの指示に幅があります。
► 終わりに
独学をしていくうえで、これらのポイントを頭の片隅に入れておくことで、確実に演奏の質が向上していくはずです。楽譜の一つ一つの要素を丁寧に読み取っていきましょう。
ソナタ形式そのものについて学びたい方は、以下の電子書籍を参考にしてください。
・大人のための独学用Kindleピアノ教室 はじめてのソナタ形式 – 名曲の中に見つける音楽の魅力
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
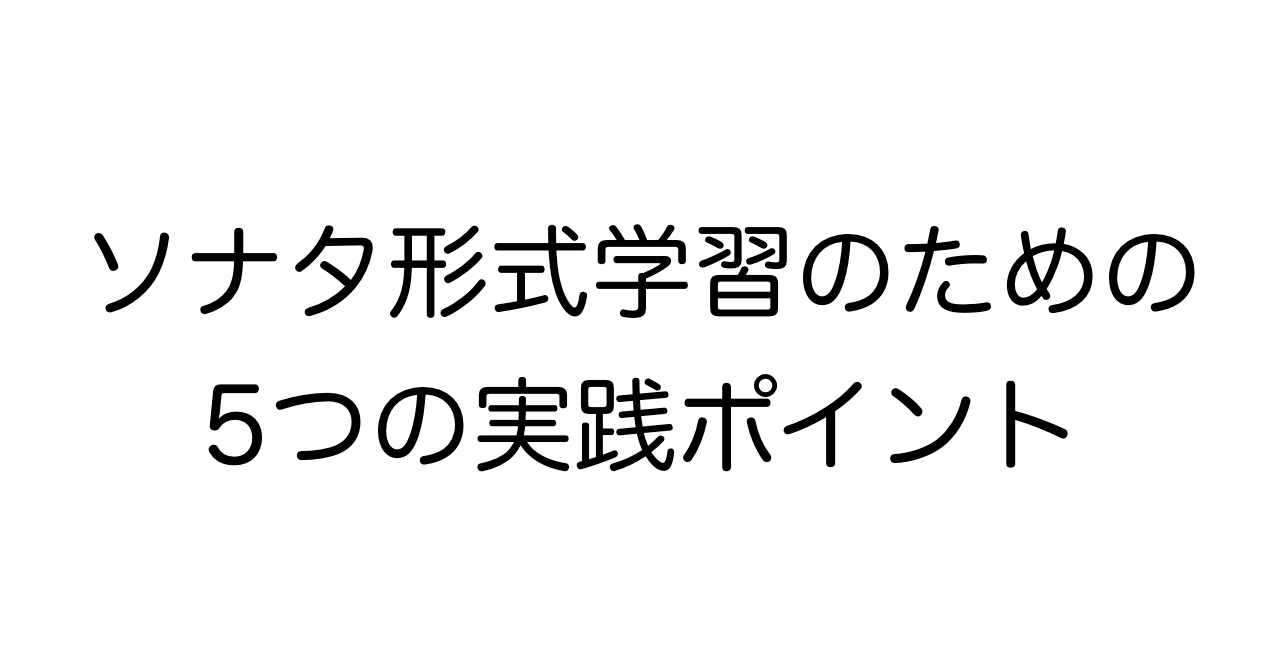


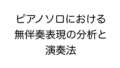
コメント