【ピアノ】人とつながり、音楽生活をもっと楽しむヒント
► はじめに
ピアノは基本的には、一人で練習し、一人で向き合う楽器です。しかし、音楽の真の魅力は、人とのつながりの中にこそあると考えています。
本記事では、ピアノ学習者が音楽生活をより豊かにするためのヒントと、筆者なりの人との関わり方のコツをお伝えします。一人モードから脱却し、音楽生活をもっと楽しくしましょう。
► A. 音楽生活のコミュニケーション方法
‣ 1. ピアノ弾きこそ、人と関わろう
ピアノを弾いていると、弾き合いのような集まりやアンサンブルに参加しない限り、一人で音楽をやることが中心となります。音楽学校でも、作曲科とピアノ科は特に一人で何かを黙々とやるような方向へ偏りがちです。
趣味、本格派関わらず、一人で音楽へ向き合う時間も大切なのですが、ピアノ弾きや創作をする方こそ外へ出ていって今よりも積極的に人と関わるようにしてみて欲しいと思います。
音楽をやっていない人物と関わるのでも全く問題ありません。
筆者は学部から大学院まで音大へ行っていましたが、その期間の唯一の後悔は、演奏科の友人をほとんど作らなかったことです。作品を演奏してもらうときに少々関わりがあった程度で、本当に自分だけの世界になっていて卒業&修了してしまいました。
学生ではなくなって数年経ったとき、プロジェクトの折にゴダイゴのとあるメンバーさんから「タカノ君の創作スタイルは、すべて自分の内側へ向いているね」と指摘されて妙に納得してしまったのを覚えています。それからは、いわゆるピアニストではなくともできる限りピアノを弾いて、アンサンブルでの作品づくりに内側からも関わるようにしました。外側からだけ関わっていたときには決して生まれなかった種のコミュニケーションも、たくさん経験できました。
2023年の年末に「なんかこの1年は、ここ数年で一番いい年だったな」などと思っていたのですが、どうしてなのかを考えてみると、2023年は一番、良い人との出逢いがあったのです。その中には、音楽とは関係なく知り合った方もいました。しかし、何となく出逢いがやってきたのではなくて、自分から人との接触を大切にしたのは事実です。
他者と関わったことで面倒臭いことに巻き込まれたりしましたし、切ない経験もしましたが、それ以上に幸福度が上がりました。
とにかく、一人で完結することの多いスタイルでの音楽をやっている方こそ、今よりも積極的に人と関わるようにしてみてください。毎日が幸せになります。
‣ 2. 気になっている人物へどんどん話しかけてみよう
音楽仲間を増やすコツは、とにかく、自分から話しかけることです。音楽をやっていない方と交流するのもいいでしょう。
以前から友人などによく言われるのですが、筆者は、色々な店へ行くとやたらに店員さんと話したり、近所さんからモノをもらったりするらしいのです。自分ではそれほど意識していなかったのですが、その頻度は東京在住にしては多いようです。
我々は社会的な生き物なので、たとえ一人の時間を大切にする人でも、結局は、どこかで人と触れ合いたいのでしょう。
筆者は決して常に付き合ってる友人が多いわけではありませんが、親しくしている方とは結構深く付き合っている気がします。思い返してみると、確かに、自分から話しかけたことがきっかけで交流が始まった方が多い印象です。
‣ 3. 職場の音楽好きへの近づき方
職場には音楽好きの情報がたっている人物もいるのではないでしょうか。趣味が合いそうなので話をしてみたいと思っても、どうすればいいのか分からないという場合もあるはずです。
筆者は音楽学校で教えている関係上、「職場の音楽好き」というよりは、当然ですが同僚(の先生方)はみんな音楽をやっている方で、スタッフの方も音楽に詳しい方ばかりです。しかし、その中でも気の合いそうな方にはみずから積極的に話しにいったものです。
「職場で友人はできない」と言われることもあるくらいですし、利害関係のある職場で話題を共有することにはハードルがあります。一方、話を共有したいわずかな相手に近づきたい場合はどうすればいいのでしょうか。
筆者のおすすめのやり方は、「少しだけ自己開示して、相手の反応をみる」というやり方です。
職場では、思いの他、ふとした瞬間に該当の人物と話す時間ができたりします:
・出勤時、退勤時のエントランス
・エレベーターの中
・廊下
そのときに、少しだけ自己開示してみてください。相手の反応が悪くなかったら、また別の機会にでもいいので話したい話題をふる。反応がイマイチだったら相手の職場におけるスタンスを理解し、引っ込める。引っ込む。
ポイントは:
・その人が(向こうの)上司と一緒にいないとき
・その人のそばに(向こうの)上司がいないとき
に話しかけることです。理由は言うまでもありませんね。
職場では困りごとがつきものなので、積極的に力を貸して仕事上のコンタクトを一回できていたりすると、自己開示の際に話しかけるハードルは下がるでしょう。
この繰り返しで、たとえ職場の中であっても気の合う音楽好きと友人になれる日がきます。
筆者は、退職した前の音楽学校の元同僚でもいまだに付き合いのある方はいますが、大抵は自分から話しかけにいって交流するようになった方達です。
このやり方に大したリスクはないので、是非お試しください。
► B. 音楽的成長のための人間関係
‣ 4. 長く付き合える音楽仲間を見つけるために
音楽をやっていて良かったと思うことの一つが、良い友人ができて幸福度が数割増しになったことです。
筆者が考える、長く付き合える音楽仲間を見つけるコツは、とにかく、積極的にアンサンブルへ参加することです。
当たり前のことのように感じるかもしれませんが、ソロばかりやっていてたまに会話するくらいだと、大人になってから仲良くなるのは結構ハードルがあります。しかし、デュオや3人以上のアンサンブルだと、文字通り、2人以上いないとできません。一緒に演奏して仕上げていく過程で、ソロで弾き合っているだけでは決してできないコミュニケーションをとることになります。この充実感が仲を深めます。
作曲や編曲をする方は、そのアンサンブル作品を演奏してもらって自分はリハーサルや本番に立ち合うといったように、外からアンサンブルに関わってもいいでしょう。しかし大切なのは、「投げっぱなしにしないでコミュニケーションをとる」ということです。
筆者は、演奏で中から関わるよりも創作で外から関わることのほうが多いのですが、それでも、アンサンブルに参加する良さを感じたり、音楽仲間と関係を築くことができます。
今の時代、ピアノを弾いている読者さんがアンサンブルに参加する機会はインターネットで探せばいくらでも見つかりますし、レベルも様々なものがありますので、今の実力に関係なく挑戦することができます。
習いに行っている方は、演奏発表会の時にソロだけでなくアンサンブルもやらせてもらえるよう頼むのもいいでしょう。
‣ 5. 学び合う喜び:教え合いから得られる成長
一部の音大では、選択科目で「ピアノの教え方」に関するクラスもあります。例えば、次のようなことをやります:
・学生同士でペアを作り、生徒役と指導者役に分かれる
・その2人が模擬レッスンをしている様子を見て、授業の担当教員による指導が入ったり
・見ている他の授業履修者に意見を言ってもらったりする
・これを、様々なペアで回していく
ただ単に改善すべきところを探すのではなく、良い点を評価したり、「どうしてそこはそのようにしようと思ったのですか?」などと素朴な疑問を投げかけてもOKです。
これが、特に指導者役にとって想像以上に勉強になるのです。例えば:
・普段一人で弾いていても気づきにくいことを、客観的な視点から把握できて
・自分の練習へ活かせることにたくさん気づける
・指摘したいけど言葉にできない部分が浮き彫りになったり
・生徒役からの質問に答えられなくて汗かいて
・自分にとって足りていない部分にも気づける
・言ってもなかなか改善してもらえなかったりして
・学習者がプライドを持っていることも分かる
主には「教え方のクラス」でとられているこの方法、レベルアップのための学習方法としても取り入れてみるべきでしょう。
教え合うのですから、まずは「力が同じくらいの友人」とやってみましょう。お互いの力があまりにも離れていると、無意識に一方が他方の意見を軽視してしまう可能性が高くなるからです。
音大生は授業の外の日常でも、この学習方法を頻繁に取り入れています。時々、希望していないのに偉そうに口を出されてマウンティングのようになり、それがストレスとなるケースもあるようですが…。
ただ、我々の日常では「練習室で練習していたら、いきなり友人が入ってくる」なんてことはありませんし、お互いが了解しあったうえでこの学習方法を取り入れられるわけです。
是非、積極的に活用してみましょう。
‣ 6. みんなで楽しくレベルアップするには、机を囲んで騒ぐに限る
指導に行っている音楽学校での筆者のクラスでは、数人でピアノや机を囲みながらひたすら一つの作品について分析し意見を出し合うスタイルで進めることがあります。意見を出し合うゼミ形式のやり方なのですが、これは筆者が大学院のときに経験してとても良い方法だと思ったものです。
研究段階までいかなくても学習方法として優れたやり方であり、「みんなで楽しくレベルアップするには、机を囲んで騒ぐに限る」とさえ考えています。
・疑問に思わなかったところでも、他者の話を聞いていると自分の考えの甘さを認識したり
・疑問に思ったところは、他者の意見で解決できたり
・みんなで分かりかけていたことは、ディスカッションによってさらに理解が深まったり
などと、とにかく利点が多い方法です。
ピアノの上達のためには、一人で楽器へ向き合う時間が必要です。一方、楽曲分析やピアノ音楽史の学習などの場合は、音楽仲間と一緒になってこのやり方を取り入れてみてください。
「みんなで」というのは、楽しく続けていくためには欠かせません。
► C. 音楽生活におけるマナーと心得
‣ 7. 音楽人生を彩る、付き合う相手の選び方
プロアマ問わず、積極的に音楽を続けている限り、たくさんの音楽をやっている人物に出会います。気が合う人、合わない人など、様々な人物と接点を持つことになります。
付き合う音楽仲間について筆者が決めていることがあります。
いたってシンプルで、「暗い人とは付き合わない」ということ。
暗いのは、とにかく伝染して幸福度が下がります。例えば:
・全部良くない方向に考えて口を開く人
・気持ちよくあいさつしても、かったるそうな感じで返してくる人
・目が合った瞬間に視線を下に落とす人
こういった人とは、付き合わないほうが得策です。
これは通常の付き合いでもほぼ同じですが、特に音楽をやっているときは、気持ちに余裕があったり幸福度が高くないと良い音楽ができません。このことに気づいてからは、暗い人から全力をあげて逃げるのを第一優先にしています。
‣ 8. 聴く側の心得:相互理解の音楽作法
ちょっとしたピアノ弾きの集まりで演奏したことはあるでしょうか。
「自分の演奏中に他の人達が会話を始めてしまって残念だった」
このような経験をしたことがある方もゼロではないはずです。特に、ティータイムなどの軽めの趣旨の集まりだとなおさら起こり得るでしょう。
筆者のまわりでも、度々、このような話題は挙がります。
・「なんで、自分の演奏を聴いてくれないのか」
・「自分のピアニッシモより、カップを置く音のほうが大きいの許せない」
・「多少ガタガタなのはお互い様じゃないか」
などとカンカンになりたくなるのも分かりますが、まず、「自分は相手の演奏をきちんと聴いているのか」を振り返ってみてください。
これは対策でも何でもありません。きちんと聴いていたって、自分の番でガサガサされてしまうことはあります。しかし、自分がやられて顔が曇りそうになることは相手にやらないようにすると、自分だけでも、ちょっと明るく幸せになります。
嫌なら離れることもできるのですから、とにかく、やられたからってやり返さないようにしましょう。そうすることで、短期的には頭に来ても中長期では幸福度が高くなります。
‣ 9. 共演者とのケンカは電話でしよう
共演者などとちょっとした言い合いになったりすることもあるでしょう。
そんなときにトラブルを大きくしないコツは、「音楽に関するものだからこそ、メールではなく電話でケンカすべき」ということです。
随分前のことですが、筆者の知り合いのピアニストが楽器奏者と共演後にケンカして、ひたすらずっとずっとメールで言い合っていたのです。
メールは直接的に冷たく響くので普通のケンカでもやめたほうがいいのに、ましてや、音楽の内容が含まれていただけあって、文字だけだと余計な誤解を生むことは目に見えています。余計にこじらせている原因は「お互いにメールへ逃げていること」だと思いました。
普段は余計な口は出さないようにしていますが、このときばかりは「メールで言い合っているからこじれるのであって、電話で話すべき」と伝えて実行してもらいました。結局仲直りにはならなかったようですが、それ以上メールでバトルすることもなかったようです。
繰り返しますが、特に音楽的な内容を含むもめ事の場合は、文字による言い合いだけはやめたほうが得策です。せめて、自分の言い分だけでも音声メールで投げてください。
► D. 感情と音楽の関係
‣ 10. なぜ、コンクールや片思い成就に期待し過ぎてはいけないのか
コンクールというのは片思いとよく似ていて、期待し過ぎてはいけないものです。
理由はシンプルで、どちらも、結果を自分の意思ではコントロールできないからです。結果を良くするために色々な努力はできますが、最終的な結果は自分では決められません。それに向けて努力するのは当然でも、上手くいかないのがデフォルトくらいで思っていないと、結果が微妙だったときに傷つきます。
よく「自己肯定感」という言葉を耳にしますが、他人に決められた結果で自己肯定感を下げるのは、本当に避けたほうがいいでしょう。
筆者もコンクールや片思いは経験してきましたが、過度な期待をせずに上手くいったらラッキーくらいで考えていました。
‣ 11. 好きな人がいると良い音が出るという話は、実際どうなのか
「好きな人がいると良い音が出る」という話をよく耳にしますが、実際はどうなのでしょうか。
正直、こういうのは一種の自己啓発で「気は心」と言えなくもありませんが、影響はあると感じています。
例えば、演奏で好きな人に何かを伝えようと思っているとしましょう。
演奏の前提として、音を出す前に頭の中で欲しい音を鳴らし、そのイメージがあるからこそ、そうするための発音動作が勝手に決まります。つまり、何かを伝えようという気持ちで演奏すると、あまり意識をしていなくてもイメージする音色や打鍵の仕方に心がこもり、発音動作に勝手に影響が出ているはずです。
次に、作曲や編曲で好きな人に何かを伝えようと思っている場合。
クラシック音楽の素晴らしさはさておき、楽譜さえ買えば誰にでも演奏できるものを使うのではなく、一つの機会のために一つの作品を生み出そうとすると、自分なりにできる限りピュアな音を選びますし、良い音になる可能性は上がるはずです。
結論、これぐらいのことしか分かりません。気は心の世界なので。
ただし、「良い音が出る」ということとは少し離れてしまいますが、好きな人がいることで音楽に好影響を及ぼすのは、筆者自身、体感したことがあります。例えば:
・「自分は今、こういう想いで音楽に向かっているな」
・「この期間、何だか学習に気合いが入っているな」
などというように、自分のやっていることを客観的に見られるようになると、随分と楽しくなったりします。そう感じながら毎日を過ごすことで、自分の生活の質が上がり、音楽に好影響を及ぼすわけです。
‣ 12. 好きな人に音楽で気持ちを伝えるコツ
今回取り上げる、好きな人に音楽で気持ちを伝えるコツは演奏方法に関してではありません。
やり方はシンプルです。
たどたどしくてもいいので、自分で音を編んで演奏する楽曲をこしらえてください。つまり、弾きたい曲をピアノアレンジするということ。作曲できるのであれば、それでも構いません。
自分で作曲や編曲をしたものの場合、たとえそのクオリティがまだだったとしても、世の中にありふれたようなものだったとしても、作った人しか持っていないレパートリーになります。この価値はすごく大きいと思ってください。
特別感が必要なのかというと、必ずしも聴いている人がそこまで分からなくてもいいのです。
前項目でも書いたように、楽譜さえ買えば誰にでも演奏できるものを使うのではなく、一つの機会のために一つの作品を生み出そうとすると、自分なりにできる限りピュアな音を選びます。また、演奏にも気合いが入って、相手に伝わる可能性が高くなるはずです。
そして、気持ちを伝えたい人を想いながら音を選ぶ過程まで含めて楽しんでください。そうすることで、仮にうまく気持ちが伝わらなくても自分にとって意味のない期間にはならないので。
力が湧き出るような、充実した期間になるとベストです。
‣ 13. 楽しい弾き合いの極意
楽器がある場所に知人といると、「弾き合いをしよう」という話になることがあるでしょう。
これが苦手な方も多いのではないかと思います。ただし、大きな本番に先がけて少人数の前で弾く機会を踏んでおくのは悪いことではありません。
簡潔に言うと、楽しく弾いて経験になればいいわけです。
楽しく弾き合うポイントがあります。
原則、他人に自分の演奏を録音させないでください。また、このときだけは自分の演奏を自分で録音するのも我慢してください。
自分の知らないうちにこっそり録音されているかと思うと楽しめません。それが、準備して迎えた本番や弾き合いならともかく、いきなり弾くことになった場合であればなおさらです。
「そのときに出てきた演奏を、その場一回限りで楽しむ」
このように考えるだけで、ずっと楽しく過ごすことができます。
筆者はどちらかというと気が強いほうなので、「お互いに録音はよしましょう。」などと言えますが、もしそれができなければ、録音に残るのが苦手だということをさりげなく伝えてください。遠回しに匂わせるだけで、相手はその行為をやめます。
► 終わりに
本記事で紹介したヒントは、音楽生活をより豊かにし、人間関係を深めるきっかけになるはずです。
大切なのは、一歩を踏み出す勇気と、オープンマインドを持つことです。音楽を通じて、新しい出会いと喜びを見つけてください。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
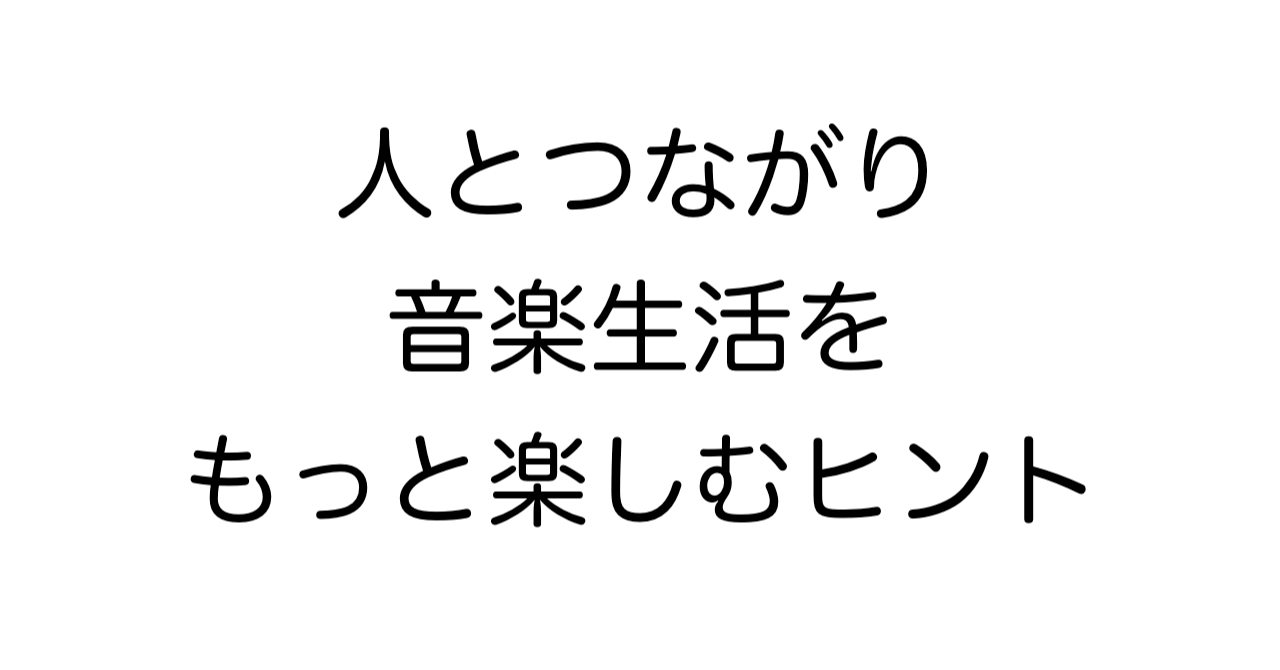
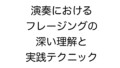
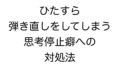
コメント