【ピアノ】映画「戦場のピアニスト」レビュー:ショパンの楽曲が果たす心理描写の役割
► はじめに
映画「戦場のピアニスト(The Pianist)」は、ピアノという楽器を通して描かれる人間の尊厳と希望の物語であり、音楽が人の心に与える力を深く掘り下げた一作です。実在のピアニスト、ウワディスワフ・シュピルマンの回想録を基にした本映画では、音楽が主人公の内面や状況を雄弁に語る「言語」として機能しています。
本記事では、劇中で使用される音楽を分析し、シュピルマンの音楽への想いがどのように表現されているかを探ります。
・公開年:2002年(フランス)/ 2003年(日本)
・監督:ロマン・ポランスキー
・ピアノ関連度:★★★★☆
► 内容について(ネタバレあり)
以下では、映画の具体的なシーンや楽曲の使われ方について解説しています。未視聴の方はご注意ください。
‣ シュピルマンによる強い気持ちが現れた状況内外音楽
音楽用語解説:
状況内音楽
ストーリー内で実際にその場で流れている音楽。 例:ラジオから流れる音楽、誰かの演奏
状況外音楽
外的につけられた通常のBGMで、登場人物には聴こえていない音楽
状況内音楽・状況外音楽より、戦時中のシュピルマンによるピアノへの強い想いが表現されている部分を見てみましょう。
· 1. CAFE CAPRIでの演奏
シュピルマンがCAFE CAPRIでピアノを演奏するシーンは、彼の音楽家としてのアイデンティティが鮮明に現れる場面の一つです。
当初は店内BGMとしてイージーリスニング系の軽い音楽を演奏していましたが、途中から自然にショパン「ピアノ協奏曲第1番 第1楽章」の美しい旋律へと変化します。この変化は、ドイツ軍の攻撃により演奏活動の中断を余儀なくされたシュピルマンの、ショパンを演奏したいという抑えきれない渇望の表れと解釈できます。
同時に、この楽曲選択は映画全体を通じて重要な役割を果たすショパンの作品群との関連音楽としても機能しており、ストーリー全体に音楽的統一感をもたらす演出でもあります。
· 2. 隠れ家でのピアノを前にした無音演奏
ドロタとその夫ミルカが提供した隠れ家で、シュピルマンがアップライトピアノの前で無音で演奏する真似をするシーン。
実際には音を出せない状況下で、観客にはショパン「華麗なる大ポロネーズ」のオーケストラとピアノが聴こえます。これは明確に「シュピルマンの心の中で鳴っている状況外音楽」であり、過去の演奏会への想いというよりは、戦後の希望に満ちた未来への憧れを表現していると考えられます。
注目すべきは、「音楽への不屈の希望」が叶い、エンディングで実際のオーケストラとこの楽曲を演奏することです。だからこそ、長調の楽曲が選ばれたのでしょう。
· 3. 廃墟病院での空中鍵盤
廃墟と化した病院に隠れているシーンでは、ピアノすらない状況で、シュピルマンが空中でピアノを弾く真似をします。
この時に流れるのはショパン「バラード 第1番」で、やはり、「シュピルマンの心の中で鳴っている状況外音楽」。飢餓状態で、身なりも汚れ果て、いつ発見されて射殺されるかもしれない極限状況において見せるこの行動は、「どんな状況でも失われない音楽への愛」を象徴しています。だからこそ、あえて短調の楽曲が選ばれたところに、上記「華麗なる大ポロネーズ」が使われる状況との差を感じます。
そしてこの楽曲は、後にドイツ軍将校ホーゼンフェルトの前で実際に演奏される楽曲でもあります。心の中の音楽が現実の音楽となり、シュピルマンの命を救う瞬間へと繋がる、感動的な伏線となっています。
‣「耳鳴り」という特殊な状況内音声
ドロタとミルカが提供した隠れ家から逃げる場面でシュピルマンが経験する「耳鳴り」は、興味深い音響表現です。
これは実際にシュピルマンに聞こえている音であるため、上述の「心の中の音楽(状況外音楽)」とは異なり「状況内音声」として分類されます。この耳鳴りは、音楽ではないものの、音による心理描写の例として着目すべきでしょう。
‣ 戦争下における音楽環境の変化
この映画が描く重要なテーマの一つは、戦争が音楽環境に与える影響です。
映画の序盤では、シュピルマンの演奏以外にもいくつもの状況内音楽が存在していました。ラジオから流れる音楽、街頭での演奏など、音楽が日常生活に自然に溶け込んでいる様子が描かれます。
しかし戦争が激化すると、状況内音楽は劇的に減少します。隠れている身では音を立てるラジオは危険でつけられず、街頭演奏は当然不可能となり、状況的に呑気に鼻歌を歌うどころでもありません。ゲットーのすぐそばの建物の一室で住人が弾いていたピアノや、ドロタが弾くチェロ等、多少の状況内音楽は確認できます。しかし、映画序盤とは明らかにその棲み分けが行われています。
音楽が日常に溢れるためには「安全」という条件が不可欠である
我々は普段、音楽がいつでもそばにあることを当然のように感じてしまいがちです。しかし、本映画は音楽が安全な環境の上に成り立つものであることを、静かに、しかし力強く物語っています。音楽の存在そのものが、人間らしい生活の象徴だと言えるでしょう。
► 終わりに
「戦場のピアニスト」は、状況内音楽と状況外音楽の巧妙な使い分けにより、主人公シュピルマンの内面と外的状況を音楽で表現した一作です。特に、心の中の音楽が現実の音楽となって命を救う瞬間は、音楽の持つ力を最も美しく描いた場面として映画史に残るでしょう。
戦争という極限状況の中で、音楽が人間の尊厳と希望を支え続ける姿を描いたこの作品は、音楽の本質的な価値について深く考えさせてくれる貴重な映画です。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
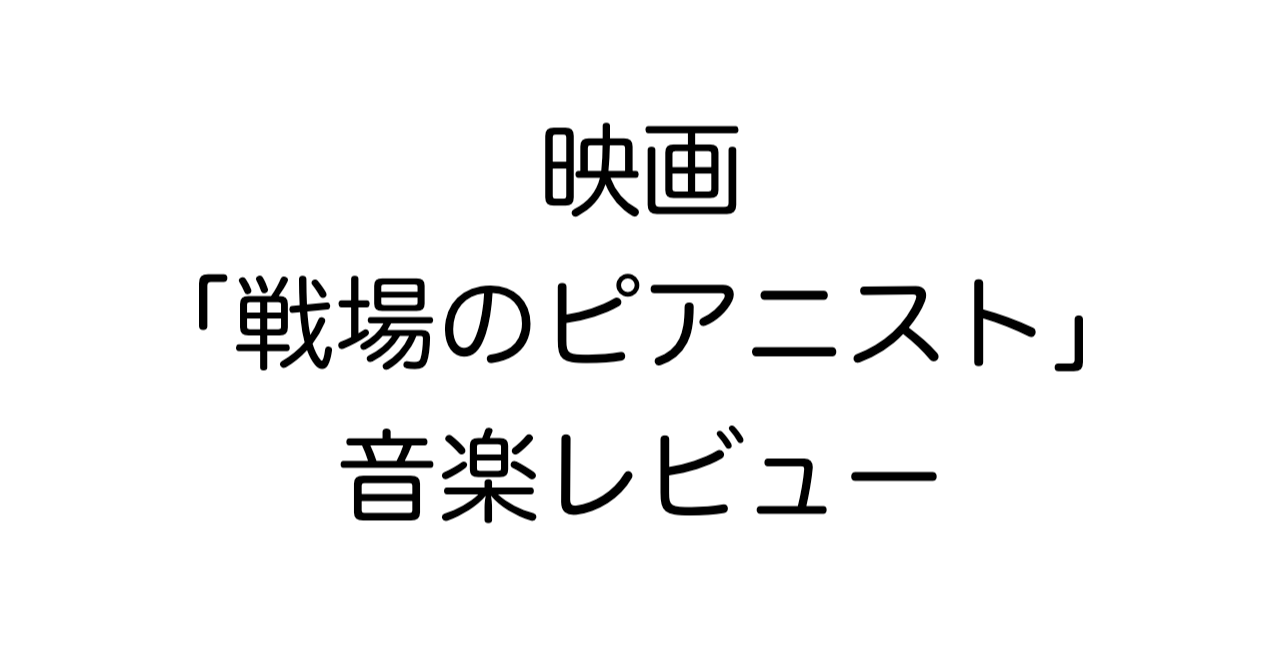
![戦場のピアニスト [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51PJmUOwc4L._SL160_.jpg)
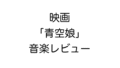
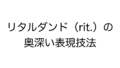
コメント