【ピアノ】映画「愛情物語」レビュー:ピアノ的視点から見た魅力と楽曲の使われ方
► はじめに
実在のピアニスト「エディ・デューチン」の波乱に満ちた人生を描いた1956年の映画「愛情物語(The Eddy Duchin Story)」。この作品は、ピアノという楽器を中心に据えた音楽的表現により、人生の喜怒哀楽と家族愛を深く描き出した名作です。
本記事では、ピアノ的視点から、この映画の魅力と特に注目すべき楽曲の使われ方について詳しく解説します。
・公開年:1956年(アメリカ)/ 1956年(日本)
・監督:ジョージ・シドニー
・ピアノ関連度:★★★★★
► 内容について(ネタバレあり)
以下では、映画の具体的なシーンや楽曲の使われ方について解説しています。未視聴の方はご注意ください。
‣ 状況内音楽と状況外音楽の巧妙な使い分け
この映画では、「状況内音楽」と「状況外音楽」の使い分けが見事にされています。
状況内音楽とは:
・ストーリーの中で実際に聴こえている音楽
・登場人物がピアノを弾いているシーンのBGMなど
本作における状況内音楽の特徴:
・主人公がピアニストだからこそ、劇中でのピアノ演奏シーンが豊富
・演奏シーンでは、実際にその場で聴こえているという設定で音楽が流れる
・だからこそ、通常のBGM(状況外音楽)ではピアノサウンドが控えられている
この棲み分けにより、ピアノ演奏シーンがより際立ち、観ている側は「音楽を聴いている」体験を疑似体験できます。
‣ ラストシーンの感動的な音楽演出
ラストシーンまでは、通常のBGM(状況外音楽)ではピアノサウンドが控えられていましたが、ラストシーンでは、意図的に状況外音楽にもピアノが使われる点に着目しましょう。
映画のクライマックスでは、ショパン「ノクターン 第2番 変ホ長調 Op.9-2」のアレンジ版を演奏する父子のピアノ演奏(状況内音楽)に、徐々にオーケストラサウンド(自宅に楽団員がいるわけではないので、状況外音楽)が重なっていきます。このハイブリッドである「現実にはあり得ない」音楽表現により、感動的なエンディングが生まれています。COLUMBIAのロゴが映し出される時点では、完全な状況外音楽となります。
なぜ、これが効果的なのか:
・ラストシーンオンリーの特別な音楽演出
・現実的な父子の演奏から始まる(状況内音楽)
・オーケストラが加わることで、音楽的な昇華を表現(状況内音楽+状況外音楽)
・観客は自然に感情移入したまま、エンドを迎えられる(COLUMBIAのロゴの時点で、状況外音楽)
‣ 同一楽曲を使った巧妙な場面転換
序盤の演奏活動シーンでは、同じ状況内音楽を引っ張ったまま映像のみを別会場へ変化させて、複数会場での演奏シーンを繋いでいる演出があります。音楽はひと繋がりにも関わらず、会場が変わる度にその会場ならではのアレンジに変化していくため、会場が変化したということが音楽からも伝わってくる面白い音楽演出となっています。
そして最後には、状況内音楽が終わるとともに、状況外音楽としての短いファンファーレへ有機的に接続されていることにも着目すべきでしょう。
‣ 現実味のある音楽表現
中盤で海軍に入隊したエディは、現地の少年とピアノ連弾をします。戦争でかなり痛んで、音も狂っているピアノ。状況外音楽の通常のBGMとしてこういった音を使うと異質で意味を持ち過ぎてしまいますが、状況内音楽なので、痛んだピアノが映った映像とともにその音色を耳にすることになり、むしろ味が出るシーンとなっています。
‣ 映像の状況とレコードから聴こえる音のテンション差
中盤、エディが自分で演奏したレコードをかけている状況内音楽が流れているシーンにおいて、外で嵐が起こります。外が大荒れに変化しますが、音楽だけはレコードの音楽のため止まらずに平和に流れていて、このテンションの差が面白い演出となっています。こういった現実味を帯びた部分も、状況内音楽だからこそ浮き立っていると言えるでしょう。
‣ 無音の効果
劇中には、映像にピアノが映っているだけでそれが弾かれていない場面も多くあります。しかし、多くの演奏シーンがあるからこそ、楽器を見ているだけで「頭の中でピアノが鳴っている」ような感覚を味わえます。
► 終わりに
「愛情物語」は、ピアノという楽器の持つ様々な面を丁寧に描いた作品です。ピアノ的視点から見た細部の音楽面でも、上記のような多彩な工夫が見られました。
音楽を通じた人間関係や、演奏することの意味を教えてくれる一作として、ピアノ学習者にもおすすめできる一作です。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
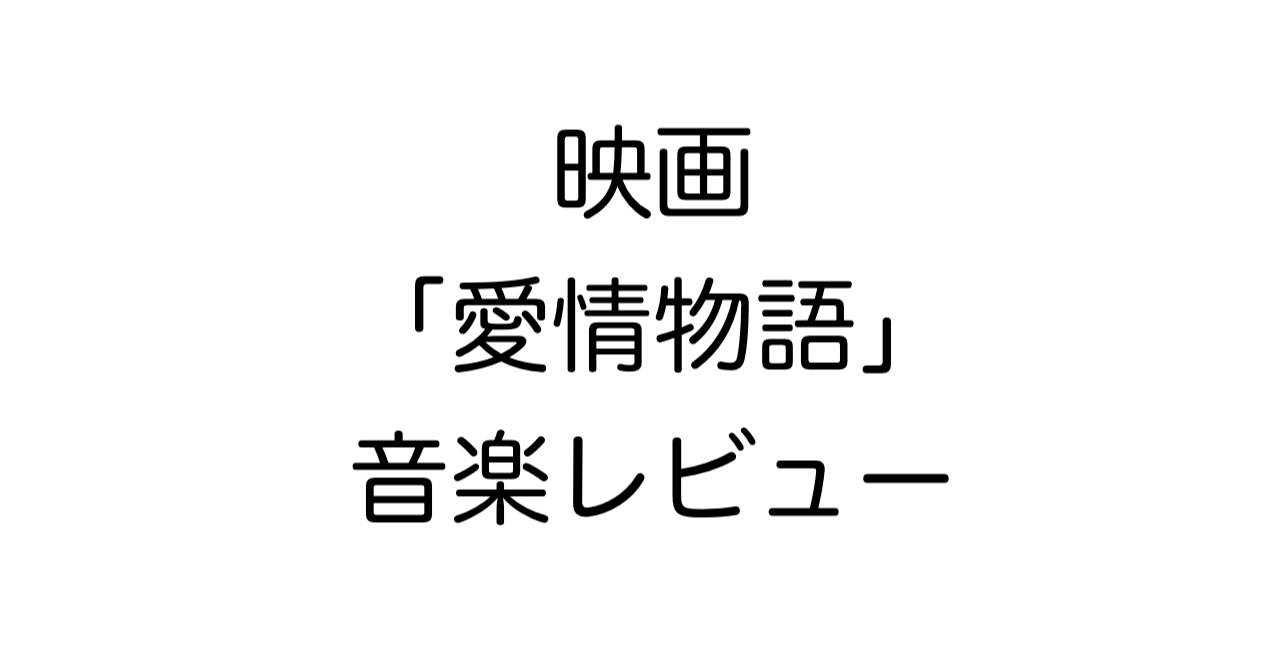

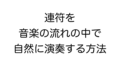
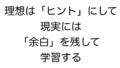
コメント