【ピアノ】映画「黒い十人の女」レビュー:音を使わない音楽表現の技法
► はじめに
映画の中でピアノがどのように表現されているかを知ることは、音楽への理解を深める貴重な機会となります。
本記事で紹介する「黒い十人の女(Ten Dark Women)」は、直接的なピアノ演奏シーンではなく、音楽演出の観点からピアノという楽器が活用されている興味深い作品です。
・公開年:1961年(日本)
・監督:市川崑
・音楽:芥川也寸志(1925-1989)
・ピアノ関連度:★☆☆☆☆
► 内容について(ネタバレあり)
以下では、映画の具体的なシーンや楽曲の使われ方について解説しています。未視聴の方はご注意ください。
‣ 音楽を使わずにピアノの音を感じさせる演出
この映画で最も興味深いのは、実際にピアノの音を鳴らすことなく、観客にピアノ演奏を想像させる演出手法です。映画のラスト間際、市子(新劇女優という設定)の引退送別会シーンにおいて、この技法が効果的に使用されています。
具体的なシーンの構成:
・ピアノから奏者らしき人物が立ち上がるカット
・送別会の様子は映されない
・すぐに閉会の言葉へと移行
このシーンではそれまでの送別会の内容は映されていないので、実際にピアノ演奏を確認したわけではありません。しかし、ピアノからピアノ奏者らしき人物が立ち上がるカットを観た時に、映画観客の中にピアノの音が想像されます。
市川崑監督がこの手法を選んだ理由としては、ラスト間際の場面で間延びを避けるために演奏シーンも含めた送別会の内容は入れず、シンプルにまとめる意図があったのでしょう。
► 音楽表現の多様性を理解する
この演出技法は、ピアノ学習にとって重要な気づきを与えてくれます。音楽は実際に音を鳴らすことだけでなく、「音楽的な瞬間」や「音楽への期待」を演出することでも表現できるということです。
実際のピアノ演奏においても、音と音の間の「間」や「余韻」が非常に重要な役割を果たしています。こういった瞬間に音楽の雰囲気とは異なる動作を入れてしまうと、演奏が台無しになってしまいます。
この映画の演出は、そうした「聴こえない音楽」の存在を視覚的に表現した優れた例と言えるでしょう。
► 終わりに
「黒い十人の女」は、ピアノが主役の映画ではありませんが、音楽演出の観点からピアノを有効に活用した作品です。実際に音を鳴らさずとも音楽的な効果を生み出す手法は、聴衆の想像力を利用することで成り立っています。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
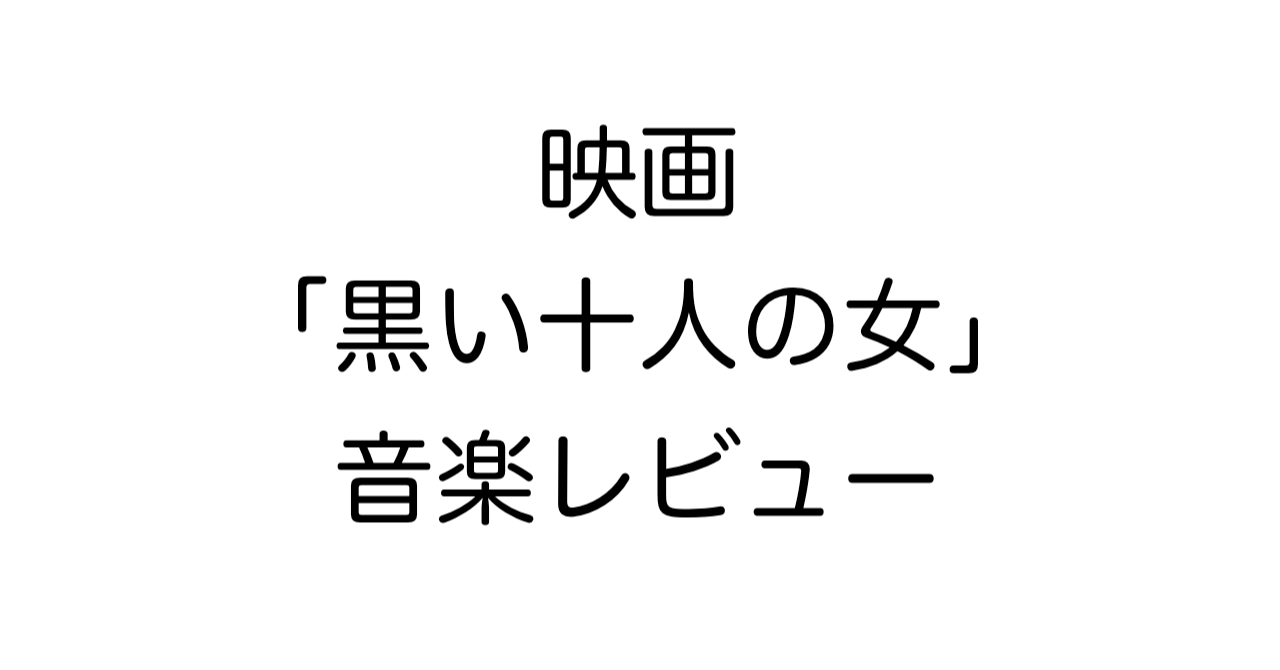
![黒い十人の女 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/412uEeSEzzL._SL160_.jpg)
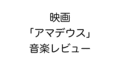
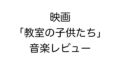
コメント