【ピアノ】シューマン「ユーゲントアルバム Op.68-25 劇場からの余韻」の詳細分析
► はじめに
本記事で取り上げる、シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-25 劇場からの余韻」は、短い作品でありながら、その内部には緻密な構造設計と多彩な音楽的アイデアが詰め込まれています。
本記事では、この作品を「リズム」と「音の形」という2つの観点から詳細に分析し、楽曲の魅力をより深く理解するための視点や演奏する際に注意すべきポイントを提供します。
► 分析:シューマン「ユーゲントアルバム Op.68-25 劇場からの余韻」
‣ 1.「リズム」に着目した分析
· 楽曲構成
シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)Op.68-25 劇場からの余韻」
譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

楽曲構造
・Aセクション:1-8小節
・Bセクション:9-23小節
・A’セクション:24-31小節
注目すべき特徴として:
・セクションの小節数の非対称性:Bセクションが15小節という奇数で構成されている点
・内部構造:13-15小節が3小節間という短い区切りを形成している
・移行部の存在:22-23小節が次のA’セクションへの「つなぎ」として機能している
シューマンは古典的な8小節や4小節などの均整の取れた構造を基本としながらも、意図的に非対称の構造を取り入れています。これは「劇場からの余韻」という標題にふさわしい、記憶の断片や印象の移り変わりを表現するための手法と考えることもできるでしょう。
· リズムパターンの発展的な使用
本楽曲の特徴の一つに、リズムパターンの発展的な使用があります。
1. リズムの展開過程
・Aセクション(1-8小節):16分音符の連続的な動きが主体
・転換点(7小節目):「付点16分音符と32分音符」の特徴的リズムパターンが初めて登場
・Bセクション(9-23小節):この付点リズムが主要素材として全面的に展開
・A’セクション(24-31小節):Aセクションの回帰
特筆すべきは、7小節目で初めて登場する付点リズムが単なる装飾的要素ではなく、後のBセクションの主要リズムへと発展する「伏線」となっている点。このように一つのリズム素材が異なるコンテキストで再利用され、変容していく過程は重要な着目ポイントです。
2. 聴覚的印象とリズムの関係
興味深いのは、実際の聴覚的印象と楽譜上のリズム複雑性が必ずしも比例しない点です:
・AセクションとA’セクション:両手で異なるリズムパターンが動くため、聴覚的にはせわしなく聴こえる
・Bセクション:「付点16分音符と32分音符」という複雑なリズムが多用されているが、ほとんどの部分で両手が同じリズム(リズミックユニゾン)で動くため、実際の印象は明快で力強い
Bセクションで中心となった両手のリズミックユニゾンも、22-23小節で左手パートが不在になることによる効果的な「崩し」により、違和感なくA’セクションのリズムパターンへ戻されています。
このコントラストは、おそらくシューマンが意図的に作り出した劇的効果であり、劇場音楽の様々な場面を想起させるものだと言えるでしょう。
3. 演奏上の留意点
リズムの特徴を踏まえた演奏上の留意点としては:
・付点リズムの正確さを保ちつつ、堂々とした響きを作る(金管楽器を思わせる音色表現)
・リズム変化の瞬間:特に7小節目や、セクション間の移行部(22-23小節)でのリズムが甘くならないように
· まとめ
シューマンの「劇場からの余韻」は、リズムの緻密な扱いや構造的な工夫が随所に見られる作品だということが分かりました。特にリズムの観点から分析すると、7小節目に現れる付点リズムがBセクションの主要素材として発展するプロセスや、両手のリズミックユニゾンとその効果的な崩しなど、多くの発見があります。
作品を演奏する際は、単に楽譜の音符を弾くだけでなく、このような分析的視点を持って楽曲の構造やリズムの発展を理解するようにしましょう。
‣ 2.「音の形」に着目した分析
· 楽曲構成の再掲
譜例(楽曲全体)

楽曲構造
・Aセクション:1-8小節
・Bセクション:9-23小節
・A’セクション:24-31小節
いくつか注目すべき特徴があります:
・13-15小節が3小節間の区切りで、Bセクション全体が15小節という奇数小節で構成されている点
・22-23小節が次のセクションへの「つなぎ」の役割を持っている点
· 調性と和声の特徴
Aセクションでは、基本的にa-mollの安定した和声構造とわずかなd-mollの色合いが見られますが、Bセクションに入るとより部分転調(調性の拡大)の冒険が始まります。
・9-12小節は2オクターヴユニゾンの書法で、明確な和声を持たない
・13-15小節:C-dur
・16-19小節:a-moll → F-dur
・20-23小節:a-moll
ノンコード、C-dur、F-durという3種の進出表現が確認できました。
·「音の形」に着目した分析
「音の形」の分析とは、和音構造と単音進行の使い分け、そして単音進行の中に潜む多声的な書法を読み解くことです。この視点から「劇場からの余韻」を見ていくと、セクションごとに明確な違いがあることが分かります。
譜例(楽曲全体)

Aセクションおよび A’セクション
・左手パート:完全にホモフォニー的な団子和音による伴奏
・右手パート:セクションの締めくくり部分(8小節目、30-31小節)以外は完全に単音メロディ
Bセクション
Bセクションでは、「音の形」が劇的に変化します:
・明確な和声を持たない2オクターヴユニゾン(9-12小節)
両手で合わせて2オクターヴを演奏するこの部分には、和声的な支えがありません。
・トゥッティのような ff による和音のファンファーレ(13-15小節)
フォルティシモと厚い和音の連打により、オーケストラの金管セクションを思わせる音響効果が生まれています。
・10度のハモリとファンファーレによるポリフォニー的な和音(16-19小節)
10度という広い音程でのハモリが使われる一方、右手ではファンファーレが鳴り響きます。
・オクターヴユニゾンとホモフォニー的な団子和音の使い分け(20-23小節)
ユニゾンと和音が交互に現れます。
これらから、明らかにBセクションの方がAセクションよりも多彩な「音の形」を持っていることが分かります。これは劇場での多様な印象や刺激を音楽的に描写するためのシューマンの意図的な選択だと考えられます。
· まとめ
シューマンの「劇場からの余韻」は、「音の形」の観点から見ると洗練された作曲技法が用いられていることが分かりました。特にAセクションの単純明快な構造とBセクションでの多彩な「音の形」の対比は、子どもが劇場で経験する様々な印象や感情を見事に描写しているかのようです。
この楽曲を演奏する際は、正確に音を再現するだけでなく、各セクションの持つ異なる「音の形」の特徴を意識し、それぞれに適した音色などを工夫するようにしましょう。
関連内容として、以下の記事も参考にしてください。
【ピアノ】和音分析の基礎:ホモフォニーとポリフォニーの違いを理解する
► 終わりに
シューマンの「劇場からの余韻」の分析を通して、この短い作品の中にいかに多くの音楽的アイデアが込められているかを確認することができました。
これらの分析的視点は、ただ楽曲を理解するためだけでなく、実際の演奏において表現を考えていくための重要な手がかりとなります。楽譜に書かれた音符の背後にある作曲家の意図を読み取ることで、より説得力のある音楽表現が可能になるでしょう。
► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
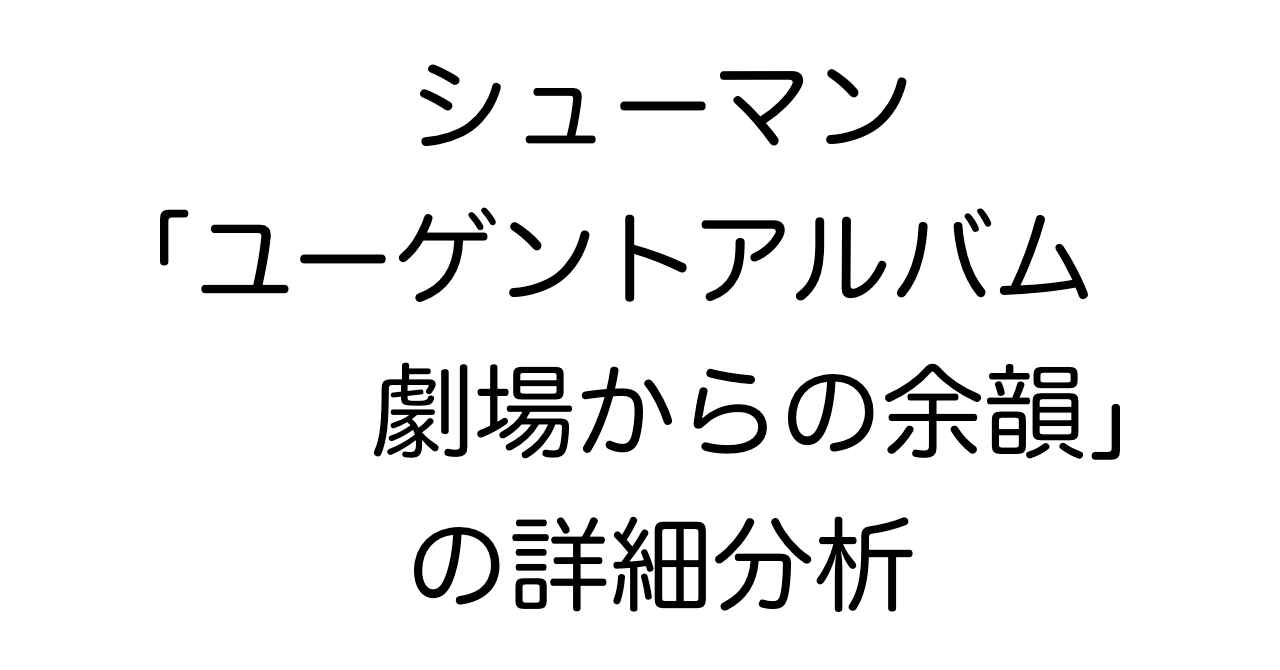
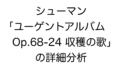
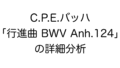
コメント