【ピアノ】シューベルトのピアノ作品入門:聴く入門と弾く入門
► はじめに
ピアノを学ぶ人にとって、シューベルトは誰もが名前を知る作曲家でありながら、意外にも距離を感じる存在かもしれません。しかし、一度その音楽の魅力に触れると離れられなくなる不思議な魅力を持つ作曲家です。
本記事では、シューベルトのピアノ作品に親しむための「聴く入門」と「弾く入門」の両方のアプローチを紹介します。
► なぜ、シューベルトは敬遠されがちなのか
シューベルトのピアノ作品、特にソナタが敬遠される主な理由として、以下の3点が挙げられます:
・地味な印象を与える作品が多い
・演奏時間が長い大作が目立つ
・表面的な派手さよりも内容の深さを重視している
しかし、これらの特徴は決して欠点ではなく、むしろシューベルト音楽の本質的な魅力と言えるでしょう。時間をかけて向き合うことで、その真価が見えてきます。
► シューベルトの聴く入門
シューベルトのピアノ音楽と親しむための第一歩は、「鑑賞」から始めることをおすすめします。以下の作品群を、まずはゆっくりと聴いてみましょう。
‣ 必聴の有名小品集
聴く入門に最適な小品集:
・楽興の時 D 780 Op.94(全6曲)
・即興曲集 D 899 Op.90(全4曲)
・即興曲集 D 935 Op.142(全4曲)
これらの小品は、シューベルトの音楽語法を理解するうえで重要な作品群です。比較的短く親しみやすい曲が多く、聴く入門として最適です。
‣ 聴く入門ピアノソナタ
特に重要なのは第13番から第21番までのソナタですが、中でも、最晩年の3大ソナタと呼ばれる以下の作品は、必ず押さえておきたい傑作です:
・ピアノソナタ 第19番 ハ短調 D 958
・ピアノソナタ 第20番 イ長調 D 959
・ピアノソナタ 第21番 変ロ長調 D 960
初めて聴く方におすすめの順序:
・第19番 → 3曲中最も親しみやすく、終楽章のタランテラは情熱的で特に魅力的
・第21番 → シューベルトの深遠な音楽世界を体現する傑作
・第20番 → 終楽章の親しみやすいロンドで人気が高い
‣ 聴くおすすめの隠れた名曲
「ピアノソナタ 第7番 変ホ長調 D 568 第4楽章」も、ぜひ聴いていただきたい作品です。ソナタ形式の楽章ですが、特に再現部でes-moll(変ホ短調)に転調した第2主題を聴くと、胸に迫るものがあります。
アンドラーシュ・シフの演奏は、抑えめのテンポでシューベルトの内面的な美しさを見事に表現しており、特におすすめです。
►「聴き流し」アプローチ
1. まずは「聴き流し」から始める
・気になる曲を日常的なBGMとして活用
・特別に理解しようとせず、とにかく流しっぱなしにする
・流し聴きで曲の全体像を何となく覚えてしまうことを目指す
2. お気に入りの曲を見つけたら
・楽譜を見ながら聴く
・楽曲の構造や和声進行に注意を向ける
・可能であれば部分的に演奏を試みる
「流し聴き」アプローチを徹底することが入門の最大のコツです。真正面からぶつかって理解しようとするよりも、時間をかけて自然に馴染んでいくといいでしょう。
► 弾く入門:やさしい曲から始めよう
初心者でも弾ける、おすすめの第一歩
シューベルト「ワルツ Op.18-6」
譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

難易度:ブルグミュラー25の練習曲後半程度
演奏時間:約1分30秒
美しい旋律がワルツのリズムに乗って奏でられます。シューベルトの入門用の作品としては最も知られている作品です。
おすすめ楽譜:
・4期のピアノ名曲集3 バロック・古典・ロマン・近現代 ブルグミュラー後半程度 全曲収録CDつき
この楽譜集には、シューベルトの「ワルツ Op.18-6」をはじめ、同程度の難易度の様々な時代の名曲が収録されており、レパートリーを広げるのに最適です。
次のステップとしては、以下の中級用有名曲へ入っていくといいでしょう:
・楽興の時 第3番 Op.94-3 ヘ短調
・即興曲集 第2番 Op.90-2 変ホ長調
・即興曲集 第4番 Op.90-4 変イ長調
► 終わりに
シューベルトのピアノ作品は、確かに取っつきにくく感じるかもしれません。しかし、徐々に理解を深めていけば、その音楽の素晴らしさが必ず伝わってくるはずです。
焦らず、じっくりとシューベルトの音楽世界を味わってみてください。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
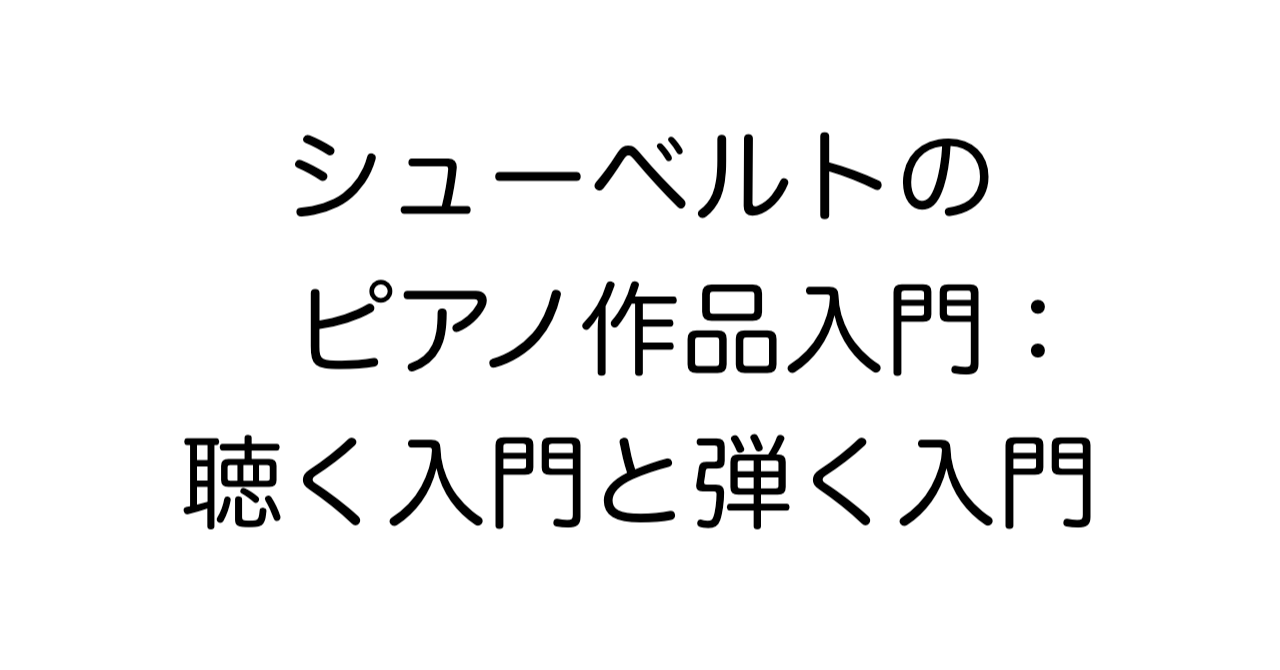

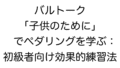
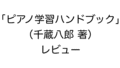
コメント