【ピアノ】「最新ピアノ講座(5) ピアノ実技指導法」レビュー
► はじめに
「最新ピアノ講座(5) ピアノ実技指導法」は、1981年に出版されたピアノ指導の専門書です。日本の著名な作曲家・ピアニスト・音楽大学教授陣による分担執筆という構成で、各分野の専門家の知見が詰まった一冊となっています。
・出版社:音楽之友社
・初版:1981年
・ページ数:239ページ
・対象レベル:初中級~上級者
・最新ピアノ講座(5) ピアノ実技指導法 / 音楽之友社
► 内容について
‣ 本書の特徴
専門家による分担執筆の強み
本書の特徴は、各章がその分野の専門家によって執筆されている点です。多視点より、理論と実践の両面から深く掘り下げられています。
体系的な学習段階の提示
第3章「15段階によるピアノの学習」では、初級(E)、中級(M)、上級(H)それぞれ5段階ずつの詳細な学習プログラムを提示。各レベルでの具体的な指導方針が明確に示されており、指導者にとって実用性の高い内容となっています。
指導者以外の方にも有益な内容
特に「第5章:各グレード代表曲の解説」「第7章:ピアノ奏法の歴史」の2つの章は、指導者以外の方におすすめの章です。学習で頻繁に取り上げられる代表曲の楽曲解釈と音楽史の一部を一冊で学べます。
‣ 章別内容解説
第1~3章:基礎理論と段階的学習法
発達段階に応じた指導法から、具体的な15段階学習システムまで、ピアノ教育の根幹となる理論が体系的に整理されています。
第4章:練習曲の効果的使用法
ツェルニー、ブルグミュラーなど主要練習曲集の詳細分析が秀逸です。各練習曲の内容を項目(練習課題、器官の練習、譜面上の問題、難易度 他)に分類し、目的を持った教材選択を可能にしています。
第5章:各グレード代表曲の解説
ピアノ指導をしていない方にも特におすすめの章です。J.S.バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、ショパン、シューマン、ドビュッシーなどの名曲について、各レベル別での演奏上のポイントが解説されています。初級段階から活用でき、楽曲解釈の基本を学ぶのに最適です。
第6章:指導上の諸問題
ピアノ学習の開始時期、初歩指導の方法論、教材選択など、実際の指導現場で直面する具体的な問題への対処法が示されています。
第7章:ピアノ奏法の歴史
これも指導者以外の方におすすめの章です。クープランからショパン、現代に至るまでのピアノ奏法の変遷を歴史的に俯瞰。音楽史の理解を深めるのに非常に有益な内容です。
► 指導者以外の方への推奨学習法
第5章「各グレード代表曲の解説」+ 最新ピアノ講座(7)(8)「ピアノ名曲の演奏解釈Ⅰ・Ⅱ」の併用
基本的な楽曲解釈を学習し、より多様な楽曲の詳細な演奏解釈へと発展させる
第7章「ピアノ奏法の歴史」+ 最新ピアノ講座(7)(8)のピアノ音楽史部分(合計43ページ)の組み合わせ
奏法の歴史と全体的なピアノ音楽史を統合的に理解(両方とも千蔵八郎氏執筆のため、整合性が高い)
・最新ピアノ講座(7) ピアノ名曲の演奏解釈Ⅰ / 音楽之友社
・最新ピアノ講座(8) ピアノ名曲の演奏解釈Ⅱ / 音楽之友社
► 本書の注意点
1981年出版のため、現代の教育法や新しい教材については触れられていません。特に指導者の方は、現代のピアノ教育書と併読することで、伝統的手法と現代的手法の両方を理解できるでしょう。
► 終わりに
「最新ピアノ講座(5) ピアノ実技指導法」は、ピアノ指導に携わる方はもちろん、演奏解釈や音楽史に興味のある学習者にとっても価値ある一冊です。特に第5章と第7章は、ピアノを弾くすべての方に学んで欲しい内容となっています。
現代のピアノ教育書と併せて読むことで、より深い理解が得られるでしょう。クラシック音楽の伝統的な教育法を学びたい方、体系的なピアノ技術の習得を目指す方には特におすすめします。
・最新ピアノ講座(5) ピアノ実技指導法 / 音楽之友社
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
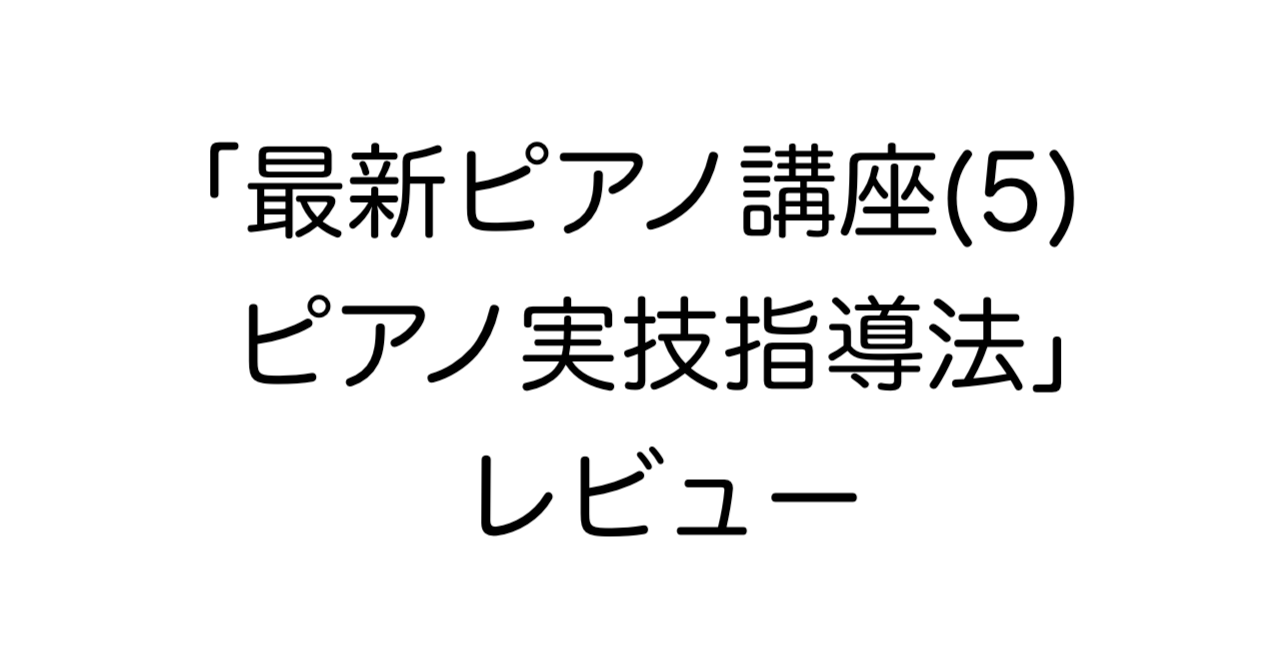



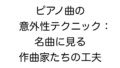
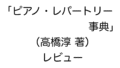
コメント