【ピアノ】練習などのマンネリ化は、順序をひっくり返すことで軽減できる
► はじめに
「当たり前だと思ってやっていることの順序をひっくり返す」という発想の転換だけで、練習などあらゆることのマンネリ化が新鮮なものに生まれ変わります。
本記事では、ピアノ練習だけでなく、演奏会のプログラム構成や日常生活にも応用できる「逆転の発想法」を取り上げます。
► 3つの提案
‣ 曲の練習順序をひっくり返してみる
毎日の練習がマンネリ化してきた時の対処法です。
毎日のピアノ学習において、一般的には、練習曲などの指練習や基礎練習から始めて「指慣らし」と言われるような段階が済んでから、大切な楽曲の練習を始めることが多いようです。
提案なのですが、 指慣らしはいったん置いておいて、この順序を逆にしてみてください。一番新鮮味や集中力がある練習の最初の時間に、その大切なレパートリー作品を練習してあげてください。時々このように順序を変えてみるだけでも、練習にバリエーションが加わって新鮮味が維持されます。
この方法のメリットは、最も大切な楽曲に対して最も高い集中力を注げることです。練習の後半になると、どうしても疲労が蓄積して集中力が落ちてきます。「今日はこの曲を上達させたい」という明確な目標がある場合、その曲を真っ先に練習することでより効率的な学習が可能になるでしょう。
注意点は、本番の直前など、練習方法に変化を与えないほうが混乱が生じなくて良いタイミングもあることです。この辺りは、失敗しながらでも試行錯誤して自身にとって最適な塩梅を見つけていってください。
‣ 本番でのプログラム順をひっくり返してみる
例えば、演奏会で以下の2曲を演奏するとします:
・ショパン「エチュード Op.10-4」
・ショパン「バラード 第2番 Op.38」
多くの方が急速なテンポで演奏時間も短い「エチュード Op.10-4」を先に弾き、その後に、より内容の深い「バラード 第2番 Op.38」を演奏するはずです。 もちろんそれでも良いのですが、もしこのプログラムを何度か弾くのであれば、時には思い切ってプログラム順を逆にしてみるのはどうでしょうか。
長い方の深い楽曲をきちんと披露してから、テンポが速くパフォーマンス性もある短い楽曲をビシッと決める。これもなかなか魅力的なステージになります。その場合は、「エチュード op.10-4」のテンポを出来る限り速めに設定すると、なお良い演出になるでしょう。
従来の常識に縛られず、聴衆に新鮮な驚きを与えるプログラム構成を考えてみてください。プログラムの順番をひっくり返すだけで、同じ作品でも全く異なる印象を与えることができます。また、聴衆の期待を裏切る構成は、演奏会全体に活気をもたらすことでしょう。
‣ 日常生活でもあらゆることをひっくり返してみる
ここまで書いてきた考え方は、日常生活にも活かせます。
例えば筆者は、健康や運動のために近所を散歩をする習慣があるのですが、いい加減やり過ぎて、知らない道は無くなってしまいました。車や電車で遠出をせずに歩いて行ける範囲でやりたい場合が多く、結局知っている道を歩くことになるため、さほど新鮮味がありません。
当初は、イヤフォンで耳にする素材にバリエーションを取り入れて変化を出し、道自体はいつもの道を歩いていました。しかしある時、「歩く方向をひっくり返せばいい」と思ったわけです。これを試してみたら驚いたのですが、知っている道でも、逆方向のルートで歩くと見える景色や感じることが異なり、新しい道を歩いているような感覚になりました。歩き方が既に20ルートある場合は、「20×2=40ルート」になります。
このように「ひっくり返す」という発想は、日常のあらゆる場面で応用可能です。例えば:
・朝食にたくさん食べて、夕食を軽くする
・普段と逆の順序で部屋の掃除をしてみる
・ピアノ音楽史の書籍を再読する時には、読む順序を変える(近現代から読み始める 等)
単純な「逆転」によって、脳に新しい刺激が与えられ、マンネリを感じにくくなります。
► 終わりに
「当たり前だと思ってやっていることの順序をひっくり返す」という単純な発想の転換は、そんなマンネリ化を打破する有効な手段です。練習順序を変える、プログラム構成を逆にする、日常の習慣を逆から行う—これらは全て我々の脳に新鮮な刺激を与え、活動への興味を再燃させてくれるでしょう。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
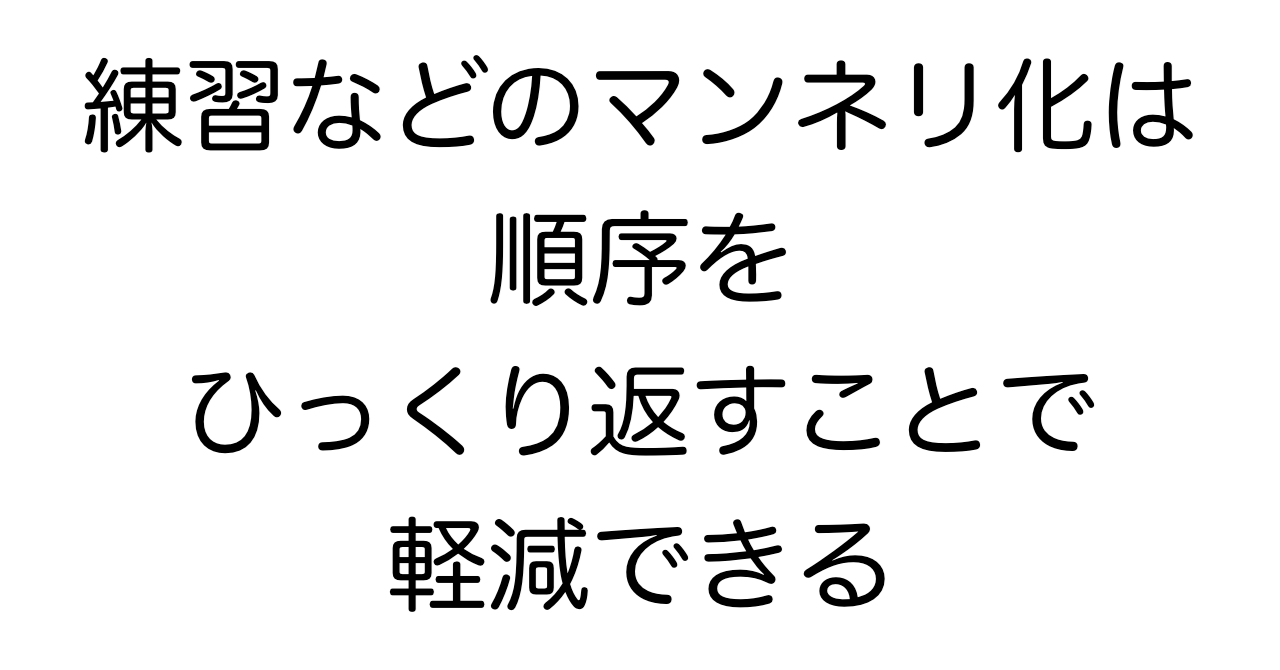
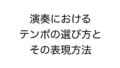
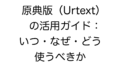
コメント