【ピアノ】ウリ・モルゼン編「文献に見る ピアノ演奏の歴史」レビュー
► はじめに
演奏技術だけでなく歴史的背景や演奏解釈を知ることは、作品への理解を深め、より高度な演奏につながります。本記事で紹介する「文献に見る ピアノ演奏の歴史 初期ハンマークラヴィーアからブラームスまで」は、まさにそのような知識を得るための、一次資料に基づいた貴重な一冊です。
・訳 : 芹澤尚子
・出版社:シンフォニア
・邦訳初版:1986年
・ページ数:215ページ
・対象レベル:初中級〜上級者
・文献に見る ピアノ演奏の歴史 初期ハンマークラヴィーアからブラームスまで 編:ウリ・モルゼン 訳:芹澤尚子 / シンフォニア
► 内容について
‣ 本書の特徴
1. 豊富な一次資料の引用集
本書の特徴は、歴史的文献からのピアノ演奏に関する479項目にも及ぶ引用が時代順に編纂されていることです。C.P.E.バッハの「正しいクラヴィーア奏法試論」から始まり、モーツァルト、ベートーヴェン、ショパン、リスト、ブラームスなど、各時代を代表する作曲家・演奏家の言葉や、当時の教則本からの抜粋が収められています。
特にロマン派、とりわけショパンに関する情報が充実しているのは、現代のピアノ学習者にとって大きな価値があります。これらの資料は、技術指導に留まらず、当時の音楽観や芸術観も伝えてくれます。
2. 歴史的視点からの演奏解釈
編者のモルゼンは「はじめに」の中で、「解釈とはテキストの個人的な解釈であり、したがってそれはある限られた方向の一つの決定である。しかし、決定ができるようになるためには、その可能性をまず一度は知っておかなければならない」と述べています。これは現代のピアノ学習者にとって重要なメッセージと言えるでしょう。
楽譜に書かれた音符や記号を再現するだけでなく、その作品が作られた時代背景や演奏習慣を知ることは重要です。例えばツェルニーの発言にある「速いテンポにおける付点リズムの短い音符が、3連符の3番目の音と同時に打鍵されるケース」の扱いなど、現代の楽譜表記だけでは分からない演奏習慣についての知識は、作品を演奏するうえで参考になります。
3. 著名な指揮者「ニコラウス・アーノンクール」の序文
ニコラウス・アーノンクールによる序文も本書の価値を高めています。アーノンクールは「今日音楽家はすべての時代の音楽を一つのいい加減な様式で片付けようとする」と指摘し、時代によって異なるスタイルを理解することの重要性を説いています。
彼は「私達があたかも『教養ある同時代人』になったかのようによく考えなければならない」と述べ、楽譜から読み取れない情報を得るための姿勢についても示唆しています。
‣ 本書の活用法
1. 演奏解釈の視野を広げる
独学でピアノを学ぶ際、「これが正しい弾き方」という固定観念に縛られがちです。本書は様々な時代の作曲家や演奏家や教師の言葉を通じて、当時重視されていた考え方と同時に、多様な解釈があり得ることも教えてくれます。モルゼンが指摘するように「いつの時代においても今日と同様にさまざまな考え方、感じ方をする人間がいて、常にさまざまな音楽が演奏されていた」のです。
2. 歴史的文脈を理解する
J.S.バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、ショパン、リストなど、それぞれの作曲家が活躍した時代のピアノ(あるいは、その他の鍵盤楽器)の特性や演奏習慣を知ることで、なぜ彼らがそのような作品を書いたのか、どのように演奏されることを想定していたのかを理解する助けになります。
3. テクニックへの新たな視点
本書に収められた引用には、運指や表現方法、ペダリングなど具体的なテクニックに関する記述も多く含まれています。現代のピアノ教則本とは異なる視点からの指導が、技術的なヒントになることもあるでしょう。
4. モチベーションの維持
独学でピアノを続けていると、時に練習のマンネリ化や孤独感を感じることがあります。本書を通じて歴史上の偉大な音楽家たちの思想や情熱に触れることは、自分自身の練習への意欲を高める機会となるでしょう。例えば、シューマンが「ダヴィッド同盟舞曲集 Op.6」をクララ・シューマンへ送る時の手紙などは、人間味にあふれていて深い感情を持つことができます。
‣ 本書の構成
本書は初期ハンマークラヴィーアの時代から始まり、ブラームスの時代までを時系列で網羅しています。C.P.E.バッハ、ハイドン、モーツァルト、クレメンティ、ベートーヴェン、シューベルト、メンデルスゾーン、ショパン、シューマン、リスト、クララ・シューマン、ブラームスなど、ピアノ音楽の発展に重要な役割を果たした人物が取り上げられています。
特にショパンの項目が充実しており、彼の人物像や演奏スタイルや教育法についての貴重な情報が含まれています。また、楽器の発展についての項目もあり、ピアノという楽器自体の変遷がピアノ音楽にどのような影響を与えたかを理解する助けとなります。
► 終わりに
一次資料をもとに音楽の本質や歴史を知ることは重要です。自身の演奏に歴史的な視点を加えたい方、「なぜそう弾くのか」という問いに対する答えを探している方にとって、本書は貴重なガイドとなるでしょう。
・文献に見る ピアノ演奏の歴史 初期ハンマークラヴィーアからブラームスまで 編:ウリ・モルゼン 訳:芹澤尚子 / シンフォニア
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
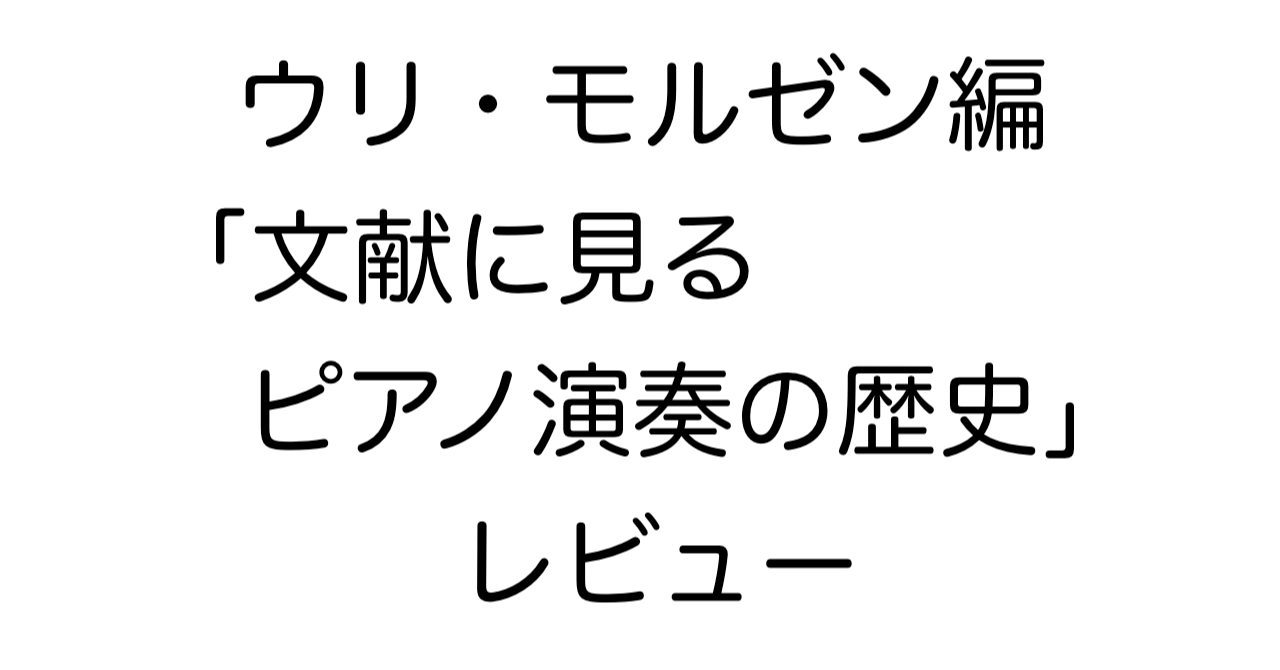

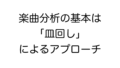
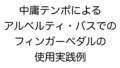
コメント