【ピアノ】ヨーゼフ・ディッヒラー「ピアノ演奏法の芸術的完成」レビュー
► はじめに
著名なピアニスト・教育者であるヨーゼフ・ディッヒラーによる「ピアノ演奏法の芸術的完成」は、ピアノ演奏と教育に関する鋭い視点を提示した一冊です。大人の独学者にとって、この本との出会いは、自らのピアノ学習を見直す契機となるでしょう。
筆者自身、この書籍を読んだ当時、「久しぶりに良い書籍と出会った」と思ったことを覚えています。
・訳 : 渡辺護、尾高節子
・出版社:音楽之友社
・邦訳初版:1957年
・ページ数:320ページ
・対象レベル:上級者
・ピアノ演奏法の芸術的完成 著:ヨーゼフ・ディッヒラー 訳 : 渡辺護、尾高節子 / 音楽之友社
► 内容について
‣ 本書の特徴
ディッヒラーは序文で、本書の目的をこう述べています:
一定の演奏法又は教育法を発展させたり,一定のメソード(方法)をとくに優秀なりとしてこれに従うなどと言うことは試みられていない。
(抜粋終わり)
これは重要な姿勢であり、本書では特定の「メソッド」を押し付けるのではなく、あらゆる演奏法や教育法に通底する普遍的な内容を探求しています。ディッヒラーは、「諸問題を,出来るだけ客観的にまた簡潔に把握」することを目指し、内容が「それぞれの個性に応じた教授において実際的な応用の可能性をも持つ」としています。
‣ 技術と音楽性の融合
本書の中心視点は明確で、「音楽性と技術との両方面を,常に同様に作り上げるようにすることが,大切である」という一文に、ディッヒラーの教育哲学が凝縮されています。特に独学では往々にして技術的側面に目が行きがちですが、本書は音楽的表現の重要性を強く訴えかけてきます。
‣ 構成と内容のピックアップ
· 第1章 種々のスクール(教則本)とメソード(方法)について
歴史的な教則本やメソッドを概観しつつ、ディッヒラーは一貫して次の原則を主張します:
ピアノのテクニックとその方法の発展は、楽器の発展とピアノ作品の発展から導き出されて来るべきである。
(抜粋終わり)
この視点は、ただ単に過去の巨匠の演奏法をなぞるのではなく、楽器そのものの特性と作品の要求を理解したうえで、適切な技術を発展させることの重要性を説いています。独学者にとって、種々の歴史的文脈を理解することは、自分の練習法や演奏法を選択するうえで役立つでしょう。
· 第2章 ピアノとその表現可能性
この章では、ピアノという楽器の物理的特性と表現可能性について詳細に解説しています。特に「アクションのメカニズムと打鍵の可能性」の節は、独学者にとって価値があります。楽器の仕組みを理解することで、効果的な練習法や演奏技術を選択できるようになるでしょう。
ペダリングに関しては、当時の教育の問題点を鋭く指摘し、独自の考えを提示しています。現代でも多くのピアノ学習者がペダリングに悩んでいることを考えると、この章の価値は色あせていません。
記譜法の特性に関する節も、実践的な知見を提供しています:
記譜の問題を理論的実際的に研究した者だけが、譜面に託された作曲者の意図のすべてを見極め理解する。
(抜粋終わり)
特に以下の点について詳細な解説があります:
・J.S.バッハの装飾音
・バロック期のクーラントなどにおける3連符と付点の扱い
・モーツァルトの前打音
これらの知識は、それぞれの時代の作品を演奏する際に必須のものであり、独学者が悩んだりつまずきやすいポイントの代表例。
· 第3章 音楽的表象
この章は本書の中核を成す部分です。「音楽的表象」とは、演奏者が頭の中で思い描く音楽像のことであり、ディッヒラーはこれこそが良い演奏の基礎であると説きます。
・指や筋肉など、およそすべて演奏の道具たるものは意志に支配される
・演奏における最高指導権を掌握するのはつねに音楽的表象と、聴力統制でなければならず、技巧上の演奏原理ではない
(抜粋終わり)
これらの言葉は、ただ単に正しい鍵盤を押すことに終始する練習から脱却し、常に音楽的表現を意識した練習へと学習者を導きます。
特に注目すべきは「アゴーギク」(テンポの微妙な変化)に関する詳細な解説です。多くの学習者が悩みがちなこの分野について、ディッヒラーは丁寧に説明しています。テンポの揺れを、気まぐれではなく「音楽的構造に基づいた表現手段」として捉える視点は参考になるでしょう。
また、ディッヒラーはこう述べています:
ピアノのけいこに行くのではなく、音楽を習いに行くべきである。ピアノあるいは一定の曲を演奏するために、偶然そこにある楽器でなくてはならない。
(抜粋終わり)
この言葉は、特に大人の独学者にとって重要な指針であり、常に「音楽」そのものを学ぶ姿勢を忘れないよう促しているのです。
· 第4章 練習法
練習に関する章では、ディッヒラーは練習の本質をこう定義しています:
練習とは1つの作品を知り、これをマスターするために役だつべきあらゆる活動性であると定義づけられよう。
(抜粋終わり)
この定義は、思考停止で同じフレーズを何度も反復するだけの練習から脱却し、作品の理解を目指した多角的な練習へと導くものです。指の練習、練習曲、ポリフォニー(複音楽)など、様々な分野に応じた効果的な練習法が提案されています。
運指法に関しても、実践的な指針が示されています:
良き指使いとは該当する音楽の完璧な演奏を可能にし、しかもこの際出来るかぎり好都合のものをいう。
(抜粋終わり)
条件を満たしたうえで「出来るかぎり好都合のもの」という部分に着目しましょう。
· 第5章 教育課程
最終章では、3年間にわたる教育課程が提案されています。この章は指導者向けではありますが、独学者も自らの学習計画を立てる際の参考になるでしょう。特に、無理のない進度計画と、初期段階からの音楽性の育成を重視する姿勢は、自己学習においても大いに参考になります。
ディッヒラーの主張する「難しいであろうことを避けておいて、後からそれが必要になり、もっと大変なやり直しをくらうくらいであれば、はじめから、難しいなどと思わずにやってみる」という姿勢は、特に大人の学習者に勇気を与えてくれるでしょう。
► 現代のピアノ学習における本書の位置付け
1957年の邦訳初版から随分と年月が経過していますが、テクニック偏重になりがちな現代のピアノ教育において、常に音楽性との均衡を説くディッヒラーの考えは、より一層重要性を増しているとさえ言えるでしょう。
特に独学の大人にとって、本書は「弾き方」の指南書を超えた、ピアノ学習の指針となります。ディッヒラーは「音楽的表象」という視点を通じて、常に頭の中で理想の音楽を思い描き、それを実現するために技術を磨くという姿勢を説いています。
► 関連書籍
同著者の「ピアノの解釈と限界」も併読することで、ディッヒラーの音楽観をより包括的に理解できます。レビューは、以下の記事を参考にしてください。
【ピアノ】ヨーゼフ・ディッヒラー「ピアノの解釈と限界」レビュー
► 終わりに
技術と音楽性の調和、楽器の特性と記譜法の理解、効果的な練習法の提案など、本書の内容は時代を超えて普遍的な価値を持っています。音楽に対する深い理解に基づいたディッヒラーの考えを、日々の学習の参考にしてみてください。
・ピアノ演奏法の芸術的完成 著:ヨーゼフ・ディッヒラー 訳 : 渡辺護、尾高節子 / 音楽之友社
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
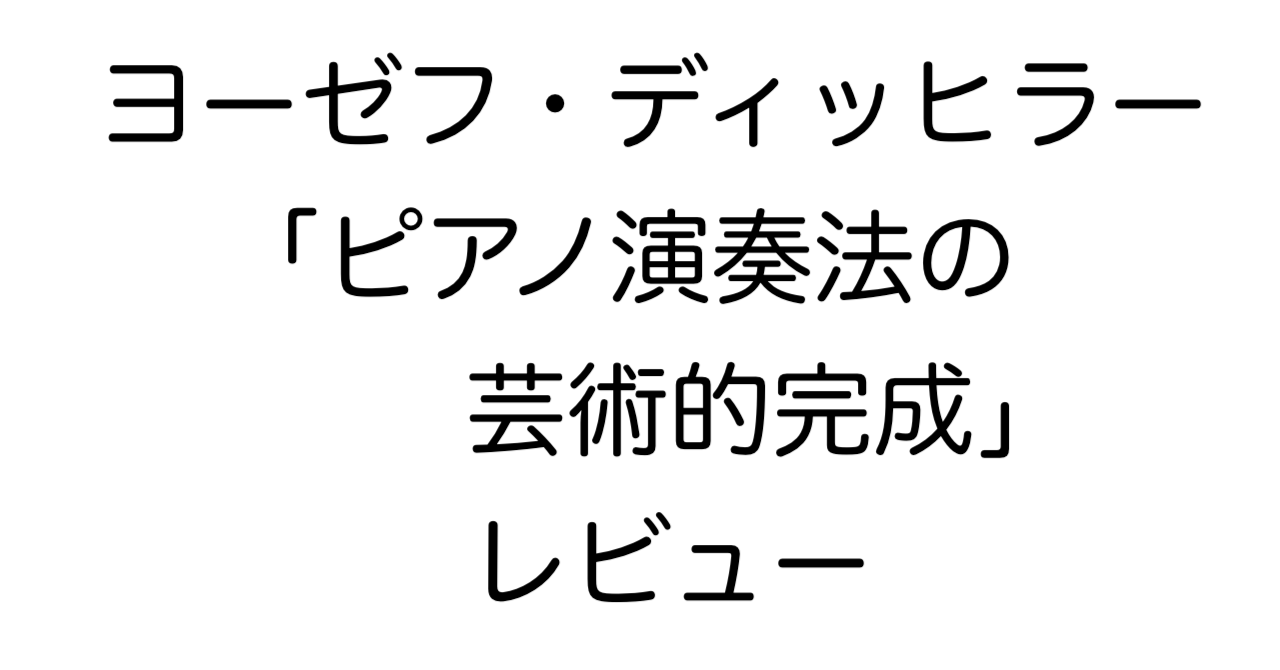

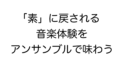
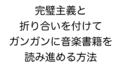
コメント