【ピアノ】弾いている作品の楽曲情報の調べ方
► はじめに
楽曲の情報を何も調べずに目の前の楽譜だけを見て、ひたすら音を追いかけている学習者は多いようです。しかし、音楽は音の羅列ではありません。明らかになっている作曲家の思いや時代背景、作品の意図を知ることで、解釈のヒントになることがありますし、そもそも演奏自体が格段に楽しくなります。
楽曲情報を調べることには、具体的に以下のようなメリットがあります:
楽曲の構造をより深く理解できる
形式や構成を理解することで、作品全体の流れを把握し、各部分の役割や関連性が明確になる
作曲家の意図に沿った解釈ができる
作曲の背景や作曲家の残した言葉を知ることで、音楽的表現の方向性が見えてくる
例えば、「水の精」がテーマの作品と知ったら、重くならないほうがいいのではないかと考える、等
同時代の他の作品との関連が見えてくる
作曲された時代の美学や他の作品との影響関係を知ることで、作品をより広い文脈で理解できる
音型の意味が理解できる
ただの技術的困難として捉えていた箇所が、実は特定の表現意図を持っていたことが分かる
本記事を通して、どのように楽曲情報を調べていけばいいのかを見ていきましょう。
► 基本的な情報の集め方:信頼できる資料を活用する
ネット情報の取り扱いに注意
インターネット上には膨大な情報が溢れていますが、ネットに落ちている情報を過信し過ぎないよう注意しましょう。特に出典が明記されていない情報などには誤りが含まれていることもあります。可能な限り、複数の情報源で確認することをおすすめします。
ピアノ曲情報が掲載された基本的な書籍資料
情報量は限られていますが、楽曲解説が掲載されている代表的な書籍として以下があります:
・ピアノ音楽史事典 著:千蔵八郎 / 春秋社
・名曲事典 ピアノ・オルガン編 著:千蔵八郎 / 音楽之友社
・鍵盤音楽の歴史 著 : F.E.Kirby 訳 : 千蔵八郎 / 全音楽譜出版社
・ピアノ音楽事典 作品篇 著:分担執筆 / 全音楽譜出版社
・ピアノ・レパートリー事典 著:高橋淳 / 春秋社
・最新名曲解説全集 独奏曲シリーズ / 音楽之友社
・作曲家別名曲解説ライブラリー / 音楽之友社(「最新名曲解説全集」と解説文言は重複している)
・新訂 ピアノの学習 著:長岡敏夫 / 音楽之友社
・ピアノ学習ハンドブック 著:千蔵八郎 / 春秋社
推奨記事:【ピアノ】ピアノ音楽事典系5冊の徹底比較レビュー:学習目的別の選び方ガイド
これらの書籍は基本的な情報を得るための最低限の資料と言えます。しかし、より深い理解を求めるためには、さらに踏み込んだ資料にあたる必要があるでしょう。
さらに深く掘り下げるために
より専門的な情報を求める場合は、本Webメディアの「【ピアノ】楽曲分析を深める方法:専門書・マスタークラス・研究論文の活用ガイド」という記事で紹介している方法で、追加資料を探していくことをおすすめします。具体的には:
・著名なピアニストによるマスタークラスの記録
・音大図書館や国会図書館に置いてある専門書
・博士論文
・音楽学術雑誌の論文
・その作品の作曲家や編曲家への直接の問い合わせ
これらは、作品の情報についてさらなるヒントを提供してくれます。
日常的な情報収集の姿勢
また、日頃その楽曲のことを常に意識しておき、近しい情報を見かけた時にすぐに拾える自分でいることが非常に重要です。例えば:
・コンサートのプログラムノート
・音楽雑誌の特集記事
・関連するドキュメンタリー
・音楽講座やセミナー
これらは偶然目にする機会があるかもしれませんが、「今取り組んでいる曲」を常に念頭に置いていれば、貴重な情報源となり得ます。情報収集は一度で終わるものではなく、継続的なプロセスです。
► 楽曲情報収集のコツ
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
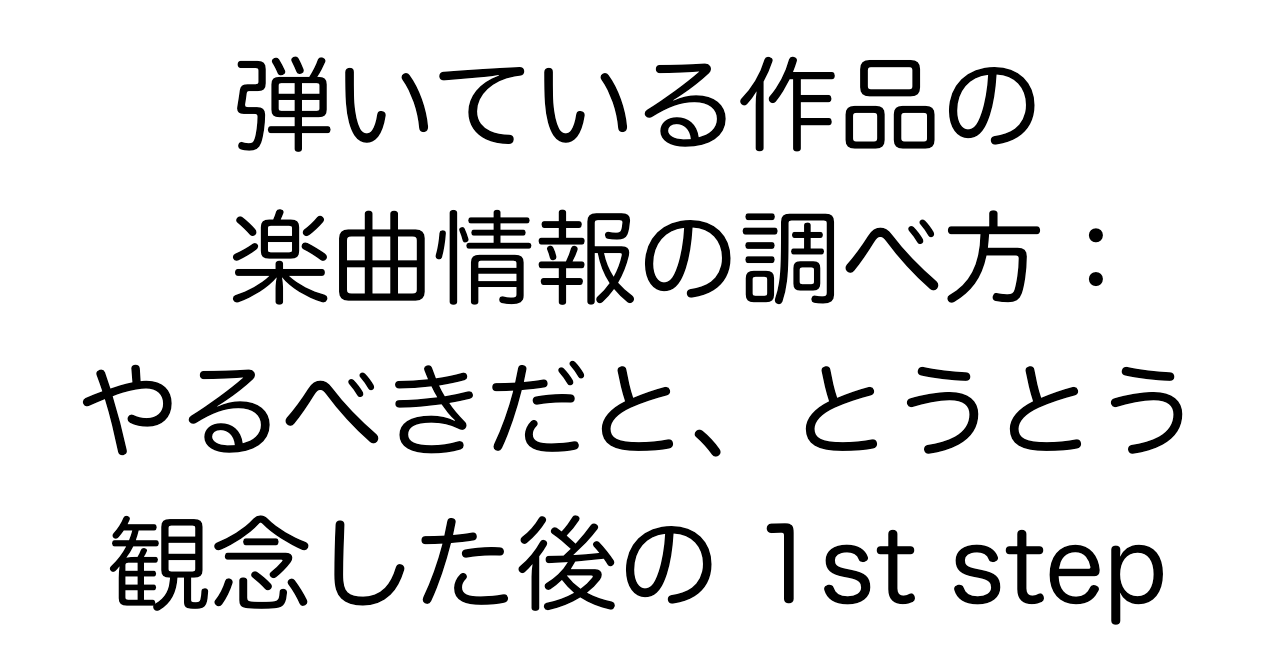

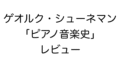
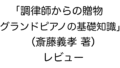
コメント