【ピアノ】楽曲分析の基本は「皿回し」によるアプローチ
► はじめに
本記事では、楽曲分析を「皿回し」に例えたアプローチを紹介します。これから紹介する方法は、初心者から上級者まで、あらゆるレベルのピアノ学習者に役立つものです。様々な視点から楽曲を観察し続けることで、より深い音楽理解へと到達できるでしょう。
► 皿回しによる3つのアプローチ
‣「皿回し」のように複数の分析視点を同時に考慮する
・一つの視点だけでなく、複数の視点から何度も楽曲を観察する
・視点を切り替えながら、相互関連性を探る
楽曲分析では、「この視点から調べる」「この視点からも調べる」「さらにこの視点からも調べる」などと、視点を切り替えながら、あらゆる方向から何度も同じ楽曲を見ていくことが深い読み取りのヒントとなります。このようにすることで、飽きがこないうえに、それぞれの視点が互いに影響し合っている要素も見つけることができるからです。
視点は様々ですが、最も基本的な分析視点を挙げておきましょう:
・楽曲構成
・調性の大まかな流れ
・楽曲を支配しているリズムや特徴的なリズム
・音の形(単音と和音の使い分け)
・多声的な書法
・音域(最高音域、最低音域、両手の音域の離れ方の移り変わり)
・音色面での工夫
・ダイナミクス
・フレージングとアーティキュレーション
・メロディ線の特徴
・各音の役割分担
・楽曲中の共通点
・繰り返しパターン
これらのような複数のアプローチ視点を持っておいて、皿回しのように調べて考えていくようにしましょう。
一つの視点につき一度調べたら終わりではありません。例えば、「ダイナミクスについて調べた後に音域について調べたら、ダイナミクスについての新たな発見があった」などといった場合には、再度ダイナミクスについて細かく見てみると効果的です。
楽曲によっては、「縮節」「和声的リズム」「無伴奏表現」など、他にも様々な視点が必要になります。これらについては「楽曲分析学習パス」を参考にしてください。また、この学習パスでは実例分析を多数用意しているので、本記事の内容の実践例を具体的に確認することもできます。
‣「皿回し」のように楽譜と音源と楽器を行き来する
「楽譜を見ることと、音源を聴くことをどのように学習に取り入れるか」についてですが、やはり以下の皿回しによるアプローチをおすすめします:
・楽譜を読む
・楽譜を読みながら音源を聴く
・楽譜を見ないで音源を聴く
・ピアノで弾いてみる
様々なやり方を使ってアプローチし、思いついたことをガンガン書き込んでください。
これらの方法を皿回しのように循環させることで、楽曲への理解が立体的になります。例えば、最初に楽譜を読んだときには気づかなかった細かなニュアンスを、音源を聴くことで発見できるかもしれません。また、ピアノで実際に弾いてみることで、指の動きや身体感覚を通じて新たな気づきが生まれることも少なくありません。
ちなみに、「楽譜を見ないで音源を聴く」時には、部屋を暗くして雰囲気を出すのも気分転換になるのでおすすめです。筆者もよくやっています。
‣「皿回し」のように複数曲を交互に分析する
例えば、「A、B、C」という3曲を分析するとしましょう。この場合、「A、A、B、B、C、C」などと1曲を長く分析するよりも、「A、B、C、A、B、C 」というように皿回しにしたほうが理想的な分析ができます。
この方法には複数の利点があります:
1. 適度な刺激になり集中力が持続する
同じ作品ばかりを分析していると、どうしても思考が固定化してしまいがちですが、異なる作品を回しながら分析することで、常に新鮮な視点を維持できるでしょう。
2. 作品比較の視点を持つことができる
複数の作品を並行して分析することで、作曲家の特徴や時代様式の共通点と相違点を発見しやすくなります。
3. 学習のバランスの達成
難易度の異なる曲を組み合わせることで、学習のバランスも取れます。高度な作品のみを連続して分析すると疲労感が増しますが、比較的シンプルな曲と交互に行うことで、持続可能な学習サイクルを作ることができるでしょう。
► 終わりに
楽曲分析を「皿回し」として捉えるアプローチは、単調になりがちな分析作業に新鮮さをもたらすだけでなく、多角的な視点を養うことにも繋がります。
重要なのは、「和声分析」という一つの視点に固執せず、様々な角度から楽曲を観察し続けることです。そして、それぞれの視点が互いに影響し合い、新たな発見へと導いてくれることを忘れないでください。
► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
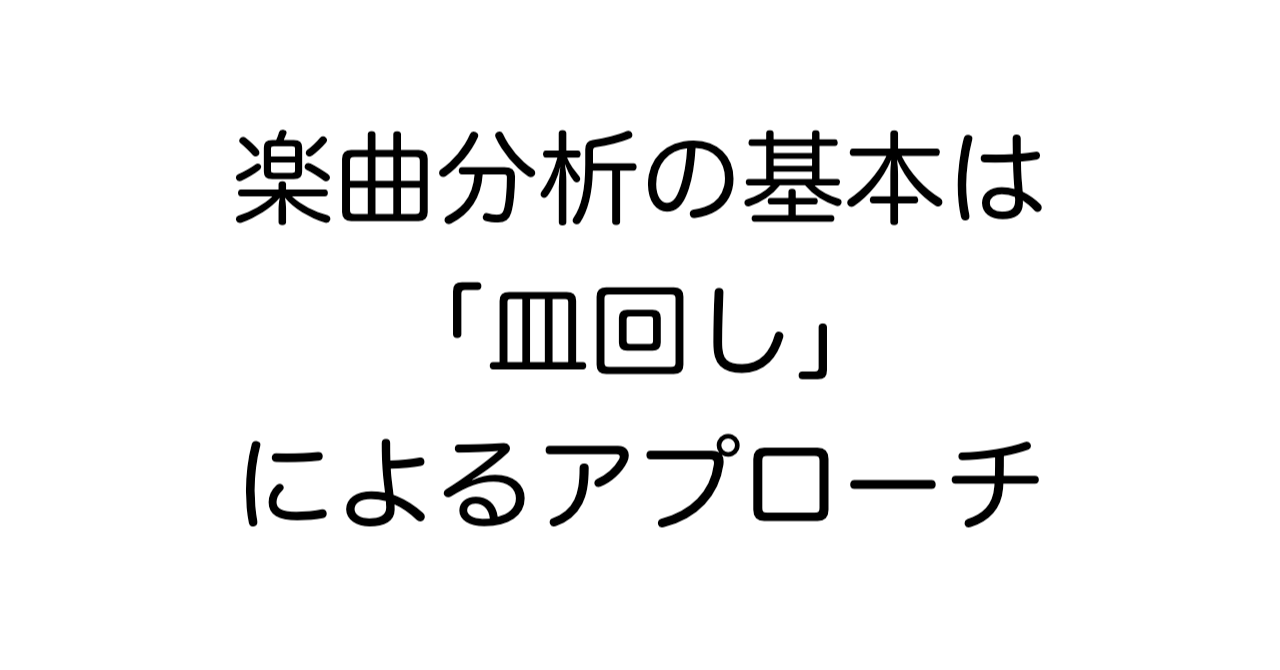
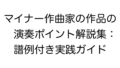
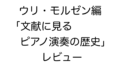
コメント