- 【ピアノ】先生に聞けない素朴な疑問10選:真面目に答えるQ&A集 vol.14
- ► はじめに
- ► 質問集
- ‣ Q1. ゆっくり練習はいつまでやるのがベスト?
- ‣ Q2. ピアノの連弾練習で、相手とのテンポのズレをどう解消すべき?
- ‣ Q3. ピアノ椅子に座布団を敷いてもいい?
- ‣ Q4. 本番前のカイロ、どう準備すればいい?
- ‣ Q5. 楽譜の保管、どうすれば散らからない?
- ‣ Q6. 楽譜の版による指示の違いにどう対応すればいい?
- ‣ Q7. 音楽をより深く楽しむために、同じ作曲家のピアノソロ以外も聴くべき?
- ‣ Q8. SNSで先生が風邪気味と言っていたが、レッスンをキャンセルしてもいい?
- ‣ Q9. 学習における「将来の目標」をどのくらいの規模で設定すべき?
- ‣ Q10. ピアノ学習を続けている自分を、他人にもっと知ってほしいという気持ちは恥ずかしい?
- ► 終わりに
【ピアノ】先生に聞けない素朴な疑問10選:真面目に答えるQ&A集 vol.14
► はじめに
・「こんなこと、先生に聞いていいのかな…」
・「ググっても明確な答えが出てこない…」
こういった、聞きにくいけど実は気になるピアノ関連の疑問に、真面目に答えます。レッスンに通っている方はもちろん、スポット(単発)レッスンを受ける独学の方にも参考になる内容です。
関連記事:
► 質問集
‣ Q1. ゆっくり練習はいつまでやるのがベスト?
結論:仕上げを想定した実際の形で練習できるのであれば、もう必要ない
「ゆっくり練習は大切」とよく言われますが、実は万能ではありません。
重要なのは「今、この箇所に困難を感じているか」という点です。すでにスムーズに弾ける部分を、わざわざスローテンポで繰り返す必要はないのです。その時間は、まだ課題が残る別の箇所に投資しましょう。
もう一つの理由があります。最終的な音楽表現は、本来のテンポでしか作れません。遅いテンポでばかり練習していると、音楽的なニュアンスや音色の変化が後回しになりがちです。
ゆっくり練習を取り入れる場合も、「できるだけ早く実際のテンポで練習できる状態」を目指すのが賢明です。
‣ Q2. ピアノの連弾練習で、相手とのテンポのズレをどう解消すべき?
結論:合図の担当を明確にし、セコンドパートの安定度を見直す
連弾でよくある悩みが「なぜか息が合わない」という問題。実は、解決の糸口は明確です。
合図は必ず「1人」が出す
よくある失敗パターンが、2人とも同時に首を振って合図を送ろうとすること。これはほぼ確実にズレます。
解決策はシンプルです:
・曲の各セクションで「誰が合図を出すか」を事前に決定
・担当者だけが明確に合図を送る
・もう一人はその合図を「受け取る」側に徹する
この役割分担が、アンサンブルの精度を劇的に向上させます。
セコンドがリズムの「軸」になっているか確認
多くの連弾作品では、セコンドがリズムの基盤を支えています。セコンドが不安定だと、どんなに合図を工夫しても噛み合いません。
チェックポイント:
・リズムを明確に刻めているか
・プリモと相談なく、勝手にテンポを揺らしていないか
セコンドが安定すれば、アンサンブル全体が格段に演奏しやすくなります。
推奨記事:【ピアノ】アンサンブルでのタイミングの合わせ方:ピアノ編成での実践的アプローチ
‣ Q3. ピアノ椅子に座布団を敷いてもいい?
結論:できる限り使わない方が望ましい
座高調整や硬い座面対策として座布団を使いたくなる気持ちは分かります。絶対NGというわけではありません。
ただし、考えてほしいのは「本番との環境差」です。
演奏会やコンクールの会場に、座布団はありません。練習環境を本番に近づけるほど、当日の違和感は減ります。「いつもと同じ」状態で演奏できることが、パフォーマンスの安定につながるのです。
どうしても必要な場合は、せめて薄手のものを選び、本番数週間前からは使わずに練習する期間を設けることをおすすめします。
‣ Q4. 本番前のカイロ、どう準備すればいい?
結論:季節を問わず、未開封のカイロを必ず持参する
「冬場の本番にはカイロを持っていく」——これは誰もが実践していることでしょう。
しかし重要なのは「春や秋でも持っていく」という点です。
緊張すると手は冷える
人間の手は、緊張状態で驚くほど冷たくなります。室温が快適でも、身体が温まっていても、手だけは氷のよう——そんな経験をしたことがあるはずです。
つまり、気温が温暖な季節でも、カイロは「精神的な保険」として機能します。使わなければそれでよし。でも必要になったときに持っていないと、演奏に支障をきたします。
「貼るタイプ」が圧倒的に有効
貼らないタイプも悪くありませんが、貼るタイプのほうが圧倒的に温かい印象です。
ステージ袖での待機中は貼らないタイプを使い、それ以外の時間帯は貼るタイプで全身を温める。この使い分けがベストでしょう。
貼るタイプは、以下のものが定番です。
‣ Q5. 楽譜の保管、どうすれば散らからない?
結論:平積み厳禁・毎日触るもの以外は即片付け・少量ずつ整理する
ピアノの上に楽譜の山。ぱんぱんに膨れた封筒の束。こんな光景、心当たりありませんか。
デジタル譜面でも同じです。フォルダ管理を怠ると、あっという間にカオス状態になります。そして最悪の事態——すでに持っている楽譜を再購入——が起こります。
楽譜管理を習慣化する3原則
原則1:少しずつ、毎日整理する
「いつか片付けよう」は永遠に来ません。半日仕事になる前に、5分でいいから毎日整理する。この差は絶大です。一度この「楽さ」を体感すると、自然と習慣になります。
原則2:平積みはNG
見た目がすっきりしても、下の楽譜を取り出すのは相当面倒です。「平積みは楽譜管理の最大の敵」——この認識を持ってください。平積みをやめるだけで、ピアノの上が楽譜置き場になる可能性までなくなります。
原則3:出しっぱなしは「毎日使うもの」だけ
それ以外は視界から消しましょう。管理が楽になるだけでなく、練習への集中力も高まります。
‣ Q6. 楽譜の版による指示の違いにどう対応すればいい?
結論:採用した情報の「出典」を明確に把握しておく
版によってアーティキュレーションが違う。場合によっては音符そのものが異なる——こんな状況に出くわすと、混乱することでしょう。
シンプルな解決法
採用した表現が「どの版由来か」を言えるようにしておく——これだけです。
例:ヘンレ版のショパン「革命のエチュード」27小節目には、他版にないタイが記されています。これを採用するのであれば、「ヘンレ版を使用している」と自覚していればOK。
複数版から情報を取り入れる場合の注意
異なる版を参照するのであれば、必ず:
・「この部分のタイは〇〇版から採用」
・「この pp は△△版の指示に従った」
このように、トレーサビリティ(追跡可能性)を確保してください。
推奨記事:【ピアノ】楽譜の版選び:悩みとモヤモヤを解消する方法
‣ Q7. 音楽をより深く楽しむために、同じ作曲家のピアノソロ以外も聴くべき?
結論:積極的に聴くべき。ただし「すぐに役立つ」ことは期待しない
「些細な発見」を喜ぶ姿勢が大切
モーツァルトの例を挙げましょう。
モーツァルト「ピアノソナタ ト長調 K.283 第1楽章」譜例(PD楽曲、Finaleで作成、16-19小節)

16-19小節の動機素材が、「ピアノ協奏曲 第17番 ト長調 K.453 第1楽章」のカデンツァにも、ほぼ同じ形で登場します。この事実を知っても、演奏技術が向上するわけではありません。でも、作品への理解が一歩深まる——その小さな喜びがあるのです。
他ジャンルの作品を聴くときは、こうした「直接的には役立たない発見」にいちいち反応してください。その積み重ねが、音楽への愛着を育てます。
学習そのものを拡張する楽しみ方
例えばシューマンの歌曲。妻のクララがピアノソロに編曲した30曲があります。「原曲の歌曲を聴く → クララの編曲版を弾く」という流れで学習を広げると、音楽体験が立体的になります。
推奨記事:【ピアノ】クララ編曲「ロベルト・シューマンの30のリートと歌」全曲:選曲・難易度 完全ガイド
‣ Q8. SNSで先生が風邪気味と言っていたが、レッスンをキャンセルしてもいい?
結論:可能だが、伝え方には最大限の配慮を
先生が体調管理に配慮する方であれば、レッスンを実施すべきでないと判断したら、自ら休講にするはずです。つまり、生徒側からのキャンセルは本来は角が立つ行為です。できる限り避けるべきでしょう。
やむを得ずキャンセルする場合の伝え方
もし申し出る場合は、以下のように「配慮」と「正当な理由」の両方を丁寧に伝えてください:
先生への思いやりを示しつつ、自分側の事情も説明する——このバランスが重要です。
‣ Q9. 学習における「将来の目標」をどのくらいの規模で設定すべき?
結論:長くても半年以内・自分でコントロール可能な内容にする
長期目標が達成されない理由
「3年後にショパンのバラード全曲を弾けるようになる」——こんな目標を立てたことはありませんか?
残念ながら、長期目標はちょっとした環境変化で簡単に崩れます。
一方、1ヶ月程度の目標なら、多少のトラブルがあっても達成できます。この成功体験を繰り返すことで、着実に実力が向上します。うまくいかないパターンも早期に発見できます。
推奨:目標期間は最長でも半年まで
「自分でコントロールできる目標」を中心に
以下は自分でコントロールできません:
・「〇〇コンクールで入賞する」
・「〇〇ホールで演奏する」
結果は外部要因に左右されます。大きなモチベーションにはなりますが、達成できなかったときの精神的ダメージが大きいのです。
対照的に、以下は完全にコントロール可能です:
「毎日2時間練習する」
「朝7-8時は必ず練習時間にする」
「2週間でこの楽曲を譜読み完了する」
こうした目標を積み重ねていきましょう。
‣ Q10. ピアノ学習を続けている自分を、他人にもっと知ってほしいという気持ちは恥ずかしい?
結論:むしろ堂々と公言すべき。隠れてやるほうが恥ずかしい
この疑問を持つのは、おそらくピアノを始めて間もない方でしょう。
筆者も最初は同じでした。「弾けるようになりたいけど、発表会は絶対に嫌だ」と本気で思っていました。
ところが不思議なもので、ある程度弾けるようになると、人前で演奏したくてたまらなくなります。この心境変化は、多くの学習者が経験することです。
継続者だけが味わう瞬間
これから長く続けていくと、いずれこんな言葉を投げかけられます。
「まだピアノやってるの?」
挫折した人からの、半ば皮肉めいた一言。このとき、恥ずかしいと思う必要は一切ありません。それどころか、今までの2倍の熱量で取り組むくらいの気概を持ってください。
継続すること——それ自体が、何よりも誇るべき実績です。
► 終わりに
先生に聞けないこと、ググってもあまり出てこないこと、たくさんあります。そんな小さな疑問を一つずつ解決していくことでピアノ学習を楽しくしていきましょう。
関連記事:
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
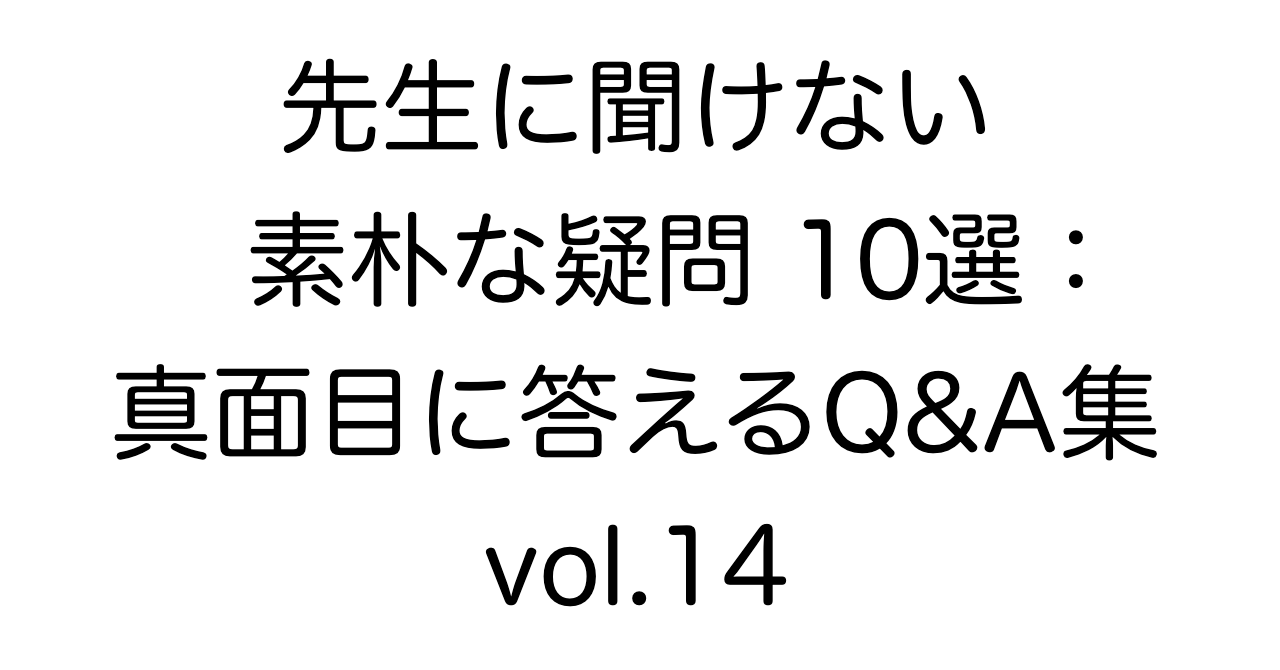

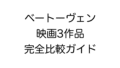
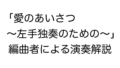
コメント