【ピアノ】エファ&パウル・バドゥーラ=スコダ「新版 モーツァルト 演奏法と解釈」レビュー
► はじめに
モーツァルトの演奏に真剣に取り組む学習者にとって、「新版 モーツァルト 演奏法と解釈」は、まさに宝庫とも言える一冊です。20世紀を代表するモーツァルト演奏の権威であるパウル・バドゥーラ=スコダとその妻エファによる本書は、モーツァルトの音楽の本質に迫る貴重な研究書となっています。
本記事では、この名著についてレビューしていきます。
・出版社:音楽之友社
・発行年:新版 2016年
・ページ数:新版 669ページ
・対象レベル:中級~上級者
・新版 モーツァルト 演奏法と解釈 著 : エファ&パウル・バドゥーラ=スコダ 訳 : 堀朋平、西田紘子 監訳 : 今井顕 / 音楽之友社

► 著者について
パウル・バドゥーラ=スコダ(1927-2019)は、ウィーン出身のピアニストであり、特にモーツァルト、ベートーヴェン、シューベルトの演奏と研究で高い評価を受けてきました。彼は演奏家としてだけでなく、研究者としても業績を残しており、モーツァルトの演奏慣習に関する深い洞察力は、この書籍に存分に発揮されています。
妻のエファ・バドゥーラ=スコダは研究者として、数多くの大学で教鞭を執り、本書の執筆においても重要な役割を果たしています。
► 内容について
‣ 内容の充実度
本書の最大の魅力は、その徹底的な情報量と緻密な分析にあります。12章構成で、各章においてモーツァルトの演奏に関わる様々な側面を詳細に論じています。特に注目すべき点を挙げていきましょう:
第1章:モーツァルトの響きの世界
この章では、モーツァルト時代の鍵盤楽器について詳述されています。その時代の楽器特性を知ることは、現代のピアノでモーツァルトを演奏する際にも重要ですし、楽曲そのものを理解するヒントにもなります。
第2章:デュナーミク(強弱)
モーツァルトの楽譜には、基本的に f(フォルテ)と p(ピアノ)の二つの強弱記号しか出てこないことが多いですが、この章では、そうした限られた記号の解釈方法と、どのように表現を実現するかについて詳しく解説されています。
第3章:テンポとリズムの問題
モーツァルト作品のテンポ設定は、しばしば演奏者を悩ませる問題でしょう。この章では、モーツァルト時代のテンポ感覚や、各テンポ指示の意味するところが、歴史的背景も含めて詳細に解説されています。
「きわめて重要なテンポ記号のリスト」では、モーツァルトの代表的なテンポ指示とその解釈が一覧化されており、実際の演奏準備に役立つ内容となっています。
第4章:アーティキュレーション
モーツァルトの音楽における「発音」の問題は極めて重要です。この章では、レガート、スタッカート、ポルタートなどの様々なアーティキュレーションの解釈と実践方法が詳述されています。
特に注目すべきは、「アーティキュレーションスラーとレガートスラー」の区別についての解説です。モーツァルトの短いスラーは現代の長いフレージングとは異なる意味を持ち、その解釈はマストでおさえておくべきでしょう。
第5章・第6章:装飾音と即興的装飾
この二つの章では、モーツァルト音楽における装飾の問題が論じられています。アッポッジャトゥーラ、ターン、トリルなどの記譜された装飾音の正しい演奏法から、モーツァルト自身が行っていたであろう即興的な装飾について、豊富な例と共に解説されています。
第7章:カデンツァとアインガング
モーツァルトのピアノ協奏曲演奏における大きな課題の一つ、カデンツァとアインガング(カデンツァよりずっと短く、多くの場合主題とは無関係)について詳細に解説されています。
フェルマータ装飾の適切な場所、そしてアインガングを演奏すべきではない箇所など、実践的な情報が満載です。
第8章:「表現と趣味」
この章では、モーツァルトの音楽における「表現」の問題が多角的に論じられています。強弱、アーティキュレーション、リズム、和声などを活用した表現方法など、モーツァルト音楽の性格を生き生きと伝えるための方法が詳述されています。
第9章・第10章:楽譜と共演の問題
これらの章では、モーツァルト作品の楽譜に関する問題と、オーケストラとの共演における実践的な課題が論じられています。
新モーツァルト全集をはじめとする楽譜版の評価や、ピアノ協奏曲におけるオーケストラとのやりとり、コンティヌオの演奏など、実演に関連する問題が詳しく解説されています。
第11章・第12章:技術的問題と個別作品の解釈
最後の2章では、モーツァルトのピアノ作品における技術的な問題と、5つの代表的作品(ピアノ協奏曲 K.466、K.488、K.491、ピアノソナタ K.310、K.331)の詳細な演奏解釈が提示されています。
これらの作品解釈は、それまでの章で論じられてきた原則や考え方が、実際の楽曲においてどのように適用されるかを示す実例として極めて価値があります。
‣ 本書の特徴
1. 歴史的背景と実践的アドバイスの融合
本書の特徴の一つは、歴史的研究と実践的な演奏アドバイスが見事に融合している点です。バドゥーラ=スコダ夫妻は、18世紀の音楽理論書や同時代の証言などの一次資料を丹念に研究しながらも、それを単なる学術的議論に終わらせず、現代のピアニストがどのように実践すべきかという具体的な提案にまで落とし込んでいます。
2. 演奏家の視点
著者のパウル・バドゥーラ=スコダは、研究者であると同時に一流のピアニストでもありました。そのため、本書の記述には常に「実際の演奏場面でどうするか」という視点が含まれており、理論と実践のバランスが絶妙です。
3. 豊富な譜例と解説
本書には数多くの譜例が掲載されており、テキストでの説明と合わせて理解を深めることができます。
4. 包括的な内容
モーツァルトの鍵盤音楽演奏に関するあらゆる側面 —楽器、テンポ、強弱、アーティキュレーション、装飾、解釈など— を包括的にカバーしており、まさに「モーツァルトの鍵盤音楽の教科書」と呼ぶにふさわしい内容です。
► 留意点
・本書は中級者以上を主な対象としており、初心者には難解な内容も含まれている
・個別の楽曲解釈は5曲のみであり、他の作品については読者自身が本書の原則を応用する必要がある
・ただし、楽曲解釈以外の項目でも、他の作品を通した解釈に準じる記述が多彩
・669ページにも及ぶ大著であり、2周目以降は「必要に応じて辞書にする」という使い方が適している
► 終わりに
「新版 モーツァルト 演奏法と解釈」は、モーツァルトの鍵盤音楽演奏に関する包括的で権威ある書籍の一つです。音楽史的知識と実践的アドバイスのバランスが絶妙であり、モーツァルトの作品に真剣に取り組む学習者にとって、まさに必携の一冊と言えるでしょう。
モーツァルトの演奏に関する書籍はいくつか存在しますが、もし一冊だけ選ぶとすれば、間違いなくこの本をおすすめします。「何となくで弾くモーツァルト」を脱したい方は、一度手に取ってみてください。
・新版 モーツァルト 演奏法と解釈 著 : エファ&パウル・バドゥーラ=スコダ 訳 : 堀朋平、西田紘子 監訳 : 今井顕 / 音楽之友社

► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
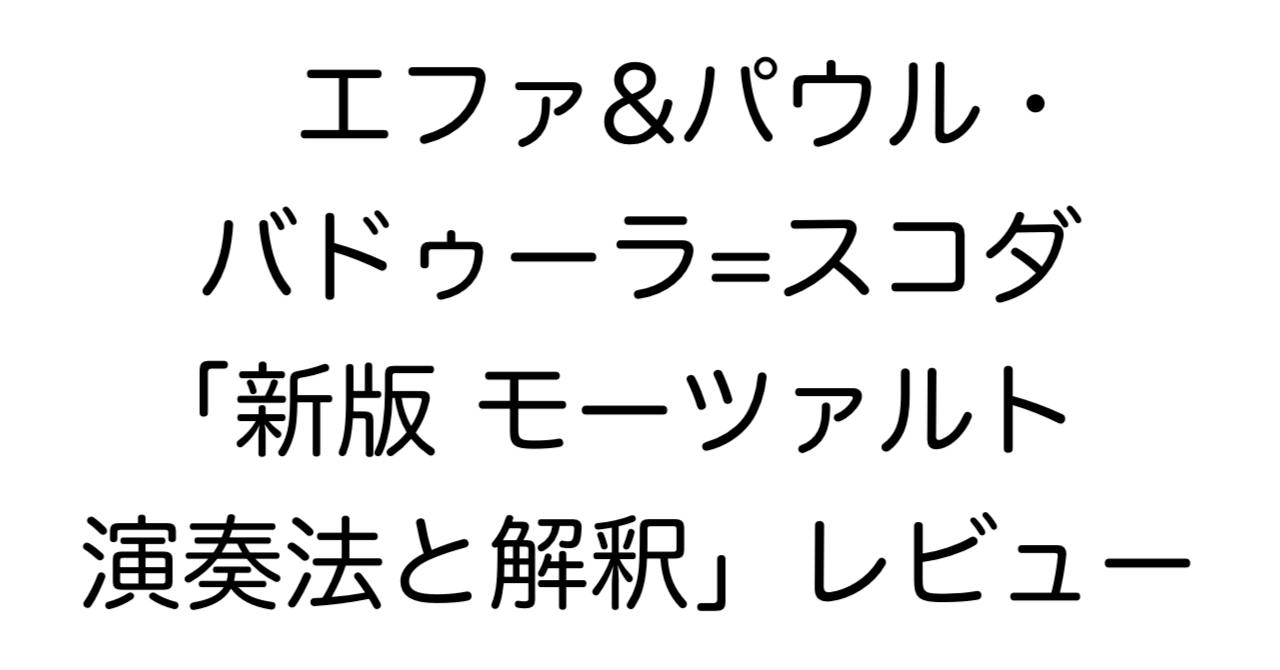
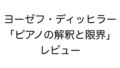
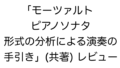
コメント