【ピアノ】映画「伴奏者」レビュー:状況内音楽が織りなす心理描写の妙技
► はじめに
クロード・ミレール監督による「伴奏者(L’accompagnatrice)」では、状況内音楽と状況外音楽の使い分けによって、登場人物の心理や物語の構造を描き出しています。
本記事では、主にピアノシーンに着目して、その音楽演出について紐解いていきます。
・公開年:1992年(フランス)/ 1993年(日本)
・監督:クロード・ミレール
・ピアノ関連度:★★★★☆
► 内容について
以下では、映画の具体的なシーンや楽曲の使われ方について解説しています。未視聴の方はご注意ください。
音楽用語解説:
状況内音楽
ストーリー内で実際にその場で流れている音楽。 例:ラジオから流れる音楽、誰かの演奏
状況外音楽
外的につけられた通常のBGMで、登場人物には聴こえていない音楽
‣ 音楽による視覚的錯覚
本作の興味深い演出の一つが、本編11分50秒頃に登場するピアノシーンです。ピアノの音が流れ、ピアノの前に立つ50代くらいの女性が映し出されます。観客は当然、これがピアノ教師であり、主人公のソフィがピアノを習っている場面だと予想するでしょう。
ところが次の瞬間、同じ部屋にいるピアノを弾いていないソフィの姿が映し出されます。この視覚的な「裏切り」によって、観客は自分の思い込みに気づかされます。実は、ソフィの母親(ピアノ教師)に習っているのはジェロームという男性で、その人物による演奏だったのです。この女性がソフィの母親だと明確に分かるのは、さらに後の本編30分頃になってからです。
この演出は、音楽が視覚情報に先行することで観客の認識を誘導し、後から状況を説明するという映画的手法の優れた例です。ピアノという楽器が持つ音色の魅力と、映像のタイミングを上手く組み合わせた場面と言えるでしょう。
‣ 状況内音楽が状況外音楽を断ち切る瞬間
本作のもう一つの注目すべき演出が、本編51分40秒頃に登場します。イレーヌの夫であるシャルルがピアノを叩いて不協和音を出す場面です。この不協和音(状況内音楽)によって、それまで流れていたBGM(状況外音楽)が急激にカットアウトされるのです。
音楽がカットアウトされる演出自体は映画でよく見られますが、状況内音楽によって状況外音楽がカットアウトされるという手法は、それほど多くありません。この演出が効果的なのは、シャルルの心理状態を音によって表現しており、状況外音楽のカットアウトによってそれが一層強調されるからです。
シャルルが叩いたピアノの音は、もはや音楽というよりは騒音です。これは状況内音楽であると同時に、「状況内音声」とも言えるでしょう。この騒音が、整った音楽的なBGMを強制的に中断させることで、シャルルの内面の混乱が鮮烈に表現されています。
‣ 暗い時代と明るい音楽の対比
「伴奏者」の舞台は1942年、ドイツ軍占領下のパリです。物語は戦争や国家問題を含み、主人公のソフィも影のある少女として描かれるため、映画全体には暗い雰囲気が漂っています。使用されるBGMも、シューマンの「森の情景 Op.82 より 第3曲 寂しい花」をはじめ、明るくない楽曲が多く選ばれています(エンドロールには使用楽曲のリストが流れます)。
しかし、ソフィの伴奏とイレーヌの歌で披露される演奏会のプログラムは、対照的に明るい曲も数曲選ばれています。この対照が実現できるのは、これらが状況内音楽だからこそです。
どんなに日常生活が暗く重苦しくても、プロの音楽家は演奏会では様々なプログラムを披露しなければなりません。この「暗い現実」と「明るい音楽」の対比は、芸術家としての使命と個人的な苦悩の間で揺れ動くソフィやイレーヌの心理を、言葉以上に強く物語っています。
► 終わりに
特に前半部分ではピアノ演奏シーンが豊富に登場し、物語の中核を成しています。ピアノという楽器が持つ繊細さと力強さ、伴奏者という立場が持つ複雑な意味合い、そして戦時下という極限状態における芸術の役割。これらすべてが音楽を通じて語られる本作は、音楽愛好家にとって必見の作品と言えるでしょう。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
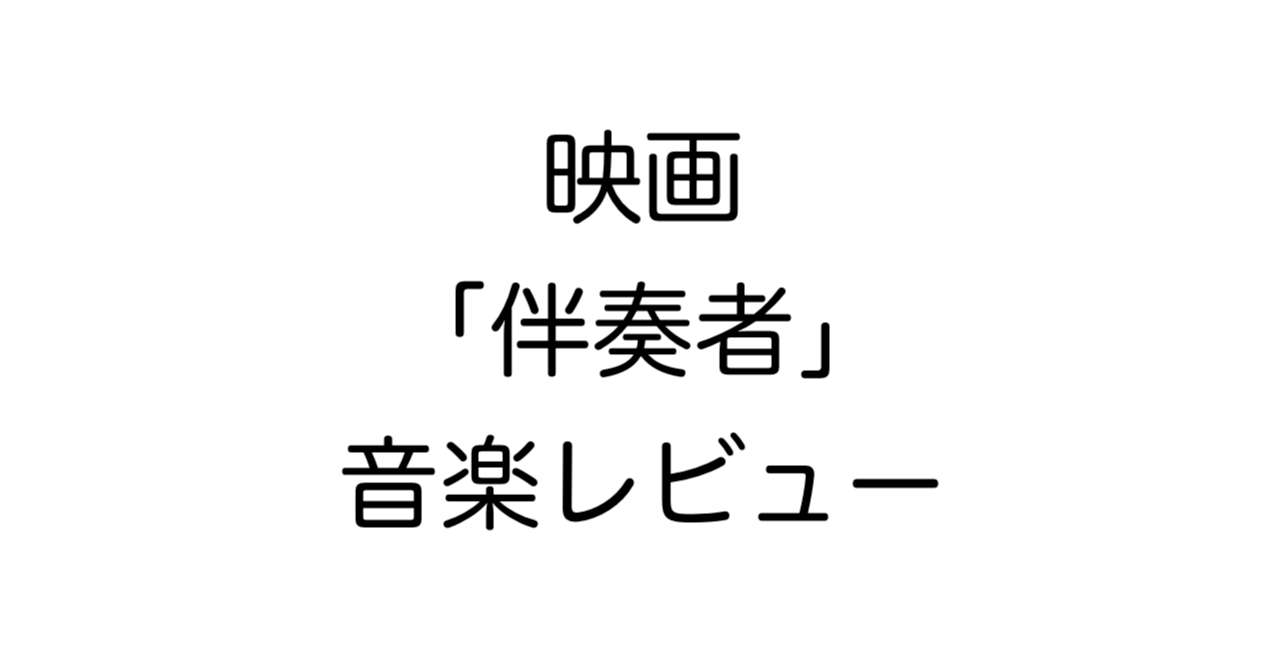
![伴奏者 クロード・ミレール監督 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51D4WS1u6SL._SL160_.jpg)
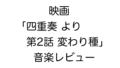

コメント