【ピアノ】映画「4分間のピアニスト」レビュー:ピアノ音楽演出の秘密を解説
► はじめに
女性刑務所を舞台に、80歳のピアノ教師トラウデ・クリューガーと、殺人罪で服役中の21歳の天才ピアニスト、ジェニー・フォン・レーベンの交流を描いた一作です。音楽を通じた人間の変容と魂の解放を、緻密な音楽演出によって描き出しています。
・公開年:2007年(ドイツ)/ 2007年(日本)
・監督:クリス・クラウス
・ピアノ関連度:★★★★★
※本作には過激な描写が含まれるため、視聴の際にはご注意ください。
► 内容について
以下では、映画の具体的なシーンや楽曲の使われ方について解説しています。未視聴の方はご注意ください。
音楽用語解説:
状況内音楽
ストーリー内で実際にその場で流れている音楽。 例:ラジオから流れる音楽、誰かの演奏
状況外音楽
外的につけられた通常のBGMで、登場人物には聴こえていない音楽
‣ オープニングの心理的トリック
映画冒頭、女性刑務所へグランドピアノが運び込まれるシーンでは、モーツァルト「ピアノソナタ ヘ長調 K.332 第2楽章」が流れます。この時点では建物の正体が明確ではなく、音楽学校かとも思わせる映像構成です。カメラが窓に注目することで、観客は「この建物の中で誰かが弾いている音楽(状況内音楽)かもしれない」と錯覚させられます。
しかし本編6分50秒頃、車のサイドブレーキをかける動作に合わせて音楽がカットアウトされることで、これが単なるBGM(状況外音楽)だったことが明かされます。全編を通して刑務所内に出てくるピアノは1台のみなので、状況内音楽から演出上移行させたとも考えられません。
この演出は、観客の期待を巧みに操り、音楽と映像の関係性について考えさせる興味深い導入となっています。
‣ 状況内音楽の革新的な使用例
本作には、独創的な状況内音楽の演出が随所に見られます:
① 楽器の切り替えによる継続演奏
本編12分頃、クリューガーが弾くモーツァルト「ピアノソナタ イ長調 K.331 第1楽章」の演奏が、オルガンからピアノへとシームレスに切り替わります。演奏の流れはそのまま継続し、楽器だけが変更されるという興味深い手法です。
② 手錠をしたままのピアノ演奏
本編35分頃、ジェニーは手錠をされたまま、制約された手の動きの範囲内で演奏します。このような特殊な状況での演奏は、刑務所を舞台にした本作ならではの表現です。
③ 机鍵盤での想像演奏
本編37分30秒頃、ジェニーは机を削って鍵盤の模様を描き、その上で演奏する動作をします。このとき流れる音楽は、彼女の頭の中で鳴っている想像上の音楽であり、厳密には状況外音楽でありながら、状況内音楽的な性格を持つ独特の表現となっています。
‣ 音楽ジャンルが象徴するジェニーの心理的変遷
本作のさらなる興味深い音楽演出は、演奏される音楽のジャンルそのものが、ジェニーの内面の変化を象徴的に表現していることです。
前半:反抗と葛藤
ジェニーが初めてピアノを弾くシーンで選ぶのは、クリューガーが「低俗な音楽」と蔑むポピュラースタイルの音楽です。これは彼女の反抗的な姿勢と荒んだ過去を象徴しています。
クリューガーの指導でクラシック音楽を演奏するようになった後も、本編35分頃には再びポピュラー音楽の演奏を始め、ビンタされてしまいます。しかし本編51分頃、ベートーヴェン「ピアノソナタ 第21番 ハ長調 Op.53 ワルトシュタイン 第1楽章」のレッスンでは、少し現代風にアレンジする程度に留まります。ここで初めてジェニーの笑顔が映し出され、彼女が心を開き始めたことが示されます。これが物語の重要な転換点となります。
後半:揺れ動く心と葛藤の深化
本編53分50秒頃、ジェニーは見ていたポピュラー音楽のTV番組をクラシック番組に変える様子が描かれ、彼女の変化が視覚的に示されます。しかし本編71分頃、ピアノ演奏を禁止されたことに反発し、再びオルガンでポピュラー音楽を演奏してしまいます。トラブルに直面すると、彼女の中の「本来の自分」が顔を出してしまうのです。
※ここで述べているジャンルの話題は、音楽の優劣の問題ではありません。映画としては、異なる文化や価値観を持つ2つの世界が、音楽を通じて対立しているさまを表現しています。
‣ クライマックスの4分間:音楽史的な意味
ラストシーンの4分間の演奏は、本作の音楽演出の集大成と言えます。
予定ではシューマン「ピアノ協奏曲 イ短調 Op.54」を演奏するはずでしたが、ジェニーは協奏曲の導入部を弾いた後、ポピュラースタイルへのアレンジと、内部奏法(ピアノ内部に手を入れ弦を引っ掻く など)をはじめとする主に20世紀以降に取り入れられた特殊奏法を取り入れた独自のアレンジを披露します。
演出の深い意味
ここで重要なのは、ジェニーが最終的にクラシックを正統的に演奏することはできなかったものの、特殊奏法という「西洋音楽史の延長線上にあるスタイル」に到達したという点です。つまり、彼女はクリューガーからの影響をしっかりと吸収し、音楽史の文脈の中で自己表現を確立したのです。
もしこのラストシーンで特殊奏法が使われていなければ、演出の意味は全く別のものになっていたでしょう。単なる反抗ではなく、クラシック音楽の影響を受けたうえでの新しい表現方法の獲得こそが、このシーンの着目点です。
そして、あれほど「低俗な音楽」と厳しく言っていたクリューガーが微笑みを浮かべる瞬間、二人の魂の交流が完結します。これは、伝統と革新、規律と自由、師弟関係の枠を超えた深い理解の到達を意味しているのです。
► 終わりに
本作では、状況内音楽と状況外音楽の巧みな使い分け、音楽ジャンルによる心理描写、音楽史的な文脈を踏まえたクライマックスの構成など、音楽演出面でも様々な工夫が見られます。
ピアノが好きな方、音楽映画を探している方、そして人間の自由と表現について考えたい方に、おすすめできる一作です。
※本作には過激な描写が含まれるため、視聴の際にはご注意ください。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
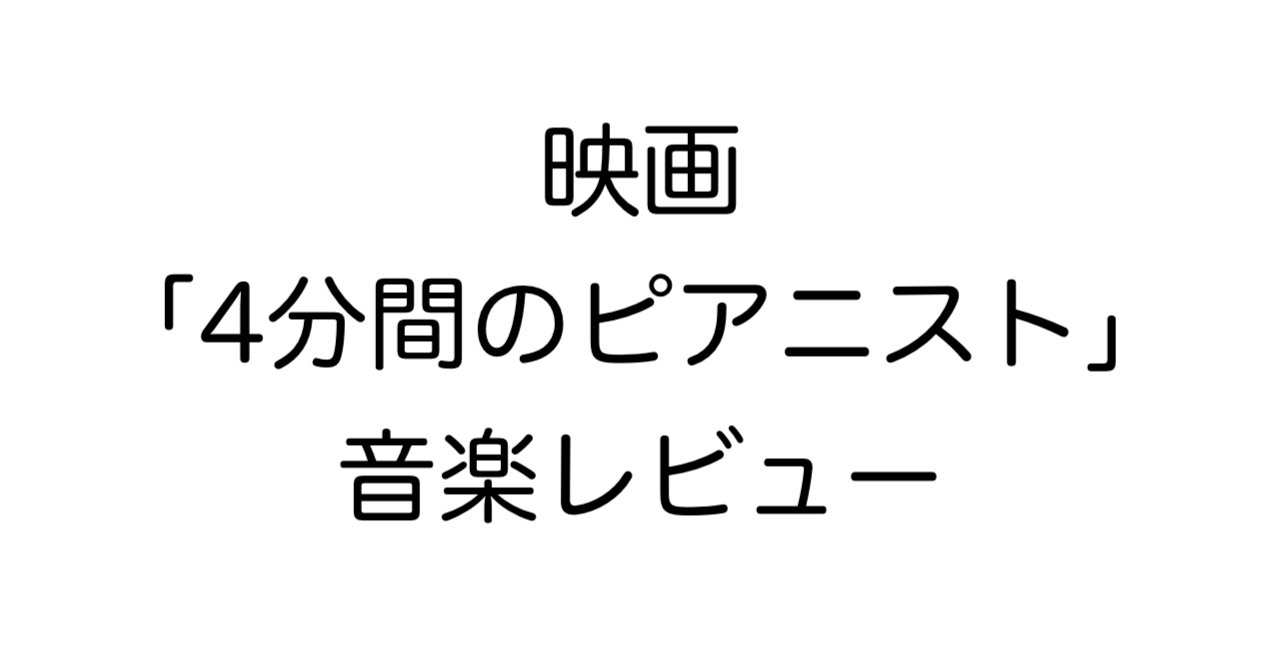
![4分間のピアニスト [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Ky+OL8J8L._SL160_.jpg)
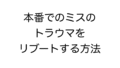
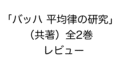
コメント