【ピアノ】映画「アメリカ交響楽」レビュー:ガーシュウィンの生涯を彩る音楽演出を解説
► はじめに
「アメリカ交響楽(Rhapsody in Blue)」は、20世紀アメリカを代表する作曲家ジョージ・ガーシュウィンの生涯を描いた伝記映画です。クラシックとジャズを融合させた音楽で時代を築いた作曲家の人生を、彼自身の名曲とともに綴る本作は、伝記映画の枠を超えた音楽映画の名作として知られています。
ロバート・アルダがガーシュウィンを演じ、オスカー・レヴァント、アル・ジョルソン、ヘイゼル・スコットといった実在の音楽家たちが本人役で出演している点も興味深く、当時の音楽シーンのリアリティを作品に与えています。
・公開年:1945年(アメリカ)/ 1947年(日本)
・監督:アーヴィング・ラパー
・ピアノ関連度:★★★★☆
► 内容について
以下では、映画の具体的なシーンや楽曲の使われ方について解説しています。未視聴の方はご注意ください。
音楽用語解説:
状況内音楽
ストーリー内で実際にその場で流れている音楽。 例:ラジオから流れる音楽、誰かの演奏
状況外音楽
外的につけられた通常のBGMで、登場人物には聴こえていない音楽
‣ 冒頭シーンに込められた予言的演出
映画開始2分頃、子供時代のガーシュウィンが登場する印象的なシーンがあります。ここで彼はアントン・ルビンシテインの「ヘ調のメロディ」を演奏するのですが、注目すべきはそれが自動ピアノとの共演である点です。
自動ピアノが奏でるメロディに合わせて、少年ガーシュウィンが別のパートを弾く──この演出は、まるでピアノデュオのような響きを生み出します。これは、後年ガーシュウィンが数多くの2台ピアノ作品を生み出すことになる彼の音楽人生を、冒頭で予言的に暗示していると考えてもいいでしょう。実際、映画の中盤以降には2台ピアノによる華麗な演奏シーンも登場します。
さらに音楽演出的に見ても、このシーンは非常に興味深い構造を持っています。自動ピアノという「状況内音楽」に、実際に演奏する「状況内音楽」が重なるという、この組み合わせによる二重の状況内音楽の構造は比較的珍しく、映画音楽の演出としても着目すべき試みと言えるでしょう。
‣「ヘ調」が紡ぐ音楽的対称性
本作には巧妙な音楽的伏線が張り巡らされています。その最たる例が「ヘ調」という調性を軸にした対称的な構成です。
映画の冒頭で少年ガーシュウィンが弾くのはルビンシテインの「ヘ調のメロディ」。そして物語の終盤、ガーシュウィンが観客の前で最後に演奏する作品として描かれるのが、彼自身の「ヘ調のコンチェルト」(ピアノ協奏曲 ヘ調)なのです。
この選曲は決して偶然ではありません。少年時代にルビンシテインの作品に触れたことから始まった音楽の旅が、映画の中では自身の「ヘ調」の大作へと結実する──この音楽的な円環構造は、一人の作曲家の人生を象徴的に表現しています。同じ調性でありながら(※)、ロマン派の作品から20世紀アメリカ音楽の大作へとつながる過程そのものが、ガーシュウィンの芸術的成長を物語っているのです。
※自動ピアノの演奏と一緒に弾いている「ヘ調のメロディ」は「ホ調」で、その後にガーシュウィンが自宅で演奏している場面では「ヘ調」になっています。
‣ BGM音楽が語るストーリーテリング
本作のBGM(状況外音楽)は、極めて「説明的」です。これは批判的な意味ではなく、むしろこの映画においては、音楽としての機能を発揮した洗練された手法と言えます。オーケストラによるBGMが、映像の内容に呼応して有機的に変化していく様は、まるで映画全体が一つのメドレーのような構成を持っています。
冒頭の引用と展開
ガーシュウィンが「ヘ調のメロディ」を弾き終えた後、BGMがその同じメロディを部分的に引用。音楽的連続性を生み出しています。
肖像画シーンの音楽的変容(本編30分頃)
シューベルト、ワーグナー、ベートーヴェンの肖像画が次々と映し出されるシーンでは、BGMが彼らの代表作へとシームレスに変化。視覚的な情報に音楽が即座に反応し、まるで音楽史を駆け抜けるような演出となっています。
ブラームスの譜面シーン(本編68分頃)
登場人物がブラームスの譜面について語るシーンでは、BGMが自然にブラームスの「子守歌 Op.49-4」へと変化。会話の内容と音楽が一体となり、知的で落ち着いた雰囲気を出す場面です。
重要なのは、これらの変化が新しく音楽を当てなおしているのではなく、前から流れている音楽をアレンジとして自然に変容させている点です。この継続性が、映画全体の音楽的統一感を生み出し、観客を音楽の流れの中に引き込みます。
これらの他にも、映像の出来事に合わせて音楽が従属的に変化していく演出が本作全編を通して見られる点に、着目すべきでしょう。
‣ 歴史的エピソードの再現
映画の中盤には、音楽史に残る有名なエピソードが描かれます。ガーシュウィンがモーリス・ラヴェルに師事を希望した際、ラヴェルが告げた言葉──
「私の元で学んでも第二のラヴェルになるだけだ」
この一節は、当時すでに独自のスタイルを確立していたガーシュウィンの才能をラヴェルが認めていたことを示す逸話として知られています。映画はこうした歴史的瞬間を再現し、ガーシュウィンの芸術的アイデンティティの確立過程を描いています。
► 終わりに
本作では、ガーシュウィンの音楽が映画の構造に深く組み込まれ、状況内音楽と状況外音楽が有機的に絡み合い、視覚と聴覚が一体となった作品として完成しています。
ピアノ演奏シーンが豊富に登場し、2台ピアノの演奏も含まれます。ガーシュウィンの代表的な作品を堪能できる、ピアノファンにとっても必見の映画と言えるでしょう。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
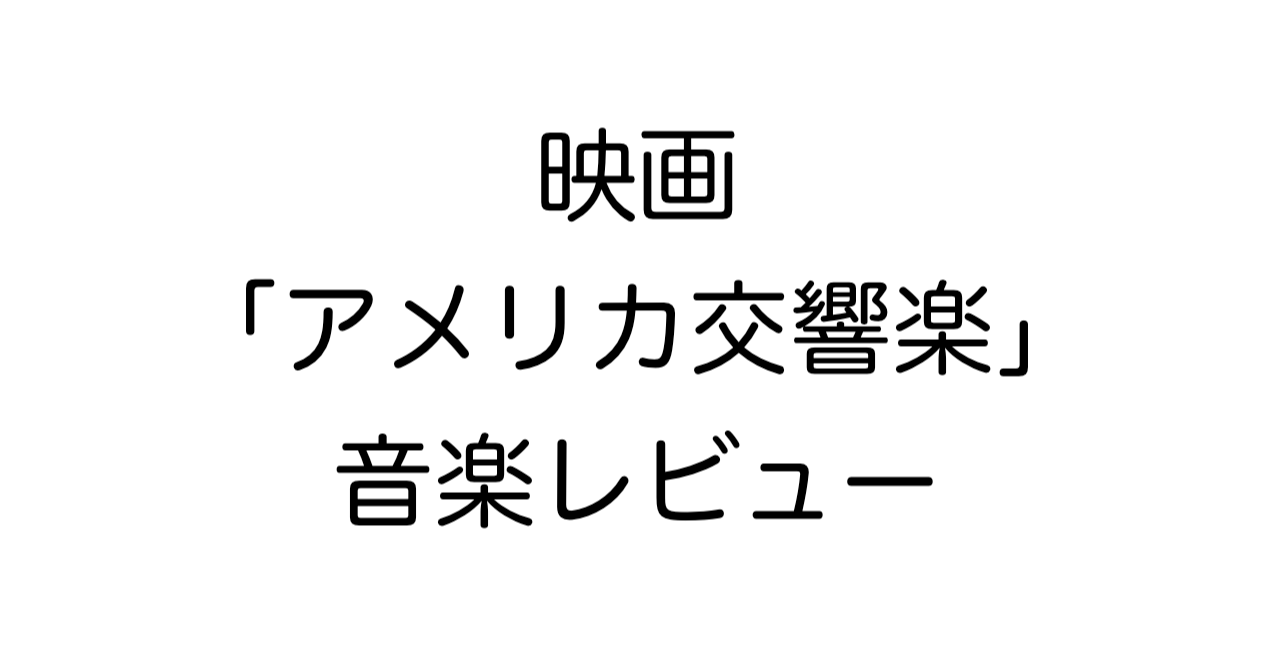
![アメリカ交響楽 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51AG4Aqjp7L._SL160_.jpg)
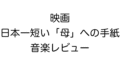
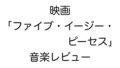
コメント