【ピアノ】ギーゼキング「ピアノとともに」レビュー
► はじめに
ピアノを学ぶ大人にとって、演奏技術だけでなく、名ピアニストの思考や姿勢から学ぶことには計り知れない価値があります。ヴァルター・ギーゼキング著「ピアノとともに」は、20世紀前半を代表するピアニストが自身の経験と演奏哲学を語った貴重な一冊です。
・訳:杉浦博
・出版社:白水社
・邦訳初版:1968年
・ページ数:本編240ページ
・対象レベル:中級~上級者
・ピアノとともに 著:ギーゼキング 訳:杉浦博 / 白水社
► 内容について
‣ 構成と内容
本書は大きく二部に分かれています:
第一部「わたしはこうしてピアニストになった」
自伝的回想録として、ギーゼキングが受けた音楽教育や人生経験が綴られています。彼の音楽的発展の軌跡をたどることで、偉大なピアニストの形成過程を垣間見ることができます。
第二部「ピアノをひく人たちのために」
ここでは演奏の本質に関する具体的な内容が展開されます。「ピアノを賛えて」「現代におけるタッチの問題」「演奏家はいかに練習するか」といった実践的なテーマから、J.S.バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、ドビュッシー、ラヴェルといった作曲家の解釈に至るまで、幅広い知見が披露されています。
‣ 本書の特徴
1. 実践から生まれた演奏哲学
ギーゼキングは、自身の経験から得た成果を伝えています。訳者あとがきにもあるように、「あくまで実際の演奏経験から得た技法上の成果を、ごく具体的に、いわば演奏者への助言という形で述べている」のが特徴です。
2. 「注意力」の強調
ギーゼキングは演奏における「注意力」の重要性を繰り返し説いています。「日常のめんどうな仕事を片づけるにも注意力は必要だが、それくらいの注意力ではとても感銘をあたえる演奏活動の前提条件である高度の精神集中を達成することはできない」と述べ、演奏に必要な集中力の深さを強調しています。
3. 美しい響きへのこだわり
「わたしの解釈は、どの曲の場合も、ただただ美しい響きでピアノをひくという、自分には自明と思われる要請から生まれたものなのである」という言葉に象徴されるように、ギーゼキングは美しい音色を生み出すことを演奏の根本に置いています。
4. 適度なユーモアのある語り口
難解な音楽論に陥ることなく、適度な辛口も挟みつつ、読者を飽きさせない語り口で専門的内容を伝えています。
‣ 本書から学べる実践的技術の例
1. 精確さの追求
「どんな作品であれ、そのどんな細かな端々にいたるまでも精確に熟達してこそ、はじめてその芸術的再現が可能になる」というギーゼキングの言葉は、演奏における精確さの重要性を説いています。技術的完成度なくして芸術的表現はありえないという基本姿勢が貫かれています。
2. 和音処理の技術
本書では、「和音の中程の音を単独で際立たせる方法」などについても解説されています。
3. 各作曲家の演奏アプローチ
J.S.バッハからラヴェルまで、各作曲家の作品に対する独自の解釈とアプローチが述べられています。特に「コンサート・ピアノによるバッハ解釈」や「ラヴェルのピアノ音楽をどうひくか」などのセクションは、それぞれのスタイルについて彼がどう捉えているのかを知れる重要な資料でもあります。
‣ 印象に残る言葉
「音楽の名作とほんとうに親密になれるのは、おそらくいつでも、自分ひとりで曲を演奏し、それを自分ひとりで、あるいは志向を同じくする仲間の友人たちのなかで、ほんとうにじっくりと会得することのできる人たちだけであろう」
(抜粋終わり)
この言葉は、音楽作品との深い対話の重要性を説いています。作品と深く向き合い、内面化する過程こそが真の音楽を生み出す土台となるというギーゼキングの信念が感じられます。
► おすすめの読者層
中級〜上級のピアノ学習者:音楽への向かい方を見直したい方、技術的な壁を感じている方
ピアノ音楽の愛好家:名演奏家ギーゼキングの思考プロセスを知りたい方
音楽解釈に悩む方:ギーゼキングが捉えている各作曲家のスタイルを理解したい方
音楽学習の方法を見直したい方:本質的な練習方法や学習方法を模索している方
► 読み方のヒント
本書は第一部と第二部のバランスが取れていますが、実践的な内容を求める方は、まずは第二部「ピアノをひく人たちのために」から読み始めるのも一つの方法です。ギーゼキングの人物像を知ったうえで演奏論を読むとより理解が深まりますが、まずは実践的な内容から入って関心が高まったら第一部に戻るという読み方も効果的でしょう。
► 併読のすすめ
本書を読む際は、「現代ピアノ演奏法」(著:ライマー=ギーゼキング、訳:井口秋子 / 音楽之友社)との併読がおすすめです。ギーゼキングとその師匠カール・ライマーによる書籍で、こちらはより体系的な演奏法の解説書となっており、「ピアノとともに」と合わせることで、ギーゼキングの演奏哲学をより立体的に理解することができます。
レビュー記事:【ピアノ】ライマー=ギーゼキング「現代ピアノ演奏法」レビュー
・現代ピアノ演奏法 著:ライマー=ギーゼキング 訳:井口秋子 / 音楽之友社
► 終わりに
「ピアノとともに」では、ギーゼキングの豊富な経験と深い洞察から、上記の他にも多くのことを学ぶことができます。独学でピアノを学ぶ大人の方々にとって、「ピアノとともに」生きるための指針となるでしょう。
・ピアノとともに 著:ギーゼキング 訳:杉浦博 / 白水社
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
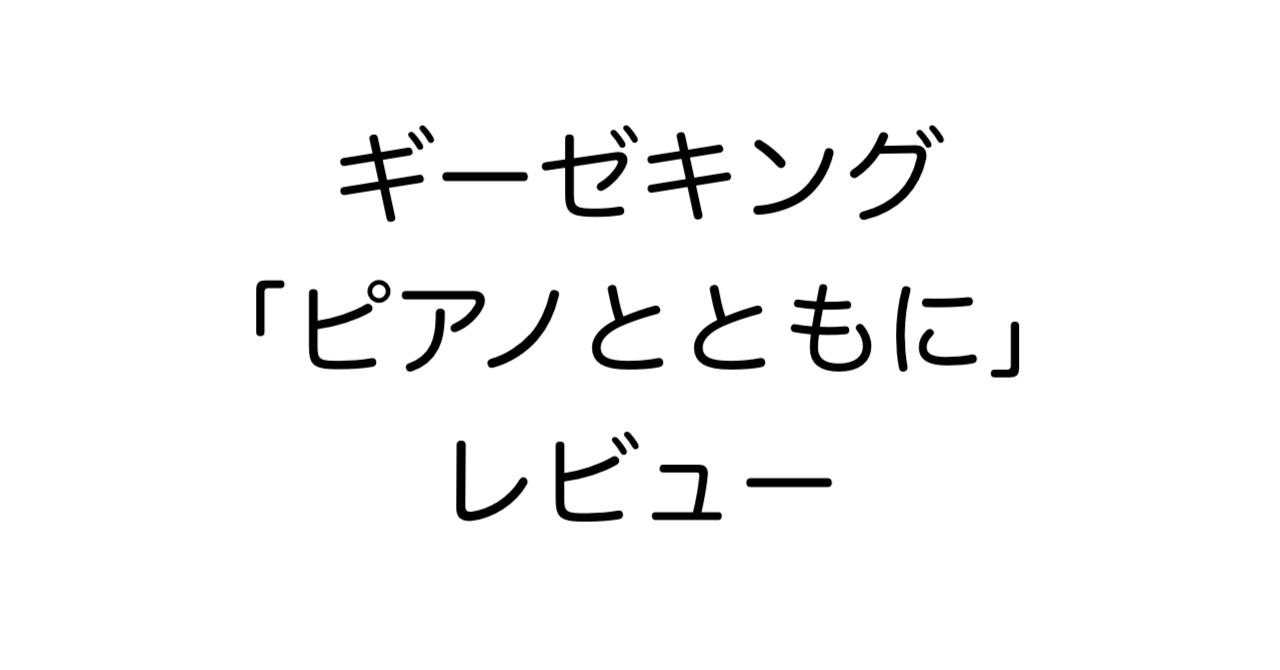


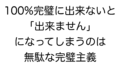
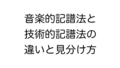
コメント