【ピアノ】楽譜管理で音楽生活を快適にする方法
► はじめに
ピアノ弾きにとって、楽譜は大切な財産です。しかし、多くの方が楽譜の管理に悩んでいるのではないでしょうか。
本記事では、楽譜を効率的に管理し、無駄な出費や混乱を防ぐための実践的なコツをお伝えします。適切な管理方法を身につけることで、音楽への集中力を高め、より豊かな音楽生活を送ることができるでしょう。
► A. 楽譜管理の基本
‣ 1. 楽譜の重複買いを防ぐ、所持楽譜を整理する方法
本当に弾きたくて買った楽譜や、すでに学習した作品の単曲楽譜は忘れません。一方、大量の作品が入っている曲集をとりあえず買った場合などは、持っていることを忘れているのではないでしょうか。
その曲集に入っている作品なのに:
・改めて楽譜を単曲買いしてしまったり
・下手したら全く同じ曲集を買ってしまったり
こういったプチトラブルは、筆者の周りでもよく耳にします。
是非一度、所持している楽譜を「すべて」出してみて、何があるのかを一から把握し直すことをやってみてください。そして再度楽譜棚へ入れるときに:
・出版社別
・編成&作曲家別
・混合の楽譜はひとまとめ
など、どのような基準でもいいので、自分なりの決まりごとを作って整理し直してみましょう。ひと目でざっくりと把握できるように整理することが重要です。
また、楽譜を買う前に必ず混合の楽譜を開いてその中に含まれていないかを確認するのを習慣にするといいでしょう。
・自分の持っている楽譜はすべて把握する
・把握できないものや気分の上がらないものは持たない
・楽譜を買うときには、その楽譜が自分の棚のどのカテゴリーに並ぶのかを考えてからにする
これくらい厳しく管理すると、以後、楽譜の運用に困らなくなります。買ったはいいものの忘れている楽譜をゼロにしましょう。
‣ 2. 楽譜店へ行く前に楽譜棚へ手を伸ばそう
昔のことですが、友人がくれた楽譜が新品だったので訳をきいてみたら、「持っているのを忘れていてもう一冊買ってしまい、返品するのも面倒だから」とのことでした。
同じように、楽譜をダブらせて買ってしまった経験はありませんか。
楽譜というのはその役割上、使わないものや長い間開かないものが出てくるのは仕方のないことです。時には、忘れてしまうこともあるでしょう。しかし、前項目で書いたように普段から管理しておいたうえで、なおかつ楽譜店へ行く前に楽譜棚へ手を伸ばしてみれば、重複買いを回避できます。
・ラフマニノフ=シュルツ「ヴォカリーズ Op.34-14」
・ラヴェル「前奏曲(1913)」
など、厚紙を一切使っていない「紙切れ一枚または数枚のペラペラの楽譜」にも注意が必要です。ほぼ厚みがないので、楽譜と楽譜の間に挟まると見事に消えてしまいます。
「持っていないという思い込み」は、意外と当てになりません。筆者自身も、「結局これ、買っていたんだった」などと気づいたり、いい加減な楽譜管理をしてしまっていた時期がありました。
► B. 管理習慣の定着
‣ 3. 楽譜管理を習慣化するための3つのコツ
楽譜の整理、できていますか。
・ピアノの上に積まれた、忘れられた楽譜集
・パンパンに膨らんだ角2茶封筒のヤマ
気づくと、このような目も当てられない状態になっている方もゼロではないでしょう。
筆者はiPadで管理している楽譜も多いのですが、デジタルデータも頻繁に整理していないとあっという間に散らかります。散らかっていると、すでに持っている楽譜を買ってしまうミスにもつながるでしょう。
面倒なのは分かりますが、いざやろうと思うと半日がかりになる状況となる前に対処しておくべきです。
楽譜管理癖がついた自分になるコツあります:
・日々少しずつ整理しておくほうが圧倒的に楽だと、心の底から認める
・よく使う楽譜に関しては、原則、平積みはやめる
・出したままにするのは、毎日確実に使う楽譜のみにする
この3点を意識して、なるはやで楽譜の整理を習慣づけましょう。
まず、日々少しずつやっておいたほうが本当に楽だということを理解しておきましょう。この楽さを一度体感すると、意外とたやすく管理癖をつけることができます。
また、細かいことなのですが、よく使う楽譜に関しては楽譜棚でもピアノの上でも、原則、平積みはやめてください。
平積みは、見た目は悪くないですし、本棚によっては立てるよりもたくさん収納できますが、下にあるものを取り出すのが相当面倒です。「平積みは、楽譜整理の敵」と言っても過言ではありません。普通に考えると、平積みをやめるだけでピアノの上が楽譜置き場になる可能性はなくなります。それとも、ピアノの上に楽譜を立てる方もいるのでしょうか。
加えて、毎日確実に使う楽譜は出したままでOKですが、それ以外は原則、視界から消しておきましょう。そのほうが管理が楽になりますし、学習にも集中できます。
‣ 4. 借りた楽譜を返し忘れないための実践的なコツ
図書館や友人などから、楽譜やCDなどの練習に必要なものを借りることはあるかと思います。
「借りてきたものを返し忘れてしまう」という失敗をしたことがある方も多いのではないでしょうか。「返そう、いや面倒だ、またにしよう」などと思っているうちについに存在すら忘れてしまって、いつの間にか約束した返却期限を過ぎてしまいます。
絶対に返し忘れないコツがあります。
常に目に入る邪魔になるところへ置いておくことです。例えば、ピアノの譜面台のど真ん中など。
借りているものは、絶対に、見えないところへは追いやらないようにしましょう。日常的な視界から消えた瞬間に、記憶からも消えてしまいます。間違っても、楽譜棚にさしてはいけません。他人の楽譜だからではなく、忘れるからです。
家族で住んでいる場合は、リビングなどの共用スペースに置いてもいいのですが、「位置を移動させないように」ということを家族と約束しておくといいでしょう。掃除のときなどに見えないところへ片付けられて、しかも忘れられてしまったら、こちら側としては何もコントロールできないからです。そして、自分の記憶からも家族の記憶からも消えてしまいます。
端末のリマインダー機能などは、知らせてくれても画面を閉じたら消えてしまうのであまりおすすめできません。借りているものを物理的に目の前に居させる方法をとりましょう。
C. その他の便利なコツ
‣ 5. 楽譜をコピーしたくなる心のおさえ方
原則、楽譜はコピーせずに原本を使わなくてはいけません。
楽譜をコピーしたくなるのには、ある程度、楽譜の状態にも問題があると考えています。
楽譜によっては、開いたまま保てず勝手に閉じてしまうものがあります。クリップをいくつ使っても開いた状態を維持できなければ実用性に欠けてしまい、「コピーしたほうが学習しやすいではないか」ということになります。
楽譜をコピーしたくなる心のおさえ方は、大きく2つあります:
・勝手に閉じてしまう楽譜はなるべく選ばない
・裁断してリング製本してしまうのもアリ
一つ目としては、勝手に閉じてしまう楽譜はなるべく選ばないこと。
せめて、クリップを一つ使うだけで開いた状態を保持できる楽譜を選びたいところです。オンラインストアだと見抜くのが難しいのですが、店頭では触れることができるので、大体見当をつけることができます。
その点、ヘンレ版の「ベートーヴェン ソナタ全集」などは優秀で、あんなに分厚いのにも関わらず、開いた状態を保持してくれます。
楽譜をコピーしたくなる心のおさえ方の二つ目としては、どうしても勝手に閉じてしまう楽譜を買わざるを得ない場合は、裁断してリング製本してしまうのもアリということです。
・裁断機(カッターでも代用可)
・多穴パンチ
・リング
この3点さえそろえれば、自宅でリング製本できます。筆者も数冊作ってみました。
出版社によっては、はじめからリング製本した状態で販売している楽譜も出しており、かさばりはしますが「勝手に閉じない楽譜」という意味においては優れています。
以上のように、「楽譜が勝手に閉じてしまう」という欠点さえ何とか回避して、コピーしたくなる心をおさえましょう。
► 終わりに
楽譜の管理は、面倒に感じるかもしれません。しかし、これらの小さな習慣が音楽生活を大きく変えてくれます。本記事で紹介した内容を少しずつ実践し、自身の最適な楽譜管理方法を見つけてください。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
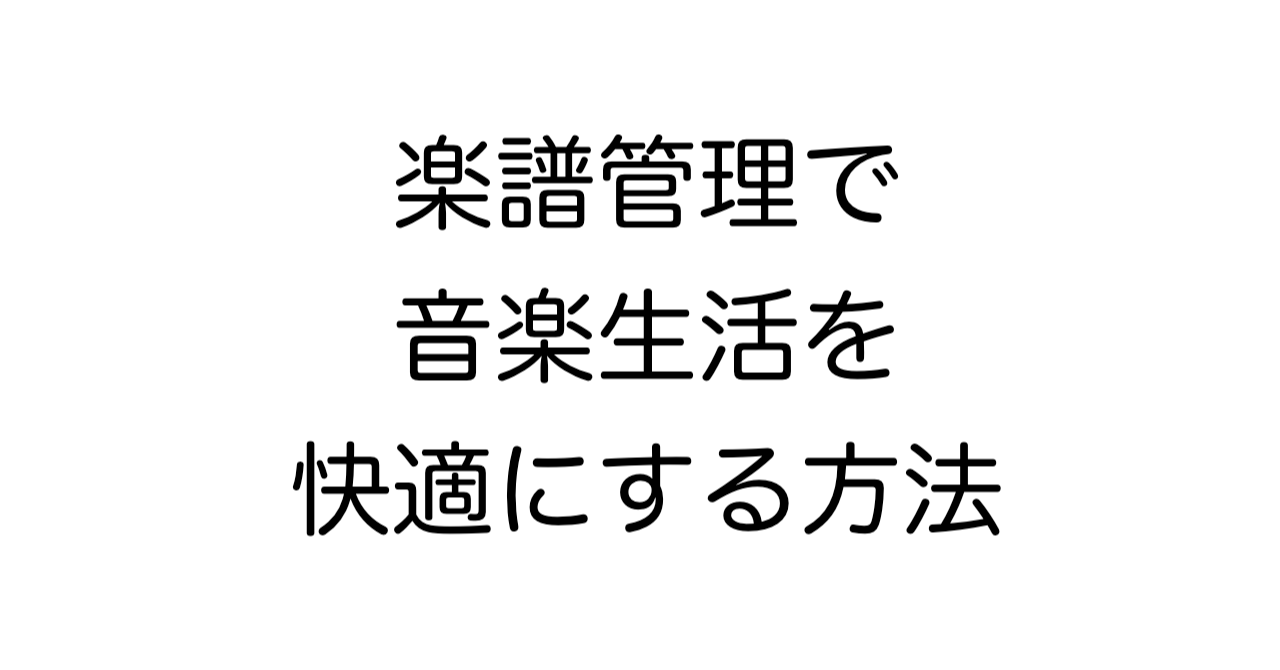

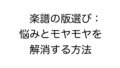
コメント