【ピアノ】ピアノ調律の基本と心得
► はじめに
ピアノは美しい音色を奏でる楽器であり、その状態を維持するためには定期的な調律が不可欠です。しかし、多くの人々が調律に対して二の足を踏んでしまうのが現状です。費用や手間、プライバシーの問題など、様々な理由から調律を躊躇する方も少なくありません。
本記事では、ピアノ調律に対する不安や迷いを解消し、より前向きに楽器のメンテナンスに取り組むためのヒントをお伝えします。
► 3つのヒント
‣ 1. いつもの調律不足との付き合い方
筆者の予想なのですが、世の中にある生のピアノの相当数が常に調律不足なのではないでしょうか。
もし、ピアノを使っているのであれば、できれば定期的に良い状態にしておくと、我々の耳のためにもピアノの保守のためにも良いでしょう。
調律不足との付き合い方ですが、いったん、費用がかさむことを頭から取っ払ってみましょう。また、部屋の中を必要以上に掃除しないといけないと思わないでください。
どんなに部屋をピカピカにしても、調律師さんが見ているピアノの中は髪の毛やら消しカスやらホコリやらでいっぱいです。特にグランドピアノの場合は。もっとひどいものを見られているわけなので、最低限失礼がない程度に片付いていればOKくらいで考えておけばいいでしょう。
・費用がかさむこと
・来客を招き入れることの大変さ
この2つが、中々調律できない原因だと思います。確かにどちらも各人にとっての問題ですが、それ以外のメリットが勝ればいいわけです。例えば:
・失礼がない程度で、ピアノの保守や構造について質問をする機会にもする
・椅子の買い替えなどを検討しているのであれば、相談してアドバイスをもらう
・純粋に、調律師さんと人と人との付き合いを楽しむ
・調律・整調・整音がされていたほうがプラスだと、心の底から認める
など、どんなことでも構わないので、調律の機会を自分にとってプラスの半日にしてください。
また、細かいことなのですが、ピアノの中の掃除機がけは自分でやらないほうがいいでしょう。筆者自身、慎重にやっていても弦を切ってしまった経験があります。
‣ 2. 失礼にならない範囲で、調律師と会話をしよう
筆者が、ピアノの構造やメンテナンスなどを学んだのは書籍からではあるのですが、実は調律師さんとの会話の中からもそれ以上にたくさんのことを学びました。
日頃、書籍などで学べることもありますが、やはり写真や文章では分かりにくい部分も出てきます。調律師さんに質問をすると、時間が許す範囲内でピアノの中を開けて説明してくれるケースもあります。
それに、自分でするべきメンテナンス」などは、そのピアノ自体や設置されている環境によっても最適なやり方が変わってきます。したがって、その現場でアドヴァイスをもらえることはこのうえなく大きなことです。
前提として、調律師さんの業務の邪魔をしてはいけません。時間をとってもらえて当たり前だと思うのは間違いでしょう。一方、調律師さんというのは、釘こそ打たなくてもピアノが好きでたまらないピアノ職人であることは事実です。
・少しでもピアノに詳しくなりたい
・大切なピアノを少しでも良い状態で使い続けたい
と思っているのであれば、話は聞いてもらえるはずです。
経験則ですが、傾向としては時間割で仕事をしている一部のメーカー所属の調律師さんよりも、個人事業主の調律師さんのほうが丁寧に話を聞いてもらえる傾向があるように感じます。
「失礼にならない範囲で、調律師と会話をする」
これは間違いなく、ピアノライフにとってプラスになるでしょう。
‣ 3. 調律の後にチェックしておきたいポイント
調律では、「ピッチの調整」だけのプランではない限り、余程手抜きの調律師でなければ「基本的な整音」もしてくれるでしょう。
一方、この「基本的な整音」という部分に意外と注意が必要です。
ピアノのハンマーに針を刺して音色を丸くしたり、様々な調整をしてくれるのですが、力のある調律師さんであっても隣の鍵盤同士で音色が揃っていないままになっているケースがあるのです。例えば、中央のA音は「丸い音」でも、その隣のH音は「カン!」といったような「硬い音」のままになっていたりします。
こういったことは、調律の後に少し弾かせてもらえば気づくこともあるでしょう。発見した場合は、調律師さんが帰る前に再調整してもらうべきです。
ここが、調律の後にチェックしておきたいポイントです。
もし、弾いてもすぐに音色の違いが分からないという方は、
などと調律前にあらかじめ伝えておくのも効果的。この一言があるかどうかで、調律師さんの注意が全く変わります。
調律というのは頻繁に行う家庭でも数ヶ月に一度、場合によっては数年に一度というケースもあります。したがって、一度調整してもらったピアノをしばらくの期間使うことになります。なるべくいい状態でキープできるように心がけて、質の高い練習を目指しましょう。
► 終わりに
本記事で紹介した内容を参考に、調律師との関係を大切にし、楽器の状態に関心を持ち続けましょう。適切なメンテナンスと少しの工夫で、ピアノは最高の状態を保ち、より豊かな音楽体験を提供してくれるはずです。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
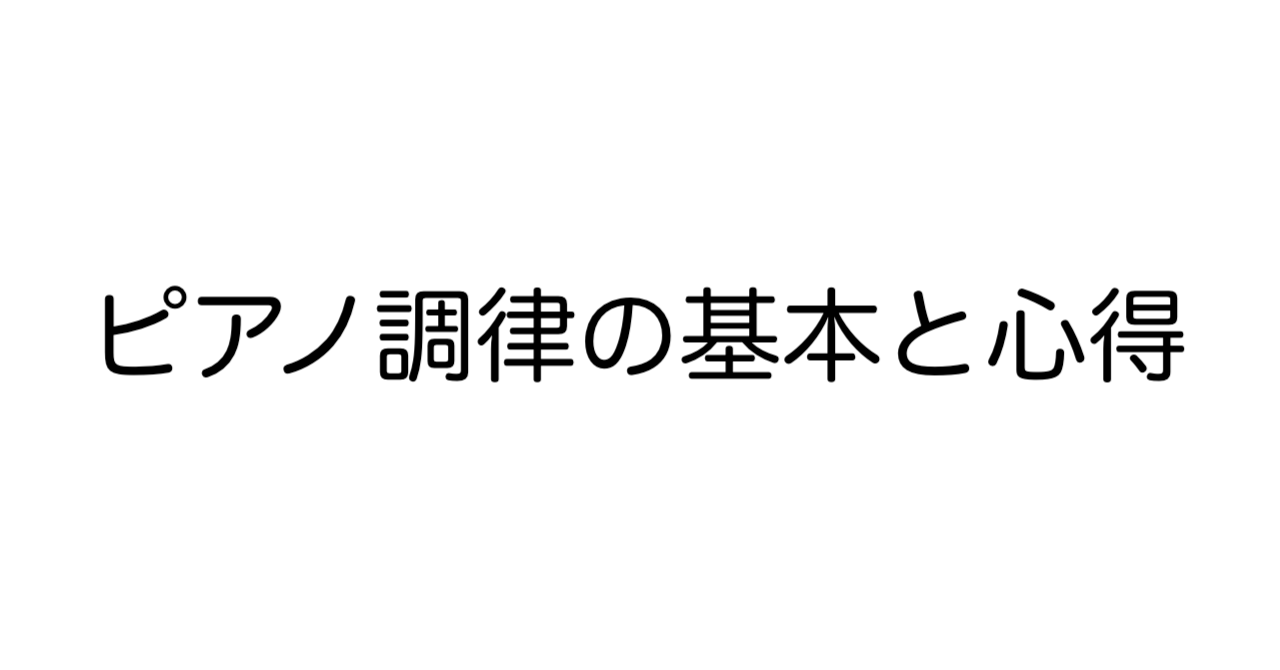
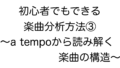
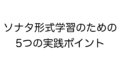
コメント