【ピアノ】原典版(Urtext)ブームの歴史と背景:ヘンレ、ウィーン原典版誕生の時代
► はじめに
今日では「ヘンレ版」や「ウィーン原典版」など、原典版(Urtext)の名前を目にすることが一般的になっていますが、これらの楽譜が広く普及するようになったのは実は比較的新しい現象です。
本記事では、第二次世界大戦後に起こった「原典版ブーム」の背景について見ていきましょう。
※本記事は、一部「ピアノ音楽史事典 著:千蔵八郎」(春秋社)の内容を参考に、大幅な補足を加えたうえで作成しています。
・ピアノ音楽史事典 著:千蔵八郎 / 春秋社
► 原典版とは何か
原典版(Urtext)とは、「作曲者の意図を、第三者の手を加えずにできる限り忠実に再現しようとした楽譜」です(実際には、原典版でも多少の編集者の判断が入る)。代表的な原典版としては:
・ヘンレ原典版(G. Henle Verlag)
・ウィーン原典版(Wiener Urtext Edition)
・ベーレンライター原典版(Bärenreiter Urtext)
・新モーツァルト全集
などが挙げられます。
一方、以下の楽譜とは明確に区別する必要があります:
・解釈版(interpretive edition):コルトー版など、作曲家や演奏家によって解釈を伝達するために校訂されたもの
・実用版(practical edition):教育用の目的などで、本来書かれていない各種記号などを補ったもの
これらは学習サポートとして重要なものではありますが、原典版と比較すると、作曲者の意図を厳密に再現することには限界があります。
► 戦後の原典版ブームの背景
‣ 19世紀から20世紀初頭:演奏家の時代
19世紀から20世紀初頭にかけてのクラシック音楽界では、個性や解釈を重視する傾向が強くあったとされています。この時代の楽譜は、編集者や有名演奏家の解釈が多分に反映されたものが主流でした。
リストやブゾーニなどの大家による「解釈版」は、原曲に彼ら自身の音楽的アイデアや演奏上の工夫を加えたもので、時には原曲を大幅に改変することもありました。これらは確かに演奏の参考になるものでしたが、「作曲家が本来意図したであろうもの」から離れていくという側面もありました。
‣「新音楽(Neue Musik)」と新即物主義の台頭
1920-30年代、つまり二つの世界大戦の間の時期は、音楽における大きな転換期でした。この時代は「新音楽(Neue Musik)」と呼ばれる新たな潮流が生まれた時期でもあります。
シェーンベルク、ストラヴィンスキー、フランスの6人組、ヒンデミットなどによる、伝統的な作曲技法からの脱却を図る動きが活発になりました。また、ストラヴィンスキーの作品に見られる「新古典主義」も登場しました。これは後期ロマン主義の感情過多で標題的な音楽への反発から生まれたもので、客観性と明晰さを重視する姿勢でした。
同じ頃、ドイツでは「新即物主義(Neue Sachlichkeit)」という美術用語が音楽界にも取り入れられました。元々は細密描写によって社会批判を行う美術様式でしたが、音楽では「原典に忠実な演奏」を求める姿勢として現れました。これは19世紀以来の「論理的な理由なく、気ままに自由に演奏する解釈」に対するアンチテーゼだったのです。
‣ 原典ブームの先駆者たち
新即物主義的な演奏姿勢の代表的なピアニストとして、アルトゥール・シュナーベル、ヴィルヘルム・バックハウス、ヴァルター・ギーゼキングらが挙げられます。彼らは基本姿勢として「作曲家の意図に忠実であること」を重視し、「過度な感情表現」や「論理的な理由なく、気ままに自由に演奏する解釈」を幾分控えた演奏を追求しました。
‣ 第二次世界大戦後:原典版ブームの到来
第二次世界大戦後、「原典に忠実であるべき」という考え方はさらに具体的な形となり、出版活動として実を結びました。この背景には以下のような複合的な要因があります:
1. 音楽学の発展と校訂理論の確立:
戦後、音楽学は急速に発展し、原典研究の方法論も洗練されていきました。作曲家の自筆譜や初版譜などの一次資料を収集・比較・分析する手法が体系化され、1950年代より以下のような重要なプロジェクトが開始されました:
・「新バッハ全集」
・「新モーツァルト全集」
・「新ベートーヴェン全集」
これらのプロジェクトは、従来見過ごされていた作曲家の意図を明らかにし、19世紀の校訂版に含まれていた誤りや恣意的な変更を修正する役割を果たしました。
2. 音楽界の価値観の変化と客観性の追求:
戦後の西洋社会では、客観性と実証的アプローチを重視する傾向が強まりました。この変化は戦前から徐々に進行していた新即物主義の流れの延長線上にありますが、戦後により広く受け入れられるようになりました。演奏においても「演奏家の主観的解釈」よりも「テクストに基づく客観的アプローチ」が求められる側面が強くなり、原典版はそのニーズに応える存在となったのです。
特に注目すべきは、戦前の新即物主義的演奏姿勢が、戦後は「原典版」という具体的な楽譜出版の形で広く普及したという点です。ヘンレやベーレンライターなどの出版社によって広く一般の音楽家にも開かれたものとなりました。
3. 録音技術の発達と演奏の相対化:
レコード技術の進化とレコード産業の拡大により、「名演奏家による決定的解釈」という概念が相対化されました。様々な演奏を聴き比べることができるようになり、「唯一の正しい演奏」ではなく、「多様な演奏の可能性」が認識されるようになりました。
こうした環境変化は、演奏家たちに「自分自身で原典に基づいて解釈する」という姿勢を促し、原典版の普及を後押ししました。また、原典版出版社も販売促進のためにレコード会社と提携することがあり、相互に発展したという側面もあります。
4. 歴史的演奏習慣研究の進展と古楽器運動
1950年代から主流化し始めた古楽器運動(period instrument movement)も原典版ブームを支える要因となりました。ニコラウス・アーノンクールやグスタフ・レオンハルトなどのパイオニアたちは、バロックや古典派の音楽を当時の楽器で演奏する実践を広め、それに伴い演奏習慣の歴史的研究も進展しました。
この動きは、原典版の出版と密接に関連していました。原典版が提供する「作曲家が記した、正確に近いテクスト」に加えて、「当時の演奏習慣」を理解することの重要性が認識され、一部の原典版にもそうした歴史的情報が序文や注釈として補足されるようになりました。
5. 主要な原典版の発展
1948年のヘンレ出版社の創立は、現代的な意味での原典版出版の象徴的な出来事でした。ベーレンライター出版社は戦前からの出版社ですが、戦後に原典版に注力しました。
戦後の原典版ブームを牽引した主要なものは以下の通りです:
・ヘンレ原典版(G. Henle Verlag)
・ウィーン原典版(Wiener Urtext Edition)
・ベーレンライター原典版(Bärenreiter Urtext)
・新モーツァルト全集
6. 原典版概念の成熟と批判的受容
1970年代以降、原典版に対する批判的考察も生まれ、「作曲家の意図」という概念自体の複雑さが認識されるようになりました。以下のような視点が提示されています:
・「最終的な原典」は実際には存在せず、常に編集者の判断が介入すること
・作曲家自身が複数の版を認めていた場合、どれが「原典」なのか一概に決められないこと
・楽譜に書かれた指示だけでなく、当時の演奏習慣の理解が不可欠であること
現代の原典版はただの「作曲家の書いた通りの楽譜」ではなく、複数の資料の比較検討、歴史的文脈の理解、当時の演奏習慣の研究などを統合した、総合的な音楽テクストとして位置づけられるようになったのです。
► 終わりに
第二次大戦後の原典版ブームは、単なる出版業界のトレンドではなく、20世紀の音楽観の大きな転換を反映したものでした。新即物主義を基礎に、戦後の歴史的・学術的研究の発展を経て、「作曲家の意図にできる限り忠実であること」の価値が広く認識されるようになったのです。
原典版の登場と普及は、「楽譜とは何か」「演奏とは何か」を問い直す機会を提供しました。今日楽譜を選び、音楽を解釈する際にも、この歴史的な流れを理解しておくようにしましょう。
・ピアノ音楽史事典 著:千蔵八郎 / 春秋社
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
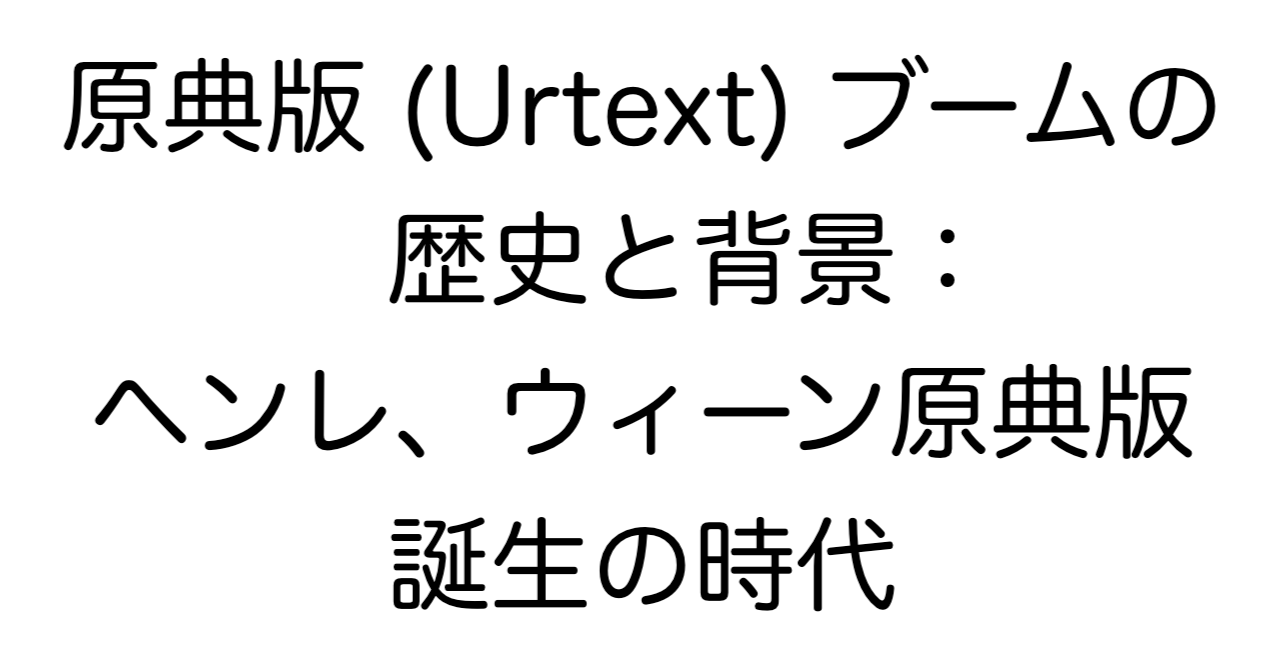

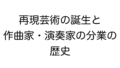
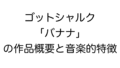
コメント