【ピアノ】映画「第七のヴェール」レビュー:クラシック音楽が織りなす各種描写の技法
► はじめに
1945年公開のイギリス映画「第七のヴェール(The Seventh Veil)」では、楽曲の選択から音楽の使用方法まで、あらゆる点で計算された音楽演出によって、登場人物の心理や関係性、そして物語の進行が細かく表現されています。
本記事では、この映画の音楽的側面に焦点を当てて、特に「状況内音楽」の革新的な使用方法について詳しく分析します。
・公開年:1945年(イギリス)
・監督:コンプトン・ベネット
・ピアノ関連度:★★★★☆
► 内容について(ネタバレあり)
以下では、映画の具体的なシーンや楽曲の使われ方について解説しています。未視聴の方はご注意ください。
‣ 状況内音楽を用いた注目すべき表現 5つ
音楽用語解説:
状況内音楽
ストーリー内で実際にその場で流れている音楽。 例:ラジオから流れる音楽、誰かの演奏
状況外音楽
外的につけられた通常のBGMで、登場人物には聴こえていない音楽
· 1. ストーリーの転換点となる状況内音楽の受け渡し
本編17分あたりで、ニコラス(フランチェスカの後見人)がモーツァルト「ピアノソナタ K.545 第1楽章」を演奏し、フランチェスカが演奏を引き継ぐ重要な場面があります。この状況内音楽の引き継ぎは「ストーリーの転換点」を意味しており、この場面を機に、フランチェスカのピアノ奏者としての内容が描かれ始めます。
楽曲選択の意図:
・ニコラスが演奏するのは比較的平易な楽曲(モーツァルト「K.545 第1楽章」、ショパン「プレリュード 第7番」)
・これはニコラス自身がそれほどピアノが達者ではないことを示している
・対照的に、フランチェスカが後のストーリーで演奏するのは高度な技術を要する楽曲:
– ショパンやブラームスのより高度な作品
– グリーグ「ピアノ協奏曲 イ短調 Op.16」
– ラフマニノフ「ピアノ協奏曲 第2番 Op.18」
· 2. キャラクター性を象徴する状況内音楽
フランチェスカがグリーグ「ピアノ協奏曲 イ短調 Op.16」を演奏する本番の直前、スーザンという旧友と再会します。この女性の一方的で騒がしい性格を象徴するかのように、軽快で愉快なオーケストラ演奏が状況内音楽として鳴り響いています。
この演出により、状況内音楽がキャラクターの内面を直接的に表現する手法として機能しています。ピアノ協奏曲の直前のプログラム曲をあえてそのような雰囲気を持つ楽曲にしたのは、意図的だと考えていいでしょう。
· 3. 音楽と感情の段階的乖離による緊張感の創出
本編63分頃の最も印象的なシーンの一つ。フランチェスカがベートーヴェン「悲愴ソナタ 第2楽章」を演奏する中、ニコラスがフランチェスカへの思いを語り始めます。
演出の特徴:
・当初は音楽の穏やかなテンションと語りが調和
・徐々にニコラスの感情が高ぶり、音楽との温度差が拡大
・最終的に杖でピアノを叩き、演奏が強制終了(状況内音楽のカット・アウト)
この手法が効果的な理由:
・本作の他の部分では、比較的音楽が映像に従属的に変化するため、この乖離が際立つから
・フランチェスカのトラウマの瞬間として、後の物語展開に重大な影響を与えるから
· 4.「同じ楽曲」「同じ人物による演奏」による二つの状況内音楽の同居
本編70分頃、治療の一環としてフランチェスカが自分のレコード録音に合わせて演奏する場面は、珍しい音楽演出です。
技術的特徴:
・「同じ楽曲」「同じ演奏者」による二つの状況内音楽の同時進行
・ピッチのズレ、タイミングのズレを意図的に表現
・録音時と現在の心境・環境の違いを音楽的に表現
その後、部屋を移動しても音量が変わらないことから、レコードのほうの状況内音楽を状況外音楽(通常のBGM)へと移行させる技術的工夫も見られます。
· 5. 状況内音楽の消去による時間経過の表現
本編83分頃、ピーターとフランチェスカが踊った思い出の音楽がレコードで流れるシーンで、映像が同じ部屋の別角度に切り替わった瞬間に音楽が止まります。物理的には同じ部屋であり、鳴ってさえいれば音楽は聴こえるはずなので、止まったことは間違いありません。ブツリと音楽が止まったわけではないので、いきなりレコードを止めたとは考えられません。
つまり、状況内音楽の消去で時間経過を表現しているのです。
‣ 音楽とセリフによる対照性の強調
フランチェスカとジャズピアニスト「ピーター」の関係は、本作における重要な対照軸として描かれています。
音楽的対照:
・クラシックピアノ(フランチェスカの世界)vs ジャズ(ピーターの世界)
・格式高い演奏会場 vs カジュアルなクラブ
・楽譜に忠実な演奏 vs 即興性重視の演奏
社会的対照:
・ピーターの台詞「僕のような貧しい音楽家が、君のような令嬢に出会うと?」
・経済格差と音楽ジャンルの対比
フランチェスカがピーターの影響でジャズを弾き始め、それを聴いたニコラスが激怒するシーンは、この対照性が物語の緊張を生み出す重要な要素として機能しています。ただし、これはあくまでニコラスの束縛的な視点から描かれた対照であり、音楽的・社会的価値判断を意味するものではありません。
‣ ショパンの楽曲を引用した状況外音楽
本作の音楽構成で注目すべき点として、状況外音楽(BGM)にショパン「エチュード Op.25-11 木枯らし」のメロディが引用されていることも挙げられます。
使用例:
・冒頭のハープによる演奏
・本編32分頃の金管楽器・弦楽器による演奏
これらは原曲の直接的なオーケストラ編曲ではなく、メロディの一部を引用してオリジナル楽曲に再構成したもの。この手法により、クラシックピアノ音楽が中心となるストーリー全体に一貫した音楽的統一性を与えています。
► 終わりに
「第七のヴェール」は、上記のように音楽の用い方でもストーリー構造の核心部分に踏み込んだ作品です。「ピアノ音楽を楽しむ」意味でも、「心理ドラマとしても楽しむ」意味でも、おすすめできる一作です。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
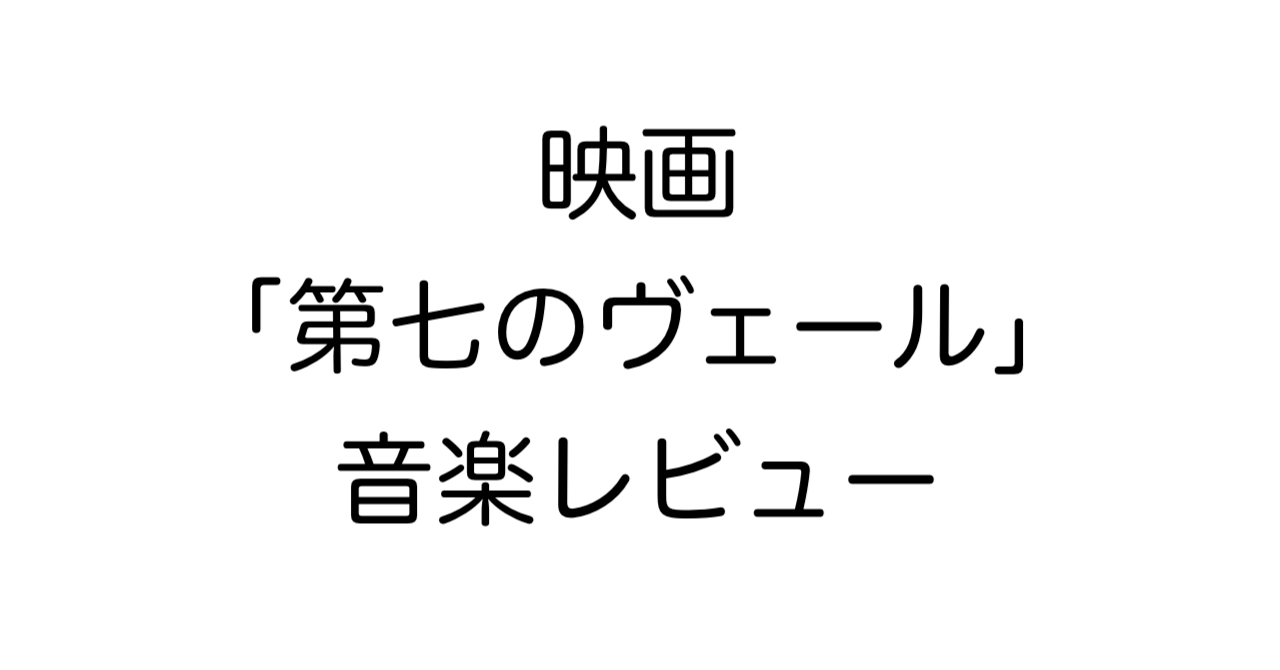

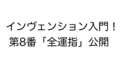
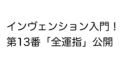
コメント