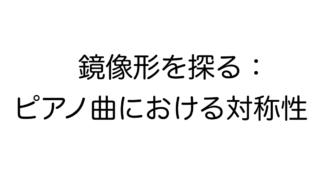 楽曲分析(アナリーゼ)方法
楽曲分析(アナリーゼ)方法 【ピアノ】鏡像形を探る:ピアノ曲における対称性
ピアノ曲における鏡像形(対称性)を、シューマン「Op.68-11 シチリアーナ」とJ.S.バッハ「ミュゼット BWV Anh.126」を例に解説。楽曲理解を深める実践的な知識を提供します。
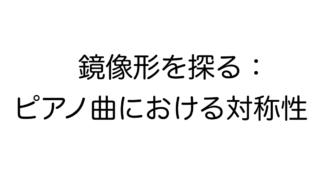 楽曲分析(アナリーゼ)方法
楽曲分析(アナリーゼ)方法 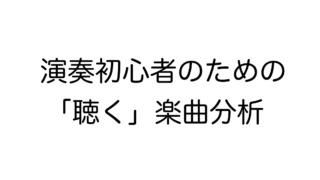 ‣ 初級者 / 初心者のために
‣ 初級者 / 初心者のために 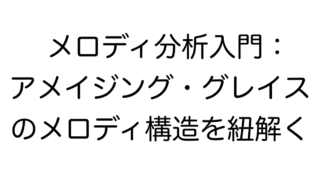 楽曲分析(アナリーゼ)方法
楽曲分析(アナリーゼ)方法 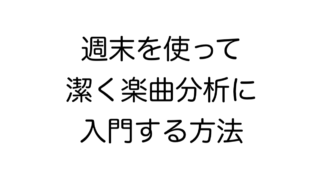 ‣ 楽曲分析パス
‣ 楽曲分析パス 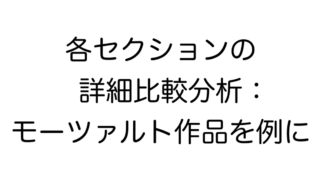 楽曲分析(アナリーゼ)方法
楽曲分析(アナリーゼ)方法 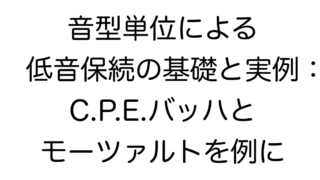 楽曲分析(アナリーゼ)方法
楽曲分析(アナリーゼ)方法 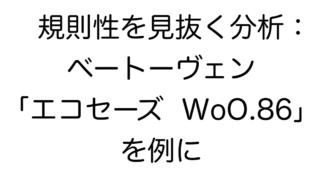 楽曲分析(アナリーゼ)方法
楽曲分析(アナリーゼ)方法 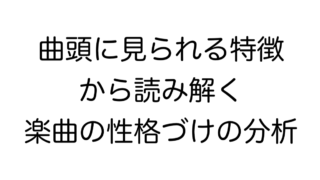 楽曲分析(アナリーゼ)方法
楽曲分析(アナリーゼ)方法 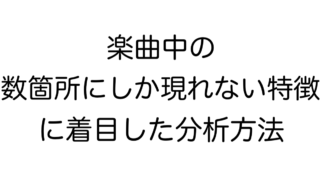 楽曲分析(アナリーゼ)方法
楽曲分析(アナリーゼ)方法 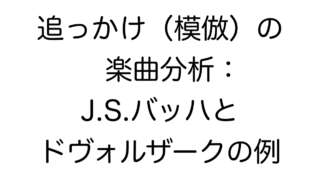 楽曲分析(アナリーゼ)方法
楽曲分析(アナリーゼ)方法 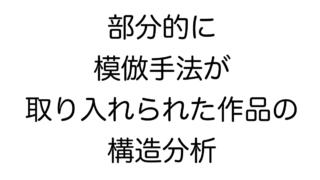 楽曲分析(アナリーゼ)方法
楽曲分析(アナリーゼ)方法 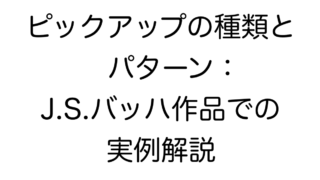 楽曲分析(アナリーゼ)方法
楽曲分析(アナリーゼ)方法