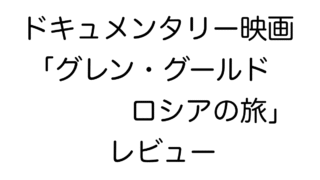 - ピアノ関連映画レビュー
- ピアノ関連映画レビュー 【ピアノ】ドキュメンタリー映画「グレン・グールド ロシアの旅」レビュー
2002年公開のドキュメンタリー映画「グレン・グールド ロシアの旅」のレビュー。1957年、24歳のグールドがソ連を訪問した際の記録を軸に、冷戦期の音楽外交と彼の演奏が与えた衝撃をアシュケナージらの証言と共に振り返る、57分の貴重な歴史的ドキュメントです。
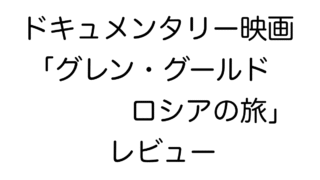 - ピアノ関連映画レビュー
- ピアノ関連映画レビュー 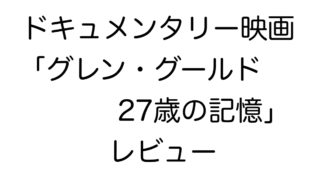 - ピアノ関連映画レビュー
- ピアノ関連映画レビュー 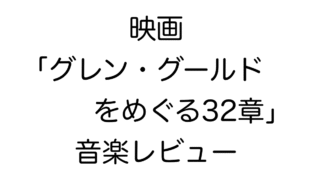 - ピアノ関連映画レビュー
- ピアノ関連映画レビュー  - ピアノ関連映画レビュー
- ピアノ関連映画レビュー 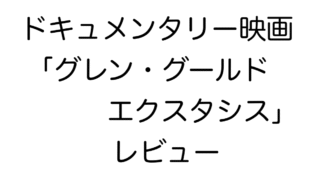 - ピアノ関連映画レビュー
- ピアノ関連映画レビュー 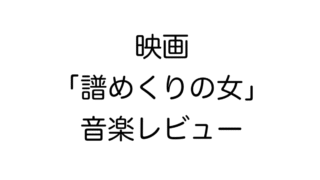 - ピアノ関連映画レビュー
- ピアノ関連映画レビュー 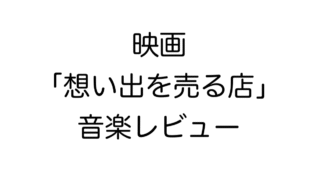 ポピュラーピアノ
ポピュラーピアノ 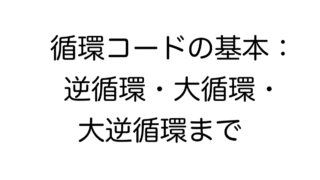 楽曲分析(アナリーゼ)方法
楽曲分析(アナリーゼ)方法  - ピアノ関連映画レビュー
- ピアノ関連映画レビュー 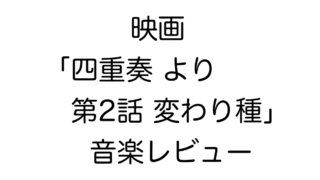 - ピアノ関連映画レビュー
- ピアノ関連映画レビュー 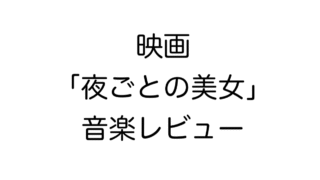 - ピアノ関連映画レビュー
- ピアノ関連映画レビュー 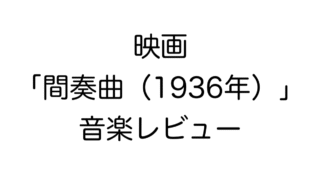 - ピアノ関連映画レビュー
- ピアノ関連映画レビュー