【ピアノ】映画「シャイン」レビュー:状況内音楽が語る実在ピアニストの人生
► はじめに
「シャイン(Shine)」は、実在のピアニスト、デイヴィッド・ヘルフゴットの半生を描いた伝記映画です。
本作の音楽の魅力は、ピアノ演奏そのものがストーリーの中心にあるだけでなく、音楽と音響が上手く演出されることで、主人公デヴィッドの心理状態や物語の転換点を効果的に表現している点にあります。
・公開年:1996年(オーストラリア)/ 1997年(日本)
・監督:スコット・ヒックス
・ピアノ関連度:★★★★★
► 内容について(ネタバレあり)
以下では、映画の具体的なシーンや楽曲の使われ方について解説しています。未視聴の方はご注意ください。
用語解説:状況内音楽とは:
・ストーリーの中で実際に聴こえている音楽
・登場人物がピアノを弾いているシーンのBGMなど
一方、外的に付けられた通常のBGMは「状況外音楽」となります。
‣ 状況内音楽と状況外音楽の織りなす世界
· オープニングにおける3つの音要素の扱い
本作では「状況内音楽」と「状況外音楽」が緻密に計算されています。
映画の冒頭、デヴィッドがバーに辿り着くシーンでは、3つの音要素が絶妙に交錯します。
・雨の音(状況内の「音声」)
・通常のBGM(状況外音楽)
・バーの中で聴こえるピアノ演奏(状況内音楽)
雨の音がはっきり聴こえ、バーのピアノが小さく聴こえるのは、デヴィッドが外からバーを覗いている視点だからです。温かくもやや不思議な曲調の状況外音楽も含め、3つの要素すべてがデヴィッドの視点から描かれており、観客は自然と主人公の心情に寄り添うことになります。
· 音でも表現される「ひどいピアノ」
本編6分頃、子供時代のデヴィッドがショパンの「英雄ポロネーズ Op.53」をコンクールで演奏するシーン。父親ピーターが「ひどいピアノ」と嘆くのは、ボロいピアノが演奏するたびに前へ動いてしまうからですが、映画はさらに「調律の狂い」という音要素を加えることで、ピアノの状態の悪さを視覚と聴覚の両方で表現しています。
この演出により、貧しい環境の中で必死に才能を磨くデヴィッドの姿が、より鮮明に伝わってきます。
· 状況内音楽の場面に合わせた柔軟な表現
本作の音楽演出において、状況内音楽の音色や音響を場面に合わせて柔軟に変化させている点も着目すべきです:
例1:グランドピアノからアップライトピアノへ(53分頃)
王立音楽院でラフマニノフの「ピアノ協奏曲 第3番 Op.30」を演奏するシーンから、自宅でアップライトピアノを弾くシーンへ切り替わります。演奏中の音楽はそのまま継続されますが、音色がグランドピアノからアップライトピアノへと自然に変化します。この演出により、場面転換の連続性が自然なものに感じられます。
例2:自宅からホールへ(97分50秒頃)
リストの「ラ・カンパネラ」が流れる中、演奏会の準備をするデヴィッドの姿が映されます(ここではまだ状況外音楽として機能している、後の状況内音楽)。その後、ホールでのリサイタルシーンに切り替わると、音楽は継続されたまま残響が深くなり、ホール特有の豊かな音響へと変化します(ここでは状況内音楽)。この微細な調整が、リアリティと臨場感を生み出しています。
·「見せかけの状況内音楽」という演出
本作では、観客に状況内音楽だと思わせておいて、実は別の意味を持つという「見せかけ」の演出が随所に見られます:
見せかけ1:心の中の「雨だれ」(68分40秒頃)
ショパンの「雨だれの前奏曲 Op.28-15」が流れ始めます。この曲はそれまで何度も実際にピアノを弾く状況内音楽として使用されていたため、観客は当然今回も誰かが弾いていると思い込みます。しかし実際は、長くピアノから離れているデヴィッドの頭や心の中で鳴っている音楽でした。デヴィッドが他人から話しかけられた瞬間、音楽がカットアウトされることで、それが明らかになります。
興味深いのは、直前の状況外音楽の終わりの和音と「雨だれ」の始まりの和音(Des-durのⅠ)が同じであることです。この和音の一致により、スムーズな移行が実現され、観客は違和感なくデヴィッドの内面世界へ引き込まれます。
見せかけ2:教会のオーケストラ(73分20秒頃)
オーケストラとチェンバロの音が聴こえ、すぐに教会での合唱練習風景が映し出されるため、状況内音楽だと思わせます。しかし、実際の演奏はミュートされており、聴こえていたのはただの状況外音楽だったという仕掛けです。
見せかけ3:ベートーヴェンの第九(86分50秒頃)
以前にも合唱シーンがあったため、ベートーヴェンの第九が聴こえてくると、また合唱シーンが始まるのだろうと観客は予想します。ところが、それは家の中で流れているレコードだったという意外性があります。
これらの演出は、観客の期待を巧みに操りながら、デヴィッドの心理状態や環境を多層的に表現しています。
‣ 劇作品における「転調」の意味
一般的に音楽でいう転調とは「旋法の種類やキーを変えること」ですが、劇作品の音楽では「音楽の雰囲気を変える」という意味で使われることがあります。キーの変化ではなく、音楽の変わり目にアクセントとなる音楽や効果音を挟むことで、シーンの転換や物語の展開を印象づける手法です。「盛り上げ」と表現されることもあります。
本作で転調が効果的に使われている例を挙げておきましょう:
転調の例1:師の変化(14分40秒頃)
場面転換と同時に音楽の雰囲気が大きく変わります。これは、デヴィッドが父親だけに習っていた状態から、コンクールで審査員をしていた音楽家のもとへ弟子入りするという、大きな転換点を音楽で表現しています。
転調の例2:アメリカ留学の可能性(19分15秒頃)
ここでも音楽の雰囲気が大きく変化し、デヴィッドの前に広がるアメリカ留学という新しい道を暗示しています。
‣ 音楽が語る、デヴィッドの人生
本作で使用されるクラシック音楽は、デヴィッドの人生そのものを表現しています:
・ショパン「英雄ポロネーズ」:才能の萌芽と貧しい環境
・ラフマニノフ「ピアノ協奏曲 第3番」:挑戦と栄光、そして崩壊
・ショパン「雨だれの前奏曲」:失われたピアノとの絆、心の中の音楽
・リスト「ラ・カンパネラ」:再生と新たな始まり
これらの楽曲をはじめとした各種クラシック音楽が、状況内音楽と状況外音楽を縦横無尽に行き来しながら、デヴィッドの内面と外面の世界を描き出します。
► 終わりに
状況内音楽と状況外音楽の巧みな使い分け、音色や音響の柔軟な変化、そして「見せかけ」の演出による観客の期待の操作。これらが、ピアニストの光と影、栄光と挫折、そして再生の物語を豊かに彩っています。音楽が好きなすべての方に観て欲しい一作です。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
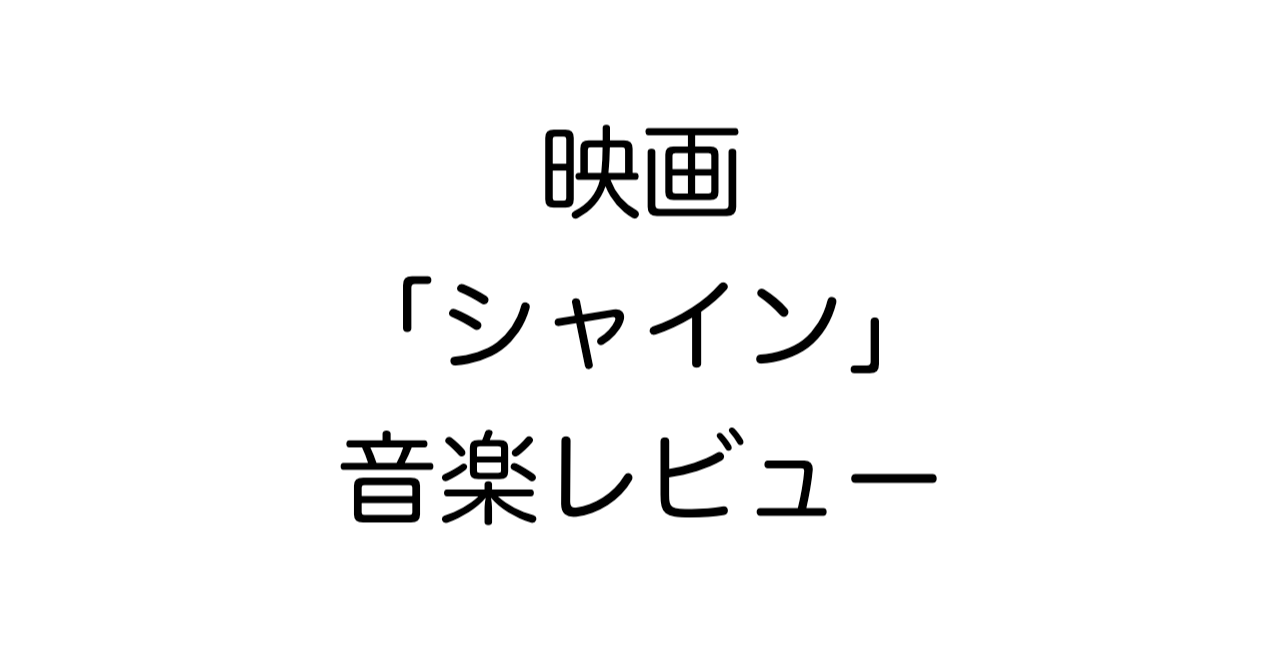
![シャイン [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/21C88GAHS8L._SL160_.jpg)
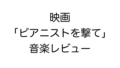
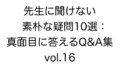
コメント