【ピアノ】映画「四重奏 より 第2話 変わり種」レビュー:ピアノ演奏の演出技法を読み解く
► はじめに
サマセット・モームの短編小説を原作とした1948年のイギリス映画「四重奏(Quartet)」は、4つの独立したエピソードで構成されるオムニバス作品です。その第2話「変わり種(The Alien Corn)」は、ピアノを愛する青年の情熱と挫折を描いた物語です。
・公開年:1948年(イギリス)/ 1951年(日本)
・監督:ハロルド・フレンチ(第2話「変わり種」)
・ピアノ関連度:★★★★★
► 内容について
以下では、映画の具体的なシーンや楽曲の使われ方について解説しています。未視聴の方はご注意ください。
‣ 時代背景と社会的コンテクスト
作中の興味深いセリフから、物語の時代設定を読み解くことができます。主人公ジョージがピアニストを職業にしたいと告げた際、家族は「映画館にピアノは要らない、今はトーキーに」と反対します。このセリフは重要な時代的マーカーとなっています。
長編トーキー(有声映画)の始まりは、アラン・クロスランド監督による「ジャズ・シンガー」(1927年)とされており、一般に浸透し始めたのは1920年代後半から1930年代初頭です。無声映画時代には映画館でのピアノ伴奏が職業として成立していましたが、トーキーの登場により、そうした音楽家の仕事が消失していく過渡期が描かれているのです。原作小説の発表が1931年であることからも、この設定は時代と呼応しています。
‣ 細部に宿るリアリティ
· 認知のタイムラグを表現した演奏停止
パリでピアノを学んで約2年後、従妹のポーラがジョージの部屋を訪ねるシーンは、演出技術の工夫が見られる一例です。ジョージはショパン「バラード 第1番 Op.23」を演奏中ですが、ポーラがドアをノックすると、約1秒の遅延を経てから演奏を止めます。
この何気ない演出が「非常にリアル」である理由は、人間の認知過程を正確に再現しているからです。音に対する認識と反応には必ず微細な時間差が存在します。もしノックと同時にピアノが止まれば、あらかじめ来訪を知っていたかのような不自然さが生じてしまいます。こうした1秒程度の演出の配慮が、作品のリアリティを高めているのです。
· 技術差を表現する多層的な演出戦略
クライマックスとなる審査シーンにも工夫された演出が施されています。2年間のパリ留学を終えたジョージは、著名な女流ピアニスト、リア・マカートに演奏を聴いてもらいます。ここで映画製作者が直面したであろう課題は、以下の点でした。
演出上のジレンマ:
・設定上、リア マカートの演奏をジョージより上手に聴かせる必要がある
・実際には、ジョージもある程度技術的には優れた演奏であり、音楽経験がない観客には差が分かりにくい
・かといってジョージの演奏を極端に下手にすると、「パリで2年間学んだ」という設定が崩壊する
この問題に対して、製作上、2つの解決策を講じています:
解決策①:明確なミスの挿入
ジョージが演奏するショパン「ワルツ 第2番 変イ短調 Op.34-1 華麗なる円舞曲」の序奏部分で、意図的に明らかなミスを入れています。このミスは音楽経験のない観客にも認識できる程度のものですが、音楽は時間芸術であり前へ進んでいくため、「2年間の研鑽を積んだ演奏者が一瞬アクシデントを起こした」という解釈が成立します。全体的な技術レベルを損なうことなく、プロとの差異を印象づける手法です。
解決策②:演奏時間の配分
両者の演奏は途中を省略して使用されていますが、その尺にも工夫があります:
・ジョージの演奏:2分21秒
・リア マカートの演奏:2分44秒(シューベルト「即興曲集 第2番 変ホ長調 Op.90-2」)
リア・マカートの演奏に長く時間を割くことで、観客の注意と記憶がそちらに向かうよう誘導しています。映画的時間の配分自体が、技術差の印象を形成しているのです。
► 終わりに
「四重奏 より 第2話 変わり種」は、30分にも満たない短編ですが、細かな音楽演出によって、芸術への情熱、階級社会の抑圧、音楽の才能といった普遍的テーマを描き出した作品です。
独立したエピソードで構成されるオムニバス作品ということもあり鑑賞しやすいので、本記事の内容を参考に、一度、もしくはもう一度鑑賞してみて欲しいと思います。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
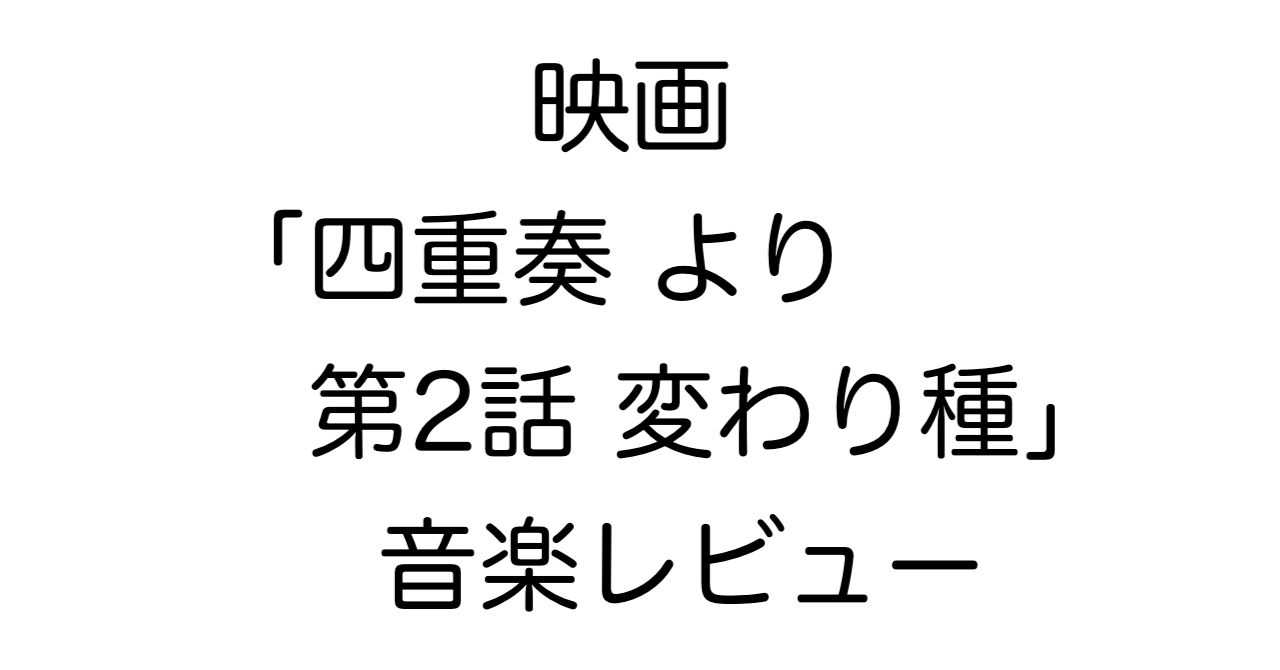
![四重奏 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41-TVHQ6q6L._SL160_.jpg)
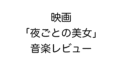
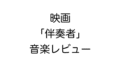
コメント