【ピアノ】パーセル「メヌエット ZD 225」の詳細分析
► はじめに
バロック時代の作曲家ヘンリー・パーセル(1659-1695)の「メヌエット ZD 225」は、シンプルながら音楽的な工夫が見られる作品です。この楽曲には、メロディの別声部への分担書法、拡大形・縮小形による動機展開、そして見せかけの模倣といったいくつもの特徴的な技法が「隠れた形」で使用されています。
本記事では、譜例を用いながらこれらの作曲技法を詳細に分析していきます。
► 分析:パーセル「メヌエット ZD 225」
‣ 1. メロディの別声部への分担書法の分析
· メロディの別声部分担とは何か
メロディの別声部分担(voice distribution)とは、本来一つの声部で演奏されるメロディラインを、作品の再現部や発展部において複数の声部に「分配」する作曲技法です。
この手法が用いられる主な目的を見てみましょう:
1. 音色の変化
同じメロディでも異なる声部で演奏することで音色が変わり、聴き手に新鮮さを提供
2. 対位法的興味
複数の声部間でメロディが行き来することで、ポリフォニー(多声音楽)としての面白さが増す
3. テクスチャーの変化
曲全体の響きを多彩にし、単調さを避けることができる
4. 構造的統一性
同じ素材を形を変えて再利用することで、曲の一貫性を保ちつつ変化をもたらす
· 分担書法の分析例
パーセル「メヌエット ZD 225」
譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

この楽譜を見ると、曲の冒頭部分と14小節目からの部分で、重要な違いがあることが分かります。
具体的に分析してみましょう:
再現部のメロディ処理(14-16小節):
・14小節目のアウフタクトから曲頭のメロディが再現されるが、完全な形ではない
・15小節目から、メロディが右手と左手に分担される
・右手パートが曲頭のメロディの一部(レッド音符)を担当
・左手パートが曲頭のメロディの残りの部分(ブルー音符)を担当
このように、パーセルは再現部において、同じメロディ素材を使いながらも、巧みに声部を入れ替えて変化をつけています。特に15-16小節のブルー音符で示されたメロディ断片は、何となく弾いていると単なる伴奏と混同してしまいがちですが、実は曲頭のメロディの一部なのです。
真のメロディは、15小節2拍目以降も右手パートのそれですが、曲頭メロディの別声部分担がされていることは把握しておきましょう。
· まとめ
パーセルの「メヌエット ZD 225」に見られるメロディの別声部への分担書法は、シンプルな小品に奥行きと変化をもたらしています。このような作曲技法を理解し、楽曲理解を深めましょう。
また、楽曲分析の視点から見ると、このような声部書法の発見は、演奏者が曲の構造を理解する上で非常に重要です。特に独学でピアノを学ぶ方にとっては、楽譜の表面だけでなく、その背後にある作曲者の意図を読み解く訓練として、こうした分析は大いに役立ちます。
‣ 2. 隠れた拡大形と縮小形の発見
· 拡大形と縮小形の基本概念
楽曲分析に入る前に、拡大形と縮小形について簡単に説明しておきましょう。
拡大形(augmentation):元の音型の音価(音の長さ)を2倍、3倍などに伸ばした形。例えば四分音符の音型を二分音符に変えるなど。
縮小形(diminution):元の音型の音価を半分、3分の1などに縮めた形。例えば四分音符の音型を八分音符に変えるなど。
通常、これらの技法は主題を変形して提示する際に用いられますが、パーセルの「メヌエット ZD 225」では、「隠れた」形で使用されています。
· 拡大形の分析
パーセル「メヌエット ZD 225」
譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、楽曲全体)

譜例で示されている5小節3拍目から始まる「Si Do Re」のモティーフに注目してみましょう。この3音からなる上行音型は、続く6小節2拍目から「SI Do Si Do Re」という形で音価が4分音符に拡大されています。
ここで興味深いのは、この拡大が単に音価を伸ばすという通常の拡大形ではなく、音型自体を「拡張」している点です。原型の3音(Si Do Re)に対して、拡大形では5音(SI Do Si Do Re)となっており、音数が増えていますが、骨格となる音型は保持されています。
さらに注目すべき点として、この拡大形が右手と左手のパートにまたがっていることが挙げられます。5小節目の「Si Do Re」は右手で演奏されますが、続く拡大形は左手のパートから始まっています。これは「見せかけの模倣」とも呼べる技法で、聴き手の耳に連続性を感じさせながらも、声部交代によって音楽に奥行きを与えています。
· 縮小形の分析
(再掲)

一方、15小節1拍目から始まる「So(Fa)Mi Fa」の音型は、16小節1拍目では「So Mi Fa」という形で縮小されています。
この縮小形は、音価を短くするという通常の縮小ではなく、音型から音を省略するという方法で実現されています。原型の4音(So Fa Mi Fa)から「Fa」を1つ省略することで、3音(So Mi Fa)の縮小形が生まれています。
これも拡大形と同様に、一般的な縮小形とは異なる動機展開技法と言えるでしょう。
· 本作品における拡大形と縮小形の意義
作曲家たちは、こうした技法を単に技巧的な遊びとしてではなく、楽曲に統一感と多様性を同時にもたらす重要な手段として活用していました。パーセルのこのメヌエットにおいても、拡大形と縮小形の使用によって、以下のような音楽的効果が生まれています:
1. 統一性の確保:同じ音型が変形されながらも基本的特徴を保持することで、楽曲全体に統一感がもたらされている
2. 多様性の創出:単純な繰り返しではなく、拡大や縮小という変形を加えることで、聴き飽きさせない変化が生まれる
3. 声部間の隠された対話:声部をまたぐ形で拡大形や縮小形を配置することで、隠された対話的な関係が構築
これらの効果は、聴き手に意識されることはなくても、無意識のうちに音楽的な満足感をもたらすものです。
· まとめ:隠れた技法を発見するための譜読みの重要性
パーセルのこのメヌエットで使用されている拡大形と縮小形は、一見して明らかではありません。特に以下の点に注意が必要です:
1. 声部をまたぐ模倣
右手と左手のパートをまたいで模倣が行われるため、単一の声部だけを追っていると見逃してしまう可能性がある
2. 変形のある拡大・縮小
通常の拡大形(音価を伸ばす)や縮小形(音価を縮める)ではなく、音の数を増やしたり減らしたりする形を併用することで変形が行われている
こうした細部に注意して譜読みをすることで、一見シンプルに思えるこのメヌエットに隠された作曲技法を発見することができます。
‣ 3. 見せかけの模倣の分析と見つけ方
この楽曲における「見せかけの模倣」については以下の記事で解説しているので、あわせて参考にしてください。
► 終わりに
シンプルな小品であっても、丁寧に分析することで多くの発見があります。バロック音楽に限らず、あらゆる時代の音楽において、このような細部への注意は重要です。音楽理論や分析は難解なものではなく、音楽をより深く体験するためのヒントと考えるべきでしょう。
自身の演奏するレパートリーでも、本記事で紹介した分析方法を取り入れてみてください。
► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
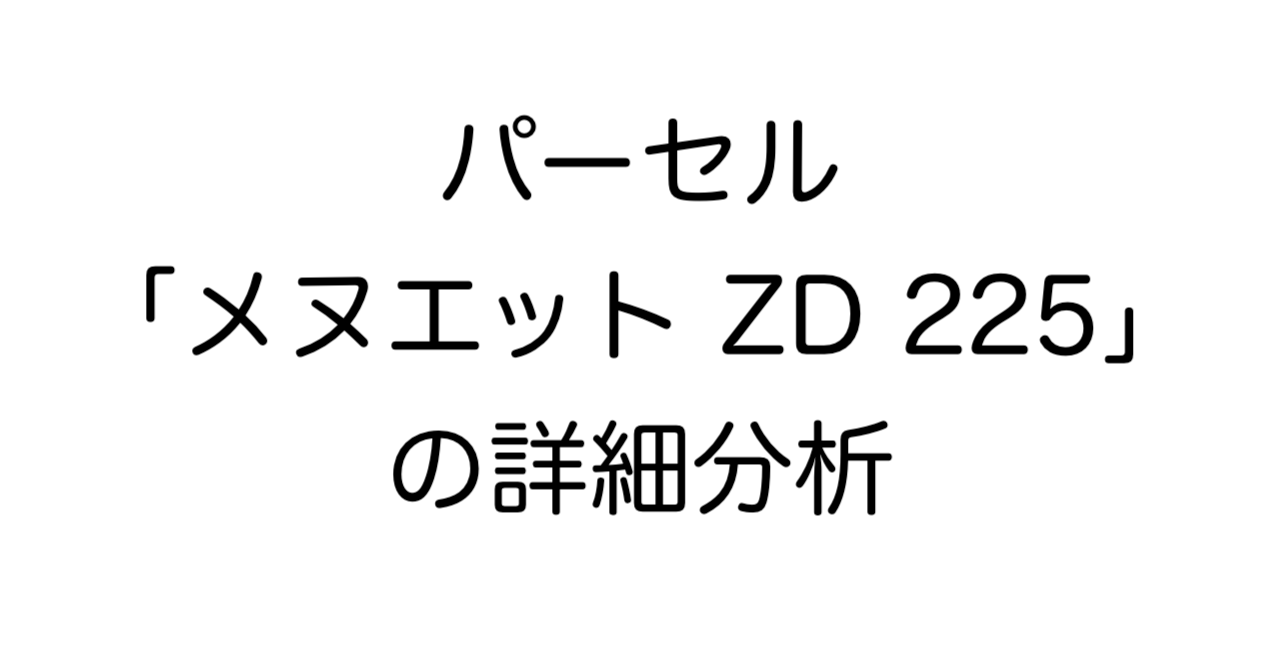
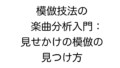
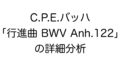
コメント