【ピアノ】ゲオルク・シューネマン「ピアノ音楽史」レビュー
► はじめに
「ピアノ音楽史」は、ドイツの音楽学者ゲオルク・シューネマン(1884-1945)による音楽史書籍です。221ページという手頃なボリュームながら、クラヴィーア演奏の黎明期から20世紀の音楽まで、ピアノ音楽の発展を幅広く取り上げています。
・訳 : 門馬直美、石多正男
・出版社:春秋社
・邦訳初版:1988年
・ページ数:本編221ページ
・対象レベル:初級〜上級者
・ピアノ音楽史 著:ゲオルク・シューネマン 訳 : 門馬直美、石多正男 / 春秋社
► 内容について
‣ 本書の特徴
1. 人物間の関係性に着目した独自の視点
本書では、単なる年代順の事実列挙のみではなく、音楽家同士の関係性や影響関係に焦点が当てられています。例えば、ショパンとその師エルスネルの関係、シューマンとベネットの交流など。これにより、音楽の発展を有機的な人間関係の中で理解することができます。
2. 独自の人物選定
音楽史上の巨匠たちだけでなく、比較的知名度の低い音楽家にも光を当て、彼らがどのように主要な音楽家と関わり、音楽史に貢献したかを解説しています。こうした視点は、他のピアノ音楽史書籍にはあまり見られない本書ならではの価値と言えるでしょう。オーソドックスなようで少しマニアックさを含む一冊です。
3. 皮肉を交えた独特の文体
著者の個性が表れた文体も本書の魅力の一つです。基本的にはオーソドックスな読みやすい文体で進んでいきますが、時にチクリと皮肉を交えた記述が見られ、音楽史を著者の視点を通した生き生きとした物語として読者に伝えています。
‣ 本書の構成
本書は全10章と「シェーンベルク以後」に関する付録で構成されています。初期のクラヴィーア演奏から始まり、バロック期、古典派、ロマン派を経て20世紀の新しい傾向まで、時代順に解説されています。
特に充実しているのは第一章から第七章までの記述です。クラヴィーア演奏の黎明期からベートーヴェンまでの時代については詳細に触れられており、著者の専門性が感じられます。一方、第八章以降のロマン派以後については比較的簡潔な記述に留まっています。
► 読者層と活用方法
本書は歴史学習の書籍なので、ピアノ演奏の初級者から上級者まで幅広い層の読者に適しています。しかし、譜例が比較的少ないので、必要に応じて自主的な調べ学習が求められます。
本書の最適な活用法としては、他の基本的な音楽史書籍で全体像を把握した後に、本書を通読して異なる視点から音楽史を捉え直すという方法がおすすめです。本書は細部まで網羅的に解説するタイプではなく、むしろ特徴的な事象や人物関係に焦点を当てているため、補完的な読み物としての価値があります。
基本的な音楽史書籍の例:
・【ピアノ】43ページの要点学習とピアノ音楽史事典を併用した体系的音楽史学習法
・【ピアノ】2週間で学ぶ「ピアノ音楽史事典」活用ロードマップ:効率的な音楽史入門法
► まとめ
本書における、人物同士の関係性という切り口で歴史を紐解いていく手法は魅力的です。基本的な音楽史の知識を補完し、より多角的な視点を得たい方にとって、貴重な一冊と言えるでしょう。
・ピアノ音楽史 著:ゲオルク・シューネマン 訳 : 門馬直美、石多正男 / 春秋社
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
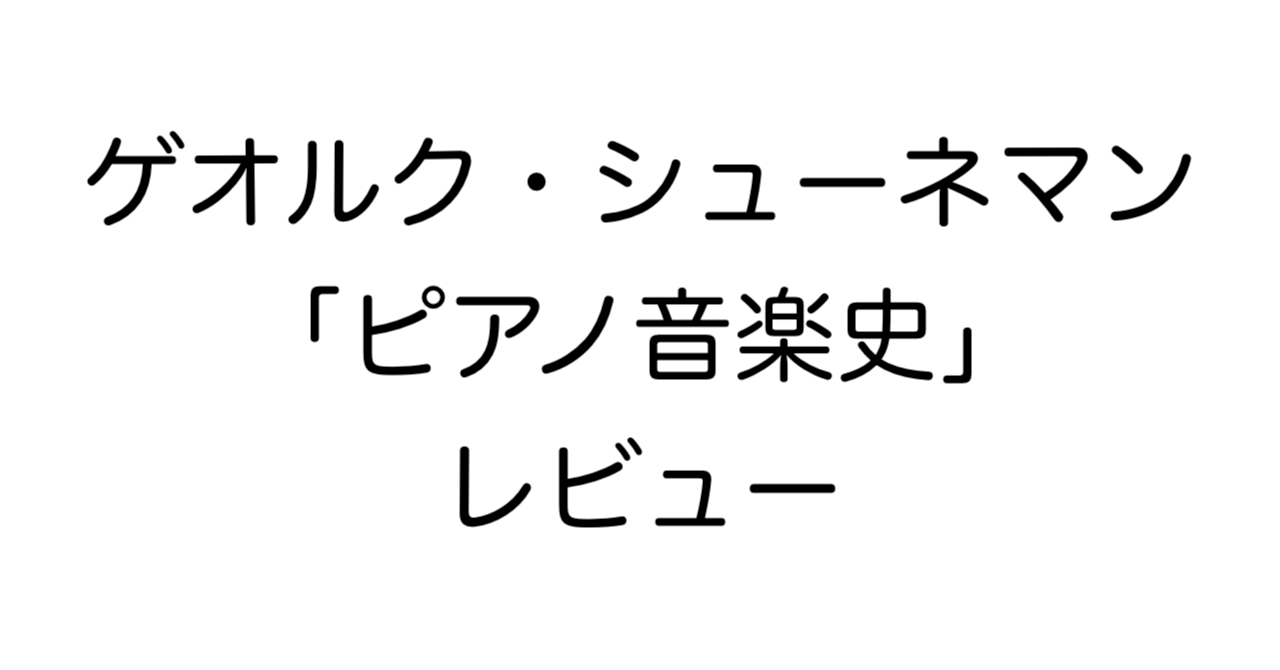

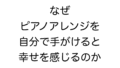
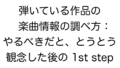
コメント