- 【ピアノ】先生に聞けない素朴な疑問10選:真面目に答えるQ&A集 vol.9
- ► はじめに
- ► 質問集
- ‣ Q1. レッスンで遅刻しそうになったとき、何分前から連絡すべき?
- ‣ Q2. 天候が悪くて休むのは失礼?
- ‣ Q3. 引っ越しで遠方になった場合、オンラインレッスンを頼むのは失礼?
- ‣ Q4. 発表会の曲を、途中で「やっぱり変えたい」と先生に言っていい?
- ‣ Q5. 弾いている途中に「止められる」のが苦手…
- ‣ Q6. 練習中、ミスが出るたびにイライラしてしまう…これって普通?
- ‣ Q7. 好きな曲を「連弾」用にアレンジしたいが、先生に相談してもいい?
- ‣ Q8. 自分で楽譜を編曲・アレンジする行為は、先生から見てどう?
- ‣ Q9. 学習の幅を広げる:無調音楽に触れるべき?
- ‣ Q10. ピアノのペダルにカバーをかけているが、練習時は外すべき?
- ► 終わりに
【ピアノ】先生に聞けない素朴な疑問10選:真面目に答えるQ&A集 vol.9
► はじめに
・「こんなこと、先生に聞いていいのかな…」
・「ググっても明確な答えが出てこない…」
こういった、聞きにくいけど実は気になるピアノ関連の疑問に、真面目に答えます。レッスンに通っている方はもちろん、スポット(単発)レッスンを受ける独学の方にも参考になる内容です。
関連記事:
► 質問集
‣ Q1. レッスンで遅刻しそうになったとき、何分前から連絡すべき?
結論:わずかでも遅刻する可能性があれば、すぐにメールかメッセージを
遅刻が判明した時点で、すぐにメールかメッセージを入れましょう。電話は避けるべきです。なぜなら、電話は先生の行動を強制的に止めてしまうからです。自分のレッスン時間前であっても、前の生徒のレッスン中かもしれません。普段は自分の前に生徒がいないと分かっている場合でも同様です。
メッセージが「既読」にならなくても問題ありません。 重要なのは「レッスン開始時刻より前に連絡を入れた」という事実です。これが後々の信頼関係を左右します。
数分の遅刻でも、1対1の約束を守れなかったという事実は変わりません。先生が致命的な損害を被るわけではありませんが、「自分よりも他のことを優先された」と感じさせてしまうと、信頼関係に傷がつきます。
‣ Q2. 天候が悪くて休むのは失礼?
結論:極端な悪天候なら失礼ではないが、必ず正直な理由を伝える
レッスンをしている知人から聞いた話ですが、悪天候の日は「体調不良」などの理由で欠席する生徒が明らかに増えるそうです。その日だけ複数の生徒が同じような理由で休むため、実際の理由は明白です。
極端な悪天候であれば休むこと自体は問題ありません。 ただし、その場合は必ず正直に理由を伝えましょう。
「台風が近づいていて、帰りの電車の運行や安全性を心配しています。今週はお休みさせていただけますか?」などといったように、天候が理由であることをそのまま話してください。もし「それは理由にならない」と感じるような天候なら、それほど悪天候ではないということです。人対人の約束を優先しましょう。
‣ Q3. 引っ越しで遠方になった場合、オンラインレッスンを頼むのは失礼?
結論:先生がオンラインレッスンを開講していれば、相談して構わない
引っ越しで遠方になっても、その先生に習い続けたいのであれば、オンラインレッスンを相談すること自体は問題ありません。ただし、その先生が日頃からオンラインレッスンを開講していることが前提条件です。
やってはいけないのは、「自分のためだけに特別対応してもらおうとする」ことです。組織やシステムの中で、勝手に自分のルールを作ろうとするのは避けましょう。
実体験から
筆者自身、引越し後に片道3時間の距離になった先生のもとへ、オンラインでスポット(単発)レッスンを何度も受けた経験があります。先生がすでにオンライン対応をされていたからこそ実現できました。
‣ Q4. 発表会の曲を、途中で「やっぱり変えたい」と先生に言っていい?
結論:正当な理由があれば相談しても構わない
以下のような正当な理由がある場合は、先生に相談してみましょう:
相談していいケース:
・選曲時には気づかなかったが、広い音程や和音が続き、自分の手の大きさでは物理的に無理がある
・技術的に明らかに背伸びし過ぎていた
避けるべきケース:
・何となく飽きたから
・他に弾きたい曲に気持ちが移ったから
・譜読みが面倒になったから
・すでに暗譜している別の曲に変えたいから
後者のような「逃げの姿勢」での変更は、先生をがっかりさせます。発表会は数週間〜数ヶ月で終わります。一度決めたことは、その程度の期間はやり抜きましょう。逃げ癖をつけないことも、ピアノ学習の大切な要素です。
‣ Q5. 弾いている途中に「止められる」のが苦手…
結論:レッスンは気持ちよく弾く披露の場ではない
レッスンのあり方は教室それぞれですが、基本的にレッスンは「上手に弾けることを先生に証明する場」ではありません。次々に弾き進めて先に進みたくなる気持ちは分かりますが、止めてまで隣でアドバイス演奏をしている先生の音と言葉をよく聴く姿勢が必要です。そこに上達のヒントが隠されています。
よくある NGパターン
先生がアドバイスとして横で弾き示している最中や、説明の途中に、生徒がさえぎるように演奏を再開してしまう
意識すべきこと
「褒めてもらうことを目的にしない」。習いに行くからには、指摘を受け入れる覚悟が必要です。
補足
もし「止められずに通して弾きたい」という気持ちが強いなら、レッスンの最初か最後に「今日は一度通して聴いていただけますか?」とお願いするのも一つの方法です。目的を明確に伝えることで、先生も対応しやすくなります。
‣ Q6. 練習中、ミスが出るたびにイライラしてしまう…これって普通?
結論:誰誰にでも起こり得ることだが、この感情をコントロールするのも学習目標の一つ
ミスへの対処法:核心
「弾き間違いをしたら、すぐ弾き直さず、少しでも間(ま)をとる」ことを徹底しましょう。
なぜ、連続した弾き直しが危険なのか
練習中に弾き間違いをすると、正しいポジションを確認しようと弾き直しをするはずです。ここまでは問題ありません。しかし、弾き直してまた失敗すると、ムキになって再度弾き直す…この繰り返しが危険なのです。
何が起きているのか:
・「とりあえず弾き間違えない」という結果だけを求めて安心しようとする
・すべてを忘れて、ただ弾き直しに終始する
・負のスパイラル=一種のパニック状態
・変なクセがつくだけで、何も身につかない
特に、大きな跳躍などミスタッチが発生しやすい箇所で、このような状態に陥りがちです。
改善方法
繰り返しますが、「弾き間違いをしたら、すぐ弾き直さず、少しでも間(ま)をとる」ことです。すぐに安心したい心を抑えて、一度立ち止まりましょう。正しい音に当たるまで無闇に弾き続けるのは、本当に意味がありません。
こういった感情処理の力をつけるのも、ピアノ学習における重要な目標の一つです。
推奨記事:【ピアノ】ひたすら弾き直しをしてしまう思考停止癖への対処法
‣ Q7. 好きな曲を「連弾」用にアレンジしたいが、先生に相談してもいい?
結論:レッスン時間内であれば構わない
連弾用の編曲は、ピアノ学習において必要とされるケースが多くあります。しかし、自分一人で作り上げるのは難しいでしょう。先生に相談してみるのは問題ありません。
期待できるメリット:
・仮に作曲や編曲にそれほど精通していない先生でも、連弾作品をたくさん知っているのは確実
・様々な参考作品を教えてもらえる
・演奏面から編曲のヒントやアドバイスがもらえる
重要な注意点:
・必ずレッスン時間内に相談する(時間外はNG)
・作曲・編曲が専門の先生の場合:
– ピアノレッスンと創作レッスンの料金が異なる場合がある
– その場合は、ピアノレッスン内で創作の話を出すと趣旨が変わってしまう
– 必ず「創作レッスン」として別枠でワンレッスン予約する
‣ Q8. 自分で楽譜を編曲・アレンジする行為は、先生から見てどう?
結論:ほとんどの先生は好意的に捉えるはず
「クラシックの、しかもピアノソロだけをやりなさい」という考えの先生も時々います。しかし、ほとんどの先生は編曲・アレンジに対して好意的でしょう。
なぜ、ピアノアレンジは幸福感をもたらすのか
ピアノ音楽の楽譜は数多く売られているにも関わらず、自分で作曲や編曲を手がけると、創作の最中や完成後に不思議な幸福感を覚えます。「レパートリーが増える」「楽曲の構造が分かり、演奏に活きる」などの実利的な恩恵もありますが、もっと別の理由もあります。
ピアノアレンジによる幸福感の源泉:
・目に見える、耳でも聴ける結果による達成感・満足感
・「今、この瞬間」を大切に味わうマインドフルな時間
・「育てていく」プロセスの楽しみ
・「誰かのため」や「共有する」喜び
・小さな「生活の理想」を叶えている感覚
・「自由」が与えてくれる喜びと充実感
詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
【ピアノ】なぜ、ピアノアレンジを自分で手がけると幸せを感じるのか
‣ Q9. 学習の幅を広げる:無調音楽に触れるべき?
結論:ツェルニー30番入門以降の学習段階に達したら、数曲触れてみるのがおすすめ
無調音楽は上級者の中にも「一曲も弾いたことがない」という方がいます。人によって楽しめるかには差があるようですし、基礎としてバロックや古典派に力を入れるのは構いません。
それでも触れてみる価値:
・なぜこのような音楽が生まれたのかを考える機会になる
・音楽史の流れを体感できる
・耳の幅が広がる
・短くて弾きやすい作品も多く、想像よりも取り組みやすい
ツェルニー30番入門以降の学習段階に達したら、以下の記事で紹介している入門的無調作品に触れてみましょう:
・【ピアノ】無調音楽入門:シェーンベルク「6つの小品 Op.19(1911)」
・【ピアノ】ブルグミュラー25の練習曲修了後に弾きたい近現代名曲3曲:3分以内(ウェーベルン作品の解説)
筆者の願い
Piano Hackの読者さんには、食わず嫌いで無調音楽を批判する学習者にはなって欲しくありません。一度体験してから判断しても遅くはないはずです。
‣ Q10. ピアノのペダルにカバーをかけているが、練習時は外すべき?
結論:絶対に外すべき
特にピアノを買ったばかりの頃は、ペダルを素足や靴下で踏むことに抵抗がある方もいるでしょう。しかし、カバーをつけたまま練習していると、足元の感覚が毎回変わってしまい、ペダリング技術が上達しません。
重要なポイント:
・練習時だけでなく、普段からペダルカバーは取り除く
・多少の変色は避けられない(むしろ使い込まれている証)
・上手なピアノ弾きの自宅のピアノで、ペダルがピカピカということはあり得ない
楽器を大切にしたい気持ちは重要ですが、「大切にする」とは「使わずに保存すること」ではなく「適切に使い込むこと」です。ペダリング技術の向上を優先しましょう。
► 終わりに
先生に聞けないこと、ググってもあまり出てこないこと、たくさんあります。そんな小さな疑問を一つずつ解決していくことでピアノ学習を楽しくしていきましょう。
関連記事:
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
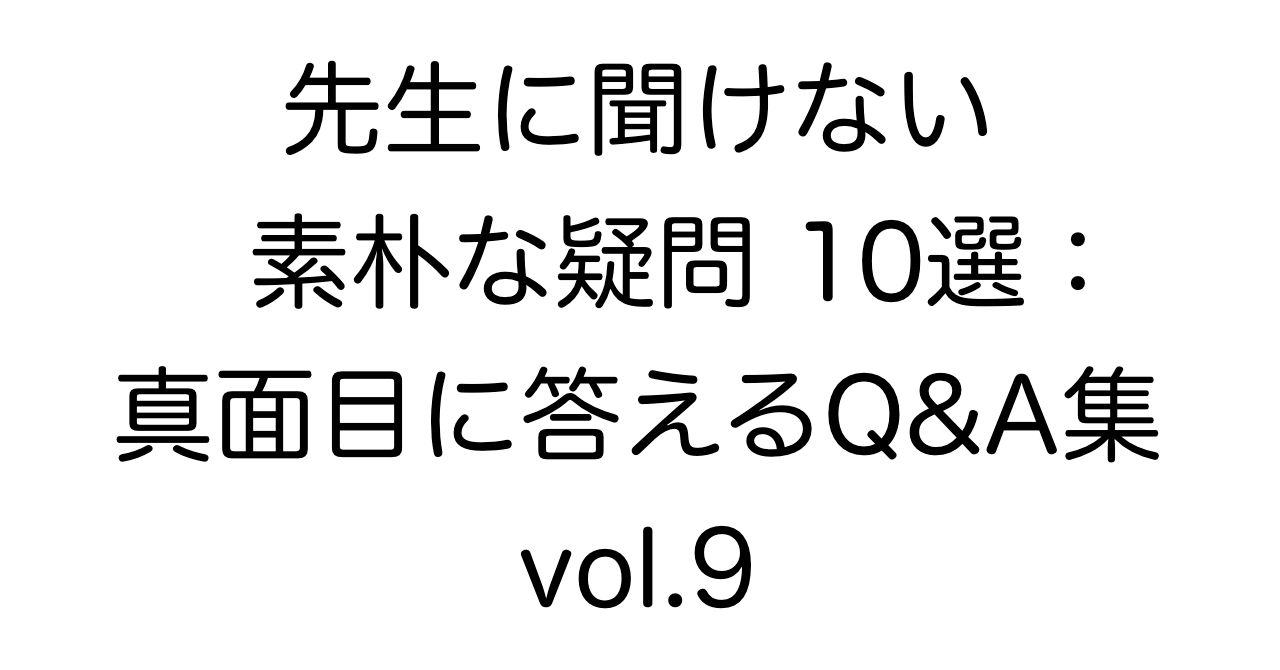
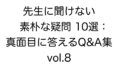
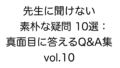
コメント