- 【ピアノ】先生に聞けない素朴な疑問10選:真面目に答えるQ&A集 vol.17
- ► はじめに
- ► 質問集
- ‣ Q1. レッスン室が寒過ぎる/暑過ぎる場合、生徒から温度調整をお願いしていい?
- ‣ Q2. ピアノの鍵盤を拭く際、アルコール除菌シートは使っていい?
- ‣ Q3. レッスンで先生が用意してくれたお茶やお菓子を断るのは失礼?
- ‣ Q4. 自分の手が小さいことを、どうカバーすべきか?
- ‣ Q5. あえて口で歌ってみる練習は、どのように取り入れるべきか
- ‣ Q6. 音楽の専門用語を、外国語で覚えるべきか、日本語訳でいいか?
- ‣ Q7. 絶版になった楽譜をどうしても手に入れたい場合、どうすればいい?
- ‣ Q8. 先生との信頼関係を深めるために、レッスン中以外でできることはある?
- ‣ Q9. 先生が自分のために追加で時間を割いてくれていることに、過剰にプレッシャーを感じる…
- ‣ Q10. 演奏会を聴く際、途中で眠くなってしまう…
- ► 終わりに
【ピアノ】先生に聞けない素朴な疑問10選:真面目に答えるQ&A集 vol.17
► はじめに
・「こんなこと、先生に聞いていいのかな…」
・「ググっても明確な答えが出てこない…」
こういった、聞きにくいけど実は気になるピアノ関連の疑問に、真面目に答えます。レッスンに通っている方はもちろん、スポット(単発)レッスンを受ける独学の方にも参考になる内容です。
関連記事:
► 質問集
‣ Q1. レッスン室が寒過ぎる/暑過ぎる場合、生徒から温度調整をお願いしていい?
結論:問題ない
これに関しては、体調に関わることなので、遠慮なく伝えて構いません。ただし、先生にとっても過ごしやすい温度があるため、まずは服装の調整など、自分でコントロールできる範囲で対応し、それでも難しい場合にお願いするのが理想的です。
音楽学校では、個人レッスンで沖縄出身の学生と北海道出身の学生が連続する場合、室温管理に特に配慮するという話をよく耳にします。体感温度の個人差は想像以上に大きいものです。
伝え方の例:
・「少し寒く感じるので、温度を上げていただけますか」
・「暑さで集中しづらいので、冷房を少し強めていただけないでしょうか」
‣ Q2. ピアノの鍵盤を拭く際、アルコール除菌シートは使っていい?
結論:避けるべき
一般的に鍵盤を乾拭きで済ませている方は多いと思いますが、以下のようなケースではウェットな処置や消毒が必要になることがあります:
・ピアノ教室など、複数の人が触るピアノの鍵盤
・鉛筆で手を汚した後の子供が触った鍵盤
・特にピアノを清潔な状態に保っておきたい場合
しかし、アルコール除菌シートの使用は避けるべきです。
なぜ、アルコールが避けられるべきなのか
多くのピアノ(アコースティックピアノや電子ピアノ)の鍵盤は、アクリル、プラスチック、人工象牙、フェノール樹脂などの素材でできています。アルコール(特に高濃度のもの)や塩素系の消毒液を使用すると、以下のような問題が起こる恐れがあります。
・ひび割れ
・変色、変質
・表面の光沢を損なう
・プラスチック製鍵盤の溶解や変質
推奨されるお手入れ・除菌方法:
1. ノンアルコールの除菌シート
ノンアルコールと明記された除菌シートで軽く拭き取った後、柔らかく清潔な布で乾拭きする方法が推奨されています。
2. 鍵盤専用のクリーナー
市販されているピアノ・電子ピアノの鍵盤専用クリーナー(キークリーナーなど)を使用するのは構いません。
3. 水拭き + 乾拭き
水で濡らして固く絞った柔らかい布で拭き、その後すぐに乾いた布で水気を完全に拭き取ります。
‣ Q3. レッスンで先生が用意してくれたお茶やお菓子を断るのは失礼?
結論:一般的には失礼にあたらない。ただし、節目のときの誘いには応じたほうがよい
先生のお心遣いはありがたいものの、お茶やお菓子を辞退することは珍しくありません。生徒さんや先生それぞれの考え方や状況によって、判断は異なります。
辞退する際のポイント:
感謝の気持ちを伝える
「お気遣いありがとうございます。せっかくですが、今回は(理由)で遠慮させていただきます」など、まずはお礼を述べましょう。
角の立たない理由を添える
・「次の予定があるため、すぐに失礼させていただきます」
・「直前に飲み物をいただいてきたので、今は大丈夫です」
・「レッスンに集中したいので、お心遣いだけで十分嬉しいです」
特に、先生によっては「レッスン時間内に集中したい」「お茶の準備の負担をかけたくない」という生徒からの気持ちを理解し、そもそも提供を控えている方もいらっしゃいます。
節目のレッスンでは応じるのがベター
ただし、以下のような節目のレッスンでは、先生も十分に会話をしたいと思っている可能性があります:
・初回レッスン
・発表会後の初レッスン
・最終レッスン(引っ越しや卒業など)
・年度の区切りとなるレッスン
日頃断っていても、このような節目で誘われたときは、コミュニケーションの一環として応じることをおすすめします。
‣ Q4. 自分の手が小さいことを、どうカバーすべきか?
結論:大きく3つの選択肢がある
手の大きさは変えられませんが、アプローチ方法は複数あります。
1. 技術的な工夫を凝らす
楽譜の上段に書いてあるからといって、必ずしも右手で弾く必要はありません。その逆も同様です。
・片方の手に余裕があれば、もう一方の手で担当する音を探す
・音程の広い和音をアルペジオ(分散和音)として演奏する
・ペダルを活用して音をつなぐ
・音楽的にあまり重要でない一部の音を省略する(最終手段)
これらの工夫だけで、難易度が大幅に下がる可能性があります。
2. 編曲を学習し、自分に「当て書き」する
ピアノ編曲を勉強することで、自分の体格に合わせて音を編むことができます。編曲スキルは、ピアノ学習者にとって大きな武器になります。
自分で編曲できるようになれば、弾ける作品の幅が飛躍的に広がり、手の大きさの問題は大幅に解消されます。
3. 体格に合う作品を優先し、合わない作品は潔く諦める
特定の作品への「憧れ」を持つことは否定しませんが、どうしても自分の体格に合わない楽曲に対しては、「諦め」も必要です。
世の中には、読者さんの体格に合った素晴らしい作品が山ほどあります。その中から最高の作品を見つけ出し、最高の演奏をすることに集中しましょう。
本Webサイトでは、上記1〜3のどの選択肢にも対応できるように、豊富なコンテンツを用意しています。
‣ Q5. あえて口で歌ってみる練習は、どのように取り入れるべきか
結論:ピアノを弾かずに取り入れるのがおすすめ
ピアノを弾かずにメロディを歌う(推奨)
声に出して歌うと、誰でも自然に抑揚をつけることができます。豊かな強弱表現を伴いながら、音楽的な揺れ動きも無理なく表現できるでしょう。
人間は呼吸によって歌うため、フレーズの切れ目では自然とテンポがゆるやかになります。これにより、意識しなくてもフレージングに適したアゴーギク(テンポの伸縮)が自然発生するのです。頭で理論的に考えるより、身体が音楽を表現してくれます。
練習中の楽曲で、この感覚を「ピアノなしで」試してみることは、表現力向上に極めて有効な学習アプローチです。
ピアノを弾きながら歌うのはおすすめできない
口で歌ってみること自体は有益ですが、弾きながら常に口に出していると、以下の問題が生じます。
・自分のピアノの音をきちんと聴くことができない
・無意識に自分の演奏の粗をごまかそうとしてしまう
・ピアノの音色や響きへの注意がおろそかになる
多くの場合、「常に歌っていた」というよりは「気づいたら歌っていることがあった」というケースでしょう。「弾きながら」歌う習慣は、意識的に控えることをおすすめします。
速いパッセージ練習への応用
鍵盤を使わず、技術的に難しいパッセージを声で歌ってみましょう。口で歌ってつまずく箇所は、ほぼ確実にピアノ演奏でもつまずいています。
加えて、「パッセージを正しいタイミングで歌いきる」技術は見過ごせません。速いフレーズでは音を乱さずに、リズミカルな部分では正確なリズムとアクセント位置を守って歌う。これらを安定してこなせることが求められます。
‣ Q6. 音楽の専門用語を、外国語で覚えるべきか、日本語訳でいいか?
結論:使用している教材で出てきたものを把握しておけばOK
基本的には、使用している教材で出てきた用語を、その都度しっかり理解することで十分です。ただし、以下の基本的な用語については、日本語と外国語の両方を把握しておくことをおすすめします。
両方を把握しておきたい基本用語:
・音階=Scale (スケール)
・分散和音 = Arpeggio (アルペジオ)
・和音 = Chord (コード)
・半音 = Semitone (セミトーン)
・全音 = Whole Tone (ホールトーン)
・異名同音 = Enharmonic(エンハーモニック)
・保続 = Pedal Point(ペダルポイント)
– Orgelpunkt(オルゲルプンクト):ドイツ語圏での呼称
– 持続低音(主に低音部で用いられる保続)
‣ Q7. 絶版になった楽譜をどうしても手に入れたい場合、どうすればいい?
結論:大きく4つの選択肢がある
基本的な入手ルート:
1. 国会図書館
オンライン閲覧可能な資料も増加しています。遠方の方でも、登録すればデジタル化された資料を閲覧できる場合があります。
2. 音楽大学図書館
多くの音楽大学図書館では、外部利用制度を設けています。事前に利用条件を確認し、申請手続きを行えば閲覧が可能です。
3. 作曲家・編曲家への直接的なアプローチ
現代に発表された作品の場合、作曲家や編曲家本人が楽譜を保管している可能性があります。礼儀正しく問い合わせてみる価値はあります。
4. 中古市場での根気強い探索
古書店、オークションサイト、フリマアプリなどで定期的に検索することで、稀に見つかることがあります。
注意点:
・オークションサイトでは、法外な価格設定に注意
・状態の確認を十分に行う
・著作権が切れていない楽譜の複製・配布は違法
さらに詳しくは、【ピアノ】楽曲分析を深める方法:専門書・マスタークラス・研究論文の活用ガイド という記事を参考にしてください。
‣ Q8. 先生との信頼関係を深めるために、レッスン中以外でできることはある?
結論:とにかく、筋を通す
レッスン中以外で信頼を得るためには、大人として最低限のマナーをしっかり守ることが最も重要です。
信頼を築く基本的な行動:
・レッスンを休むときは、必ず事前に連絡を入れる
・体調不良の場合でも、連絡できる状態になり次第すぐに連絡する
・無断欠席は絶対にしない
・レッスン時間に遅刻する場合は、事前に連絡する
・月謝の支払いは期日を守る
とにかく、何があってもブッチしないことです。
重要な心構え
最低限の筋を通すだけで、ある程度の信頼を得ることができます。しかし、そのときの気分や気持ちで一度でもこういった場面を適当に扱うと、信頼はゼロに近くなります。
信頼は積み重ねで築かれ、一度の失態で崩れることを肝に銘じましょう。指導者が「この生徒は今後も筋を通してくれそうだな」と思えるかどうかが重要です。
さらに信頼を深めるために:
・レッスンの課題にしっかり取り組む
・学習の成果や課題を素直に伝える
・先生のアドバイスを実践し、その結果を報告する
・発表会やコンサートなど、先生の活動に関心を示す
‣ Q9. 先生が自分のために追加で時間を割いてくれていることに、過剰にプレッシャーを感じる…
結論:お互いの目指している方向性をはっきりさせる
生徒が抱える複雑な心理状態
感謝の感情:
・先生の熱心な指導に対する感謝の念
・自分のために割いてくれる時間と労力への認識
困惑やストレスの感情:
・先生の期待に十分応えられない罪悪感
・マイペースで学びたいという本音
・双方の熱量の違いから生まれる心理的負担
こうした相反する感情を放置してしまうと、ピアノ学習自体が苦しいものになりかねません。
最初に取り組むべき対応策
レッスン時間を1回分確保して、先生と誠実に対話する機会を設けましょう。
対話で扱うべきテーマ:
・お互いが目指す学習の方向性を明確にする
・自分が望む学習ペースや到達目標を率直に共有する
・先生の指導ビジョンや生徒への期待を確認する
・レッスンの実施頻度や内容の調整が可能か相談する
伝え方の例
「先生がたくさんの時間を割いて指導してくださることに、とても感謝しています。ただ、正直に申し上げますと、私自身はもう少しゆっくりとしたペースで学びたいと考えています。今日は、お互いの目指す方向性についてお話しできたらと思っています。お時間をいただけないでしょうか」
この問題に関しては、【ピアノ】先生の熱心さが辛い、イライラする…ピアノの悩みQ&A という記事で詳細に解説しています。
‣ Q10. 演奏会を聴く際、途中で眠くなってしまう…
結論:演奏会鑑賞の眠気対策には、事前準備がものを言う
実は、少しの準備と心構えで、演奏会での集中力と楽しさは劇的に変わります。
演奏会を深く楽しむ4つの方法:
・演奏される楽曲を事前に予習する
・眠気対策を万全にする
・早めに会場入りして、当日配られたプログラム冊子に目を通す
・物音に過敏に「気をつけ過ぎない」「気をつけ過ぎさせない」
この問題については、【ピアノ】ピアノリサイタルを今までの2倍楽しむ方法という記事で詳細に解説しています。
► 終わりに
先生に聞けないこと、ググってもあまり出てこないこと、たくさんあります。そんな小さな疑問を一つずつ解決していくことでピアノ学習を楽しくしていきましょう。
関連記事:
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
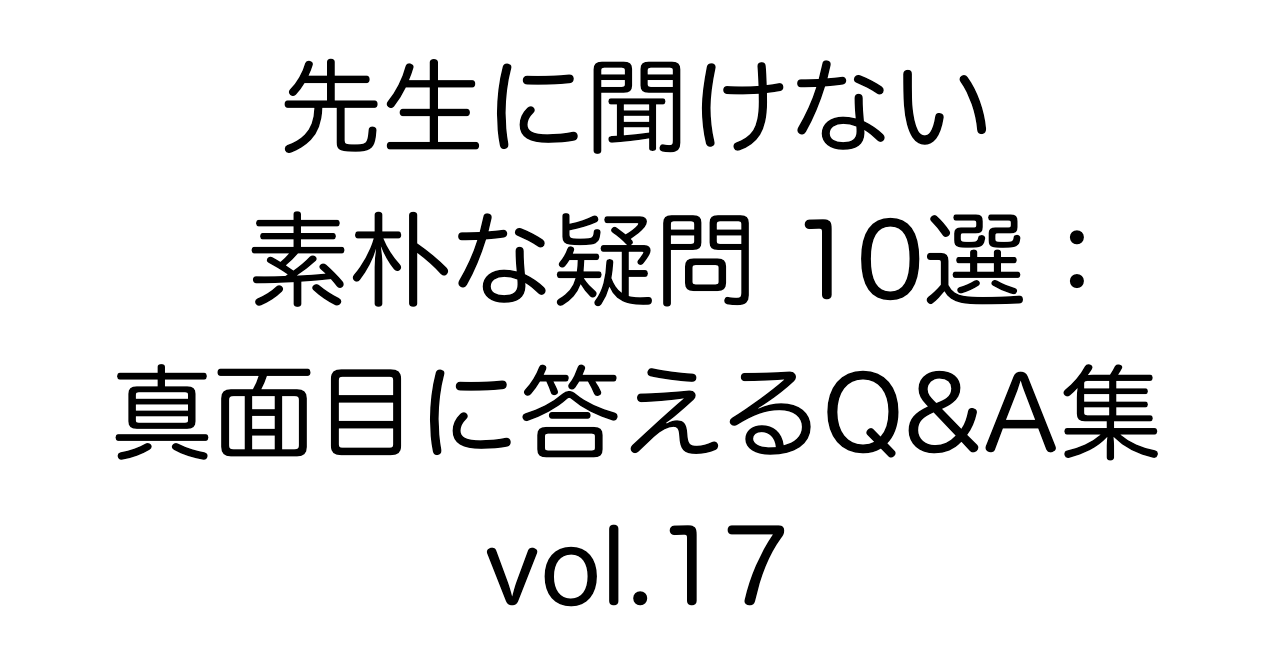
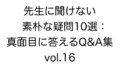
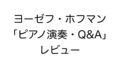
コメント