【ピアノ】「ピアノ演奏の論理」(東貞一 著)レビュー
► はじめに
著者の東貞一氏(1903-1980)は、京都帝国大学文学部哲学科を卒業後、音楽大学で教鞭をとりながら演奏活動も行っていました。哲学と音楽双方に精通した人物であり、本書にもその両面からのアプローチが色濃く表れています。
・出版社:音楽之友社
・初版:1983年
・ページ数:166ページ
・対象レベル:上級者
・ピアノ演奏の論理 著:東貞一 / 音楽之友社
► 内容について
‣ 本書の特徴
「ピアノ演奏の論理」というタイトルからは純粋に演奏技術に関する本と思われるかもしれませんが、実際には演奏と作品の本質的な関係性、さらには演奏家と作曲家の関わりという深いテーマに踏み込んだ哲学的考察を含む書籍です。
本書の核心部分は次の言葉に集約されています:
「音楽は作曲家によって創造されたものの範囲に止まる限り、まだなお完成された芸術として存在し得ないのである。」
「作曲を第1の創造、演奏を第2の創造と言うことができるであろう。そして第2の想像こそ第1の創造の完成なのである。」
(抜粋終わり)
‣ 主要概念
コンセプション(conception)の重要性
本書の中核をなす概念が「コンセプション」。これは、「演奏家によって指向された作品の本質」を意味し、著者は、作品の本質を捉えるコンセプションこそが真の演奏に不可欠だと説きます。
特に「Ⅰ部 ピアノ演奏の論理」では:
・コンセプションを獲得する方法
・コンセプションに基づいた楽曲分析の手法
・コンセプションがもたらす効果
について詳細に解説されています。
3つの演奏様式
「Ⅱ部 ピアノ演奏における基礎的な3つの様式」では、以下の演奏様式について詳細に解説されています:
・古典的演奏様式
・ロマン的演奏様式
・表現主義的演奏様式
これらの様式の特徴と違いを理解することで、時代や作風に応じた適切な演奏アプローチを考えるヒントとなるでしょう。特に「IV章 補遺」では、これらのキーポイントがコンパクトにまとめられており、実践的な参考になります。
‣ 印象的な考察
本書の中で印象的なのは、作曲家の体験から楽譜への変換プロセスについての考察です:
「作曲家を作曲に駆り立てる人生経験は、具体的個別的なものであるが、しかしそれが楽譜に書かれた時、すなわち対自の段階ではすでに一般的なものに変るのである。」
(抜粋終わり)
この視点は、演奏家が楽譜から作曲家の意図を読み取り、再び具体的な音として表現する際の哲学的基盤を提供しています。
► おすすめの読者層
本レビューでは主に、重要かつ理解が比較的容易な部分を中心に紹介しました。ただし、実際には専門性が高く、深い内容の書籍であり、明らかに上級者向けの専門書です。具体的には:
・ツェルニー50番中盤以上の技術レベルに達している学習者
・音楽理論や音楽美学に深い関心を持つ方
・哲学的思考を通して音楽の深層に迫りたい方
・ピアノ演奏だけでなく、作曲や編曲に取り組む上級者
初心者や中級者には難解な内容が多いため、ある程度の演奏経験と音楽知識を持ったうえで読み始めることをおすすめします。
► 終わりに
哲学を専門で学んでいた東貞一氏の洞察は、技術的に一定の域に達した学習者に新たな視点と思考の枠組みを提供してくれるでしょう。特に「コンセプション」という概念をはじめ、演奏と作品、演奏家と作曲家の関係性について深く考察するきっかけとなる一冊です。
・ピアノ演奏の論理 著:東貞一 / 音楽之友社
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
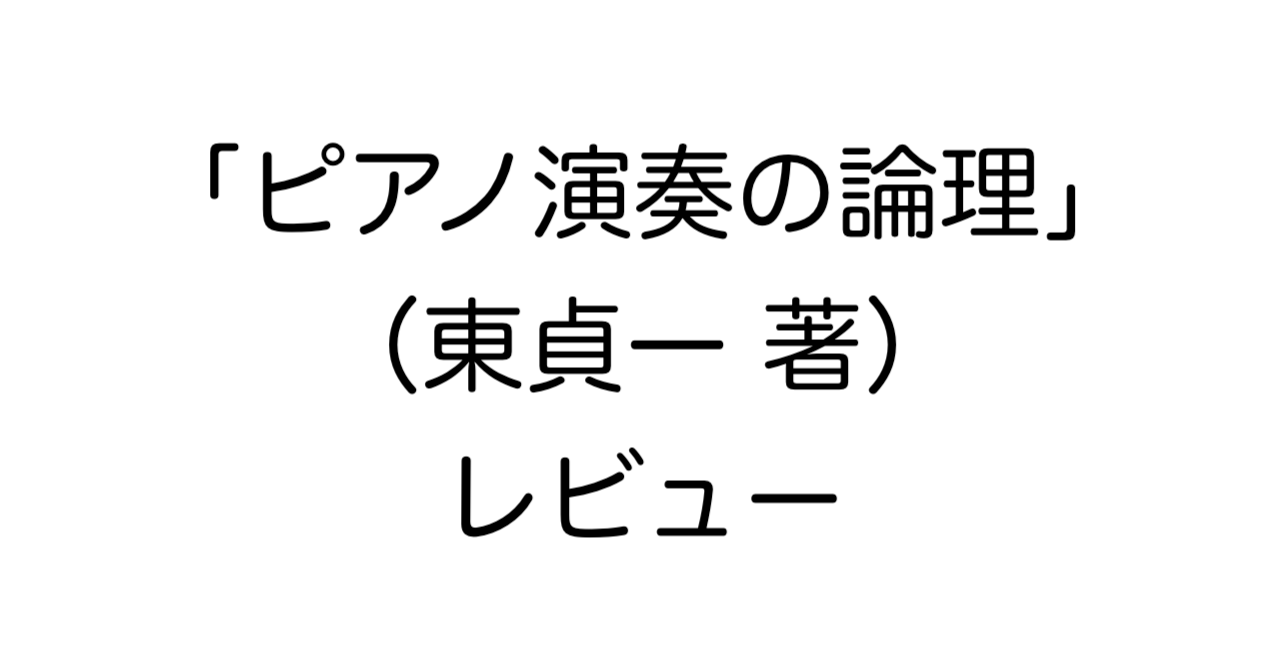

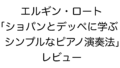
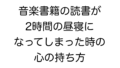
コメント