【ピアノ】映画「課外授業」レビュー:ピアノ音楽が紡ぐ心理描写
► はじめに
映画「課外授業(Lezioni private)」は、田舎の音楽学校を舞台に若い男性生徒と女性ピアノ教師の関係を描いた作品です。音楽演出では、物語の奥行きを生み出すことに成功した注目すべき点が複数あるため、本記事で解説していきます。
※本作には成人向けの描写が含まれますので、視聴の際はご注意ください。
・公開年:1975年(イタリア)
・監督:ヴィットリオ・デ・システィ
・ピアノ関連度:★★★★☆
► 内容について
以下では、映画の具体的なシーンや楽曲の使われ方について解説しています。未視聴の方はご注意ください。
音楽用語解説:
状況内音楽
ストーリー内で実際にその場で流れている音楽。 例:ラジオから流れる音楽、誰かの演奏
状況外音楽
外的につけられた通常のBGMで、登場人物には聴こえていない音楽
‣ 状況外音楽が起点となるストーリーの展開
映画冒頭から28分間、ピアノ演奏などの状況内音楽は聴かれますが、通常のBGM(状況外音楽)は一切使用されません。この沈黙は意図的なもので、28分の時点で初めて状況外音楽が流れることで、物語が新たな局面へと移行することを音楽的に示しています。
状況外音楽が使用される場面には明確な傾向があり、アルトフルートやエレクトリックピアノを用いた官能的な楽曲が、いつも大人なシーンで効果的に使われています。例えば:
・ラウラ先生の写真をガブリエルが撮影する場面
・アレッサンドロがパオラの血を吸う場面
・ラウラ先生のブラウスやスカートが持ち上がる場面
・アレッサンドロとガブリエルがラウラ先生の毛を剃る場面
・ラウラ先生とアレッサンドロがキスをする場面
・アレッサンドロとパオラが結ばれ、緑の草原で自由になっているラストシーン
この音楽設計により、作品全体に統一感が生まれるとともに、登場人物の状況が視覚だけでなく聴覚からも伝わってくるのです。
‣ ブラームス「ハンガリー舞曲第5番」の計算された使用
状況内音楽から状況外音楽への転換でも、注目すべき場面があります。
本編20分頃、ラウラ先生は、アレッサンドロにピアノを弾くように言います。ラウラ先生とアレッサンドロの連弾シーンでは、ブラームスの「ハンガリー舞曲 第5番」が演奏されますが、画面には一度も演奏する2人の姿が映されません。会話の内容と音楽だけで、これが劇中で実際に演奏されている状況内音楽であることを観客に理解させる手法です。
さらに面白いのは、その音楽を継続させたまま屋外のコミカルな騒動シーンへと映像が切り替わる点です。テンポの速さや中間部のコミカルさを持ち合わせた「ハンガリー舞曲 第5番」は、屋内の親密なシーンと屋外の滑稽なシーンの両方に機能する楽曲として選ばれており、緻密な計算が確認できます。
後にラウラ先生とアレッサンドロがこの楽曲を連弾する場面があるので、それを見たときに、本編20分頃の連弾のもうひとりの奏者はラウラ先生だったと推測できる点も凝っていると言えるでしょう。
‣ 演奏の中断が生む心理描写
本作では「カット・アウト(音楽の突然の中断)」が効果的に使用されています。例えば:
・本編7分頃、授業中の風船が割れる音で、ラウラ先生が演奏をやめる
・本編10分頃、自宅でピアノを練習しているアレッサンドロは、過保護な母親に触れられて演奏をやめる
・本編31分頃、自宅でピアノを練習しているアレッサンドロは、やはり母親に話しかけられて演奏をやめる
・本編43分頃、授業中に学生が本を落とした音で、ラウラ先生が演奏をやめる
同じ「中断」でも、その表現方法に微妙な差異を持たせている点に着目しましょう。ゆるやかに演奏が止まる場合と、急激に音が途切れる場合では、その場の緊張感や登場人物の心理状態が大きく異なって伝わります。この繊細な音楽演出により、セリフに頼らない心理描写が実現されているのです。
► 終わりに
本作は、上記のような様々な音楽的な工夫で物語の心理的な奥行きを生み出すことに成功した作品です。成人向けの描写などが含まれており、やや特殊なピアノ映画ですが、音楽表現を意識しながら一度鑑賞してみるのもいいでしょう。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
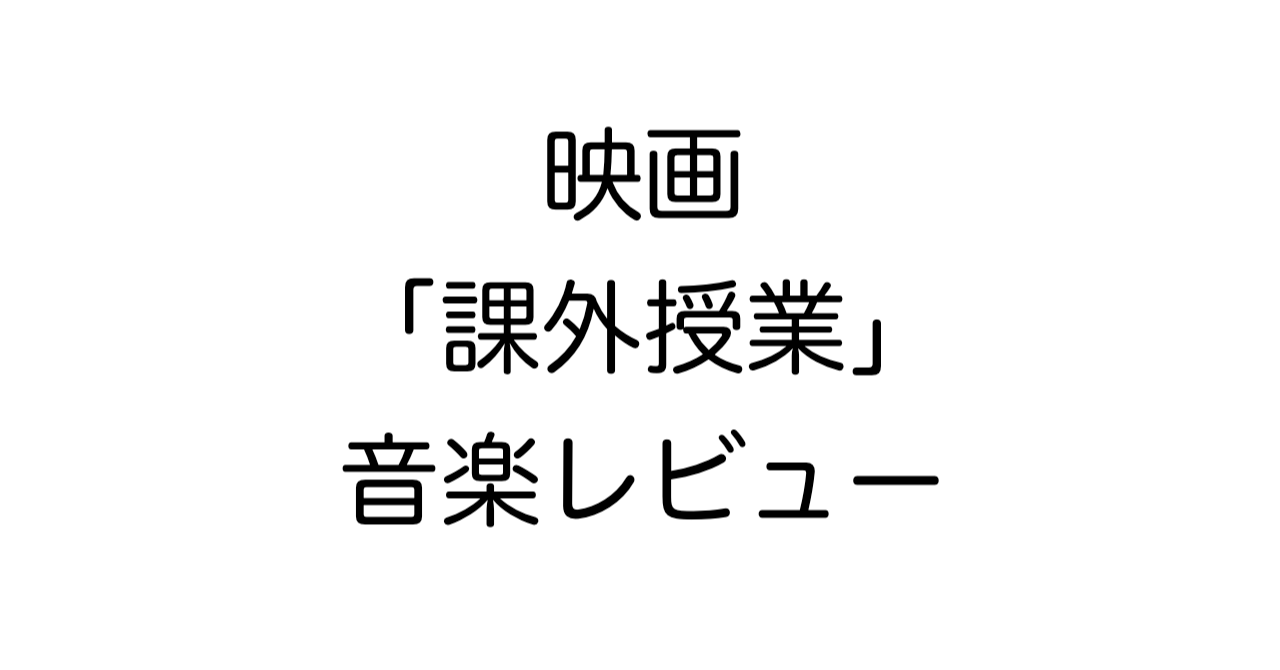
![課外授業 [デジタル・リマスター版] [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Eac4jkmmL._SL160_.jpg)
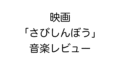
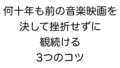
コメント