【ピアノ】中古音楽書籍の他者のアンダーラインから学ぶ方法
► はじめに
中古の音楽書籍を手に取ったとき、前の持ち主が引いたアンダーラインや書き込みを見つけたことはありませんか。「汚れている」と思われがちですが、実はそこには思わぬ学びのチャンスが隠されています。
本記事では、「他者のアンダーライン」から新たな気づきを得る方法について考えてみましょう。
► 人それぞれの「大事だと思う部分」の違い
筆者も中古で音楽書籍を手に入れることがありますが、そこで時々出会うのが「アンダーラインが引かれた古本」です。前の所有者が勉強した跡ですね。興味深いことに、そこには次のような発見があります:
・「どうしてここに線を引いたのだろう?」
・「どうしてここに線を引かないのだろう?」
筆者が重要だと感じる部分と、前の読者が重要視した部分が異なっていることが多々あるのです。これは言うまでもなく、人によって大事だと思う部分や心に響く部分は違うということの証明です。
► 筆者の経験談
このような「ズレ」は、実は我々に新たな視点を与えてくれます。例えば、筆者が所持している「ピアノ音楽史事典」(千蔵八郎 著)には、前の所有者のアンダーラインが残されています。
フランツ・リストについての記述で:
弟子たちには、オクターヴを征服できればピアノ奏法の八分通りは達成されたことになるといい、毎日2時間はオクターヴの練習をしろと教えられたという。彼の場合には、右手と左手に5本ずつの指があるという考え方ではなく、手には10本の指があるという考え方だったから、どんなパッセージでも、ここは右手で、ここは左手で弾くのが合理的という考え方はなかったようである。
(抜粋終わり)
前の所有者は、上記の太字の部分にアンダーラインを引いていました。おそらく「演奏」を主とする方だったのでしょう。一方、「作曲」を主とする筆者は、むしろ後半の部分に興味をもちます。なぜなら、「音をどのように選択するか」「作品のコンセプトをどう構築するか」という作曲の本質に関わる部分だからです。
► 他者の視点から学ぶ方法
‣ 学びを深める3つの視点
では、こうした「他者のアンダーライン」から学びを深めるには、どうすればいいのでしょうか。
1. 違いを認識する
まず、自身が重要だと思う部分と前の所有者が線を引いた部分の違いを明確に認識しましょう。その違いこそが、新たな視点を得るきっかけになります。
2. 「なぜ」を考える
重要だと思う部分の「ズレ」が確認できた場合には、前の所有者がなぜその部分に線を引いたのか、推測してみましょう。
・その人はどのような目的でこの本を読んでいたのか
・どのような背景や経験を持っていたのか
・どのような気づきを得ようとしていたのか
3. 自分の視点を広げる
他者のアンダーラインを通して、自分が見落としていた視点や解釈の可能性を探ります。これは、自分の固定観念から脱却する良い機会です。
‣ 読み始める前に他者の書き込みを消さない
音楽学習においては、多角的な視点を持つことが非常に重要です。他者のアンダーラインを発見したときは、それを「邪魔なもの」として消してから読み始めるのではなく、貴重な学習の機会と捉えましょう。必ずしも良いアンダーラインばかりとは限りませんが、ヒントになることも多いはずです。
‣ ある程度ピンときたものには目を通してみる
一般書籍に比べて音楽書籍の数は限られています。そのため、時間のロスを気にし過ぎず、どんどん手を伸ばしていくくらいの気持ちでいいでしょう。
他者が判断した「書籍要約レビュー」「書籍要約動画」で満足せずに、ある程度ピンときたものには目を通してみることが重要です。
► 終わりに
他者のアンダーラインから学ぶということは、単に知識を得るだけでなく、異なる視点や考え方に触れることでもあります。これは、ピアノ学習に限らず、あらゆる学びの場面で価値のあることです。
次に中古の音楽書籍を手に取ったとき、前の所有者が残したアンダーラインに少し目を留めてみてはいかがでしょうか。
・ピアノ音楽史事典 著:千蔵八郎 / 春秋社
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
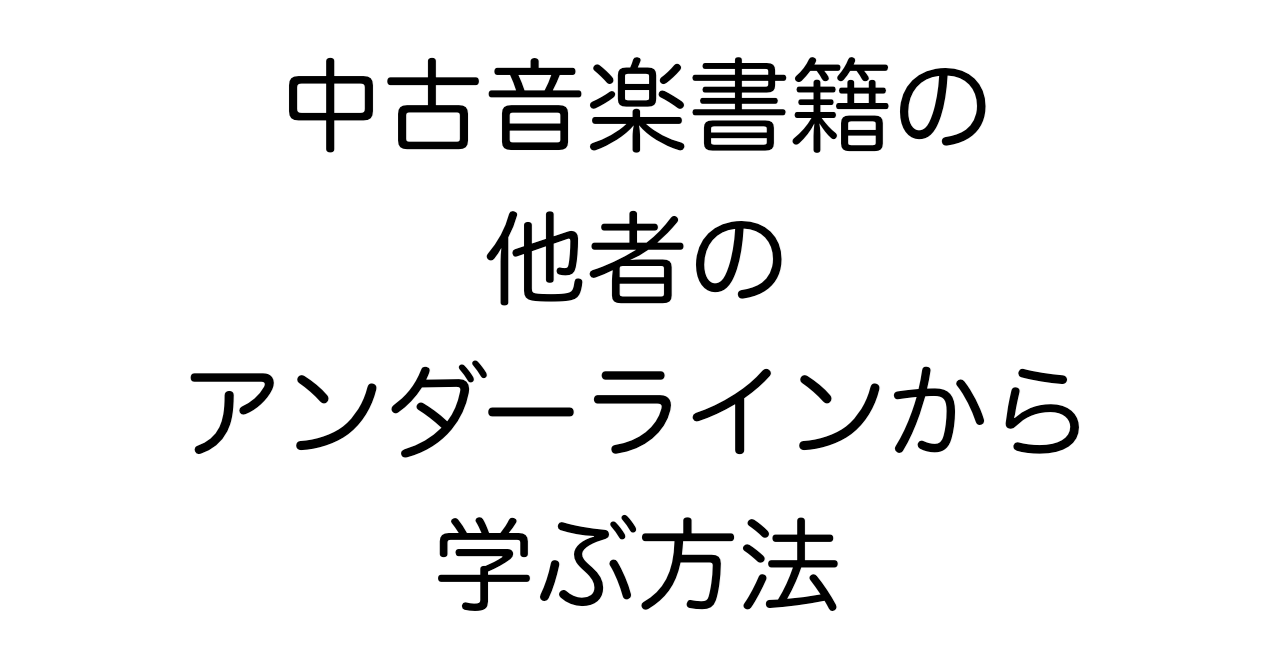

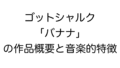
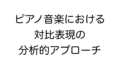
コメント