【ピアノ】「最新ピアノ講座(6) ピアノ技法のすべて」レビュー
► はじめに
書籍「最新ピアノ講座(6) ピアノ技法のすべて」は、まさにピアノ技法の百科事典と呼ぶにふさわしい一冊です。215ページに及ぶ本書は、ピアノ演奏に必要なあらゆるテクニックを網羅し、初中級から上級者まで幅広いレベルの読者に対応しています。
・出版社:音楽之友社
・初版:1982年
・ページ数:215ページ
・対象レベル:初中級~上級者
・最新ピアノ講座(6) ピアノ技法のすべて / 音楽之友社
► 内容について
‣ 本書の特徴
1. 専門家による分担執筆方式
本書の特徴は、日本の著名なピアニスト、作曲家、音楽大学教授陣による分担執筆形式を採用している点です。各章は、その分野のスペシャリストによって執筆されており、音楽家たちの知見が詰まっています。これにより、それぞれの技法について専門的かつ実践的な解説が可能になっています。
2. 充実した譜例
本書のもう一つの大きな強みは、とにかく豊富な譜例が掲載されていることです。例えば、「レガート・カンティレーナ」の項目だけでも、39もの譜例が用意されています。これらの譜例は、古典から近現代までの様々な作品から採られており、各テクニックがどのように実際の楽曲で活用されているかを具体的に示しています。
3. 図鑑のような構成
本書はただの練習法のマニュアルではなく、ピアノ技法の「図鑑」としての役割を果たしています。各テクニックについて、その定義や特徴を詳しく解説した上で、様々な使用例を紹介しています。これにより、読者は同じテクニックでも、作曲家や曲想によって異なる使われ方があることを理解できます。
‣ 内容の詳細
本書は5つの章から構成されています。以下、各章の内容を見ていきましょう。
第1章 練習について
第1章では、練習の基本的な考え方から具体的な方法まで幅広く解説されています。機械的練習の危険性を指摘、練習時間の効果的な配分や、暗譜のしかた、初見視奏の練習法など、ピアノ学習者が直面する様々な課題に対する具体的なアドバイスが盛り込まれています。
第2章 種々の技巧のマスター法
本書の核心部分と言える第2章では、レガート・カンティレーナからペダルの用法まで、全17項目にわたってピアノ技法が詳解されています。各技法について、その定義、基本的な考え方、そして実際の楽曲における使用例が豊富な譜例とともに解説されています。
例えば「半音階」では、作曲家がどういった時にその表現を使用するのかが解説されていたり、電光石火の速さで弾ける運指の提案などが解説されている点で、有益な資料と言えるでしょう。
第3章 伴奏・アンサンブルのテクニック
第3章では、ソロ演奏とは異なる伴奏やアンサンブルの際に必要なテクニックが解説されています。器楽伴奏、歌曲伴奏、室内楽、連弾、協奏曲など、様々な形態の合奏における技術的・音楽的課題と、その解決法が示されています。
特に興味深いのは、この章だけでも5名の専門家を立てていることです。一般的に「伴奏・アンサンブル」と一括りにされがちですが、その中に分野毎の深い専門性を秘めていることを再認識させられます。
第4章 通奏低音奏法
通奏低音について、基礎的な部分が解説されています。三和音の基本形や転回形、属七の和音、掛留音などの概念が、実践的な例を通して理解することができるでしょう。
第5章 コード・ネームによる伴奏法
最終章では、ポピュラー音楽などの伴奏に必要なコード・ネームの理解と活用法が解説されています。基本的なコードの種類や読み方から始まり、メロディにコードを与える方法、効果的な伴奏の作り方まで、実用的な基礎知識が凝縮されています。
‣ 本書の価値
1. 演奏者にとっての価値
上記のように、本書では、各技法の本質的な理解と音楽的表現への活用を促す内容となっています。
2. 教育者にとっての価値
ピアノ指導者にとって本書は、生徒の技術的問題を分析し、適切なアドバイスを与えるための参考書として役立ちます。各技法の解説が体系的で明確なため、レッスンの中で特定の技術的課題に取り組む際の指針となるでしょう。また、豊富な譜例は、技術練習と実際の楽曲をつなぐ架け橋として、教材選択の参考にもなります。
3. 作曲・編曲に挑戦するピアノ学習者とっての価値
本書は、ピアノという楽器の可能性を理解するための資料としても価値があります。様々な技法の解説と譜例を通じて、どのような音型がピアノで効果的に演奏できるかを学ぶことができ、ピアノのための作曲や編曲に取り組む際の参考になるでしょう。「作曲や編曲をする」ということは、「楽器を知る」ということとイコールです。
► 使い方のヒント
1. 興味のある項目を一通り読む
2. 以降は辞書的な使い方として、必要に応じてピンポイントで開き直す
3. 教えている場合は、レッスンの準備時に教材として活用する
図鑑のような充実した内容だからこそ、2周目以降はレファレンスにするのがおすすめ。常に近くへ置いておきましょう。
► 終わりに
「最新ピアノ講座(6) ピアノ技法のすべて」は、ピアノ演奏に必要な技法を網羅的に解説した、まさに「ピアノの図鑑」と呼ぶにふさわしい一冊です。豊富な譜例と複数の専門家による深い洞察により、ピアノという楽器に関してより理解を深めることができるでしょう。
「最新ピアノ講座」シリーズの他の巻と併せて読むことで、ピアノ演奏に関する総合的な理解がさらに深まるでしょう。特に「最新ピアノ講座(1)」との組み合わせは、演奏の理論と実践の両面から学ぶうえで理想的です。レビューは以下の記事で取り上げています。
【ピアノ】「最新ピアノ講座(1)」レビュー:演奏者・教育者必携の決定版ガイド
・最新ピアノ講座(6) ピアノ技法のすべて / 音楽之友社
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
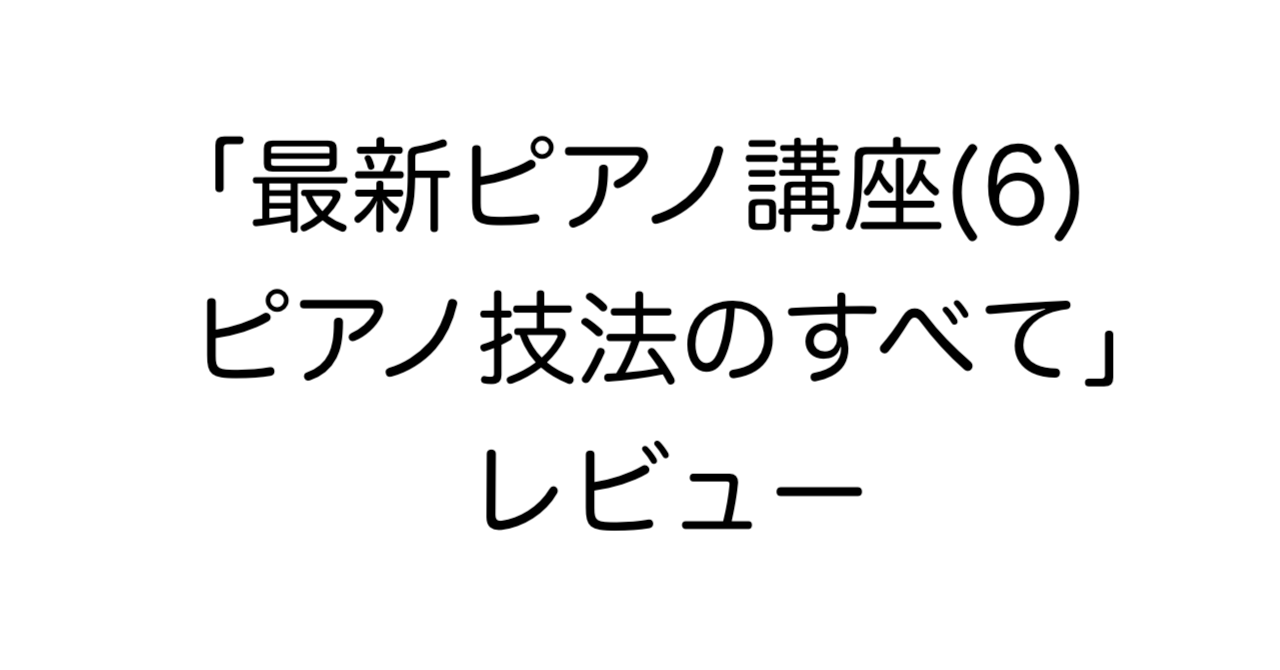

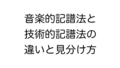
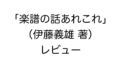
コメント