【ピアノ】映画「別離(1939年)」レビュー:ピアノ音楽の効果的演出
► はじめに
1939年公開のアメリカ映画「別離(Intermezzo: A Love Story)」は、音楽的に注目すべき工夫が見られる作品です。本作では、ベートーヴェン、グリーグ、ショパンといったクラシック音楽の名曲が、状況内音楽(ストーリー内で実際にその場で流れている音楽)と状況外音楽(BGM)の両方で使い分けられています。
特に注目すべきは、同一楽曲を異なる形で繰り返し使用することで、音楽そのものが物語の構造と深く結びついている点。音楽家同士の恋愛を描いた作品だからこそ実現できた、音楽と映像が一体となった表現技法を解説していきます。
この映画は1936年に公開されたスウェーデンの映画「間奏曲」のハリウッドリメイクです。同じくバーグマンが主演を務め、映画のテーマ的ヴァイオリン曲「間奏曲」も両作品で使用されるなど、物語の流れもかなり近いリメイクとなっています。
・公開年:1939年(アメリカ)/ 1952年(日本)
・監督:グレゴリー・ラトフ
・ピアノ関連度:★★★☆☆
► 内容について(ネタバレあり)
以下では、映画の具体的なシーンや楽曲の使われ方について解説しています。未視聴の方はご注意ください。
‣ 状況内音楽と状況外音楽の関連性
音楽用語解説:
状況内音楽
ストーリー内で実際にその場で流れている音楽。 例:ラジオから流れる音楽、誰かの演奏
状況外音楽
外的につけられた通常のBGMで、登場人物には聴こえていない音楽
本作では、状況外音楽としてクラシック音楽をオーケストラ編曲したものが効果的に使用されています。注目すべき楽曲は:
・ベートーヴェン「ピアノソナタ 第20番 ト長調 Op.49-2 第1楽章」のメロディを引用したBGM
・グリーグ「ピアノ協奏曲 イ短調 Op.16 第1楽章」のメロディを引用したBGM
・ショパン「ワルツ 第10番 ロ短調 Op.69-2」のメロディを引用したBGM
これらは原曲をそのままオーケストラ編曲するのではなく、一部を引用してオリジナルの音楽に改編されたもの。特にベートーヴェンの楽曲は、アレンジを変えながら本編中に5回もBGMとして使用されます。
本作の秀逸な点は、状況内音楽と状況外音楽の関連性にあります:
・上記ベートーヴェンのBGMが流れた後、ホルガーの娘がピアノで原曲を演奏
・グリーグの楽曲を、アニタとホルガーがデュオで演奏
このように、映画のテーマ曲「間奏曲」も含めて、状況内音楽・状況外音楽の両方で同曲を使用することで、音楽が物語の構造そのものと深く結びついています。
‣ 気持ちを繋げる状況内音楽と状況外音楽
気持ちを繋げる状況内音楽
本編15分頃、アニタとホルガーがピアノとヴァイオリンでアンサンブルする場面は、二人の関係性の転換点として機能しています。音楽家同士という設定を活かし、言葉を交わさずとも音楽を通して心を通わせる様子が自然に描かれています。この「音楽による対話」こそが、その後の二人の関係の深まりを予感させる重要なシーンと言えるでしょう。
気持ちを繋げる状況外音楽
本編23分頃の印象的な演出では、アニタとホルガーが親密な距離で会話した後、映像は二人から離れて川や空の風景に移ります。しかし、BGM(状況外音楽)は継続し、より感情的に盛り上がります。この音楽の高揚により、二人がキスを交わしたことを暗示的に表現していると解釈できるでしょう。
直接的な描写を避け、音楽と映像の組み合わせによって観客の想像力に委ねる、洗練された映画的表現といえます。
‣「記憶のBGM」が語る内面の葛藤
本編63分頃に見られる演出にも注目すべきでしょう。かつてアニタとホルガーがアンサンブルを行った自宅のピアノを映し出しながら、約10秒間グリーグ「ピアノ協奏曲 イ短調 Op.16 第1楽章」のピアノパートのみが流れます。
これは「ホルガーの記憶の中で鳴っているBGM」と解釈していいでしょう。かつて自分が演奏したヴァイオリンパートを意図的に除外し、ピアノパートのみを聴かせることで、以下のような複雑な心情を表現しています:
・事故に遭った娘への心配と家族への責任感
・アニタへの愛情という、相反する感情の間での揺れ動き
音楽の使い方一つで、主人公の内面の葛藤を効果的に描写しています。
► 終わりに
「別離」は1939年という早い時期に、音楽映画の可能性を引き出した一作と言えます。音楽と映像が織りなす映画表現を、実際に「一度」あるいは「もう一度」体感してみてください。クラシック音楽の新たな魅力を発見できるはずです。
リメイクの元となった映画「間奏曲(1936年)」と比較しながら鑑賞してみるのもおすすめです。
推奨記事:【ピアノ】映画「間奏曲(1936年)」レビュー:状況内音楽の演出技法とリメイク版比較
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
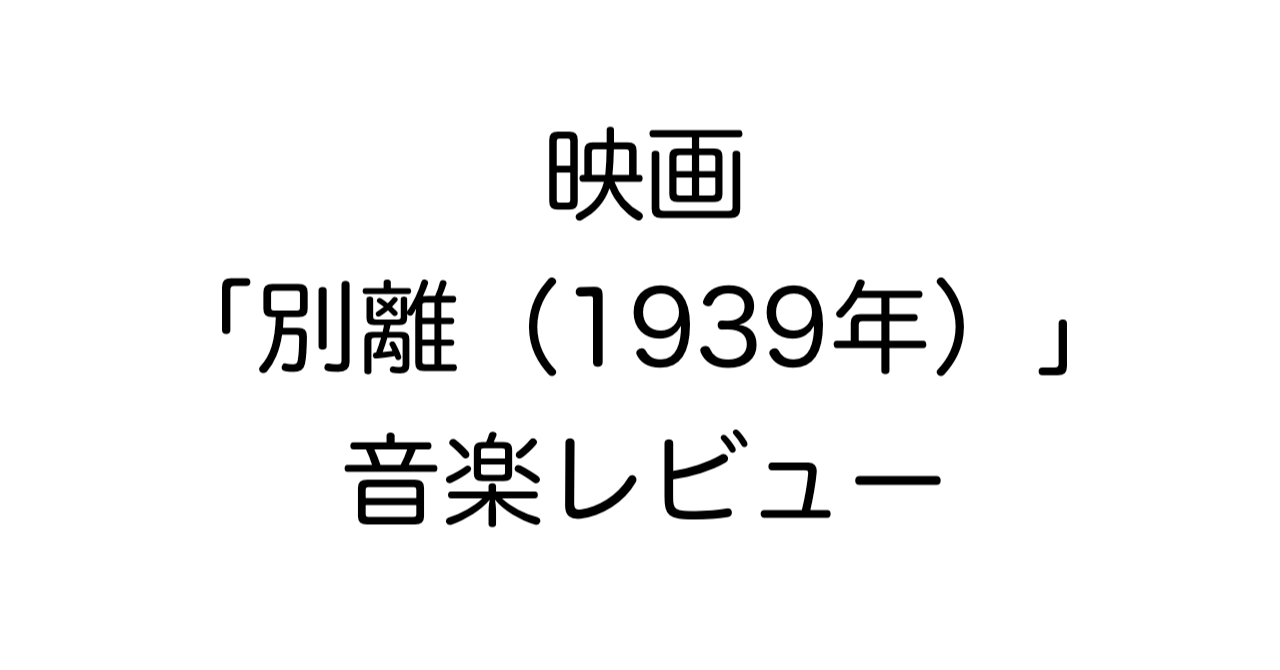

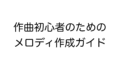
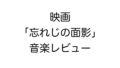
コメント