【ピアノ】映画「間奏曲(1936年)」レビュー:状況内音楽の演出技法とリメイク版比較
► はじめに
「間奏曲(Intermezzo)」は、1936年に制作されたスウェーデン映画で、若き日のイングリッド・バーグマンが前途有望なピアニスト、アニタを演じた作品です。有名なヴァイオリニスト、ホルガー(エスタ・エクマン)との禁断の恋を描いた本作は、音楽家を主人公とすることで、音楽演奏が物語の重要な要素となっています。
この映画は1939年にハリウッドでリメイクされ、映画「別離」として公開されました。同じくバーグマンが主演を務め、映画のテーマ的ヴァイオリン曲「間奏曲」も両作品で使用されるなど、物語の流れもかなり近いリメイクとなっています。
・公開年:1936年(スウェーデン)/ 1989年(日本)
・監督:グスターヴ・モランデル
・ピアノ関連度:★★★☆☆
► 内容について
以下では、映画の具体的なシーンや楽曲の使われ方について解説しています。未視聴の方はご注意ください。
音楽用語解説:
状況内音楽
ストーリー内で実際にその場で流れている音楽。 例:ラジオから流れる音楽、誰かの演奏
状況外音楽
外的につけられた通常のBGMで、登場人物には聴こえていない音楽
‣ 注目すべき音楽演出
· 音源を映していなくても状況内音楽だと予測させる演出
本編5分頃、屋外のシーンでショパンの「バラード 第3番 Op.47」が聴こえてきます。この時点ではまだ映像がアニタを映していないため、誰が演奏しているのか分かりません。しかし、観客は複数の手がかりから、これが状況内音楽であると予測できるのです。
予測を可能にする要素:
既存曲の使用
ショパンという既存の楽曲が使われているため、BGMというよりは実際に流れている音楽なのではないかと予測がつきます。
作品設定の共有
アニタがピアニストである設定が知られている映画なので(現在では)、彼女が弾いているのではないかと推測できます。
演奏の質感
そしてもっとも興味深いのは、その演奏が上手ではあるものの、明らかにミスをしているという点です。これにより、録音物を流しているのではなく生演奏ではないかと予測がつきます。
ミスの頻度
ミスが一箇所だけでなく、何ヶ所かで発生しているため、一層その予測が強くなります。
このように、映像がアニタを映すことに頼らずとも、音楽的な手がかりだけで状況内音楽だと予測できる点が、この場面の面白い音楽演出と言えるでしょう。完璧過ぎない演奏が、かえってリアリティを生み出し、「今、この場で誰かが弾いている」という臨場感を創出しているのです。
· J.S.バッハ作品のヴァイオリン演奏による伏線の回収
本編10分頃になると、J.S.バッハ「無伴奏ヴァイオリンソナタ 第1番 ト短調 BWV 1001 より Adagio」が聴こえてきます。この楽曲を演奏するホルガーは映し出されていませんが、直前にホルガーが別の楽曲の演奏をしている場面が映し出されています。先ほどのショパンのシーンで確立された手法とやり方は異なりますが、観客は映像に頼らず、この作品もホルガーの演奏する状況内音楽ではないかと予測できるようになっています。
· 状況内音楽から別の状況内音楽へのシームレスな移行
本編15分頃、別の興味深い音楽演出が展開されます。レコードで映画のテーマ曲「間奏曲」が流れており、ホルガーの娘がアニタ(この場面ではピアノレッスンの先生をしている)に向かって「パパの演奏よ」と言います。
そして間もなくその演奏が終わり、つまりレコードの音という状況内音楽が終わると、ホルガーの娘がピアノを弾くピアノレッスンへシームレスに移行していきます。これは、状況内音楽から別の状況内音楽へのシームレスな移行という、洗練された技法です。
現実世界で考えれば、「なぜ、丁度いいタイミングで楽曲が終わるのか」「なぜ、レコードから次の曲が流れ始めないのか」などと思ってしまいます。しかし、これを綺麗に整理して聴かせているのが映画の世界ならではの音楽演出と言えるでしょう。
この音楽演出の効果:
・レコード(録音された音楽)から生演奏へという、音楽の「時間性」の対比
・父の演奏を娘が学ぶという、世代を超えた音楽の継承というテーマの暗示
・大きな切れ目のない音楽の流れが、登場人物たちの生活に音楽が自然に溶け込んでいることを表現
‣ リメイク版「別離(1939年)」との音楽面での比較
映画「別離(1939年)」は本作のハリウッドリメイクですが、音楽演出のアプローチには大きな違いがあります。
「間奏曲(1936年)」の音楽的特徴
クラシック音楽は主に状況内音楽として、ピアノ演奏などで使われる程度に留まっています。状況外音楽としてのクラシック音楽の引用は控えられています。
「別離(1939年)」の音楽的特徴
状況外音楽としてクラシック音楽のメロディを引用したアレンジ曲が多用され、より華やかで感情的な音楽演出が特徴です。
注目すべき楽曲:
・ベートーヴェン「ピアノソナタ 第20番 ト長調 Op.49-2 第1楽章」のメロディを引用したBGM
・グリーグ「ピアノ協奏曲 イ短調 Op.16 第1楽章」のメロディを引用したBGM
・ショパン「ワルツ 第10番 ロ短調 Op.69-2」のメロディを引用したBGM
これらは原曲をそのままオーケストラ編曲するのではなく、一部を引用してオリジナルの音楽に改編されています。特にベートーヴェンの楽曲は、アレンジを変えながら本編中に5回もBGMとして用いられています。
なぜ、このような違いが生まれたのか
1936年のスウェーデン版は、より簡素なアプローチを取り、音楽家たちの日常に根ざした音楽の使い方をしています。一方、1939年のハリウッド版は、より感情的で壮大な音楽演出を採用しています。ヴァイオリンやピアノ演奏として状況内音楽で用いられた作品を、通常のBGMとして状況外音楽でも使用する箇所を増やすことで、それらの垣根を少なくしています。
この違いは、スウェーデン映画とハリウッド映画の文化的・美学的な違いを反映していると言えるでしょう。
► 終わりに
「間奏曲(1936年)」の魅力は、状況内音楽を中心とした音楽演出により、観客が物語世界に自然に没入できる点にあります。音楽家を主人公とした作品だからこそ可能な、音楽と物語の有機的な結びつきが実現されています。
リメイク版「別離(1939年)」との比較により、同じ物語でも音楽演出のアプローチによって作品の印象が大きく変わることが分かります。両作品を鑑賞することで、音楽の可能性と多様性を実感できるでしょう。
推奨記事:【ピアノ】映画「別離(1939年)」レビュー:ピアノ音楽の効果的演出
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
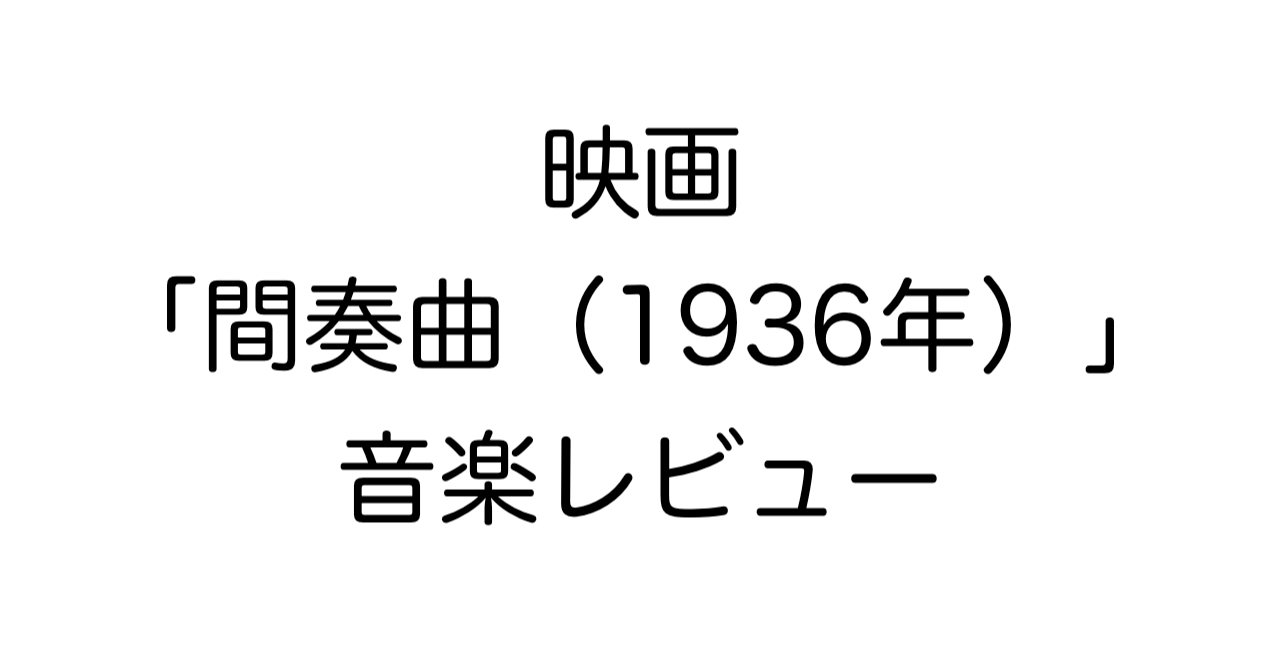
![間奏曲 [レンタル落ち] [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51xUIvtFokL._SL160_.jpg)
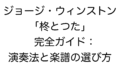
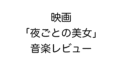
コメント