【ピアノ】何十年も前の音楽映画を決して挫折せずに観続ける3つのコツ
► はじめに
ピアノや音楽をテーマにした作品はあらゆる時代に存在しますが、1930年代〜60年代の作品となると、途中で観るのをやめてしまう方が多いのも事実です。
そこで本記事では、「古典音楽映画を挫折せずに観る方法」をまとめておきます。
► 何十年も前の音楽映画が観づらい3つの理由
必ずしも音楽映画に限った話ではありませんが、一般的に以下の3つの理由が挫折を招いています:
1. 技術的な制約
・白黒作品が多い
・経年劣化により音声が聞き取りにくい
・画質が現代の水準より劣る
2. テンポの違い
映像作品のリズムは、その時代の人々の生活リズムを反映しています。そのため、現代の映画に比べてゆっくりとしたテンポで進行し、眠気を誘うことがあります。
3. 前提知識の必要性
現代に作られている作品と比べ、時代背景や音楽の知識がないと理解しにくい作品も少なくありません。
► 挫折を防ぐ3つの実践的テクニック
上記の問題を解決し、内容をしっかり理解できれば、古典音楽映画も十分に楽しめます。以下の3つの方法を試してみてください。
‣ 1. ネタバレを気にせず、事前にあらすじを読んでおく
なぜ、効果的なのか
物語の流れを頭に入れておくことで、本編を観たときに内容がスムーズに理解できます。
実践方法:
・ひと時代前の映画であれば、無料であらすじが公開されていることが多い
・キャスト欄で「俳優名」と「役名」を確認し、リンクさせておく
・たくさんの映画を観て俳優の顔と名前を覚えると、この作業が楽になる
鑑賞中に迷ったら
内容が分からなくなったら、すぐに一時停止してあらすじを読み返しましょう。「訳が分からないまま最後まで進んでしまった」という失敗を防げます。
‣ 2. 音声が聞き取りにくい作品では、邦画でも日本語字幕をオンにする
意外と知られていませんが、邦画でも日本語字幕を表示できる作品があります。ディスクやサービスによって対応状況は異なりますが、字幕メニューを一度確認してみる価値は十分にあります。
おすすめする理由:
・特に白黒時代の映画は、音声が不明瞭なことが多い
・セリフが文字で確認できると理解度が格段に上がる
・重要な台詞を聞き逃さない
‣ 3. Wikipediaを画面に出しっぱなしにする
準備:
・PCやタブレットで作品のWikipediaページを開きっぱなしにする
・またはあらすじサイトでキャスト一覧が見られるページを開きっぱなしにする
活用方法:
・登場人物の関係が分からなくなったら即座に確認
・複雑な人名や人物関係の多い作品で特に有効
・スマホより大きな画面の方が見やすい
► 終わりに:1度で理解することを前提にして観る
これらのテクニックに共通するのは、「1度の鑑賞で内容を理解する」ことを前提に準備するという考え方です。
もちろん、何度も観返すことで新たな発見がある作品もあります。しかし、古典映画の場合、上記のような挫折しやすい原因を持っているので、初回で内容が入ってこないと時間だけが過ぎ、結局見続けられません。
細かな工夫を色々試しながら、自分に最も合った鑑賞方法を見つけてみましょう。
ピアノ関連映画については、「年代順:ピアノ関連映画ライブラリー」でまとめていますので、あわせて参考にしてください。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
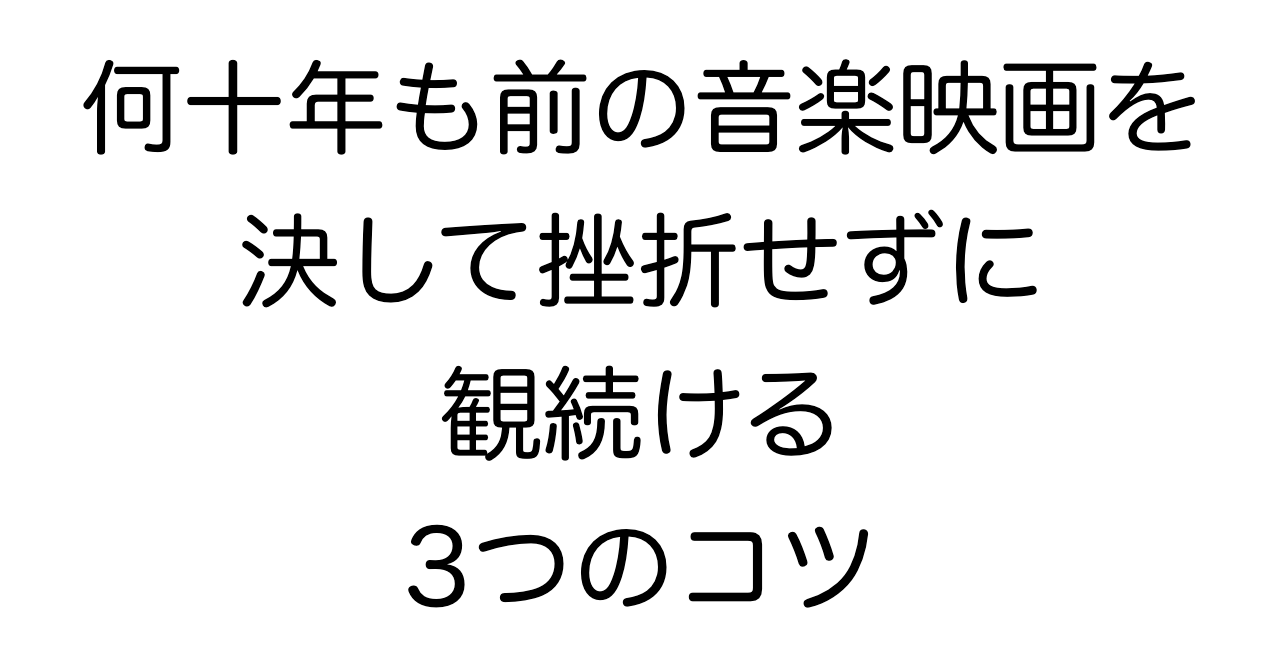
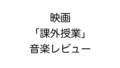

コメント