【ピアノ】映画「教室の子供たち」レビュー:ピアノソロのみで構成された劇音楽
► はじめに
羽仁進監督の記録映画「教室の子供たち」(1955年)は、劇音楽をすべてピアノソロで構成した珍しい作品です。現在でも時折テレビ番組で取り上げられるこの短編記録映画から、ピアノ音楽の可能性について考えてみましょう。
・公開年:1955年(日本)
・監督:羽仁進
・ピアノ関連度:★★★★☆
► 映画音楽におけるピアノの一般的な使われ方
まず、映画音楽でピアノがどのように使われるかを整理してみましょう。
主な使用パターン:
1. ピアノソロ楽曲
2. ピアノと他のアコースティック楽器とのアンサンブル
3. メイン楽器のアクセントとしてのスパイス効果
‣ ピアノソロだけの劇音楽が抱える課題
劇音楽を純粋なピアノソロ「だけ」で構成することは、実は意外と難しい側面があります:
音色変化の限界
ほとんど音色の変化をつけることができないからです。もちろん「演奏法」によって音色に変化をつけることは可能ですが、それはあくまでも「ピアノが出せる音色の中での変化」に留まります。
単調性の問題
また、楽曲が変わっても楽器が同じため、聴き手が「同じ曲」と錯覚する可能性があります。音楽経験の浅い知人は、「劇作品の中で、楽曲が変わっても楽器が変わらないと同じ曲だと思ってしまうことがある」と話していました。
‣ 成立させるための一般的な方法
即興的要素を強く打ち出す
パターンを予測しにくくすることで「またか」という感覚を軽減する
環境音による聴覚的補佐
周囲の音で変化をつける
電子加工によるバリエーション
音響技術で音色に変化を与える
ピアノソロばかりの劇音楽でも成立するのは、例えば、ソロ楽器という編成を活かして「即興的要素を強く打ち出した音楽にした場合」が挙げられます。即興性が強い場合、観客はパターンを予測しにくいため、「ああ、またか」という認識を和らげることが期待できます。
また、「環境音による聴覚的な補佐(雨の音や鳥の声などの状況内音声が、聴覚的に退屈感を減らしてくれること)」が多くある場合や、「音自体に電子加工でバリエーションを与える」といった場合にも、この編成に偏った劇音楽が成立することはあるでしょう。
その他の例として挙げられるのが、本記事で扱う「教室の子供たち」の内容です。
► 内容について(ネタバレあり)
以下では、映画の具体的なシーンや楽曲の使われ方について解説しています。未視聴の方はご注意ください。
‣ なぜ、「教室の子供たち」ではピアノソロオンリーが成立するのか
全ての音楽がピアノソロのみで構成されている本作。興味深いことに、本作品は上記の一般的な解決方法を用いていません。では、どのようにしてピアノソロのみの構成を成立させているのでしょうか。
映画本編の短さという側面
「約30分」という短編であることが一つの要因です。全体の曲数自体は長編映画に比べると少なく、音色自体にも飽きずに観ることができます。
舞台設定とのマッチング
「小学2年生を取材した小学校舞台の記録映画」という設定が秀逸です。小学校といえば「ピアノの音」は最も身近で代表的な音の一つ。この設定により、映像と音楽の関連性が自然に生まれ、違和感のない音楽体験を実現しています。
‣ 段々と分かりやすくなっていく音楽構成と本編との関連
近現代風の不協和音も交えたスケルツォ的音楽から始まります。以降、様々な場面で音楽が流れますが、段々と分かりやすい音楽になっていくのが特徴です。
これには明確な意図があると考えられます。本編最後では、学芸会で器楽合奏や合唱をする場面(状況内音楽:ストーリー内で実際にその場で流れている音楽)があり、そこへ有機的に接続する意図。状況外音楽としてのBGMのメロディを引き継ぐ形で、学芸会の音楽へと接続します。そして、学芸会の最後のお辞儀で「Ⅰ-Ⅴ-Ⅰ」という最も分かりやすいピアノ音が鳴って終わります。
► 終わりに
「教室の子供たち」は、ピアノソロだけで構成された劇音楽の例として、注目すべき作品です。
一時期は視聴が難しかった本作でしたが、現在は以下のDVDでも鑑賞することができるようになりました。音楽にも着目しながら「一度」、もしくは「もう一度」視聴してみてください。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
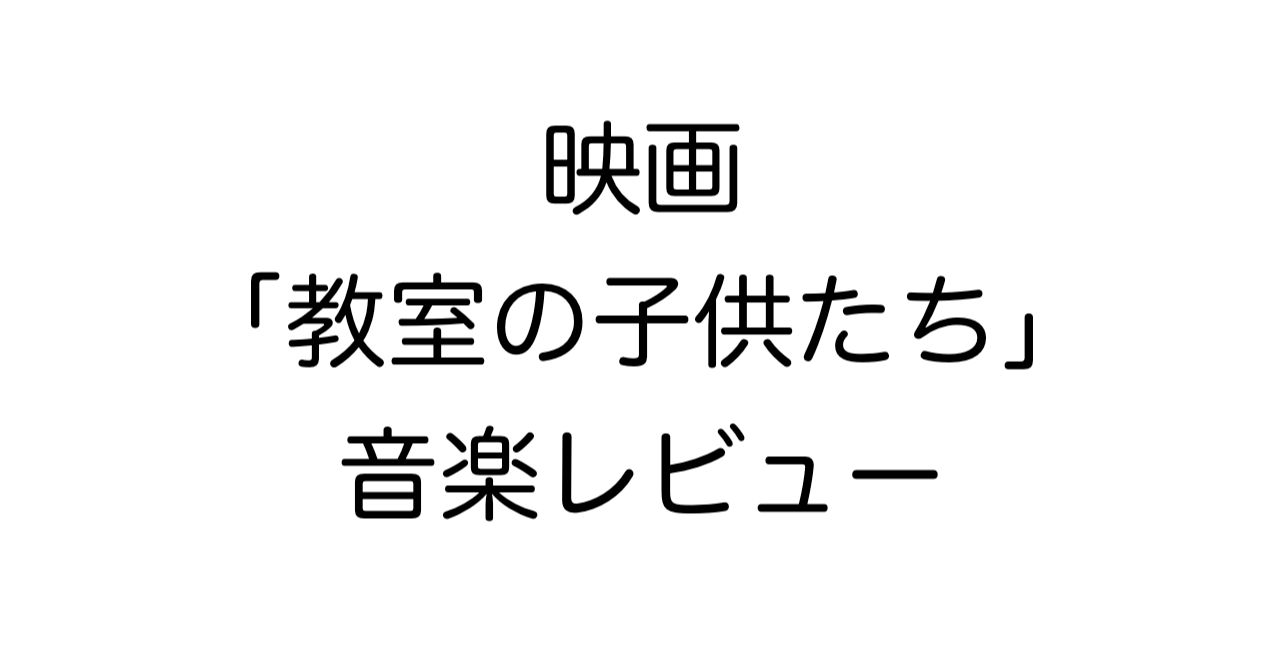

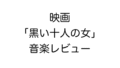
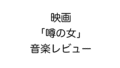
コメント