【ピアノ】映画「クララ・シューマン 愛の協奏曲」レビュー:楽曲選択で描く複雑な人生と音楽の交錯
► はじめに
映画「クララ・シューマン 愛の協奏曲(Geliebte Clara)」は、19世紀ロマン派音楽界の巨匠たち―クララ・シューマン、ロベルト・シューマン、ブラームスの複雑な愛と音楽の交錯を描いた作品です。
本記事では、ピアノ的視点から、この映画の魅力と特に注目すべき楽曲の使われ方について詳しく解説します。
・公開年:2008年(ドイツ)/ 2009年(日本)
・監督:ヘルマ・サンダース=ブラームス
・ピアノ関連度:★★★★★
► 内容について(ネタバレあり)
以下では、映画の具体的なシーンや楽曲の使われ方について解説しています。未視聴の方はご注意ください。
用語解説:状況内音楽とは:
・ストーリーの中で実際に聴こえている音楽
・登場人物がピアノを弾いているシーンのBGMなど
一方、外的に付けられた通常のBGMは「状況外音楽」となります。
‣ クララの作曲家時代の対比演出
1853年設定:ブラームス20歳、クララ34歳
シーン1:現在のクララ(本編33分頃)
演奏楽曲:ロベルト・シューマン「5つの音楽帳 第1曲 Op.99-4」(1836年作曲)
演奏者:ブラームス
演出効果:クララとロベルト両方に関連する楽曲を選ぶことで、3人の複雑な関係性を音楽で表現
本編33分頃、クララとロベルトの前でブラームスがピアノを弾く場面があります。「ロベルト・シューマンの曲を僕のやり方で弾く」と言って弾き出したのが、ロベルトの「5つの音楽帳 第1曲 Op.99-4」でした。この作品はクララにとって思い入れのある作品であり、この原曲からクララは「ローベルト・シューマンの主題による変奏曲 嬰ヘ短調 Op.20」を作り、同年(1953年)に夫へ贈っています。
クララは34歳くらいの設定ですが、当時のクララはロベルトの作品を紹介するピアニストとしての活動や子育てに忙しく、作曲活動が少なくなっていました。本編10分頃にも、ロベルトに「作曲は辞めたんだろ?」と言われる場面があり、「クララが今現在 “ほとんど” 作曲をしていない」ことが映画にとって重要な視点となっています。
同じ旋律が用いられている作品に、以下の3曲があります:
・ロベルト・シューマン「5つの音楽帳 第1曲 Op.99-4」(原曲)
・クララ・シューマン「ローベルト・シューマンの主題による変奏曲 嬰ヘ短調 Op.20」
・ブラームス「シューマンの主題による変奏曲 嬰ヘ短調 Op.9」
この場面は1853年設定なので、1854年に作曲されたブラームスのものではないと分かります。エンドロール表記によるとロベルトの原曲が使われたことになっています。
対照的なのが以下の場面です。
シーン2:過去のクララ(本編86分頃)
演奏楽曲:クララ・シューマン「ロマンスと変奏 Op.3」(1831年作曲)
演奏者:ブラームス
クララの反応:「昔の曲、作曲は大昔に辞めたわ」
本編86分頃に、ブラームスがクララと子供達の前でピアノを弾く場面があります。弾いたのは、クララ・シューマン「ロマンスと変奏 Op.3」でした。
それを聴いたクララは、「昔の曲、作曲は大昔に辞めたわ」と言います。子供達が映し出されていることからも、今のクララの多忙な状況がより一層強調されています。
この2つのシーンの対比により、作曲家クララの変遷が見事に表現されています。活発に作曲していた若い頃と、ピアニスト・母親として生きる現在の対比が、楽曲の選択によって強調されているのです。
‣ ピアノ協奏曲による物語の枠組み
クララとブラームスの仲には音楽史上は様々な見解があります。本映画では、「一度一線は越えたものの、良き友人として、二人の絆はクララが亡くなるまで続いた」というまとめ方がされています。
これを前提に、以下の内容が印象的です:
オープニング:
・ロベルト・シューマン「ピアノ協奏曲 イ短調 Op.54 第1楽章」をクララが弾いている
・ロベルトもブラームスも居合わせている
エンディング:
・ブラームス「ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 Op.15 第1楽章」をクララが弾いている
・ロベルトはすでに亡くなっており、ブラームスが居合わせている
エンディングシーンでは、クララの演奏を目に涙を浮かべて聴いているブラームスの表情が長時間映し出されます。このとき、音楽以外の「状況内音声」は完全にミュートされ、音楽とブラームスの感情だけが浮き彫りにされる秀逸な演出となっています。
ロベルトのピアノ協奏曲から始まり、ブラームスのピアノ協奏曲で終わる楽曲配置からも、時間経過とクララを取り巻く環境の変遷が表現されています。
‣ その他の印象的な音楽演出
ロベルトの内面音楽(本編11分頃)
ロベルトのセリフ:「頭痛さえなければすぐにピアノを弾くのに…頭には音楽があふれているんだ」
演出:このときに短時間音楽が流れる
効果:状況内でも状況外でもある、ロベルトの頭と心の中で鳴っている想像上の音楽を映像化
これは「心の中で音楽を聴く」という、音楽家特有の体験を見事に映像化した演出です。
シューマン家の日常に溶け込む音楽(本編12分頃)
シーン:子供達が「付点リズムの繰り返し」を歌いながら階段を上る
音楽的背景:ロベルト・シューマンの楽曲の特徴である「付点リズムの執拗な反復」
演出効果:家庭内にロベルトの音楽が自然に浸透していることを表現
3人の作曲家による音楽の交錯
作曲家でありピアニストでもある3人だからこそ実現する、複層的な音楽演出:
クララ:ブラームス、ロベルト、自身の作品を演奏
ロベルト:クララのOp.20をブラームスとの連弾で演奏
ブラームス:クララの作品や自身の作品を演奏
この相互的な音楽の交錯により、単純な三角関係を超えた、音楽を通じた深い絆が表現されています。
‣ 留意点
詳細は映画本編で確認して欲しいのですが、本映画の内容は、有力とされているクララの音楽史の内容と異なる点もあります。あくまで映画として楽しむことを重視しましょう。
► 終わりに
「クララ・シューマン 愛の協奏曲」は、音楽が物語そのものを語る言語として機能している作品です。楽曲の選択、演奏シーンの配置、音響演出のすべてに工夫が見られ、音楽史の知識があるほどその巧妙さに感動できる構成になっています。
特に、クララ・シューマンという女性音楽家の複雑な人生を彼女が関係する作品を通じて描き出す手法は、独特の魅力を持っています。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
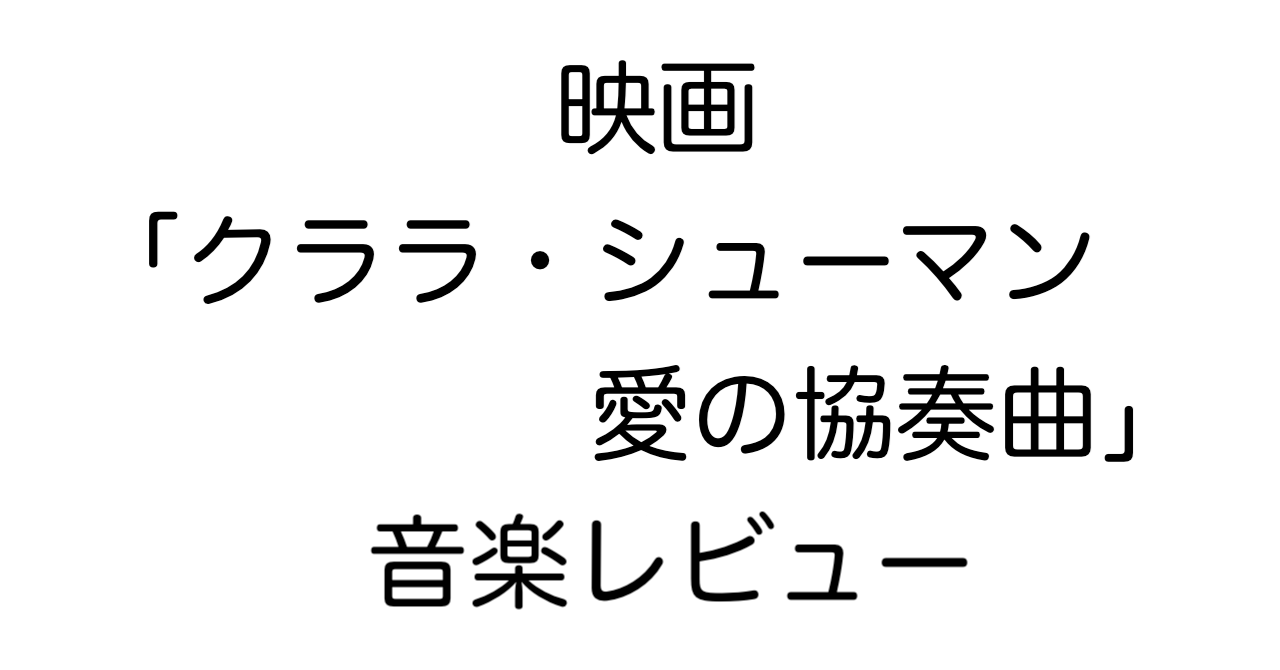
![クララ・シューマン 愛の協奏曲 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51zHdbIsEiL._SL160_.jpg)
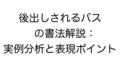
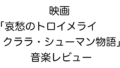
コメント