【ピアノ】映画「別れの曲(ドイツ語版)」レビュー:ショパン音楽の使われ方を解説
► はじめに
映画「別れの曲(Abschiedswalzer)」は、フレデリック・ショパンの1831年から1838年のマジョルカ島行き直前までの約7年間を描いた音楽伝記映画です。ロシアの圧政下にあったポーランドでの独立運動に思いを馳せながら、音楽家としての才能を開花させていくショパンの姿と、歌手志望の少女コンスタンティアとの悲恋が描かれています。
本作はフランス語版とドイツ語版が存在し、同じシナリオが後に「楽聖ショパン(1945年)」としてリメイクされました。本記事ではドイツ語版を基に、ピアノ的視点も織り交ぜながら音楽の使われ方に焦点を当てて解説します。
・公開年:1934年(ドイツ)/ 2010年(日本)
・監督:ゲツァ・フォン・ボルヴァリー
・ピアノ関連度:★★★★★
► 内容について(ネタバレあり)
以下では、映画の具体的なシーンや楽曲の使われ方について解説しています。未視聴の方はご注意ください。
用語解説:状況内音楽とは:
・ストーリーの中で実際に聴こえている音楽
・登場人物がピアノを弾いているシーンのBGMなど
一方、外的に付けられた通常のBGMは「状況外音楽」となります。
‣「別れの曲」が語る愛と別離
「エチュード Op.10-3」の多彩な表現
映画のタイトルにもなっている「別れの曲」は、作品中で複数の形態で登場します。すべて状況内音楽として用いられている点が特徴的です。
「別れの曲」の登場シーン:
・本編8分頃:ショパンがコンスタンティアにピアノを弾きながら愛を語る
・本編22分頃:コンスタンティアが愛の歌詞を付けて歌唱
・本編中盤:恩師エルスナーが、ショパンにコンスタンティアを思い出させるために、右手パートのみで演奏
・ラストシーン:コンスタンティアとの別れで、ショパンが語りなしで演奏
心の移り変わりを表す演出
この曲の使われ方には、巧妙な演出意図が隠されています。
・前半(ジョルジュ・サンドと出会う前):すべて語りか歌詞付き
・後半(サンドと出会った後):語りも歌詞もなし
この変化は、ショパンの心がコンスタンティアからサンドへと移っていく過程を音楽的に表現しています。同じ旋律でありながら、言葉の有無によって感情の質が変化していく様子は、観る者の心に深く響きます。
‣ 戦争を連想させるファンファーレの活用
本作では、随所にファンファーレが効果的に使用されています。
主なファンファーレの使用箇所
・本編16分頃:屋外シーンへの場面転換
・本編27分頃:街中での合図・信号音
・本編29分頃:「華麗なる大円舞曲」(オーケストラ版)冒頭
・本編42分頃:「木枯らしのエチュード」(オーケストラ版)のアレンジ
巧妙な聴覚トリック
特に注目すべきは本編27分から29分にかけての演出です。街中の信号ファンファーレに続いて金管楽器の音が鳴り響くため、観客は「また同じファンファーレか」と思いますが、実はそれが「華麗なる大円舞曲」冒頭の同音連打だったと後から気づかされる仕掛けになっています。
ワルシャワでの戦争が物語の重要なテーマとなっているため、軍隊を連想させるファンファーレが多用されているのでしょう。「木枯らしのエチュード」の編曲では軍楽隊の象徴である小太鼓まで聴こえてきます。
‣ オーケストラアレンジの妙技:繰り返しに込められた工夫
本作ではショパンのピアノ曲がオーケストラ編曲され、同じ楽曲が何度も登場します。しかし、ただの使い回しではなく、シーンに応じた細やかな配慮が施されています。
「ワルツ 第3番」の場合
本編26分頃:ショパンとコンスタンティアの別れのシーン
前に使われていた同曲のアレンジよりもテンポを落とし、最も切ない部分だけを抽出した編曲で、別離の悲しみを音楽が深く表現しています。
「華麗なる大円舞曲」の場合
ショパンがジョルジュ・サンドの著作を求めて街へ繰り出すシーン
前に使われていた同曲の使用部分とは異なり、曲の中で最もロマンティックな部分(主要テーマへ回帰する直前)が使用され、サンドへの興味と高揚感が音楽で表現されています。
‣ 革命のエチュードと「錯覚の演出」:リストとショパンの逆転劇
オルレアン侯爵夫人邸での演奏会シーン
薄暗いサロンで「革命のエチュード」が流れ始めます。観客は当然、招かれた名ピアニスト、リストの演奏だと思い込みます。しかし、ジョルジュ・サンドが掲げた灯りに照らし出されたのは、ピアノに向かうショパンと、その傍らで聴き入るリストの姿でした。
これは「状況内音楽でありながら演奏者を錯覚させる」という、珍しい演出手法です。観客の予想を裏切ることで、ショパンの才能の輝きをより強調する効果を生んでいます。
► 映画史における本作の意義
DVD特典「作品解説」より
本来ショパンがつけていない「別れの曲」という楽曲タイトルが日本で広く親しまれるようになったのは、実はこの映画のフランス語版がきっかけです。戦前の日本公開時にメインテーマとして使用されたことで、「エチュード Op.10-3」は「別れの曲」という愛称で定着しました。
また、本作のシナリオは後に「楽聖ショパン」(1945年)としてリメイクされ、ショパン映画の古典として映画史に名を刻んでいます。
► 終わりに
音楽面での本作の魅力:
・ショパンによる同じ楽曲が異なる形で登場し、心の変化を表現
・オーケストラアレンジの繊細な使い分け
・ファンファーレによる時代背景の表現
・音楽を通じた視覚的トリックの実現
ピアノが好きな方、ショパンの音楽が好きな方にとって、本作は必見の一作です。楽曲の使われ方を意識しながら鑑賞することで、音楽と映像が織りなす豊かな世界をより深く味わうことができるでしょう。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
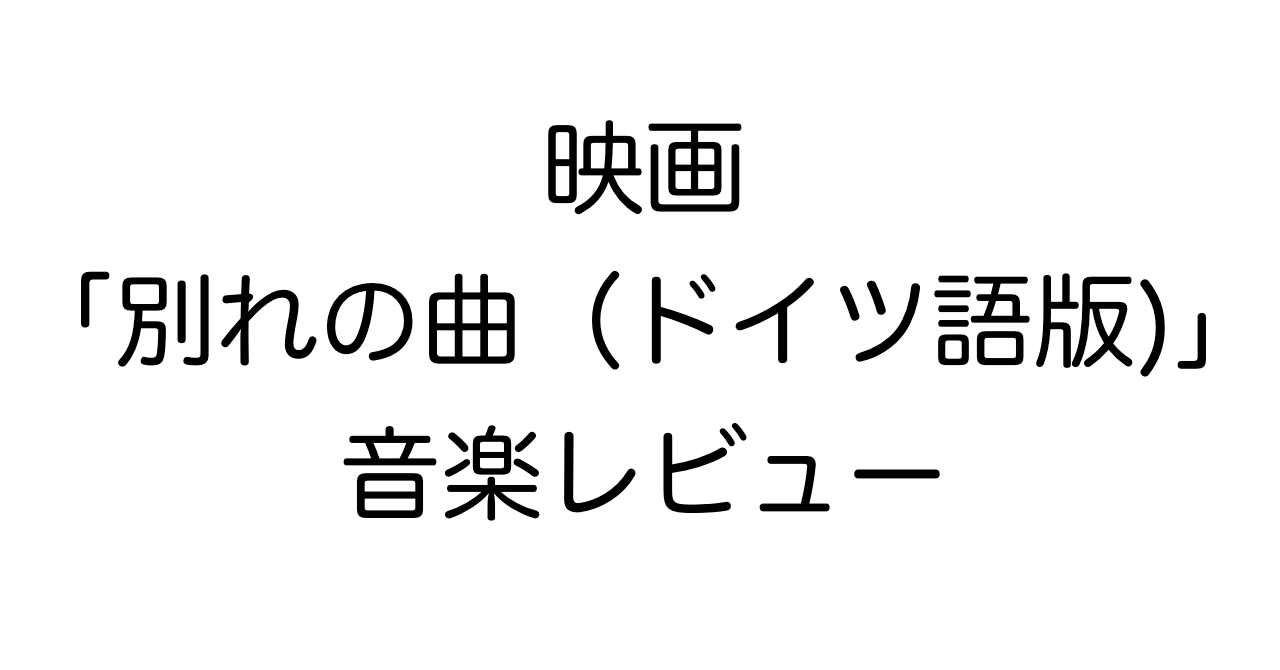
![別れの曲 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51B1jNyp1gL._SL160_.jpg)
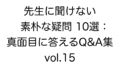
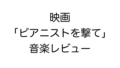
コメント