【ピアノ】映画「楽聖ベートーヴェン」レビュー:ピアノ的視点から見た魅力と楽曲の使われ方
► はじめに
映画「楽聖ベートーヴェン(Beethoven’s Great Love)」は、ベートーヴェンの生涯を描いた112分の伝記映画であり、彼の人間的な苦悩と音楽の関係性が、フィクションを交えながらも情感豊かに描かれています。
本記事では、ピアノ的視点から、この映画の魅力と特に注目すべき楽曲の使われ方について詳しく解説します。
・公開年:1936年(フランス)
・監督:アベル・ガンス
・ピアノ関連度:★★★☆☆
► 内容について(ネタバレあり)
以下では、映画の具体的なシーンや楽曲の使われ方について解説しています。未視聴の方はご注意ください。
‣ 映画で使用されるベートーヴェンのピアノ曲一覧
映画で使用されているベートーヴェンの楽曲のうちピアノ曲を、初出の登場順で一覧にしておきましょう(楽曲タイトルは簡略化しています):
・悲愴ソナタ 第2楽章 (オーケストラ版)
・テレーゼソナタ 第1楽章
・月光ソナタ 第1楽章
・20番のト長調ソナタ 第2楽章
・熱情ソナタ 第1楽章、第2楽章 (途中でオーケストラ版に移行)
・告別ソナタ 第2楽章 (オーケストラ版)
・エリーゼのために
・月光ソナタ 第1楽章 に歌詞をつけた歌曲版
運命交響曲やラストで流れる第九交響曲など、重要なオーケストラ作品も使われています。一方、後述するように、ピアノ曲の中でストーリーにとって一番重要な位置付けになっているのは、月光ソナタ 第1楽章です。
また、熱情ソナタの第2楽章から、スムーズにそのオーケストラ版へ移行する場面はグッとくるものがありました。
‣「状況内音楽」としての巧妙な演出
この映画における音楽演出の大きな特徴は、ピアノ曲を「状況内音楽」として効果的に使用している点です。
状況内音楽とは:
・ストーリーの中で実際に聴こえている音楽
・登場人物がピアノを弾いているシーンのBGMなど
月光ソナタ 第1楽章 の名シーン:
特に印象的なのは、ベートーヴェンがジュリエッタに伯爵への想いを告げられるシーンです。演奏中の月光ソナタのテンポが、ベートーヴェンの心情変化に合わせて変化していく演出は見事と言っていいでしょう:
動揺:テンポが次第に速くなる
落ち着き:再びテンポが安定
落胆:最終和音の余韻を突然断ち切る
ジュリエッタが、伯爵に気持ちがあることをベートーヴェンに伝えた時に、だんだん動揺していくベートーヴェンの気持ちを示すかのように演奏テンポが速くなっていきます。後半ベートーヴェンの気持ちが少し落ち着いてきたのがセリフから分かるのですが、そのあたりでは演奏テンポもまた落ち着いてきます。そして、ジュリエッタが部屋から去るや否や、落胆して鳴らしていた最終和音の余韻をブツっと切ってしまいます。
心情変化に合わせたこういった細かな音楽表現は、通常のBGM(状況外音楽)でも表現できなくはありませんが、ベートーヴェン自身が演奏しているという設定の状況内音楽だからこそ、よりリアリティを持った表現となっています。
‣「月光ソナタ 第1楽章」がピアノ曲の中心的存在
上記のように、運命交響曲やラストで流れる第九交響曲など、重要なオーケストラ作品も登場します。一方、映画全体を通じて、ピアノ曲の中では「月光ソナタ 第1楽章」が最も重要な位置を占めています。数ある使用シーンのうち、主要な3つは:
・ジュリエッタとの悲しい別れ:ジュリエッタに伯爵への気持ちを告げられた時の繊細な心情変化表現
・ジュリエッタの想いと悲劇:ジュリエッタがベートーヴェンへの想いを持って弾き、伯爵から暴力を振るわれる
・ベートーヴェンの最期:ラスト近く、歌詞をつけられて歌曲へ編曲されてベートーヴェンの最期を演出する
このように、一つの楽曲が様々な場面で使われることで、音楽の持つ多面性を感じることができます。
‣ 音楽史的視点から見た留意点
詳細は映画本編で確認して欲しいのですが、本映画の内容は、有力とされているベートーヴェンの音楽史の内容と異なる点もあります。あくまで映画として楽しむことを重視しましょう。
► 終わりに
「楽聖ベートーヴェン」は、ただの伝記映画以上の価値があります。上記のような音楽表現の工夫が他のシーンでも多く見られるので、そういった内容も探して楽しみながら鑑賞してみてください。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
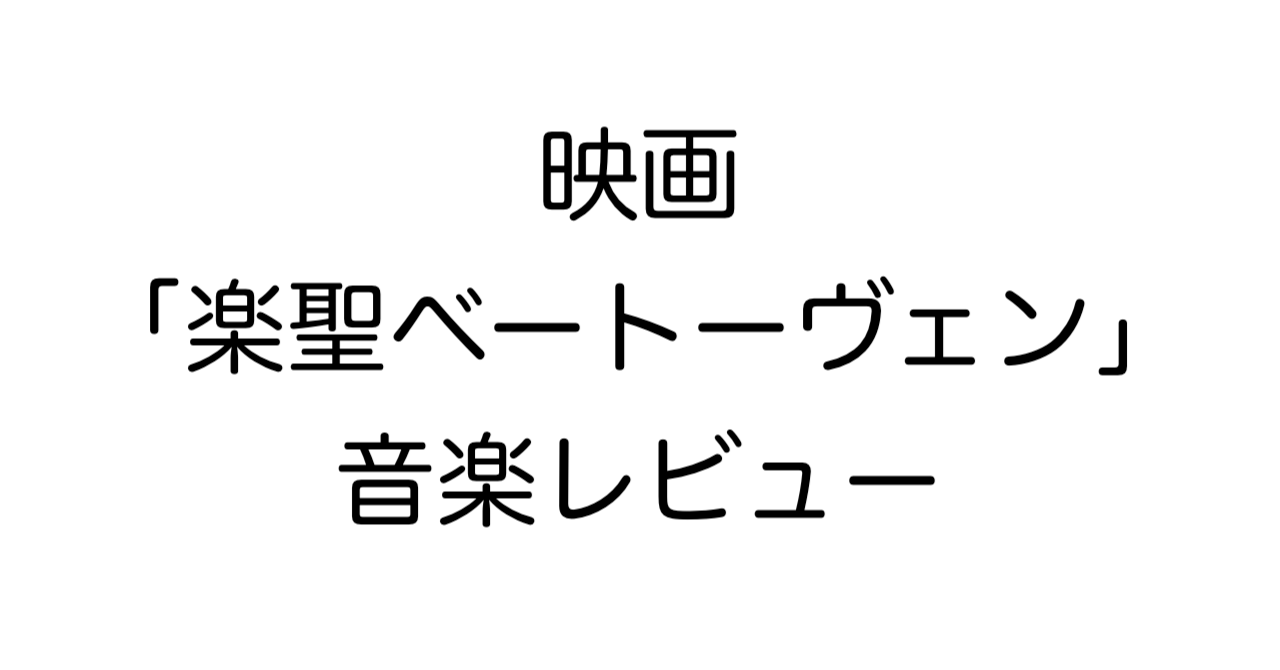

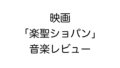
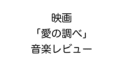
コメント