【ピアノ】映画「ピアニストを撃て」レビュー:状況内音楽と対位法
► はじめに
フランソワ・トリュフォーの「ピアニストを撃て(Tirez sur le pianiste)」は、ヌーヴェルヴァーグを代表する作品であると同時に、音楽映画としても卓越した作品です。本作の音楽演出は、状況内音楽と状況外音楽の使い分け、そして映像と音楽の対位法関係などが特徴的です。
・公開年:1960年(フランス)/ 1963年(日本)
・監督:フランソワ・トリュフォー
・ピアノ関連度:★★★★☆
► 内容について(ネタバレあり)
以下では、映画の具体的なシーンや楽曲の使われ方について解説しています。未視聴の方はご注意ください。
用語解説:状況内音楽とは:
・ストーリーの中で実際に聴こえている音楽
・登場人物がピアノを弾いているシーンのBGMなど
一方、外的に付けられた通常のBGMは「状況外音楽」となります。
‣ オープニングに込められた詩学
アップライトピアノの内部、ハンマーが音楽に呼応して動く様子が映し出された印象的な映像で幕を開けます。映画の内容からすればエドゥアル(シャルリ)が弾いていることは間違いありません。しかし、映像では固定でピアノの内部しか示されていないので、ここでの音楽は、状況内音楽を思わせながら実は状況外音楽という面白みのある仕掛けとなっています。
この視覚的モチーフは本編44分頃に再び登場し、掃除夫として雇われたエドゥアル(シャルリ)が古ピアノを弾く場面と呼応します。異なる楽曲でありながら、同じ映像言語を用いることで、映画全体に一貫したテーマを与えています。ここではエドゥアル(シャルリ)が実際に弾いているのが映像として分かるので「状況内音楽」であることを区別しましょう。
‣ 緊張感の表現①:オスティナートの効果的な使用
本作の音楽で特筆すべきは、オスティナート(執拗に繰り返される音型)の効果的な使用です。
本編21分頃、エルネストとモモが偵察に来る場面では、反復する音型が持続的な緊張感を生み出します。さらに本編42分頃、テレザがエドゥアル(シャルリ)に過去の過ちを告白する緊張感のある場面でも、別の楽曲ながら同じくオスティナートが支配しています。やがてティンパニの音が加わり緊張感は頂点に達し、テレザの投身自殺という悲劇的結末へと導いていきます。
‣ 緊張感の表現②:映像と音楽の対位法
他に本作の音楽演出で注目すべきなのは、映像と音楽の対位法の使用です。
本編50分頃、レナとプリーヌが激しく言い争う場面に、あえて明るいピアノ曲(店で弾いている状況内音楽)を重ねます。この不一致は意図的なもので、映像と音楽に「ズレ」を生じさせることで感情移入を拒否し、観客にドラマを客観的に見つめさせる効果を生んでいます。
一方、直後のエドゥアル(シャルリ)が誤ってプリーヌを殺してしまう場面、そして映画のクライマックスであるレナの射殺シーンでは、弦楽器のトレモロを用いたストレートな緊張音楽が用いられています。
緊張感の表現においても、対位法とダイレクトな手法が使い分けられていることに着目しましょう。
‣ その他の注目点:音楽をテーマにした洒落た演出 など
本編18分頃、シャルリとクラリスが同じ部屋にいる場面で、クラリスがメトロノームを動かします。これは状況内「音声」であり、音楽がテーマとなっている本作らしい洒落た演出です。視覚的にも聴覚的にも、音楽という主題が作品全体を貫いています。
音楽が実際に「聴こえている」ことを示す演出も秀逸です。本編33分頃、廊下を歩くヴァイオリンを持った女性が、ピアノの音で一瞬立ち止まります。この何気ない動作が、ラルス・シュメル音楽事務所から聴こえるエドゥアル(シャルリ)のピアノ演奏が状況内音楽であることを観客に明示しています。
► 終わりに
ここまで取り上げてきた音楽手法のすべてが、トリュフォーの映像を支える重要な要素です。ピアノという楽器を中心に据えながら音楽映画としての可能性を引き出した本作を、本レビューの内容を踏まえて鑑賞してみてください。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
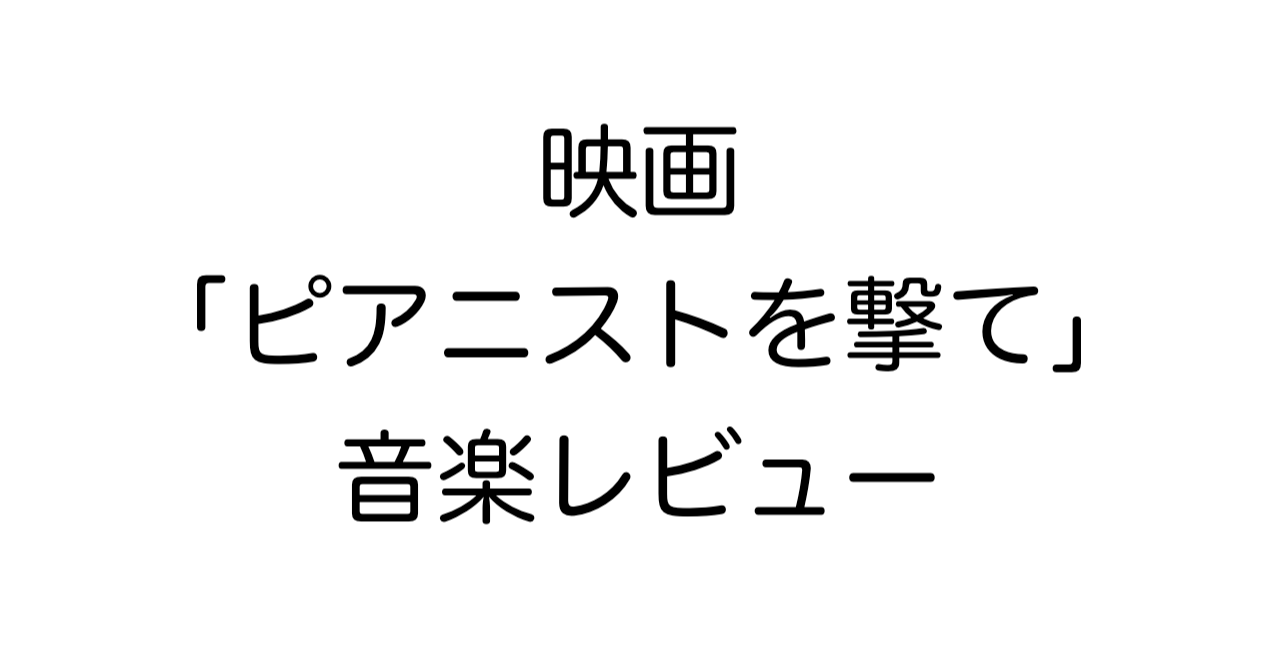
![ピアニストを撃て〔フランソワ・トリュフォー監督傑作選5〕 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41DQG5WQWZL._SL160_.jpg)
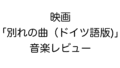
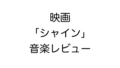
コメント